高等教育研究センター 准教授
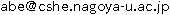
2025/04/01 更新

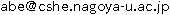
博士(教育学) ( 2009年3月 広島大学 )
人文・社会 / 高等教育学
名古屋大学 高等教育研究センター 准教授
2021年10月 - 現在
名古屋大学 教育基盤連携本部・高等教育研究センター 准教授
2021年10月 - 現在
大阪大学 全学教育推進機構 准教授
2016年12月 - 2021年9月
大阪大学 高等教育・入試研究開発センター 准教授
2016年6月 - 2016年12月
大阪大学 グローバルアドミッションズオフィス 特任准教授
2016年5月
大阪大学 グローバルアドミッションズオフィス 特任講師
2016年4月
大阪大学 未来戦略機構戦略企画室 特任講師
2013年12月 - 2016年3月
九州大学教育改革企画支援室 特任助教 特任助教
2009年3月 - 2013年11月
広島大学 教育学研究科博士課程後期 教育人間科学専攻
2006年4月 - 2009年3月
国名: 日本国
広島大学 教育学研究科博士課程前期 高等教育開発専攻
2003年4月 - 2005年3月
国名: 日本国
東洋大学 社会学部 応用社会学科
1994年4月 - 1998年3月
国名: 日本国
American College Personnel Association
2022年5月 - 現在
日本高等教育学会
日本協同教育学会
大学教育学会
文部科学省 先導的改革推進委託事業審査委員
2016年7月 - 現在
団体区分:政府
日本学生支援機構 学生支援の取り組み状況に関する調査協力者委員
2009年4月 - 現在
学生の学習を促進する日本の学寮プログラムとアセスメントの実態と課題 査読有り
蝶慎一,安部有紀子
名古屋高等教育研究 ( 23 ) 頁: 141 - 160 2023年3月
米国学生寮LLC(Living Learning Community)の実態と課題ー教育的アプローチの開発に着目してー 査読有り
安部有紀子、植松希世子
大学論集 54 巻 頁: 107 - 120 2022年3月
米国大学教育の学生支援における統合の概念の実態と課題について 査読有り
安部 有紀子
名古屋高等教育研究 24 巻 頁: 357 - 377 2024年3月
米国学生支援における学習成果の参照基準の変容に関する考察―学生支援アセスメントにおける学習成果の位置付けに着目して―
安部 有紀子, 蝶 慎一
大学経営政策研究 14 巻 ( 0 ) 頁: 1 - 17 2024年
安部 有紀子, 蝶 慎一
大学経営政策研究 = The journal of management and policy in higher education / 東京大学大学院教育学研究科大学経営・政策コース 編 ( 14 ) 頁: 3 - 17 2023年
学修の選択肢の拡大に伴うリスクと対策ーシンポジウムのディスカッションを踏まえてー 招待有り
安部有紀子、丸山和昭
名古屋高等教育研究 21 巻 頁: 43 - 52 2022年3月
米国学生寮LLC(Living Learning Community)の実態と課題 : 教育的アプローチの開発に着目して 査読有り
安部 有紀子, 植松 希世子
大学論集 54 巻 頁: 105 - 120 2022年3月
学修の選択肢の拡大に伴うリスクと対策ーシンポジウムのディスカッションを踏まえてー
安部 有紀子
名古屋高等教育研究 21 巻 頁: 43 - 52 2022年
外活動・学生表彰・ピア・サポート・ボランティア活動
安部 有紀子
大学等における学生支援の取組状況に関する調査(令和3年度)結果報告 2022 巻 頁: 139 - 148 2022年
安部有紀子
大学等における学生支援の取組状況に関する調査(令和元年度)結果報告 頁: 131 - 139 2020年11月
学習・学修支援に携わる学生スタッフの取組実態と課題
安部有紀子
大学教育学会誌 42 巻 ( 1 ) 頁: 51 - 55 2020年5月
課外活動・学生表彰・ピア・サポート・ボランティア活動
安部 有紀子
大学等における学生支援の取組状況に関する調査(平成元年度)結果報告 - 巻 頁: 131 - 139 2020年
学習・学修支援に携わる学生スタッフの取組実態と課題
安部 有紀子
大学教育学会誌 42(1) 巻 頁: 19 - 36 2020年
学習・学修支援に携わる学生スタッフの取組実態と課題
安部 有紀子
大学教育学会誌 42 巻 頁: 19 - 36 2020年
課外活動・学生表彰・ピア・サポート・ボランティア活動
安部 有紀子
大学等における学生支援の取組状況に関する調査(平成元年度)結果報告 2020 巻 頁: 131 - 139 2020年
教養教育の最前線 査読有り
Albertine, Susan, 安部有紀子
大阪大学高等教育研究 ( 7 ) 頁: 41 - 57 2019年3月
米国学寮プログラムにおける学習者中心主義の影響について
安部 有紀子
高等教育研究叢書 145 巻 頁: 19 - 36 2019年3月
課外活動・学生表彰・ピア・サポート・ボランティア活動
安部有紀子
大学等における学生支援の取組状況に関する調査(平成29年度)結果報告 頁: 133 - 144 2018年11月
学生支援の「今」を見る(10)日本学生支援機構『大学等における学生支援の取組状況に関する調査(平成27年度)』から 課外における学生活動支援の現状と課題 : 国際教養大学・立命館大学での実地調査から 招待有り
安部(小貫) 有紀子
文部科学教育通信 ( 426 ) 頁: 12 - 14 2017年12月
学生支援の「今」を見る(9)大学等における学生活動の支援に関する現状と課題 招待有り
安部(小貫) 有紀子
文部科学教育通信 ( 425 ) 頁: 12 - 15 2017年12月
学生支援における学習成果を基盤としたアセスメントの実態と課題 (特集 高等教育研究のニューフロンティア) 招待有り 査読有り
安部(小貫) 有紀子, 橋場 論, 望月 由起
高等教育研究 20 巻 頁: 113 - 133 2017年4月
課外活動,学生表彰,ピア・サポート,ボランティア活動 招待有り
安部 有紀子
大学教育の継続的変動と学生支援—大学等における学生支援の取組状況に関する調査— 頁: 55 - 74 2017年3月
世界的研究大学との協力による学生経験調査の実施と阪大生の特徴に関する考察 : Student Experience Survey in Research Universityへの参加と実施
齊藤 貴浩, 和嶋 雄一郎, 廣森 聡仁, 安部(小貫, 有紀子, 藤井 翔太, 前原 忠信, Saito Takahiro, Wajima Yuichiro, Hiromori Akihito, Abe(Onuki) Yukiko, Fujii Shota, Maehara Tadanobu, サイトウ タカヒロ, ワジマ ユウイチロウ, ヒロモリ アキヒト, アベ(オヌキ) ユキコ, フジイ ショウタ, マエハラ タダノブ
大阪大学高等教育研究 = Osaka University higher education studies ( 4 ) 頁: 1 - 14 2016年4月
米国における大学教育の質保証と教育改革の動向 : 米国訪問調査の報告
安部(小貫) 有紀子, 川嶋 太津夫, 山口 和也, 南岡 宏樹, 妹尾 純子, アベ(オヌキ) ユキコ, カワシマ タツオ, ヤマグチ カズヤ, ミナミオカ ヒロキ, セノ ジュンコ, Abe(Onuki) Yukiko, Kawashima Tastuo, Yamaguchi Kazuya, Minamioka Hiroki, Seno Junko
大阪大学高等教育研究 = Osaka University higher education studies ( 4 ) 頁: 35 - 42 2016年4月
米国高等教育におけるピアプログラムの現状とアセスメントの意義 査読有り
安部(小貫) 有紀子
大学論集 48 巻 ( 48 ) 頁: 129 - 144 2016年3月
米国高等教育におけるピアプログラムの現状とアセスメントの意義 査読有り
安部(小貫) 有紀子
大学論集 ( 48 ) 頁: 129 - 144 2016年3月
アクティブラーニングとしての反転学習(2)実践編 (第37回大会 ラウンドテーブル)
本田 周二, 安部(小貫, 有紀子, 七田 麻美子
大学教育学会誌 = Journal of Japan Association for College and University Education 37 巻 ( 2 ) 頁: 49 - 53 2015年11月
大学の構成員に対する効果的な広報方法とは?
和嶋 雄一郎, 石田大成社, 安部, 小貫] 有紀子, 齊藤 貴浩
JSAI大会論文集 2015 巻 ( 0 ) 頁: 1D5OS22b5 - 1D5OS22b5 2015年4月
第2外国語における反転学習の導入実践報告
安部有紀子, 岩根久, 本田周一
2015年2月
米国学生支援の評価の動向と現状 (シンポジウム 学生支援の評価 : "支援の成果"を用いた評価への転換可能性)
小貫 有紀子
大学教育学会誌 = Journal of the Liberal and General Education Society of Japan 36 巻 ( 1 ) 頁: 94 - 97 2014年5月
学修支援活動に携わる学生スタッフの変容プロセスに関する探索的研究 査読有り
橋場 論, 小貫 有紀子, 橋場 論, 小貫 有紀子
名古屋高等教育研究 ( 14 ) 頁: 279 - 298 2014年3月
米国学生支援における学習者中心主義への転換要因とアセスメントのインパクトについて 査読有り
小貫 有紀子, 小貫 有紀子
名古屋高等教育研究 ( 14 ) 頁: 97 - 116 2014年3月
「学生支援」の専門性と教職員の能力開発を取り巻く課題 : 米国における学生担当職の能力開発指標を手掛かりに (シンポジウム 学生支援に携わる教職員に求められる能力とは何か)
小貫 有紀子
大学教育学会誌 = Journal of the Liberal and General Education Society of Japan 35 巻 ( 1 ) 頁: 102 - 104 2013年5月
ラウンドテーブル 大学教育におけるピア・サポートの位置づけ : 正課と正課外の狭間で
小貫 有紀子, 森 朋子, 泉谷 道子
大学教育学会誌 34 巻 ( 2 ) 頁: 73 - 76 2012年11月
米国高等教育における学生担当職員の専門職能開発(PD)の体系化 (特集 スタッフ・ディベロップメント) 招待有り
小貫 有紀子
高等教育研究 13 巻 頁: 81 - 100 2010年4月
第3章 学生支援の組織と業務の役割分担に関する一考察 (大学職員の開発 : 専門職化をめぐって)
小貫 有紀子
RIHE 105 巻 頁: 24 - 36 2009年3月
海外事例 米国学生支援における学生担当職の専門性と専門職団体
小貫 有紀子
大学と学生 ( 49 ) 頁: 54 - 61 2008年1月
組織班報告 : 大学組織とガバナンスの変容 : 戦後日本型高等教育構造の着地点 (21世紀型高等教育システム構築と質的保証 : 第34回(2006年度)『研究員集会』の記録 : 21世紀COEプログラム報告)
羽田 貴史, 大場 淳, 黄 福涛, 村澤 昌崇, 杉本 和弘, 葛城 浩一, 田中 正弘, 米澤 彰純, 福留 東土, 渡邊 あや, 小貫 有紀子
RIHE 93 巻 頁: 81 - 89 2007年7月
米国高等教育における学生支援の概念モデルと学生担当職の役割に関する一考察
小貫 有紀子
大学行政管理学会誌 ( 11 ) 頁: 31 - 38 2007年4月
第4章 大学職員の流動及び意思決定への参画に関する一考察 : アンケート調査の結果から (SDの制度化に関する研究 : 第二部 : 「大学における職員に関するアンケート調査」結果)
小貫 有紀子
COE研究シリーズ 30 巻 頁: 63 - 84 2007年3月
第3章 JABEEによる教育プログラムの展開と課題 (大学改革における評価制度の研究)
小貫 有紀子
COE研究シリーズ 28 巻 頁: 37 - 44 2007年2月
第5章 部局を超えた組織の構築と学生の参加 (大学の組織変容に関する調査研究)
大場 淳, 小貫 有紀子
COE研究シリーズ 27 巻 頁: 65 - 78 2007年2月
アメリカ高等教育における学習支援プログラムの基準と評価システム 査読有り
小貫 有紀子
大学教育学会誌 27 巻 ( 2 ) 頁: 81 - 87 2005年11月
米国大学における学習支援職員の発展についての研究--ユニバーサル段階における職務の専門職分化 査読有り
小貫 有紀子
大学行政管理学会誌 ( 9 ) 頁: 23 - 28 2005年4月
理工学系DBリンク集の作成--インターネットを利用した情報の収集から発信まで (2001年度私立大学図書館協会東地区部会 館長会・研究講演会、研究分科会報告大会記録) -- (研究分科会報告大会)
龍田 由紀子, 小貫 有紀子, 宇田川 和男
私立大学図書館協会会報 ( 118 ) 頁: 148 - 154 2002年11月
大学等における学生支援の取組状況に関する調査(2021年度)実地調査報告ーコロナウイルス感染症の対応を踏まえた取組ー
沖清豪、安部有紀子、佐藤純、立石慎治、蝶慎一、橋場論、望月由起( 担当: 分担執筆 , 範囲: 実地報告(東北大学、一橋大学、成城大学))
日本学生支援機構 2022年3月
学寮プログラムの現代的展開
安部(小貫) 有紀子, 望月 由起, 橋場 論 編( 担当: 共著)
広島大学高等教育研究開発センター 2019年3月 ( ISBN:9784866370125 )
安部 有紀子, 望月 由起 , 橋場 論
広島大学高等教育研究開発センター 2019年 ( ISBN:9784866370125 )
アクティブラーニング型授業としての反転授業[理論編]
森朋子, 溝上慎一( 担当: 分担執筆)
ナカニシヤ出版 2017年5月 ( ISBN:4779510880 )
大場 淳, 小貫 有紀子, 田中 岳, 神保 啓子, 林 一夫 (文部科学省), 廣内 大輔, 芦沢 真五, 叶 林, 王 琳( 担当: 共著)
広島大学高等教育研究開発センター 2009年 ( ISBN:9784902808513 )
学生の学習を促進するための大学教育としての学生支援の展開
安部 有紀子
大学教育改革フォーラムin東海2023 分科会第I部I-a 2023年3月4日 大学教育改革フォーラムin東海
Development and Challenges of Student Residence Life Programs in Japanese Higher Education 国際会議
Yukiko Abe and Shinichiro Cho
Hawaii International Conference on Education 2023年1月5日 Hawaii International Conference on Education
大学教育における学生支援の位置付けの再考:学寮プログラムの教育的アプローチ事例から見る葛藤と追求
安部有紀子
高等教育学会研究交流集会 2022年12月24日 日本高等教育学会
学生の学習を促進するための大学教育としての学生支援の展開 招待有り
安部 有紀子
グラスルーツ「学生・院生の学修・生活・発達に関わる支援の高度化・共同化ならびに研究・教育・学生支援の再結合」講演会 2022年10月31日 立命館大学
日本の大学における学生寮の展開と課題:学寮プログラムに質保証の取り組みを取り入れた先駆的事例を中心に
安部 有紀子
日本高等教育学会第25回大会 2022年5月29日 日本高等教育学会
ニューノーマル時代に おける学生の学びを促進 する学生支援活動とは? 招待有り
安部有紀子
日本学生相談学会第40回大会 ワークショップ8領域E 2022年5月6日 日本学生相談学会
学習者中心のプログラムアセスメントと学習効果測定について 招待有り
安部有紀子
南山大学国際センターFD・SD講演会 2022年2月16日 南山大学
日本の学生寮における教育的アプローチの意義と現状
安部有紀子, 沖清豪, 蝶慎一
学寮セミナー 2021年8月21日 学寮科研研究グループ(代表 安部有紀子)
ランドテーブル「学生寮におけるレジデント・アシスタント(RA)の意義と教育効果」
植松希世子, 北澤泰子, 望月由起, 安部有紀子, 水野貴子, 蝶慎一, 日暮トモ子、沖清豪
大学教育学会第43回大会 2021年6月5日 大学教育学会
学生の成長を促す学生支援のための何が必要か?ー米国学生支援の動向を足がかりにー 招待有り
安部有紀子
日本相談学会第39回大会 2021年5月15日 日本学生相談学会
事例紹介セッション2「コロナ禍におけるピア・サポートー1年生支援を中心にー」
安部有紀子(モデレーター), 石井和也, 岡本直輝, 山口昌弘
令和2年度学生生活にかかる喫緊の課題に関するセミナー 2020年12月11日 日本学生支援機構
米国学寮における教育プログラムの開発, 「ラウンドテーブル『現代の学生寮における改革動向とその教育的意義』」
安部有紀子
大学教育学会第42回大会 2020年6月6日 大学教育学会
学生を成長させる学生支援を目指して‐米国からの示唆‐ 招待有り
安部有紀子
ニューノーマル時代の大学職員のスタッフ・ディベロップメント(SD)-わが国におけるSDの新たな地平を切り拓く‐ 2020年2月2日 株式会社ビズアップ総研
大学教員の包摂的教育実践における高等教育の質保証のための課題検討とモデル構築
研究課題/研究課題番号:24K06079 2024年4月 - 2028年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(C)
松本 みゆき, 佐藤 万知, 安部 有紀子, 永井 靖人
担当区分:研究分担者
学生の多様性増加の中、大学教育について包摂的な取り組みの必要性が世界的に高まっており、様々な実践が行われている。しかしながら、日本ではその取り組みがいまだ遅れているという現状がある。そこで本研究は、日本における多様な学生のニーズを満たすための教育方法を探求し、その教育方法を支える大学教員の認識を明らかにすることで、大学教員の包摂的教育実践が、高等教育の質保証に資するための課題を検討しモデルを構築する。高等教育における平等で包摂的な教育のための教員の取り組みと認識は、学生ひいては社会のウェルビーイングや繁栄にきわめて重要な役割を担っている。本研究の成果は、日本における高等教育の質保証に貢献する。
学生の学習を促進する質保証を基盤とした学生支援プログラムの開発
研究課題/研究課題番号:23K02524 2023年4月 - 2027年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(C)
安部 有紀子, 蝶 慎一, 日暮 トモ子
担当区分:研究代表者
配分額:4810000円 ( 直接経費:3700000円 、 間接経費:1110000円 )
近年、大学教育の質保証の文脈において学生の成長や成果測定の様々な取組が実践されているが、い ずれも正課教育が対象となっており、教室外での学生支援については、学生の学習を促進 するため学習成果基準や、戦略的なプログラム開発に関する知見は、ほとんど見られない。
本研究は、学生の学習促進を目的にした、教室外での学生支援プログラムの教育的プアロ ーチについて、その特徴と効果的な運用に関する体系系的な知見を得ることを目的とする。また、現代的な学生支援の教育的意義や、学生支援活動を通じて統合的、包括的な学生の学びをどのよう に促進することができるか具体的に明らかにしていく。
研究課題/研究課題番号:19H00619 2019年4月 - 2024年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(A)
松繁 寿和, 村澤 昌崇, 妹尾 渉, 家島 明彦, 大谷 碧, 川嶋 太津夫, 和嶋 雄一郎, 平尾 智隆, 小貫, 白井 詩沙香, 飯田 星良, 森 朋子, 岡嶋 裕子, 柿澤 寿信, 堀 一成, ヴ マン・ティエン, 山田 礼子, 梅崎 修, 勇上 和史, 山下 仁司, 井川 静恵, ALBERTINE SUSAN
担当区分:研究分担者
非認知能力やコンピテンシーと呼ばれる社会的能力の長期的影響力を探ることを目的とする。まず、それが小中義務教育期間、高等学校、大学という各学校段階で育成され成績等に影響を及ぼすメカニズムをできるだけ精度の高いデータを収集し分析する。次に、それらの結果を繋ぎ社会的能力が学校段階を跨いで影響を及ぼしていること、さらに社会に出てからの就業にも影響していることを検証する。このため、各教育段階において、個別の生徒・学生を入学当初から卒業まで追跡調査したパネルデータを独自に構築する。また、推定は複雑な構造となるために、すでに応用が進んだ統計手法だけでなくAIを応用した分析も試みる。
社会的能力の長期的な生成過程を解明し、さらに社会的能力が認知能力、特に学業成果、そして卒業後のキャリアにどのような影響をあたえるのかを探ることが研究の目的である。そのために、小・中・高・大の各教育期間において、社会的能力が学習やその他の活動によってどのように育成されるかを、生徒・学生レベルのマイクロデータを用いて検証する。まず、2019年度は、研究体制の整備と先行研究の吟味および必要な知識および技術の洗い出しと習得が目標とされた。
本格的調査に入る準備として、2019年度前半は、生徒や学生に関するマイクロデータを収集する対策と作業スケジュールを決定し、さらに、いくつかの作業グループに分け、担当する教育期を決めた。後半は、主に全教育過程から社会に出る段階まで社会的能力を一貫して計測できる指標の開発とその測定方法を議論し試行した。そのために、研究報告会を定期的に開き専門家を招くなどをして検討を重ね、アンケート項目等の洗い出しを行なった
一方、新たなデータが作成されるまでに、既存の資料やデータを用いて行える研究も進めた。特に、小学校期における教育や経験が持つ長期的効果の測定が、既存のマイクロデータを利用し進められ、学習以外の習い事が、非認知能力や社会的能力の育成を通じて、卒業後のキャリア形成にまで影響を及ぼしている可能性を示した。また、学校教育期間終了後にも効果を維持する教育の内容を補足するために、大学教育をキャリア形成の視点から見直す試みも行った。大学教育と社会で重視されるコンピテンシーの関係を分析した研究や、キャリア教育が学生の意識に与える効果を準社会的実験環境下で補足しようとする試みが進められた。これらの成果はいくつかの学会で報告されるとともに、専門雑誌に掲載された。
2019年度前半は、ほぼ計画通り、研究体制の構築と社会的能力指標の検討が行われた。義務教育期間に関しては、複数の自治体の教育関係団体との関係を構築し、生徒を対象とするアンケートの実施、および、学習成果に関するデータの継続的確保について協議した。また、教員経験者を対象に教育環境や学級の状況に応じてとられる学校・学級現場での対応についてのインタビューを行い、統計分析結果を解釈する際の留意点等を把握した。
高校に関しては、ある都道府県が全高校の生徒を対象に行った意識・行動調査の項目から社会的能力を捕捉できるかどうかを検討した。また、学習成果に関するデータの利用の可能性、さらに突合しパネルデータ化できるかも検討した。これらの点に加え、データの質や整備状況を確認するために、データセットの一部にアクセスし、非認知能力や社会的能力に関するアンケート項目と学業成績との関係に関して試験的分析を行った。
大学教育に関しては、複数の大学において、学生の属性、入試、学業成果に関するデータベースの作成と利用可能性を探った。また、2019年度新入生を対象に既存テストを利用して、社会人基礎力を測定する調査を複数回行うとともに、そのテストを開発した企業と調査項目に関する共同研究を行うこととなった。
ただし、2020年1月からのCOVID-19の感染拡大により、研究協力を依頼していた上記の自治体や教育委員会等における職務環境の変化や学校における年度計画や学事歴の変更等があり、研究計画の変更が必要となった。また、予定していた海外の研究協力者の招聘も不可能となった。加えて、研究対象大学での授業のオンライン化により、調査対象学生の確保や調査環境の確保が不可能となり、いくつかの調査の延期が避けられなくなった。
第一に、COVID-19の感染拡大により生じた遅延を余儀なくされた作業に対応する。学校段階別に社会的能力の育成と認知能力に関するデータ収集・作成およびそれらを利用した分析作業に関しては、まず、関係団体・組織との協力関係の継続確認と研究体制および計画の見直しを行う。また、学校に出向いて行う予定であった聞き取り調査は、可能な限りアンケート調査等で代替する方向で検討する。
第二に、複数年度に跨がる追跡調査は、調査年度数を減らす一方、学校や関係組織内に蓄積されている過去のデータを掘り起こし補完的利用する可能性を探る。特に、高校段階においては、既存のデータの入手を働きかける一方で、新たな調査を開始する計画があることから、担当者を増加し研究体制の強化を図る。また、調査年度を1年ずらすことで対応が可能な調査は、新たに新入生の追跡を始め、各学校段階の前半と後半に分けた分析の可能性を検討する。
第三に、教育段階の接続に関する研究に関しては、前段階の学校からの入手を計画していたが、後段階に入学後に追加的なアンケート調査を行うなどで補完する。また、完全なデータの構築を待たず、アクセス可能なデータを利用し順次分析を始める。
第四に、比較的アクセスが可能な大学が保有するデータの統合作業を進め、パネル分析が可能なデータセットを作るとともに、一部のデータを利用して試験的分析を開始する。具体的には、出身地域、出身高校属性、入試成績等に加え、SSH・SGH 校出身、高校での探求学習の経験等に注目し、それらが入学後の成長に与える効果を補足する分析に着手する。また、卒業後の就職先と初任配属部門に関する追跡調査を可能とするために、関係組織・機関、あるいは、協力を依頼できる企業等との調整を進める。
日本の高等教育における学寮の教育的展開と質保証を基盤としたプログラム開発
研究課題/研究課題番号:19H01688 2019年4月 - 2023年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(B)
小貫, 望月 由起, 蝶 慎一, 植松 希世子, 日暮 トモ子, 杉本 和弘
担当区分:研究代表者
配分額:16900000円 ( 直接経費:13000000円 、 間接経費:3900000円 )
本研究は、日本の学寮プログラムの教育的展開の実態と特徴を明らかにし、質保証を基盤にした教育的な学寮プログラムを開発することを目的とする。本研究では各国の学寮改革の進展状況や、日本の学寮の教育的プログラムの実像へアプローチするとともに、質保証を基盤とした学寮プログラムの開発を試みる。
研究初年度のため、計画通りに次年度以降の海外調査のための対象国の高等教育機関について、社会的・文化的背景の情報収集、および先駆事例の収集に努めた。東アジア、北欧についてはプレ調査を実施し、新たな研究課題が生じたため、調査課題の焦点化を2回にわたる研究会においてメンバー間で話し合いを行った。
また、国内の先駆事例についても収集を進め、いくつかの大学の事例をもとに、国内の学生寮のトレンドを明らかにするとともに、海外に比べて学寮内で提供するプログラムの希薄さという問題点が明らかになった。また、高等教育機関外の寮に関するステークホルダー(社会人寮、民間管理会社等)の課題については、本研究でどのように扱うかは次年度以降の課題として残った。
今年度の調査を通じて、各国の学生寮については、その国の社会的動向や高等教育の位置づけ、学生と大学の関係性等の影響が大きいことが明らかになった。特に海外では、教育的な学生寮プログラムを展開している場合、学生寮においてコミュニケーション・スキルなど多様な能力を獲得するための体験的学習を通じた学習コミュニティが形成されていることが明らかとなった。
今後は、その国の学生寮の歴史的動向を押さえる際に、①学生に対する寮スタッフの役割、立場の変化、②教育的プログラムの導入状況、③学生寮の存在意義と大学の教育目標の関係等の視点から整理していく。また、派生するテーマとして、学生寮の中で活動する学生スタッフ(RA)の存在、アセスメントの推進を含め、多様な課題が学生寮には存在しているため、今後の海外調査を通して、今後研究目的と課題の精査を行っていくこととなった。
当初計画していた通り、研究初年度として必要な基盤となる研究課題に対する情報収集、学術文献の収集、各国先駆事例の収集を通じて、調査課題の焦点化まで進展した。また、次年度以降の調査実施に際して、年度途中でメンバーを増やし、各国の調査の主担当者を確定させ、各担当者のもと、調査計画を立てることができた。
国内は学生寮の形態に関する歴史的発展の諸相等について調査を行うとともに、複数の大学の訪問調査、高等学校における学生寮設置状況の現状把握、また、学寮担当者のネットワークと連携し、最新動向の収集に努めるとともに、現場の課題を吸い上げ、研究の方向性等に活かすことができた。
海外はシンガポール、韓国、北欧・欧州圏の大学寮の現地調査を実施し、比較的新しい事例、伝統的な学生寮の形態の両側面からの情報収集に努めた。
また、学寮には実に多様な取組、活動のあり方があるため、どのタイプの学生寮を本研究の対象とするかは、追加の調査を踏まえて検討していく。
地域別の主担当を中心に、国内の学生寮の重点校、および海外の学生寮の訪問調査を実施する。そのために、今年度中に①どのような学生寮を対象とするか、②分析視点の整理、③調査項目の精査を行っていく。
また、コロナウイルスの感染拡大に伴い、厳重警戒地域では、学生寮が閉鎖される等の非常事態に直面している。調査については、既にコンタクトを取っている各国の学寮担当者に対して、オンラインやメール等で代替していくとともに、調査項目にコロナウイルス対策について①学生寮の現状と対策、②学寮アシスタントといった学生スタッフや学生リーダーの活動状況とコロナ対策に関する活動の諸相、の2つの項目を追加して調査していく。
また、調査の基盤となる学寮に関する教育プログラムの定義、構造、条件等の理論的基盤を整理するとともに、関連する先行研究の収集を引き続き行い、分析を進めていく。
また、国内外の学会に参加し、情報収集に努めるとともに、これまでの科研の研究成果を発信していく。
研究チーム内の情報共有はSNSを通じて日常的に継続していくが、今年度からさらにオンライン学習会、オンライン研究会(年2回)についても、対面と同様に継続していく。
データ分析とシミュレーションによるオーダーメイド型学修活動・学生生活支援の探索
研究課題/研究課題番号:15K13205 2015年4月 - 2018年3月
科学研究費助成事業 挑戦的萌芽研究
村澤 昌崇, 森 朋子, 小貫, 渡邉 聡, 安部 保海, 原田 健太郎, 松宮 慎治, 中尾 走
担当区分:研究分担者
本研究は、学生調査データを元に学生の学習履歴や生活実態を分析し、その結果をもとに個々の学生の成長に望ましい学習行動や生活パターンのシミュレーションを導き、個別の学生へのアドバイス・支援を行うシステムを構築することを目指した。成果は、①欠損や未回答の多い学生調査データを有効活用できる統計手法の有効性を確認、②学習時間に影響を与える多様な要因の発見、③二つの大学において、学生調査データの分析結果に基づく学生支援システムの導入、の3点が得られた。
研究課題/研究課題番号:26381135 2014年4月 - 2017年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(C)
安部 有紀子(小貫), 小島 佐恵子, 秦 喜美恵, 平井 達也, 望月 由起, 橋場 論
担当区分:研究代表者
配分額:4810000円 ( 直接経費:3700000円 、 間接経費:1110000円 )
本研究は学修成果に基づいた大学教育におけるピアプログラムのあり方を明らかにするものである。ピアプログラムは過去20年において急速に発展してきた取組であり、その原型は米国高等教育に見ることができる。いくつかの事例から得たことは、米国においては学生支援やピアプログラムのアセスメントは学習成果だけでなく、プログラムや活動全体を含んでおり、また活動の中期的な戦略計画の重要性であった。転じて日本の学生支援にとっては、学習成果アセスメントは大学の教育戦略や目標、また他の教育活動やプログラムといった全体的な教育の質を向上させるための方策と密接に関連づけられていなければならない。
研究課題/研究課題番号:25590250 2013年4月 - 2016年3月
科学研究費助成事業 挑戦的萌芽研究
川島 啓二, 齋藤 憲司, 橋場 論, 安倍 有紀子, 田中 岳
担当区分:連携研究者
学生支援は、大学教育の基盤を支える手段的なものなのか、学習成果を展望できる目的的な教育的関与なのか、はたまた、個別の能力に還元できない人間的成長を促す「場」の実現なのか、理論的定位が切に求められている。学生の多様化に合わせて、領域やサービスの方法それ自体も多様化してきた学生支援は、学生自身が支援者にまわるというフェイズへの展開を経て、大学そのもののマネジメントやガバナンスの問題へと発展していった。そのことは、肥大化・複雑化しながらもその提供主体やコスト負担の在り方をめぐる公共サービスの問題構造を大学が受け止めなければならなくなったことを意味している。
研究課題/研究課題番号:23330232 2011年4月 - 2014年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(B)
芦沢 真五, 秋庭 裕子, 太田 浩, 小貫 有紀子, 北脇 学, 関山 健, 堀江 未来, 横田 雅弘, 米澤 彰純, 米澤 由香子, 工藤 和宏, 竹内 愛, 鳥居 朋子, 平井 達也
担当区分:研究分担者
海外学習機会の「多様化」と「大衆化」が進む中で、学生の「学び」をどう可視化し、学習成果をどう評価するか、が喫緊の課題となっている。欧州や北米においては、履修科目数、学習時間数などのアウトプット評価ではなく、実際に学生が「何を学び、何ができるようになったか」というアウトカム(学習成果)が重視されている。多くの大学でEポートフォリオによる学習成果分析が行われるとともに、学生自身が学習プロセスを振り返るために活用されている。本科研では、こうした先行事例から学び、国際教育プログラムの質保証と学習成果分析の実証究をおこなった。また。Eポートフォリオと活用した学習成果分析の有効性について検証した。
大学ガバナンス改革における組織文化と職員開発に関する国際比較研究
研究課題/研究課題番号:23531062 2011年 - 2013年
科学研究費助成事業 基盤研究(C)
大場 淳, 芦沢 真五, 小貫 有紀子, 田中 岳, 前田 一之
担当区分:連携研究者
日本の大学改革では意思決定における上意下達的側面や制度改革が重視され、一定方向のガバナンス改革が一律の全大学に適用される傾向がある中において、本研究は、国内外の調査に基づいて、個々の大学が有する諸条件によって望ましいガバナンスの在り方は異なっていることを明確にした。そのことは、大学運営に関する改革の在り方は、例えば学長の権限拡大や教授会の権限縮小といった一律の制度改革を行うことではなく、個々の大学が適切なガバナンスの在り方を構想することを支援することにあるべきことを示唆するものである。研究成果については、学会等での発表、雑誌論文の掲載、書籍への執筆等を通じて、日本語及び外国語で行った。
大学教育における学習成果ベースの学生支援モデル構築に関する研究
研究課題/研究課題番号:23730797 2011年 - 2013年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究(B)
小貫 有紀子
担当区分:研究代表者
配分額:3250000円 ( 直接経費:2500000円 、 間接経費:750000円 )
本研究では、日米の学生支援における学習成果にかかわる近年の状況と、学生支援活動全体に与えるインパクトについて学生インタビュー及び訪問、文献調査によって明らかにした。米国では2000年以降、学習成果ベースのアセスメント活動が盛んになってきている。その結果、学生担当副学長のトップダウンによる組織的な学生支援のマネジメントや様々なアセスメントツールが開発されていた。一方、日本では、学生支援プログラムは問題応答的、かつ模索的な側面が強いが、一部のプログラムでは、参加学生の研修プロセスを取り入れることで、学生の学習成果向上に寄与する学生支援プログラムとして開発可能であることが明らかとなった。
高等教育における学生支援とその専門分化に関する研究
研究課題/研究課題番号:07J00350 2007年 - 2008年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 特別研究員奨励費
小貫 有紀子
本研究は100年にわたって先駆的取り組みを続けてきた米国高等教育における学生支援の変遷プロセスと実態を明らかにすることを通じて、大学教育における学生支援の意義と役割について考察することを目的とした。1960年代の米国高等教育における学生数の急増を受け、学生支援の発展が急激に促され、組織、人員、提供するプログラムなどにおいて量的拡大が進行し、1980年代の大学教育改革ブームにおいては教室外における学生の成長を重視する傾向が全米で強まり、学生支援の質的向上に注目が集まった。これらの外的要因に加え、学生支援の専門性開発という内的動機が合わさり、学生支援の活動の根本となる理念の変革が意図的に誘導され、現在の学生の学習を支援するための学生支援のあり方へと転換が図られた経緯を持つ。現在、米国大学教育の中心は学生の学習成果を元にした教育効果の明示化である。そしてそれは学生支援においても同様で、特に学生の知力発達に学生の内面的成長が欠かせないという視点から、多様な学習経験を提供するための要素として、学生支援が果たす役割の大きさが強調されている。
本研究では上記の視点を歴史的背景、1980年代における転換期の議論、過去20年間における学習を中心にした学生支援への転換プロセス、そしてブリッジウォーター州立大学、ペンシルバニア州立大学における事例研究の比較から見た、現代的学生支援の実態を明らかにすることで実証した。
女性リーダーとの対話
2020年
大学院生のためのトランスファラブル・スキルズ・トレーニング
2019年
学問への扉
2019年
女性リーダーとの対話
2019年
女性リーダーとの対話
2018年
ハイブリッド授業の運営と授業支援
役割:司会, 企画, 運営参加・支援, 報告書執筆
東海国立大学機構 アカデミック・セントラルQTA・GSIトレーニングセンター/名古屋大学高等教育研究センター スキルアップセミナー 2023年3月
QTA研修ワークショップ
役割:助言・指導, 企画, 運営参加・支援, 報告書執筆
東海国立大学機構 アカデミック・セントラルQTA・GSIトレーニングセンター 2023年3月
QTA研修ワークショップ
役割:司会, 講師, 助言・指導, 企画, 運営参加・支援, 報告書執筆
東海国立大学機構 アカデミック・セントラルQTA・GSIトレーニングセンター 2023年3月
大学教育改革フォーラムin東海
役割:司会, 助言・指導, 企画, 運営参加・支援, 報告書執筆
大学教育改革フォーラムin東海実行委員会 2023年3月
授業・研究に使える動画作成法
役割:司会, 企画, 運営参加・支援, 報告書執筆
東海国立大学機構 アカデミック・セントラルQTA・GSIトレーニングセンター/名古屋大学高等教育研究センター スキルアップセミナー 2023年2月
シラバスの書き方セミナー
役割:講師, 企画, 報告書執筆
東海国立大学機構 アカデミック・セントラル QTA・GSI トレーニングセンター、名古屋大学高等教育研究センター 2022年12月
ピア・サポートの視点から学生支援を捉え直す
役割:企画, 運営参加・支援, 報告書執筆
高等教育研究センター、名古屋大学学生支援本部 第3回 学生支援担当者講習会、第206回招聘セミナー 2022年11月
大学の統合や連携によって学生の学びはどう変わるのだろう
役割:司会, 助言・指導
教育基盤連携本部高等教育システム開発部門 教育基盤連携本部 高等教育システム開発部門シンポジウム 2022年11月
学生支援における連携と協議
役割:企画, 運営参加・支援, 報告書執筆
高等教育研究センター 第2回 学生支援担当者講習会 2022年9月
QTA研修ワークショップ
役割:助言・指導, 企画, 運営参加・支援, 報告書執筆
東海国立大学機構 アカデミック・セントラルQTA・GSIトレーニングセンター 2022年9月
QTA研修ワークショップ
役割:司会, 講師, 助言・指導, 企画, 運営参加・支援, 報告書執筆
東海国立大学機構 アカデミック・セントラルQTA・GSIトレーニングセンター 2022年9月
大学が災害に遭った際の心のケア
役割:企画, 運営参加・支援, 報告書執筆
高等教育研究センター、学生支援本部 第203回招聘セミナー、第1回 学生支援担当者講習会 2022年9月
QTA研修ワークショップ
役割:司会, 講師, 助言・指導, 企画, 運営参加・支援, 報告書執筆
東海国立大学機構 アカデミック・セントラルQTA・GSIトレーニングセンター 2022年3月
オンライン・ハイブリッド環境下での授業運営・グループワーク手法
役割:司会, 企画, 運営参加・支援, 報告書執筆
東海国立大学機構 アカデミック・セントラルQTA・GSIトレーニングセンター/名古屋大学高等教育研究センター スキルアップセミナー 2022年2月
大学院生の教育力を高めるために
役割:司会, 助言・指導, 企画, 運営参加・支援, 報告書執筆
東海国立大学機構 アカデミック・セントラルQTA・GSIトレーニングセンター/名古屋大学高等教育研究センター オンラインセミナー 2022年2月
授業・研究に使える動画作成法
役割:司会, 企画, 運営参加・支援, 報告書執筆
東海国立大学機構 アカデミック・セントラルQTA・GSIトレーニングセンター/名古屋大学高等教育研究センター スキルアップセミナー 2022年2月
大学のデジタルトランスフォーメーション(DX)と学生生活
役割:司会, 助言・指導
教育基盤連携本部高等教育システム開発部門 教育基盤連携本部 高等教育システム開発部門シンポジウム 2021年11月