細胞生理学研究センター 准教授
大学院創薬科学研究科
工学部 化学生命工学科
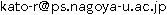
2025/10/09 更新

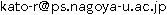
博士(工学) ( 2004年3月 名古屋大学 )
医療情報
生体材料
品質管理
安全性管理
再生医療
その他 / その他 / 医用生体工学・生体材料学
その他 / その他 / 医用システム
その他 / その他 / 生物機能・バイオプロセス
その他 / その他 / ナノ材料・ナノバイオサイエンス
その他 / その他 / 生体生命情報学
その他 / その他 / 社会システム工学・安全システム
その他 / その他 / 応用生物化学
その他 / その他 / 機能材料・デバイス
血管内皮細胞再生ペプチドの医工共同デザインとステントへの応用
再生医療実用化に向けた画像による細胞品質管理システムの開発
名古屋大学 未来社会創造機構 マテリアル研究所 バイオマテリアル研究部門 兼担
2022年4月 - 現在
名古屋大学 糖鎖生命コア研究所(iGCORE) 兼担
2021年1月 - 現在
名古屋大学 医療健康データ統合研究教育拠点 (C-HiT) 兼担
2020年12月 - 現在
名古屋大学 未来社会創造機構ナノライフシステム研究所 兼担
2018年10月 - 現在
名古屋大学 予防早期医療創成センター 准教授
2015年4月 - 現在
名古屋大学 大学院創薬科学研究科 准教授
2012年4月 - 現在
国名:日本国
名古屋大学 工学部 兼担・准教授
2012年4月 - 現在
名古屋大学 大学院工学研究科 助教
2006年9月 - 2012年4月
国名:日本国
名古屋大学 医学部寄附講座 助手
2004年11月 - 2006年9月
国名:日本国
名古屋大学 大学院工学研究科 COE ポスドク研究員
2004年4月 - 2004年10月
国名:日本国
名古屋大学 工学研究科 生物機能工学専攻
2001年4月 - 2004年3月
国名: 日本国
奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科 細胞生物学専攻
1999年4月 - 2001年3月
国名: 日本国
東北大学 工学部 化学・バイオ系
1994年4月 - 1998年3月
国名: 日本国
日本生物工学会中部支部 庶務・幹事
2023年4月 - 現在
ISO/TC276 WG4 国内委員・Expert
2014年4月 - 現在
団体区分:学協会
ものづくり日本大賞 経済産業大臣賞
2023年1月 経済産業省
加藤 竜司
内田・鮫島法律事務所特別賞
2020年12月 アクセラレーションプログラムBRAVE2020
加藤 竜司
LinkJ ライフサイエンス賞
2020年12月 アクセラレーションプログラムBRAVE2020
加藤 竜司
Remarkable Paper Award
2019年10月 The Japanese Society for Regenerative Medicine
Ryuji Kato
生物工学論文賞
2018年10月 日本生物工学会
藤谷 将也、Noor Saika Huddin、河合 駿、蟹江 慧、清田泰次郎、清水 一憲、本多 裕之、加藤 竜司
次世代人工知能・ロボット中核技術開発/次世代人工知能技術分野 優れたベンチャー技術 健康、医療・介護分野 最優秀賞
2018年7月 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) AIによる高純度間葉系幹細胞の品質検査高度化の調査研究
加藤 竜司
Johnson & Johnson Innovation Award
2018年3月 日本再生医療学会 細胞画像情報解析を用いた治療用細胞製造のための品質管理技術の開発
加藤 竜司
生物工学奨励賞(照井賞)
2017年10月 日本生物工学会 画像情報処理を用いた再生医療用製品製造工程における非破壊的品質管理技術の開発
加藤 竜司
化学工学論文集 優秀論文賞
2013年4月 化学工学会 全網羅ミルクペプチドアレイを用いたアレル ギー診断ペプチド探索への分布関数解析法の応用
中杤 昌弘, 片山 真, 加藤 竜司, 大河内 美奈, 高瀬 智和, 吉田 安子, 川瀬三雄, 本多裕之
APBioChEC 2009 Best Presentation Award
2009年11月 Asia Pacific Biochemical Engineering Conference (APBioChEC)
Ryuji Kato
Yang, J; Kato, R; Choi, J
NANOSCALE 2025年8月
Sakakibara, K; Tanaka, K; Iida, M; Imai, Y; Okada, M; Sahashi, K; Hirunagi, T; Maeda, K; Kato, R; Katsuno, M
DISEASE MODELS & MECHANISMS 18 巻 ( 6 ) 2025年6月
Hirono, K; Hayashi, Y; Udugama, IA; Gaddem, MR; Tanaka, K; Takemoto, Y; Kato, R; Kino-oka, M; Sugiyama, H
COMMUNICATIONS BIOLOGY 8 巻 ( 1 ) 頁: 657 2025年5月
Shiina T, Kimura K, Takemoto Y, Tanaka K, Kato R
Journal of bioscience and bioengineering 139 巻 ( 4 ) 頁: 329 - 339 2025年4月
細胞産業における AI技術の応用と課題 Open Access
田中 健二郎, 加藤 竜司
人工知能 40 巻 ( 2 ) 頁: 141 - 147 2025年3月
Medicinal cannabis extracts are neuroprotective against Aβ<sub>1-42</sub>-mediated toxicity in vitro
Marsh, DT; Shibuta, M; Kato, R; Smid, SD
BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 135 巻 ( 5 ) 頁: 575 - 592 2024年11月
Hart, ML; Kato, R; Rolauffs, B
FRONTIERS IN IMMUNOLOGY 15 巻 頁: 1443534 2024年6月
Oka, H; Kojima, T; Kato, R; Ihara, K; Nakano, H
JOURNAL OF BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY 22 巻 ( 03 ) 頁: 2450017 2024年6月
Hirono, K; Hayashi, Y; Udugama, IA; Takemoto, Y; Kato, R; Kino-oka, M; Sugiyama, H
AICHE JOURNAL 2024年4月
Hisada T, Imai Y, Takemoto Y, Kanie K, Kato R
Journal of bioscience and bioengineering 2024年3月
Development of novel waxy bone haemostatic agents composed of biodegradable polymers with osteogenic-enhancing peptides in rabbit models 査読有り Open Access
Ohno, T; Suenaga, H; Yamawaki-Ogata, A; Kanie, K; Kato, R; Uto, K; Ebara, M; Ito, H; Narita, Y; Usui, A; Mutsuga, M
Interdisciplinary cardiovascular and thoracic surgery 37 巻 ( 5 ) 2023年11月
The structurally diverse phytocannabinoids cannabichromene, cannabigerol and cannabinol significantly inhibit amyloid β-evoked neurotoxicity and changes in cell morphology in PC12 cells. 査読有り 国際共著 Open Access
Marsh DT, Sugiyama A, Imai Y, Kato R, Smid SD
Basic & clinical pharmacology & toxicology 2023年9月
Automated cell isolation from photodegradable hydrogel based on fluorescence image analysis. 査読有り
Shinji Sugiura, Shinya Yamahira, Masato Tamura, Kazumi Shin, Mayu Shibuta, Taku Satoh, Yui Matsuzawa, Gen Fujii, Fumiki Yanagawa, Michihiro Mutoh, Masumi Yanagisawa, Ryuji Kato, Hirofumi Matsui
BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING 2023年3月
Novel functional peptide for next-generation vital pulp therapy 査読有り Open Access
Watanabe Masakatsu, Okamoto Motoki, Komichi Shun, Huang Hailing, Matsumoto Sayoko, Moriyama Kiichi, Ohshima Jun, Abe Shotaro, Morita Masayoshi, Ali Manahil,, Takebe Katsuki, Kozaki Ikko, Fujimoto Akiyo, Kanie Kei, Kato Ryuji, Uto Kenichiro, Ebara Mitsuhiro, Yamawaki-Ogata Aika, Narita Yuji, Takahashi Yusuke, Hayashi Mikako
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 102 巻 ( 3 ) 頁: 322 - 330 2023年3月
Bioinformatics in bioscience and bioengineering: Recent advances, applications, and perspectives 査読有り Open Access
Uesaka Kazuma, Oka Hiroya, Kato Ryuji, Kanie Kei, Kojima Takaaki, Tsugawa Hiroshi, Toda Yosuke, Horinouchi Takaaki
JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING 134 巻 ( 5 ) 頁: 363 - 373 2022年11月
特集 小児外科を取り巻く最新テクノロジー Hirschsprung病に対する機械学習を用いた病理診断支援システムの開発 査読有り
天野 日出, 木村 和恵, 今井 佑太, 加藤 竜司, 中澤 温子, 城田 千代栄, 滝本 愛太朗, 住田 亙, 牧田 智, 岡本 眞宗, 安井 昭洋, 高田 瞬也, 中川 洋一, 加藤 大幾, 檜 顕成, 内田 広夫
小児外科 54 巻 ( 10 ) 頁: 1007 - 1011 2022年10月
Suyama Takashi, Takemoto Yuto, Miyauchi Hiromi, Kato Yuko, Matsuzaki Yumi, Kato Ryuji
INFLAMMATION AND REGENERATION 42 巻 ( 1 ) 頁: 30 2022年10月
Label-free morphological sub-population cytometry for sensitive phenotypic screening of heterogenous neural disease model cells 査読有り Open Access
Imai Yuta, Iida Madoka, Kanie Kei, Katsuno Masahisa, Kato Ryuji
SCIENTIFIC REPORTS 12 巻 ( 1 ) 頁: 9296 2022年6月
Bi-layered carboxymethyl cellulose-collagen vitrigel dual-surface adhesion-prevention membrane 査読有り Open Access
Wang Yue, Kanie Kei, Takezawa Toshiaki, Horikawa Miki, Kaneko Kyoshiro, Sugimoto Ayako, Yamawaki-Ogata Aika, Narita Yuji, Kato Ryuji
CARBOHYDRATE POLYMERS 285 巻 頁: 119223 2022年6月
Myc supports self-renewal of basal cells in the esophageal epithelium. 査読有り 国際共著 Open Access
Tomoaki Hishida, Eric Vazquez-Ferrer, Yuriko Hishida-Nozaki, Yuto Takemoto, Fumiyuki Hatanaka, Kei Yoshida, Javier Prieto, Sanjeeb Kumar Sahu, Yuta Takahashi, Pradeep Reddy, David D O'Keefe, Concepcion Rodriguez Esteban, Paul S Knoepfler, Estrella Nuñez Delicado, Antoni Castells, Josep M Campistol, Ryuji Kato, Hiroshi Nakagawa, Juan Carlos Izpisua Belmonte
FRONTIERS IN CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY 10 巻 頁: 786031 2022年3月
Collection of Data Variation Using a High-Throughput Image-Based Assay Platform Facilitates Data-Driven Understanding of TRPA1 Agonist Diversity 査読有り Open Access
Terada Yuko, Tanaka Kenjiro, Matsuyama Minami, Fujitani Masaya, Shibuya Masatoshi, Yamamoto Yoshihiko, Kato Ryuji, Ito Keisuke
APPLIED SCIENCES 12 巻 ( 3 ) 2022年2月
Imai Yuta, Kanie Kei, Kato Ryuji
INFLAMMATION AND REGENERATION 42 巻 ( 1 ) 頁: 8 2022年1月
Enhancement of protein thermostability by three consecutive mutations using loop-walking method and machine learning 査読有り Open Access
Yoshida Kazunori, Kawai Shun, Fujitani Masaya, Koikeda Satoshi, Kato Ryuji, Ema Tadashi
SCIENTIFIC REPORTS 11 巻 ( 1 ) 頁: 11883 2021年6月
Takemoto Yuto, Imai Yuta, Kanie Kei, Kato Ryuji
JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING 131 巻 ( 2 ) 頁: 198 - 206 2021年2月
機械学習を用いた浸炭熱処理品のミクロ組織画像からの炭素濃度予測技術の開発 査読有り Open Access
谷地 宣紀, 服部 清幸, 加藤 竜司
熱処理 61 巻 ( 5 ) 頁: 257 - 263 2021年
身近となった画像解析とAI Open Access
加藤 竜司
生物工学会誌 99 巻 ( 8 ) 頁: 432 - 435 2021年
Screening of FFAR1-activating peptides by molecular structural analysis 査読有り
Yoshioka Keitaro, Yamashita Haruki, Fujitani Masaya, Kato Ryuji, Shimizu Kazunori, Honda Hiroyuki
KAGAKU KOGAKU RONBUNSHU 47 巻 ( 3 ) 頁: 64 - 68 2021年
Yamashita Haruki, Fujitani Masaya, Shimizu Kazunori, Kanie Kei, Kato Ryuji, Honda Hiroyuki
ACS BIOMATERIALS SCIENCE & ENGINEERING 6 巻 ( 11 ) 頁: 6117 - 6125 2020年11月
Nagashima Takunori, Hadiwidjaja Stacy, Ohsumi Saki, Murata Akari, Hisada Takumi, Kato Ryuji, Okada Yohei, Honda Hiroyuki, Shimizu Kazunori
ADVANCED BIOSYSTEMS 4 巻 ( 11 ) 頁: e2000121 2020年11月
Reproducible production and image-based quality evaluation of retinalpigment epithelium sheets from human induced pluripotent stem cells. 査読有り Open Access
Ye Ke, Takemoto Yuto, Ito Arisa, Onda Masanari, Morimoto Nao, Mandai Michiko, Takahashi Masayo, Kato Ryuji, Osakada Fumitaka
SCIENTIFIC REPORTS 10 巻 ( 1 ) 頁: 14387 2020年9月
The importance of scoring recognition fitness in spheroid morphological analysis for robust label -free quality evaluation 査読有り
Shirai Kazuhide, Kato Hirohito, Imai Yuta, Shibuta Mayu, Kanie Kei, Kato Ryuji
REGENERATIVE THERAPY 14 巻 頁: 205 - 214 2020年6月
Performance of a biodegradable compositewith hydroxyapatite as a scaffold in pulp tissue repair. 査読有り Open Access
Okamoto Motoki, Matsumoto Sayako, Sugiyama Ayato, Kanie Kei, Watanabe Masakatsu, Huang Hailing, Ali Manahil, Ito Yuki, Miura Jiro, Hirose Yujiro, Uto Koichiro, Ebara Mitsuhiro, Kato Ryuji, Yamawaki-Ogata Aika, Narita Yuji, Kawabata Shigetada, Takahashi Yusuke, Hayashi Mikako
POLYMERS (BASEL) 12 巻 ( 4 ) 頁: 937 - 941 2020年4月
Novel cannabis flavonoid, cannflavin A displays both a hormetic and neuroprotective profile against amyloid β-mediatedneurotoxicity in PC12 cells: Comparison with geranylated flavonoids, mimuloneand diplacone. 査読有り 国際共著
Eggers Carly, Fujitani Masaya, Kato Ryuji, Smid Scott
BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY 169 巻 頁: 113609 2019年8月
Effect of mechanical vibration stress in cell culture on human inducedpluripotent stem cells. 査読有り Open Access
Kanie Kei, Sakai Teppei, Imai Yuta, Yoshida Kei, Sugimoto Ayako, Makino Hodaka, Kubo Hirotsugu, Kato Ryuji
REGENERATIVE THERAPY 12 巻 頁: 27 - 35 2019年6月
Quantitative analysisof operators' flow line in the cell culture for controlled manual operation. 査読有り Open Access
Kanie Kei, Sasaki Hiroto, Ikeda Yurika, Tamada Masaki, Togawa Fumio, Kato Ryuji
REGENERATIVE THERAPY 12 巻 頁: 43 - 54 2019年5月
Identification of an early cell fate regulator bydetecting dynamics in transcriptional heterogeneity and co-regulation duringastrocyte differentiation. 査読有り Open Access
Ando Tatsuya, Kato Ryuji, Honda Hiroyuki
NPJ SYSTEMS BIOLOGY AND APPLICATIONS 5 巻 ( 1 ) 頁: 18 2019年5月
Numerical investigation of particle dispersion in the preprocessing stage for a staticcell cultivation. 査読有り
Sekimoto Atsushi, Kanemaru Yoshiki, Okano Yasunori, Kanie Kei, Kato Ryuji, Kino-oka Masahiro
REGENERATIVE THERAPY 12 巻 ( 83 ) 頁: 87 2019年4月
Activation of cancer-related and mitogen-activated protein kinase signaling pathways in human mature osteoblasts isolated from patients with type 2 diabetes. 査読有り Open Access
Kuroiwa Tomoyuki, Matsumoto Megumi, Kato Ryuji, Nimura Akimoto, Yoshii Toshitaka, Okawa Atsushi, Fujita Koji
BONE REPORTS 10 巻 頁: 100199 2019年2月
Time-course colony tracking analysis for evaluating induced pluripotent stem cellculture processes. 査読有り Open Access
Yoshida Kei, Okada Mai, Nagasaka Risako, Sasaki Hiroto, Kanie Kei, Kato Ryuji
JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING 128 巻 ( 2 ) 頁: 209 - 217 2019年2月
Morphology-based analysis of myoblasts for prediction of myotube formation. 査読有り Open Access
Ishikawa Kiyoshi, Yoshida Kei, Kanie Kei, Omori Kenji, Kato Ryuji
SLAS DISCOVERY 24 巻 ( 1 ) 頁: 47 - 56 2019年1月
細胞形態情報解析を用いた 1 細胞~細胞集団の応答性の解析 Open Access
加藤 竜司
日本プロテオーム学会大会要旨集 2019 巻 ( 0 ) 頁: 131 - 131 2019年
In-process evaluation of culture errors using morphology-based image analysis. 査読有り Open Access
Imai Yuta, Yoshida Kei, Matsumoto Megumi, Okada Mai, Kanie Kei, Shimizu Kazunori, Honda Hiroyuki, Kato Ryuji
REGENERATIVE THERAPY 9 巻 ( 15 ) 頁: 15 - 23 2018年12月
Effective screening for hypolipidemic bile acid-binding peptides by hierarchical clustering-based catalog array. 査読有り
Kato Ryuji, Kanie Kei, Kaga Chiaki, Okochi Mina, Nagaoka Satoshi, Honda Hiroyuki
JOURNAL OF BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND APPLIED BIOCHEMISTRY 1 巻 ( 1 ) 頁: doi: 10.31546/BBAB.1001 2018年8月
Imaging cell picker: A morphology-based automatedcell separation system on a photodegradable hydrogel culture platform. 査読有り
Mayu Shibuta, Masato Tamura, Kei Kanie, Masumi Yanagisawa, Hirofumi Matsui, Taku Satoh, Toshiyuki Takagi, Toshiyuki Kanamori, Shinji Sugiura, Ryuji Kato
JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING 126 巻 ( 5 ) 頁: 653 - 660 2018年6月
画像情報処理を用いた再生医療用製品製造工程における非破壊的品質管理技術の開発
加藤 竜司
生物工学会誌 96 巻 ( 3 ) 頁: 121 - 128 2018年
細胞画像情報処理を用いた医療用細胞製造プロセス管理 Open Access
加藤 竜司
精密工学会誌 84 巻 ( 11 ) 頁: 901 - 904 2018年
Morphology-based non-invasive quantitative prediction of the differentiationstatus of neural stem cells. 査読有り Open Access
Fujitani Masaya, Huddin Noor Safika, Kawai Shun, Kanie Kei, Kiyota Yasujiro, Shimizu Kazunori, Honda Hiroyuki, Kato Ryuji
JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING 124 巻 ( 3 ) 頁: 351 - 358 2017年9月
Heat-stimuli-enhanced osteogenesis using clinically available biomaterials. 査読有り Open Access
Ota Takehiro, Nishida Yoshihiro, Ikuta Kunihiro, Kato Ryuji, Kozawa Eiji, Hamada Shunsuke, Sakai Tomohisa, Ishiguro Naoki
PLOS ONE 12 巻 ( 7 ) 頁: e0181404 2017年7月
Visualization of morphological categories of colonies formonitoring of effect on induced pluripotent stem cell culture status. 査読有り Open Access
Nagasaka Risako, Matsumoto Megumi, Okada Mai, Sasaki Hiroto, Kanie Kei, Kii Hiroaki, Uozumi Takayuki, Kiyota Yasujiro, Honda Hiroyuki, Kato Ryuji
REGENERATIVE THERAPY 6 巻 頁: 41 - 51 2017年6月
Image-based cell quality evaluation to detect irregularities under same cultureprocess of human induced pluripotent stem cells. 査読有り Open Access
Nagasaka Risako, Gotou Yuto, Yoshida Kei, Kanie Kei, Shimizu Kazunori, Honda Hiroyuki, Kato Ryuji
JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING 123 巻 ( 5 ) 頁: 642 - 650 2017年5月
Prediction of differentiation tendency toward hepatocytes from gene expression in undifferentiated human pluripotent stem cells. 査読有り Open Access
Yanagihara Kana, Liu Yujung, Kanie Kei, Takayama Kazuo, Kokunugi Minako, Hirata Mitsuhi, Fukuda Takayuki, Suga Mika, Nikawa Hiroki, Mizuguchi Hiroyuki, Kato Ryuji, Furue-Kusuda Miho
STEM CELLS AND DEVELOPMENT 25 巻 ( 24 ) 頁: 1884 - 1897 2016年12月
Focused screening of ECM-selective adhesion peptides on cellulose-bound peptide microarrays. 査読有り
Kanie Kei, Kondo Yuto, Owaki Junki, Ikeda Yurika, Narita Yuji, Kato Ryuji, Honda Hiroyuki
BIOENGINEERING (BASEL) 3 巻 ( 4 ) 頁: 31 2016年11月
Combinational effects of polymer viscoelasticity and immobilized peptides on cell adhesion to cell-selective scaffolds. 査読有り Open Access
Kurimoto Rio, Kanie Kei, Uto Koichiro, Kawai Shun, Hara Mitsuo, Nagano Shusaku, Narita Yuji, Honda Hiroyuki, Naito Masanobu, Ebara Mitsuhiro, Kato Ryuji
ANALYTICAL SCIENCES 32 巻 ( 11 ) 頁: 1195 - 1202 2016年11月
Parametric analysis of colony morphology of non-labelled live human pluripotent stem cells for cell quality control. 査読有り Open Access
Kato Ryuji, Matsumoto Megumi, Sasaki Hiroto, Joto Risako, Okada Mai, Ikeda Yurika, Kanie Kei, Suga Mika, Kinehara Masaki, Yanagihara Kana, Liu Yujung, Uchio-Yamada Kozue, Fukuda Takayuki, Kii Hiroaki, Uozumi Takayuki, Honda Hiroyuki, Kiyota Yasujiro, Furue-Kusuda Miho
SCIENTIFIC REPORTS 6 巻 頁: 34009 2016年9月
Exploring high-affinity binding properties of octamer peptides by principal component analysisof tetramer peptides. 査読有り
Kume Akiko, Kawai Shun, Kato Ryuji, Iwata Shinmei, Shimizu Kazunori, Honda Hiroyuki
JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING 123 巻 ( 2 ) 頁: 230 - 238 2016年9月
Screeningof osteogenic-enhancing short peptides from BMPs for biomimetic material applications. 査読有り Open Access
Kanie Kei, Kurimoto Rio, Tian Jing, Ebisawa Katsumi, Narita Yuji, Honda Hiroyuki, Kato Ryuji
MATERIALS (BASEL) 9 巻 ( 9 ) 頁: 730 2016年9月
Morphological evaluation of nonlabeled cells to detect stimulation of nerve growth factor expression by Lyconadin B. 査読有り Open Access
Kawai Shun, Sasaki Hiroto, Okada Norihiro, Kanie Kei, Yokoshima Satoshi, Fukuyama Tohru, Honda Hiroyuki, Kato Ryuji
JOURNAL OF BIOMOLECULAR SCREENING 21 巻 ( 8 ) 頁: 795 - 803 2016年9月
Non-invasive quality evaluation of confluent cells by image-based orientation heterogeneity analysis 査読有り
Sasaki Kei, Sasaki Hiroto, Takahashi Atsuki, Kang Siu, Yuasa Tetsuya, Kato Ryuji
JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING 121 巻 ( 2 ) 頁: 227 - 234 2016年2月
Comparisons of cellculture medium using distribution of morphological features in microdevice. 査読有り
Sasaki Hiroto, Enomoto Junko, Ikeda Yurika, Honda Hiroyuki, Fukuda Junji, Kato Ryuji
JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING 121 巻 ( 1 ) 頁: 117 - 123 2016年1月
Combinational effect of cell adhesion biomolecules and their immobilized polymer property to enhance cell-selective adhesion. 査読有り Open Access
Kurimoto Rio, Kei Kanie, Koichiro Uto, Shun Kawai, Mitsuo Hara, Shusaku Nagano, Yuji Narita, Hiroyuki Honda, Masanobu Naito, Mitsuhiro Ebara, Ryuji Kato
INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER SCIENCE 2016 巻 頁: 2090985 2016年
Combinational effects of polymer viscoelasticity and immobilized peptides on cell adhesion to cell-selective scaffolds. 査読有り Open Access
Kurimoto Rio, Kei Kanie, Koichiro Uto, Shun Kawai, Mitsuo Hara, Shusaku Nagano, Yuji Narita, Hiroyuki Honda, Masanobu Naito, Mitsuhiro Ebara, Ryuji Kato
ANALYTICAL SCIENCES 32 巻 ( 11 ) 頁: 1195 - 1202 2016年
Differential variability and correlation of geneexpression identifies key genes involved in neuronal differentiation. 査読有り Open Access
Ando Tatsuya, Kato Ryuji, Honda Hiroyuki
BMC SYSTEMS BIOLOGY 9 巻 ( 1 ) 頁: 82 2015年11月
Sasaki K, Miyata H, Sasaki H, Kang S, Yuasa T, Kato R.
JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING 120 巻 ( 5 ) 頁: 582 - 590 2015年11月
Sasaki Kei, Miyata Hirofumi, Sasaki Hiroto, Kang Siu, Yuasa Tetsuya, Kato Ryuji
JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING 120 巻 ( 5 ) 頁: 582 - 590 2015年11月
Effects of theproperties of short peptides conjugated with cell-penetrating peptides on theirinternalization into cells. 査読有り Open Access
Matsumoto Ryo, Okochi Mina, Shimizu Kazunori, Kanie Kei, Kato Ryuji, Honda Hiroyuki
SCIENTIFIC REPORTS 5 巻 頁: 12884 2015年8月
配向性解析によるコンフレント細胞の非侵襲品質評価 (医用画像)
佐々木 啓, 佐々木 寛人, 高橋 厚妃, 蟹江 慧, 姜 時友, 加藤 竜司, 湯浅 哲也
電子情報通信学会技術研究報告 114 巻 ( 482 ) 頁: 167 - 172 2015年3月
Nakatochi Masahiro, Ushida Yasunori, Yasuda Yoshinari, Yoshida Yasuko, Kawai Shun, Kato Ryuji, Nakashima Toru, Iwata Masamitsu, Kuwatsuka Yachiyo, Ando Masahiko, Hamajima Nobuyuki, Kondo Takaaki, Oda Hiroaki, Hayashi Mutsuharu, Kato Sawako, Yamaguchi Makoto, Maruyama Shoichi, Matsuo Seiichi, Honda Hiroyuki
PLOS ONE 10 巻 ( 2 ) 頁: e0117591 2015年2月
In vivo heat-stimulus-triggered osteogenesis. 査読有り
Ikuta Kunihiro, Urakawa Hiroshi, Kozawa Eiji, Hamada Shunsuke, Ota Takehiro, Kato Ryuji, Honda Hiroyuki, Kobayashi Takeshi, Ishiguro Naoki, Nishida Yoshihiro
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYPERTHERMIA 31 巻 ( 1 ) 頁: 58 - 66 2015年2月
Characterization of time-course morphological features for efficientprediction of osteogenic potential in human mesenchymal stem cells. 査読有り Open Access
Matsuoka Fumiko, Takeuchi Ichiro, Agata Hideki, Kagami Hideaki, Shiono Hirofumi, Kiyota Yasujiro, Honda Hiroyuki, Kato Ryuji
BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING 111 巻 ( 7 ) 頁: 1430 - 1439 2014年7月
Label-free morphology-based prediction of multiple differentiation potentials ofhuman mesenchymal stem cells for early evaluation of intact cells. 査読有り Open Access
Sasaki Hiroto, Takeuchi Ichiro, Okada Mai, Sawada Rumi, Kanie Kei, Kiyota Yasujiro, Honda Hiroyuki, Kato Ryuji
PLOS ONE 9 巻 ( 4 ) 頁: e93952 2014年4月
ペプチドアレイを用いたECMタンパク質由来機能性ペプチドの探索ストラテジーとその可能性 Open Access
蟹江 慧, 加藤 竜司
化学と生物 52 巻 ( 6 ) 頁: 361 - 370 2014年
培養中の幹細胞品質評価 : 画像を用いた評価技術とその貢献 (特集 再生医療実現に向けた幹細胞培養工学の最前線) Open Access
加藤 竜司, 清田 泰次郎, 備瀬 竜馬
生物工学会誌 92 巻 ( 9 ) 頁: 495 - 499 2014年
Orientation based segmentation for phase-contrast microscopic image of confluent cell 査読有り
Sasaki Kei, Yuasa Tetsuya, Sasaki Hiroto, Kato Ryuji
PROCEEDINGS OF THE ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY 頁: 3323 - 3326 2013年10月
Sugita Tomoya, Katayama Makoto, Okochi Mina, Kato Ryuji, Ichihara Takamitsu, Honda Hiroyuki
BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 79 巻 頁: 33 - 40 2013年10月
Analysing the substrate multispecificity of a proton-coupled oligopeptide transporter using a dipeptide library. 査読有り Open Access
Ito Keisuke, Hikida Aya, Kawai Shun, Vu Thi Tuyet Lan, Motoyama Takayasu, Kitagawa Sayuri, Yoshikawa Yuko, Kato Ryuji, Kawarasaki Yasuaki
NATURE COMMUNICATIONS 4 巻 頁: 2502 2013年9月
Morphology-based prediction of osteogenic differentiation potential of humanmesenchymal stem cells. 査読有り Open Access
Matsuoka Fumiko, Takeuchi Ichiro, Agata Hideki, Kagami Hideaki, Shiono Hirofumi, Kiyota Yasujiro, Honda Hiroyuki, Kato Ryuji
PLOS ONE 8 巻 ( 2 ) 頁: e55082 2013年2月
Hikida Aya, Ito Keisuke, Motoyama Takayasu, Kato Ryuji, Kawarasaki Yasuaki
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 430 巻 ( 4 ) 頁: 1217 - 1222 2013年1月
Nakatochi Masahiro, Katayama Makoto, Kato Ryuji, Okochi Mina, Takase Tomokazu, Yoshida Yasuko, Kawase Mitsuo, Honda Hiroyuki
KAGAKU KOGAKU RONBUNSHU 39 巻 ( 1 ) 頁: 40 - 45 2013年
実用化に資する医薬品生産培養技術の課題と展開~抗体医薬品から細胞医薬品まで~) Open Access
長森 英二, 加藤 竜司, 清水 一憲, 柳原 佳奈
生物工学会誌 91 巻 ( 9 ) 2013年
再生促進型医療材料開発のための細胞選択的接着ペプチドの探索と応用 Open Access
蟹江 慧, 加藤 竜司, 桑原 史明, 成田 裕司, 本多 裕之
生体医工学 51 巻 ( 3 ) 頁: 202 - 206 2013年
Orientation based segmentation for phase-contrast microscopic image of confluent cell 査読有り
Sasaki Kei, Yuasa Tetsuya, Sasaki Hiroto, Kato Ryuji
2013 35TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY (EMBC) 頁: 3323 - 3326 2013年
Combinational risk factors ofmetabolic syndrome identified by fuzzy neural network analysis of health-checkdata. 査読有り Open Access
Ushida Yasunori, Kato Ryuji, Niwa Kosuke, Tanimura Daisuke, Izawa Hideo, Yasui Kenji, Takase Tomokazu, Yoshida Yasuko, Kawase Mitsuo, Yoshida Tsutomu, Murohara Toyoaki, Honda Hiroyuki
BMC MEDICAL INFORMATICS AND DECISION MAKING 12 巻 ( 1 ) 頁: 80 2012年8月
Screening for silver nanoparticle-binding peptides by using a peptide array 査読有り
Kuboyama Masashi, Kato Ryuji, Okochi Mina, Honda Hiroyuki
BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 66 巻 頁: 73 - 77 2012年7月
Collagen type IV-specific tripeptides forselective adhesion of endothelial and smooth muscle cells. 査読有り
Kanie Kei, Narita Yuji, Zhao Yingzi, Kuwabara Fumiaki, Satake Makoto, Honda Susumu, Kaneko Hiroaki, Yoshioka Tomohiko, Okochi Mina, Honda Hiroyuki, Kato Ryuji
BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING 109 巻 ( 7 ) 頁: 1808 - 1816 2012年7月
Screening of an α-amylaseinhibitor peptide by photolinker-peptide array. 査読有り
Ochiai Takashi, Sugita Tomoya, Kato Ryuji, Okochi Mina, Honda Hiroyuki
BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY 76 巻 ( 4 ) 頁: 819 - 824 2012年4月
ヒト Collagen における細胞選択的ペプチドの分布 査読有り Open Access
蟹江 慧, 成田 裕司, 桑原 史明, 佐竹 真, 本多 勧, 兼子 博章, 本多 裕之, 加藤 竜司
高分子論文集 69 巻 ( 3 ) 頁: 129 - 134 2012年3月
位相差顕微鏡による細胞画像の領域分割と特徴量抽出 (医用画像)
佐々木 啓, 佐々木 寛人, 加藤 竜司, 湯浅 哲也, 武澤 康範, 松本 阿佐子
電子情報通信学会技術研究報告 : 信学技報 111 巻 ( 389 ) 頁: 343 - 348 2012年1月
Sasaki Hiroto, Matsuoka Fumiko, Yamamoto Wakana, Kojima Kenji, Honda Hiroyuki, Kato Ryuji
COMPUTATIONAL MODELING IN TISSUE ENGINEERING 10 巻 頁: 207 - 226 2012年1月
Novel small-caliber vascular grafts with trimeric peptide for acceleration of endothelialization. 査読有り
Kuwabara Fumiaki, Narita Yuji, Yamawaki-Ogata Aika, Kanie Kei, Kato Ryuji, Satake Makoto, Kaneko Hiroaki, Oshima Hideki, Usui Akihiko, Ueda Yuichi
ANNALS OF THORACIC SURGERY 93 巻 ( 1 ) 頁: 156 - 163 2012年1月
Enhancement of the Activity of a Lactobacilli-Aggregating Peptide by Freezing Treatment 査読有り
Asai Yuji, Sugita Tomoya, Kato Ryuji, Okochi Mina, Nakagawa Kyuya, Honda Hiroyuki
JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING OF JAPAN 45 巻 ( 8 ) 頁: 609 - 614 2012年
Screening of peptides with a high affinity to bile acids using peptide arraysand a computational analysis. 査読有り
Takeshita Toshiyuki, Okochi Mina, Kato Ryuji, Kaga Chiaki, Tomita Yasuyuki, Nagaoka Satoshi, Honda Hiroyuki
JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING 112 巻 ( 1 ) 頁: 92 - 97 2011年4月
The ratio of adiponectinto homeostasis model assessment of insulin resistance is a powerful index ofeach component of metabolic syndrome in an aged Japanese population resultsfrom the KING Study. 査読有り
Nakatochi Masahiro, Miyata Seiko, Tanimura Daisuke, Izawa Hideo, Asano Hiroyuki, Murase Yosuke, Kato Ryuji, Ichihara Sahoko, Naruse Keiko, Matsubara Tatsuaki, Honda Hiroyuki, Yokota Mitsuhiro
DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE 92 巻 ( 3 ) 頁: 61 - 65 2011年3月
Amino acid sequence preferences to control cell-specific organization of endothelial cells, smooth muscle cells, and fibroblasts. 査読有り 国際誌
Kanie Kei, Kato Ryuji, Zhao Yingzi, Narita Yuji, Okochi Mina, Honda Hiroyuki
JOURNAL OF PEPTIDE RESEARCH 17 巻 ( 6 ) 頁: 479 - 486 2011年2月
Gingival and dermal fibroblasts their similarities anddifferences revealed from gene expression. 査読有り
Ebisawa Katsumi, Kato Ryuji, Okada Mai, Sugimura Tomotaka, Abdul Latif Mazlyzam, Hori Yusuke, Narita Yuji, Ueda Minoru, Honda Hiroyuki, Kagami Hideaki
JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING 111 巻 ( 3 ) 頁: 255 - 258 2011年2月
Peptide array-based peptide-cell interaction analysis. 査読有り 国際誌
Kato Ryuji, Kaga Chiaki, Kanie Kei, Kunimatsu Mitoshi, Okochi Mina, Honda Hiroyuki
MINI-REVIEWS OF ORGANIC CHEMISTRY 8 巻 ( 2 ) 頁: 171 - 177 2011年
Screening ofpeptides with a high affinity for ZnO using spot-synthesized peptide arrays andcomputational analysis. 査読有り 国際誌
Okochi Mina, Ogawa Masatoshi, Kaga Chiaki, Sugita Tomoya, Tomita Yasuaki, Kato Ryuji< Honda Hiroyuki
ACTA BIOMATERIALIA 6 巻 ( 6 ) 頁: 2301 - 2306 2010年12月
Acompact, automated cell culture system for clinical scale cell expansion fromprimary tissues. 査読有り 国際誌
Kato Ryuji, Iejima Daisuke, Agata Hideki, Asahina Izumi, Okada Kunihiko, Ueda Minoru, Honda Hiroyuki, Kagami Hideaki
TISSUE ENGINEERING PART C METHODS 16 巻 ( 5 ) 頁: 947 - 956 2010年11月
Novel strategy for prevention ofesophageal stricture after endoscopic surgery. 査読有り 国際誌
Mizutani Taro, Tadauchi Akimitsu, Arinobe Manabu, Narita Yuji, Kato Ryuji, Niwa Yasumasa, Ohmiya Naoki, Itoh Akihiro, Hirooka Yoshiki, Honda Hiroyuki, Ueda Minoru, Goto Hidemi
HEPATOGASTROENTEROLOGY 57 巻 ( 102-103 ) 頁: 1150 - 1156 2010年9月
Practical cell labeling with magnetitecationic liposomes for cell manipulation. 査読有り 国際誌
Ito Hiroshi, Nonogaki Yurika, Kato Ryuji, Honda Hiroyuki
JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING 110 巻 ( 1 ) 頁: 124 - 129 2010年2月
Directed evolution of angiotensin II-inhibiting peptides using a microbeaddisplay. 査読有り 国際誌
Gan Rui, Furuzawa Seiji, Kojima Takaaki, Kanie Keie, Kato Ryuji, Okochi Mina, Honda Hiroyuki, Nakano Hideo
JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING 109 巻 ( 4 ) 頁: 411 - 417 2009年11月
Magnetic manipulation device for theoptimization of cell processing conditions. 査読有り 国際誌
Ito Hiroshi, Kato Ryuji, Ino Kosuke, Honda Hiroyuki
JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING 109 巻 ( 2 ) 頁: 182 - 188 2009年8月
Peptide array-based analysis of the specific IgE andIgG4 in cow's milk allergens and its use in allergy evaluation. 査読有り 国際誌
Matsumoto Naoki, Okochi Mina, Matsushima Miyoko, Kato Ryuji, Takase Tomokazu, Yoshida Yasuko, Kawase Mitsuo, Isobe Ken-ichi, Kawabe Tsutomu, Honda Hiroyuki
PEPTIDES 30 巻 ( 10 ) 頁: 1840 - 1847 2009年7月
Cancer DNA microarrayanalysis considering multi-subclass with graph-based clustering method. 査読有り 国際誌 Open Access
Kawamura Takashi, Hutoh Hironori, Tomita Yasuyuki, Kato Ryuji, Honda Hiroyuk
JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING 106 巻 ( 5 ) 頁: 442 - 448 2008年12月
Size dependent heat generation of magnetite nanoparticles under AC magneticfield for cancer therapy. 査読有り 国際誌
Motoyama Jun, Hakata Toshiyuki, Kato Ryuji, Yamashita Noriyuki, Morino Tomio, Kobayashi Takeshi, Honda Hiroyuki
BIOMAGNETIC RESEARCH AND TECHNOLOGY 6 巻 頁: 4 2008年10月
A motif detection and classificationmethod for peptide sequences using genetic programming. 査読有り 国際誌
Tomita Yasuyuki, Kato Ryuji, Okochi Mina, Honda Hiroyuki
JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING 106 巻 ( 2 ) 頁: 154 - 161 2008年9月
Screening of anovel octamer peptide, CNSCWSKD, that induces caspase-dependent cell death. 査読有り 国際誌
Kaga Chiaki, Okochi Mina, Nakanishi Mari, Hayashi Hiroki, Kato Ryuji, Honda Hiroyuki
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESARCH COMMUNICATIONS 362 巻 ( 4 ) 頁: 1063 - 1068 2008年8月
Computationally assistedscreening and design of cell-interactive peptides by a cell-based assay usingpeptide arrays and a fuzzy neural network algorithm. 査読有り 国際誌 Open Access
Kaga Chiaki, Okochi Mina, Tomoita Yasuyuki, Kato Ryuji, Honda Hiroyuki
BIOTECHNIQUES 44 巻 ( 3 ) 頁: 393 - 402 2008年5月
Identification of HLA-A24-restricted epitopes with high affinities to Hsp70using peptide arrays. 査読有り 国際誌
Okochi Mina, Hayashi Hiroki, Ito Akira, Kato Ryuji, Tamura Yasuaki, Sato Noriyuki, Honda Hiroyuki
JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING 105 巻 ( 3 ) 頁: 198 - 203 2008年4月
Screening of cell adhesive peptide from the human laminin-5 alpha 3 chain globular 2 and 3 domains. 査読有り 国際誌
Okochi Mina, Nomura Shigeyuki, Kaga Chiaki, Honda Hiroyuki
JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING OF JAPAN 41 巻 ( 3 ) 頁: 206 - 209 2008年3月
Cryopreservation of mouse adipose tissue-derived stem/progenitorcells. 査読有り 国際誌
Oishi Koichi, Noguchi Hirofumi, Yukawa Hiroshi, Miyazaki Takamichi, Kato Ryuji, Kitagawa Yasuo, Ueda Minoru, Hayashi Shuji
CELL TRANSPLANTATION 17 巻 ( 1-2 ) 頁: 35 - 41 2008年1月
Peptide array-basedinteraction assay of solid-bound peptides and anchorage-dependant cells and itseffectiveness in cell-adhesive peptide design. 査読有り 国際誌
Kato Ryuji, Kaga Chiaki, Kunimatsu Mitoshi, Kobayashi Takeshi, Honda Hiroyuki
JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING 101 巻 ( 6 ) 頁: 485 - 495 2006年8月
High-throughputscreening of cell death inducible short peptides from TNF-related apoptosis-inducing ligand sequence. 査読有り 国際誌
Okochi Mina, Nakanishi Mari, Kato Ryuji, Kobayashi Takeshi, Honda Hiroyuki
FEBS LETTERS 580 巻 ( 3 ) 頁: 885 - 889 2006年1月
Novel strategy for protein exploration high-throughput screening assisted withfuzzy neural network. 査読有り 国際誌
Kato Ryuji, Nakano Hideo, Konishi Hiroyuki, Kato Katsuya, Koga Yuchi, Yamane Tsuneo, Kobayashi Takeshi, Honda Hiroyuki
JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 351 巻 ( 3 ) 頁: 683 - 692 2005年6月
Angiotensin IIinhibitory peptide found in the receptor sequence using peptide array. 査読有り 国際誌
Kato Ryuji, Kunimatsu Mitoshi, Fujimoto Seigo, Kobayashi Takeshi, Honda Hiroyuki
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESARCH COMMUNICATIONS 315 巻 ( 1 ) 頁: 22 - 29 2004年1月
Hidden Markov model-based approach as the first screening of binding peptides that interact with MHC class II molecules. 査読有り 国際誌
Kato Ryuji, Noguchi Hideki, Honda Hiroyuki, Kobayashi Takeshi
ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY 33 巻 ( 4 ) 頁: 472 - 481 2003年6月
Hidden Markov model-based prediction of antigenic peptides that interact with MHC class II molecules. 査読有り 国際共著 国際誌
Noguchi Hideki, Kato Ryuji, Hanai Taizo, Matubara Yukari, Honda Hiroyuki, Vladimir Brusic, Kobayashi Takeshi
JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING 94 巻 ( 3 ) 頁: 264 - 270 2002年11月
細胞産業における AI技術の応用と課題
田中 健二郎, 加藤 竜司( 担当: 共著)
人工知能 2025年3月
JIS Q 2101 細胞製造マネジメントシステム
( 担当: 監修)
日本規格協会 2025年2月
加藤 竜司( 担当: 分担執筆 , 範囲: 巻頭)
生物工学会 2024年5月
第4節 細胞品質管理に向けた細胞培養DXの重要ポイントと画像解析による効率的デザインスペースの理解
加藤竜司、伊藤智哉、蟹江慧( 担当: 共著)
技術情報協会 2023年12月 ( ISBN:978-4-86104-994-1 )
第11節 動物細胞培養の計測と自動化の取り組み、今後の展望
蟹江慧、百瀬賢吾、加藤竜司( 担当: 共著)
技術情報協会 2023年12月 ( ISBN:978-4-86104-994-1 )
第10章 医薬品の開発、製造への応用事例 2節 インフォマティクスを応用した細胞接着制御界面デザイン
杉山亜矢斗、藤本瑛代、蟹江慧、加藤竜司( 担当: 共著 , 範囲: マテリアルズインフォマティクスのためのデータ作成とその解析、応用事例)
技術情報協会 2021年7月
3節 細胞画像情報解析を用いた培養細胞品質のモニタリング
久田拓海、加藤竜司( 担当: 共著 , 範囲: バイオリアクターのスケールアップと物質生産事例集~ラボから工業化検討・シングルユース使用・スマートセル技術)
技術情報協会 2021年4月
細胞形態情報解析を用いたマテリアル培養性能のプロファイリング
藤谷将也、蟹江慧、加藤竜司( 担当: 共著 , 範囲: バイオマテリアル-生体材料-)
日本バイオマテリアル学会 2019年10月
創薬現場に向けたデータサイエンス~データサイエンスを活かすには~
加藤竜司、蟹江慧、清水志保( 担当: 共著 , 範囲: 生物工学会誌)
日本生物工学会 2019年8月
細胞形態情報解析を用いた筋分化予測
加藤竜司( 担当: 単著 , 範囲: 骨格筋研究を核とした筋スマート社会 10章)
(株)シーエムシー・リサーチ 2019年6月
画像を用いた細胞の非侵襲品質解析技術
竹本悠人、加藤竜司( 担当: 共著 , 範囲: 医薬品モダリティの特許戦略と技術開発動向 16節)
技術情報協会 2019年5月
高分子材料への細胞選択的ペプチド修飾による生体適合性付与
栗本理央、蟹江慧、荏原充宏、加藤竜司( 担当: 共著 , 範囲: 無機/有機材料の表面処理・改質による生体適合性付与 第6章)
(株)シーエムシー出版 2019年5月
細胞品質管理のための非侵襲モニタリング技術:細胞形態情報解析
加藤竜司( 担当: 共著 , 範囲: Pharm Stage)
技術情報協会 2019年3月
画像取得・解析技術を用いた培養工程の安定化
加藤竜司( 担当: 単著 , 範囲: 再生医療の開発戦略と最新研究事例集第 4章 第7節)
技術情報協会 2019年2月 ( ISBN:978-4-86104-737-4 )
「細胞を見る」ことはどこまで変われるか~見たあとのデータの活用に向けて~
加藤竜司( 担当: 単著 , 範囲: 再生医療 コメンタリー)
メディカルレビュー社 2019年2月
インシリコ技術を活用したペプチドのスクリーニング
蟹江慧、伊藤圭祐、加藤竜司( 担当: 共著 , 範囲: in silico創薬におけるスクリーニングの高速化・高精度化技術第1章 8節 )
(株)技術情報協会 2019年1月
細胞画像情報処理を用いた医療用細胞製造プロセス管理
加藤竜司( 担当: 単著 , 範囲: 精密工学会誌)
精密工学会 2018年11月
画像情報解析を用いたiPS細胞培養における品質管理
加藤竜司( 担当: 単著 , 範囲: 生物工学会誌)
日本生物工学会 2018年6月
第22章 ペプチドアレイを用いた新規機能性ペプチドの探索
蟹江慧、加藤竜司、本多裕之( 担当: 共著 , 範囲: 細胞・生体分子の固定化と機能発現)
(株)シーエムシー出版 2018年4月
画像情報処理を用いた再生医療用製品製造工程における非破壊的品質管理技術の開発
加藤竜司( 担当: 単著 , 範囲: 生物工学会誌)
日本生物工学会 2018年3月
細胞培養におけるAI関連技術の応用-画像解析による細胞品質管理
加藤竜司( 担当: 単著 , 範囲: AI導入によるバイオテクノロジーの発展 第5章・第2節)
(株)シーエムシー出版 2018年2月
三次元培養細胞分離装置によるがん不均一性の解析
杉浦慎治、田村磨聖、渋田真結、加藤竜司、金森敏幸、柳沢真澄( 担当: 共著 , 範囲: 実験医学 第1章・8)
羊土社 2018年1月
三次元ゲル培養からの形態情報を用いた細胞塊自動選別装置の開発
田村磨聖、杉浦慎治、渋田真結、加藤竜司、金森敏幸、柳沢真澄( 担当: 共著 , 範囲: 動物細胞培養における分離・精製手法と自動化技術 第7章第4節 )
(株)技術情報協会 2017年11月
画像取得・解析技術を用いた培養工程の安定化
吉田啓、加藤竜司( 担当: 共著 , 範囲: 動物細胞培養における分離・精製手法と自動化技術 第7章第8節)
(株)技術情報協会 2017年11月
培養細胞の非破壊的品質予測手法
藤谷将也、加藤竜司( 担当: 共著 , 範囲: 動物細胞培養における分離・精製手法と自動化技術 第8章第4節)
(株)技術情報協会 2017年11月
移植留置型の医療機器表面に再生能を付与する細胞選択的ペプチドマテリアル
蟹江慧、成田裕司、加藤竜司( 担当: 共著 , 範囲: 医療・診断をささえるペプチド科学 : 再生医療・DDS・診断への応用 (バイオテクノロジー) 第 IV 編第2 章 )
(株)シーエムシー出版 2017年10月
インフォマティクスを活用した細胞選択的ペプチド被覆型医療機器材料の設計
蟹江慧、成田裕司、加藤竜司( 担当: 共著 , 範囲: 医療用バイオマテリアルの研究開発)
(株)シーエムシー出版 2017年2月
細胞接着の性能を高める「ペプチド‐合成高分子」ハイブリット素材の開発
蟹江慧、栗本理央、荏原充宏、加藤竜司( 担当: 共著 , 範囲: バイオサイエンスとインダストリー)
バイオインダストリー協会 2016年11月
画像を用いた細胞加工物および培養工程の評価
加藤竜司、蟹江慧( 担当: 共著 , 範囲: 再生医療・細胞治療のための細胞加工物評価技術)
(株)シーエムシー出版 2016年10月
細胞画像情報処理解析を用いた培養細胞の品質評価
加藤竜司、清田泰次郎、備瀬竜馬( 担当: 共著 , 範囲: 第5節3次元ティッシュエンジニアリング~細胞の培養・操作・組織化から品質管理、脱細胞化まで~)
NTS出版 2015年2月
再生医療実現に向けた幹細胞培養工学の最前線
加藤竜司、清田泰次郎、備瀬竜馬( 担当: 共著 , 範囲: 生物工学会誌)
日本生物工学会 2014年9月
細胞品質管理のための細胞画像情報解析を用いた客観的評価法
佐々木寛人、加藤竜司( 担当: 共著 , 範囲: 動物細胞培養の手法と細胞死・増殖不良・細胞変異を防止する技術第3章7節 )
技術情報協会 2014年4月
細胞と化学の狭間に秘められた可能性-生体分子・高分子を用いたバイオマテリアル
蟹江慧、荏原充宏、加藤竜司( 担当: 共著 , 範囲: 化学)
化学同人 2014年4月
ペプチドアレイを用いたECMタンパク質由来機能性ペプチドの探索ストラテジーとその可能性
蟹江慧、加藤竜司( 担当: 共著 , 範囲: 化学と生物)
日本農芸化学会 2014年4月
大豆たん白質加水分解物の発酵特性へ寄与するペプチド輸送体の基質多選択性の解明
伊藤圭祐、本山貴康、北川さゆり、加藤竜司、河原崎泰昌( 担当: 共著 , 範囲: 大豆たん白質研究)
大豆たん白質研究会 2013年9月
Image-based cell quality assessment: Modeling of cell morphology and quality for clinical cell therapy, Chapter Computational modeling in tissue engineering
( 担当: 共著 , 範囲: Studies in Mechanobiology, Tissue Engineering and Biomaterials, Springer)
Springer 2012年5月
ヒトCollagen における細胞選択的ペプチドの分布
蟹江慧、成田裕司、桑原史明、佐竹真、本多勧、兼子博章、本多裕之、加藤竜司( 担当: 共著 , 範囲: 高分子論文集)
高分子学会 2012年3月
長期追跡健康診断データにおける遺伝・環境要因を用いた生活習慣病リスク決定法
牛田泰徳、加藤竜司、谷村大輔、井澤英夫、安井健二、高瀬智和、吉田安子、川瀬三雄、吉田勉、室原豊明、本多裕之( 担当: 共著 , 範囲: 生物工学会誌)
日本生物工学会 2010年10月
医療機器コーティングのためのペプチドマテリアル
蟹江慧、加藤竜司、成田裕司、本多裕之( 担当: 共著 , 範囲: バイオサイエンスとインダストリー)
財団法人バイオインダストリー協会 2010年9月
培養システムの意義と役割 培養のインテリジェント化
加藤竜司、塩野博文( 担当: 共著 , 範囲: 細胞治療・再生医療のための培養システム第5編)
(株)シーエムシー出版 2010年1月
コレステロール低下機能性食品のためのカタログペプチドアレイによる胆汁酸結合ペプチド探索
加藤竜司、蟹江慧、加賀千晶、大河内美奈、長岡利、本多裕之( 担当: 共著 , 範囲: New Food Industry)
株式会社食品資材研究会 2009年4月
心理・背景因子データからの妊産期うつ病発症リスク診断
冨田康之、加藤竜司、野坂幸世、武藤裕紀、富田真紀子、金井篤子、村瀬聡美、後藤節子、尾崎紀夫、本多裕之( 担当: 共著 , 範囲: 生物工学会誌)
日本生物工学会 2008年10月
生物情報解析を利用した機能性ペプチドの探索
加賀千晶、大河内美奈、加藤竜司、本多裕之 ( 担当: 共著 , 範囲: FRAGRANCE JOURNAL)
フレグランスジャーナル社 2008年3月
細胞測定用ペプチドアレイ
加賀千晶、野村茂幸、大河内美奈、加藤竜司、本多裕之( 担当: 共著 , 範囲: マイクロアレイ・バイオチップの最新技術)
(株)シーエムシー出版 2007年12月
再生医療の審美へのアプローチ ~線維芽細胞の細胞特性と培養法~
加藤竜司、蛯沢克己、各務秀明( 担当: 共著 , 範囲: 再生医療とインプラント-究極のQOL向上医療を目指して- 第4章)
(株)クインテッセンス 2007年9月
動物実験代替のためのバイオリアクターを用いた3次元組織培養~
加藤竜司、本多裕之( 担当: 共著 , 範囲: 動物実験代替のためのバイオマテリアルデバイス 第4章8節)
(株)シーエムシー出版 2007年9月
歯槽骨再生の基礎 ~再生医療をとりまく法的枠組み~
各務秀明、加藤竜司( 担当: 共著 , 範囲: 再生医療とインプラント-究極のQOL向上医療を目指して- 第2章)
(株)クインテッセンス 2007年9月
細胞移植による美容医療を行うにあたって
各務秀明、加藤竜司( 担当: 共著 , 範囲: 再生医療と美容 III章)
(株)クインテッセンス 2007年4月
再生医療における細胞品質管理を目指した細胞画像データへの多変量解析の有効性
加藤竜司、山本若菜、各務秀明、上田実、本多裕之( 担当: 共著 , 範囲: ソフトウェアバイオロジー)
日本化学工学会情報科学分科会 2007年3月
ゲノム工学~プロテオーム編 第4章 ペプチドアレイ
國松己歳、加藤竜司、本多裕之( 担当: 共著 , 範囲: ゲノム医学)
メディカルレビュー社 2005年2月
ペプチドチップを用いた適合生体分子の探索 Functional peptide discovery by peptide chip
加藤竜司、本多裕之( 担当: 共著 , 範囲: バイオサイエンスとインダストリー)
財団法人バイオインダストリー協会 2004年7月
加藤竜司( 担当: 単著 , 範囲: 研究紹介WebメディアLaborify)
Laborify 2019年3月
ナノバイオテクノロジーを支えるインフォーマティクス
本多裕之, 加藤竜司( 担当: 共著 , 範囲: ナノバイオテクノロジーの最前線 第4章)
(株)シーエムシー出版 2004年10月
JIS Q 2101の実践的解釈 招待有り
加藤竜司
細胞製造コトづくり拠点細胞製造コトづくり講座「細胞製造標準化促進コース」 2025年3月24日
QbD実現におけるPATとしての最新細胞画像解析 招待有り
加藤竜司
シンポジウム28 「細胞加工製品製造のためのQbDアプローチ」、第24回日本再生医療学会総会 2025年3月22日
JIS Q 2101~細胞製造安定化のための標準~ 招待有り
加藤竜司
シンポジウム16「国際標準に基づく製品認証」 、第24回日本再生医療学会総会 2025年3月21日
細胞製造品質管理のための積極的なDXに向けて~細胞画像AI解析の応用~ 招待有り
加藤竜司
RINK festival 2025, SessionB:AIが切り拓く再生医療の未来 2025年2月14日
細胞培養の効率化技術の細胞農業への応用 招待有り
加藤竜司
細胞農業セミナー「細胞農業の最新動向と培養技術の進展に向けた課題」 2024年12月16日
標準化に向けた取り組み 招待有り
加藤竜司
AMED QbDに基づく再生医療等製品製造の基盤開発事業 成果報告会(公開シンポジウム) 2024年12月11日
再生医療・組織工学に学ぶ再生促進型医療機器材料の設計 招待有り
加藤竜司
物質科学特論セミナー 2024年11月20日
AI画像解析を活用した細胞機能性評価の定量化とデータ活用 招待有り
加藤竜司
学振R031ハイブリッド量子ナノ技術委員会第18回研究会 2024年11月1日
QbDに基づく細胞製造工程開発を実現する先端工学技術 招待有り
加藤竜司
令和6年度AMED 再生・細胞医療・遺伝子治療プロジェクト研究交流会 2024年9月30日
Morphology-based label-free phenotypic screening for the enhancement of drug screening 招待有り 国際会議
Ryuji Kato
Symposium “De novo platform technologies for biopharmaceutical engineering", The Korean Society for Biotechnology and Bioengineering(KSBB) fall meeting 2024 2024年9月26日
細胞製造産業を支える次世代人材の育成に向けて 招待有り
加藤竜司
シンポジウム:次世代のバイオ産業を支える人材育成システムと産学連携の課題と展望【本部企画】、第76回日本生物工学会大会 2024年9月10日
細胞製造の産業化に向けた標準化 招待有り
加藤竜司
シンポジウム:細胞製造産業に向けた標準化の最前線 ~細胞培養の標準とは何か~、第76回日本生物工学会大会 2024年9月9日
「細胞の形」を用いた治療薬探索 AI 技術の開発 招待有り
加藤竜司
シンポジウム:データ駆動型バイオツールの新展開、第76回日本生物工学会大会 2024年9月9日
再生医療のための画像解析AI技術における最新の取り組み 招待有り
加藤竜司
医工学シンポジウム 2024年7月3日
Label-free image-based analysis for cell manufacturing and tissue engineering 招待有り 国際会議
Ryuji Kato
7th Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society (TERMIS) World Congress 2024 2024年6月27日
大量培養に向けたデータ解析の応用について 招待有り
加藤竜司
第23回日本再生医療学会総会、共催学術セミナー24 2024年3月23日 第23回日本再生医療学会総会
Process Analysis Technologyとしての細胞画像解析 招待有り
加藤竜司
第23回日本再生医療学会総会、シンポジウム20細胞製造の安定化に向けた最新技術 2024年3月22日 第23回日本再生医療学会総会
JISとしての細胞製造マネジメントシステムの開発 招待有り
加藤竜司
第23回日本再生医療学会総会、シンポジウム20標準 ~アカデミアと産業界をつなぐためのツール~ 2024年3月21日 第23回日本再生医療学会総会
バイオ計測としての画像解析AI技術と細胞製造マネジメントへの応用 招待有り
加藤竜司
バイオ技術コンソーシアム(JMAC)第164回定例会特別講演会 2024年2月13日 バイオ技術コンソーシアム(JMAC)
データサイエンスを応用した細胞ものづくりと産業的発展 招待有り
加藤竜司
岡山地区化学工学懇話会 第74回コロキウム 2024年1月25日 岡山地区化学工学懇話会
Intelligent Integration of Image Processing, AI, and Lab Automation Technologies for Morphology-based Cell Quality Assessment 国際会議
Ryuji Kato
16th Asian Congress on Biotechnology(ACB2023) 2023年10月18日 16th Asian Congress on Biotechnology(ACB2023)
Morphology-based quality control and intelligent process management for cell-based product manufacturing 招待有り 国際会議
Ryuji Kato
2023年9月4日
細胞製造の標準開発と細胞のためのQbDに向けて 招待有り
加藤竜司
ジャパン・ティッシュエンジニアリング 特別講演 2023年8月1日 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
Morphology-based cell quality control for AI-guided iPSC manufacturing 国際会議
Ryuji Kato
The 28th Symposium of Young Asian Biological Engineers’ Community 2023年7月19日 The 28th Symposium of Young Asian Biological Engineers’ Community
Morphology-based label-free image analysis for data-driven culture optimization 招待有り 国際共著 国際会議
Ryuji Kato
Annual Spring Meeting of the Korean BioChip Society 2023 2023年6月2日 the Korean BioChip Society 2023
Cell-selective surface design using short-peptides and data science 国際共著 国際会議
Ryuji Kato
Korea-Japan Joint Meeting on Biomolecules and Nano-particles 2023年5月26日 Korea-Japan Joint Meeting on Biomolecules and Nano-particles
Risks and benefits of introducing AI in Regenerative Medicine – How to bridge wet and dry approaches – 招待有り 国際共著 国際会議
Ryuji Kato
Symposium 52, Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society (TERMIS)2023 EU chapter 2023年3月31日 Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society (TERMIS)2023 EU chapter
QbDコンセプトに基づくイメージング・AIを活用した工程開発・品質管理の可能 招待有り
加藤竜司
第22回日本再生医療学会総会 シンポジウム19 2023年3月24日 第22回日本再生医療学会総会
イントロダクション:再生医療実用化に向けたイメージングに期待されること 招待有り
加藤竜司
第22回日本再生医療学会総会 シンポジウム28 2023年3月25日 第22回日本再生医療学会総会
DX challenge for designing consistent process for cell-based product manufacturing 招待有り 国際会議
Ryuji Kato
The 11th Japan-China Symposium on Chemical Engineering 2023年3月17日
Data-driven Biotechnology in the recent Japanese Academia-Industry Collaborations 招待有り 国際共著 国際会議
Ryuji Kato
2023年1月26日
Standardization in Cell Processing Management 招待有り
2022年12月16日
iPS細胞安定製造に向けたQbDコンセプトに基づくプロセス解析 招待有り
加藤竜司
日本生物工学会中部支部主催2022年度第9回Chubu懇話会 2022年12月15日 日本生物工学会中部支部
再⽣医療産業化に向けた画像情報解析技術による細胞品質管理 招待有り
加藤竜司
第30回Link-Jオンラインネットワーキング・トーク 2022年11月22日 iGCORE
QbDを志向した画像解析を用いたiPS細胞培養モニタリング 招待有り
加藤竜司
日本動物実験代替法学会 第35回大会 2022年11月20日 日本動物実験代替法学会
Morphology-based drug effect profiling for delicate label-free phenotypic screening
2022年10月25日
近赤外光イメージング解析によるフェロイド品質モニタリングの可能性
加藤竜司、林咲希、永井美希、蟹江慧、五十嵐陽子、本村麻子、菅沼寛
第74回日本生物工学会(2022) 2022年10月17日 日本生物工学会
細胞培養DX~高品質な治療用細胞を得るためには~ 招待有り
加藤竜司
JSRMR2022第4回日本再生医療とリハビリテーション学会学術大会 2022年9月24日 日本再生医療とリハビリテーション学会学術大会
QbDに向かう細胞培養DXの重要性 招待有り
加藤竜司
第35回 日本動物細胞工学会2022年度大会 (JAACT2022) 2022年7月26日 日本動物細胞工学会
Image-based label-free analysis for quantitative and real-time understanding of cellular status 招待有り 国際会議
Ryuji Kato
Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society (TERMIS) European Chapter Conference 2022 2022年6月28日 Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society (TERMIS) European Chapter
QbDに重要な画像情報を用いたプロセスモニタリング 招待有り
加藤竜司
第21回日本再生医療学会本会 シンポジウム20「QbDに学ぶ細胞培養プロセスの制御と管理」 2022年3月19日
細胞品質管理におけるAI活用とデータ品質 招待有り
加藤竜司
第21回日本再生医療学会 シンポジウム37「再生医療におけるAI技術の応用」 2022年3月18日
画像を用いた細胞培養における in process 評価の重要性 招待有り
加藤竜司
第 66 回 バイオ・マイクロ・ナノテク研究会 2022年3月18日
細胞製品製造品質管理に向けたDXへの試み 招待有り
加藤竜司
化学工学会第87年会 SS-1 日本の産業を支える技術イノベーション 2022年3月17日
QbDに基づく細胞形態情報解析による品質管理 招待有り
加藤竜司
幹細胞のための培養法・培養工学に関するコンソーシアム 第5回シンポジウム 2021年11月27日
Morphological non-invasive evaluation of spheroids 招待有り 国際会議
Ryuji Kato
The 26th Symposium of Young Asian Biological Engineers' Community (YABEC) 2021 2021年11月18日
Image-based quantitative evaluation of mechanical stress effect on iPSC automatic culture 招待有り 国際会議
Ryuji Kato
6th World Congress Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society (TERMIS) 2021 SymposiumET8 "Geometrical and Topographical cues for cells and scaffolds in Regenerative Medicine" 2021年11月17日
生体イメージングを支える細胞画像情報解析 招待有り
加藤竜司
第38回医用高分子研究会講座 2021年11月15日
細胞産業の加速に向けた細胞形態情報を用いた細胞品質管理の可能性 招待有り
加藤 竜司
東北大学学際科学フロンティア研究所研究セミナー 2021年10月15日 東北大学学際科学フロンティア研究所
神経細胞研究におけるAI関連技術を用いた挑戦 招待有り
加藤 竜司
協和キリン株式会社主催Neurological Disease Forum ~For Young Neurologist~ 2021年8月26日 協和キリン株式会社
インフォマティクスを活用したデータ駆動型細胞培養への取り組み 招待有り
加藤 竜司
JACI(新化学技術推進協会)ライフサイエンス部会材料分科会勉強会 2021年8月11日 JACI(新化学技術推進協会)ライフサイエンス部会材料分科会
細胞品質管理に向けたインプロセス計測モダリティとしての非破壊イメージング解析 招待有り
加藤竜司
日本再生医療学会 シンポジウム19 「再生医療開発基盤としてのイメージング技術のフロンティア」 2021年3月13日 第20回日本再生医療学会総会
細胞画像情報解析からの間葉系幹細胞免疫抑制品質の非破壊予測
今井祐太、蟹江慧、加藤竜司
第20回日本再生医療学会総会 2021年3月11日 第20回日本再生医療学会総会
細胞画像からの定量化による培養細胞メンテナンスの可能性
今井祐太、加藤竜司
第20回日本再生医療学会総会 2021年3月11日 第20回日本再生医療学会総会
細胞培養自動化に向けて ~細胞製造現場の観点から~ 招待有り
加藤竜司
第10回 超異分野学会 本大会 2021年3月5日
生体組織構築のインプロセスモニタリングと品質管理 招待有り
加藤竜司
ダイナミック組織研究会 招待講演 2021年2月12日
細胞を育てるための化学(基礎編)、細胞培養を支える培養界面設計とインフォマティクス(応用編) 招待有り
加藤竜司
九州大学先導物質化学研究所 特別講義(非常勤講師) 2021年2月9日
生きた薬を創る ~最新の創薬科学~ 招待有り
加藤竜司
静岡理工科大学 令和2年度 第2回公開講座【開学30周年記念事業】 2021年1月30日
AIを活用した創薬の取組み 招待有り
加藤竜司
日本神経学会主催 産学官創薬スクール 2021年1月22日
創薬研究・細胞培養における画像情報解析の意義 招待有り
加藤竜司
科学技術交流財団・招待講演 2021年1月18日
画像情報解析を用いた「細胞の形」の活用 招待有り
加藤竜司
日本薬学会東海支部講演会 2021年1月14日
再生医療研究×AI ~AIを製造に活かすには~ 招待有り
加藤竜司
AMED 再生・細胞医療・遺伝子治療研究開発交流会 セッションシンポジウム 2020年12月21日
細胞培養界面の理解と設計 招待有り
加藤竜司
住友化学本社 招待講演 2020年12月10日
創薬研究におけるバイオ計測とインフォマティクス 招待有り
加藤竜司
電気学会調査専門委員会主催 招待講演会 2020年11月24日
再生医療の産業革命を目指して
加藤竜司
Beyond Next Ventures主催 BRAVE2020 2020年10月17日
細胞品質管理のためのSaaS型細胞情報管理システム
加藤竜司
BioJapan2020 2020年10月15日
細胞選択性界面デザインのためのインフォマティクス解析 招待有り
加藤竜司、蟹江慧
日本化学会講演会「インフォマティクス技術の導入から産業応用まで~高分子・機能性材料・バイオ・半導体~」 2020年9月25日
データ数が制限された品質予測モデルのためのデータ精錬技術開発
木村和恵、竹本悠人、蟹江慧、加藤竜司
生物工学若手会の第二回オンラインセミナー 2020年8月22日
細胞接着ペプチドにおける物性リンカーとの組み合わせの網羅検証
藤本瑛代、蟹江慧、緒方藍歌、成田裕司、加藤竜司
生物工学若手会の第二回オンラインセミナー 2020年8月22日
再生医療における品質管理 招待有り
加藤竜司
リバネス主催 第1回 インナーリソース ナレッジセミナー 「再生医療」 2020年6月8日
iPS細胞自動培養における播種工程の計測と理解
蟹江慧、酒井徹平、今井祐太、牧野穂高 、久保寛嗣 、加藤竜司
化学工学会 第85回年会 2020年3月15日
細胞形態情報解析を用いた非破壊的高感度フェノタイプアッセイ 招待有り
加藤竜司
iCell ユーザーミーティング 2020 2020年2月21日
再生医療用細胞製造における画像品質管理の可能性 招待有り
加藤竜司
慶応JKiCセミナー 2020年1月21日
hiPSおよびMPSを用いた細胞評価支援技術としての画像情報解析の可能性 招待有り
加藤竜司
2019年度シンポジウム「細胞アッセイ技術の現状と将来」 2020年1月20日
AIによる高純度肝要系幹細胞の品質検査高度化の調査研究
加藤竜司
NEDO AI&ROBOT NEXT シンポジウム 2020年1月16日
Cell morphometry analysis for non-invasive evaluation for cellular models 招待有り 国際会議
Ryuji Kato
Special Lecture in Bond University 2019年12月20日
Imaging and AI technology for non-invasive evaluation to control cell quality 招待有り 国際会議
Ryuji Kato
Australia-Japan Funding (AJF) Symposium: Exploiting technologies for personalised and precision medicine 2019年12月18日
AI-based early prediction of post-performance of human mesenchymal stem cells after cryopreservation 招待有り 国際会議
25th Young Asian Biological Engineers’ Community (YABEC 2019) 2019年11月23日
近赤外光情報を用いたスフェロイドの非破壊的品質評価
永井美希,山本涼平,渋田真結,蟹江慧,五十嵐陽子,菅沼寛,加藤竜司
動物実験代替法学会第32回大会 2019年11月21日
細胞形態情報解析による神経系ヘテロ細胞集団の化合物応答プロファイリング
今井祐太、吉田啓、蟹江慧、 飯田円、 勝野雅央、加藤竜司
動物実験代替法学会第32回大会 2019年11月21日
がんスフェロイドの画像解析を用いた評価技術の開発
加田ゆり子、渋田真結、加藤寛人、 日下部涼子、蟹江慧、藤井元、 武藤倫弘、松井裕史、金森敏幸、 柳沢真澄、杉浦慎治、加藤竜司
動物実験代替法学会第32回大会 2019年11月20日
再生促進型表面設計を目指した細胞選択的ペプチド 招待有り
加藤竜司
第36回医用高分子研究会講座講演 2019年11月8日
再生医療・創薬分野を支援するAI関連技術の可能 招待有り
加藤竜司
京都産業21 第2回ライフサイエンス・ビジネスセミナー 2019年10月30日
再生医療用細胞製造における画像情報を用いた品質管理 招待有り
加藤竜司
日本再生医療学会第1回秋季科学シンポジウム Remarkable Papersセッション 2019年10月18日
Measurement and modelling of cell shape for evaluating cellular function 招待有り 国際会議
Ryuji Kato
EORS (European Orthopaedic Research Society) 2019 2019年10月3日
Cell-selective peptide functionalized polysaccharide-collagen hybrid material for medical application 国際会議
Wang Yue, Kei Kanie, Kyoshiro Kaneko, Ayako Sugimoto, Aika Ogata, Yuji Narita, Ryuji Kato
APCchE2019 2019年9月26日
細胞形態情報解析を応用した細胞医薬品の品質管理 招待有り
加藤竜司
RINK第1回公開フォーラム2019 「遺伝子治療」&「IT×再生医療」 2019年9月4日
細胞形態情報解析を用いた1細胞~細胞集団の応答性の解析 招待有り
加藤竜司
JPrOS2019 / JES2019 日本プロテオーム学会2019年大会・第70回日本電気泳動学会総会 2019年7月26日
AI-guided morphology-based non-invasive cell quality control system for enhancing cell manufacturing consistency 招待有り 国際会議
Ryuji Kato
TERMIS(Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society) EU chapter 2019 2019年5月27日
Image-based non-invasive quality evaluation for regenerative medicine products 招待有り 国際会議
Ryuji Kato
Sakura-Bio Symposium 2019年3月30日
画像解析を用いたリアルタイム細胞評価に向けたインフォマティクス
加藤竜司
第18回日本再生医療学会総会 2019年3月23日
形態的逸脱iPSクローンの生物学的プロファイル解析
吉田啓、長坂理紗子、館野浩章、小沼泰子、 伊藤弓弦、 蟹江慧、 加藤竜司
第18回日本再生医療学会総会 2019年3月23日
非破壊的な細胞品質管理を実現する細胞画像解析技術の進展
加藤竜司
第18回日本再生医療学会総会 2019年3月22日
細胞形態情報解析を用いた神経系細胞の集団プロファイリング
今井祐太、吉田啓、蟹江慧、 飯田円、 勝野雅央、加藤竜司
第18会再生医療学会総会 2019年3月22日
細胞培養作業の数量的記述および理解のためのデータ解析
蟹江 慧、玉田 正樹、佐々木 寛人、池田 友里圭、加藤竜司
第18会再生医療学会総会 2019年3月22日
再生医療産業化を目指した画像情報解析の取り組み 招待有り
加藤竜司
山梨大学・発生工学技術・開発セミナー 2019年1月28日
再生医療における画像情報解析を用いた品質管理の可能性 招待有り
加藤竜司
医工学フォーラム 2018年11月30日
Morphology-based image analysis of cellular responses for their non-invasive profiling 招待有り 国際会議
Ryuji Kato
2018年11月29日
iPS細胞培養プロセス評価のための形態情報解析
吉田啓、長坂理紗子、館野浩章、小沼泰子、 伊藤弓弦、 蟹江慧、 加藤竜司
2018年度日本生物工学会 中部支部例会 2018年11月20日
再生医療産業化に向けた画像を用いた細胞品質管理の可能性 招待有り
加藤竜司
第3回岐阜大学しずい細胞プロジェクトイノベーション研究会 2018年10月12日
Image-based Cell Morphology Analysis for Enabling Cell Manufacturing in Regenerative Medicine 招待有り 国際会議
Ryuji Kato
2018 The Korean Society for Biotechnology and Bioengineering (KSBB) Interna-tional Academia-Industry Joint Meeting 2018年10月11日
再生医療における画像情報解析を用いた品質管理の可能性 招待有り
加藤竜司
第3回再生医療産学連携バリューチェーンセミナー・FIRM基準説明会 2018年10月1日
細胞形態計測による細胞フェノミクス解析 招待有り
加藤竜司
第70回日本生物工学会大会 2018年9月8日
細胞形態情報解析を用いた細胞培養評価 招待有り
加藤竜司
日本セラミックス協会第31回秋季シンポジウム 2018年9月5日
Morphology-based iPS cell colony evaluation for cell manufacturing 招待有り 国際会議
Ryuji Kato
24th iCeMS International Symposium 2018年9月4日
治療用細胞製造における細胞画像情報解析を用いた品質管理 招待有り
加藤竜司
第39回日本炎症・再生医学会 2018年7月12日
細胞形態情報を用いたノンラベルイメージサイトメトリーの可能性 招待有り
加藤竜司
第28回日本サイトメトリー学会 2018年5月27日
細胞形態画像計測を用いた再生医療用細胞培養の管理 招待有り
加藤竜司
第5回SBJシンポジウム 2018年5月25日
細胞加工・製造プロセスの機械化・自動化における情報活用 招待有り
加藤竜司
第17回日本再生医療学会総会ランチョンセミナー「人工知能時代の細胞加工・製造プロセスを考える」 2018年3月23日
細胞画像情報解析を用いた治療用細胞製造のための品質管理技術の開発 招待有り
加藤竜司
第17回日本再生医療学会総会受賞講演 2018年3月22日
細胞形態情報解析を用いた間葉系幹細胞培養プロセスにおける品質工学的逸脱管理
今井祐太、吉田啓、松本恵、蟹江慧、加藤竜司
第17回日本再生医療学会総会 2018年3月22日
細胞形態プロファイリングを用いた培養面コーティング剤の機能性評価
藤谷将也、蟹江慧、加藤竜司
第17回日本再生医療学会総会 2018年3月22日
細胞形態情報解析による凍結ストレスに対する間葉系幹細胞品質変化の評価
松本恵、蟹江慧、清水一憲、本多裕之、加藤竜司
第17回日本再生医療学会総会 2018年3月22日
細胞画像情報を用いた細胞品質管理の可能性と課題 招待有り
加藤竜司
第17回日本再生医療学会総会シンポジウム26:「インフォマティクスが拓く再生医療」 2018年3月22日
細胞選択的骨化促進ペプチドの探索と機能性評価
蟹江慧,栗本理央,田婧,緒方藍歌,宇都甲一郎,本多裕之,成田裕司,荏原充宏,加藤竜司
第17回日本再生医療学会総会 2018年3月21日
細胞画像情報を用いた医療用細胞製造プロセス管理の可能性 招待有り
加藤竜司
精密工学会2018年度春季大会 2018年3月16日
画像情報処理を用いた非侵襲細胞品質評価 招待有り
加藤竜司
第5回レクチン利用技術研究会・ワークショップ 2018年1月15日
Interaction between Cellular Adhesion and Surface Physicochemical Properties 招待有り 国際会議
Ryuji Kato
IGER International Symposium on Cell Surface Structures and Functions 2017 2017年11月30日
3次元培養細胞塊の画像解析と自動ピッキングシステム開発 招待有り
加藤竜司
細胞凝集研究会2017 2017年11月17日
再生医療における細胞品質画像解析事業の可能性 招待有り
加藤竜司
ひろしま医療関連産業研究会特別講演 2017年10月31日
画像情報処理を用いた再生医療用製品製造工程における非破壊的品質理技術の開発 招待有り
加藤竜司
日本生物工学会受賞講演(照井賞) 2017年9月12日
細胞画像情報解析を用いた細胞品質管理の可能性 招待有り
加藤竜司
第7回細胞再生医療研究会 2017年8月19日
細胞培養における画像解析を用いた品質管理 招待有り
加藤竜司
情報機構主催「細胞培養セミナー」(AC170831) 2017年8月3日
Label-free Morphology-based Cellular Evaluation Based on Phase-contrast Microscopic Images 招待有り 国際会議
Ryuji Kato
International Drug Discovery Science and Technology (IDDST) 2017 2017年7月25日
実験データ解析の可能性 招待有り
加藤竜司
株式会社ジェイテクト特別講演 2017年7月21日
細胞画像情報を用いた非破壊評価の可能性 招待有り
加藤竜司
2017年製薬放射線コンファレンス研修会開催 2017年6月22日
インフォマティクスを用いた研究効率化と原因究明の可能性 招待有り
加藤竜司
東海トライボロジー研究会(第103回) 2017年6月20日
再生医療用細胞および組織の画像情報を用いた品質管理の可能性 招待有り
加藤竜司
日本動物細胞工学会 2017年3月30日
動画撮影を利用した細胞培養作業数値化と作業効率化検証
蟹江慧、玉田正樹、佐々木寛人、加藤竜司
第16回日本再生医療学会総会 2017年3月9日
画像取得・解析技術を用いた培養工程の安定化 招待有り
加藤竜司
第16回日本再生医療学会総会 2017年3月9日
細胞播種における攪拌操作最適化のための流体シミュレーション
松岡毅、蟹江慧、山田剛史、吉田啓、藤谷将也、杉本礼子、佐々木寛人、加藤竜司
第16回日本再生医療学会総会 2017年3月9日
iPS研究実用化開発の現状と動向 招待有り
加藤竜司
第5回超異分野学会・シンポジウム 2017年3月2日
Map analysis of combinational effects between viscoelastic polymers and peptides for design of selective cell adhesion surface 国際会議
Rio Kurimoto, Kei Kanie, Koichiro Uto, Shun kawai, Masanobu Naito, Ryuji Kato and Mitsuhiro Ebara
2017年3月1日
生体内における組織再生を促進する細胞選択的ペプチド
蟹江慧、加藤竜司
平成28年度 中部地区 医療・バイオ系シーズ発表会 2016年12月8日
Image-based Cell Quality Evaluation for Regenrative Medicine Products 招待有り 国際会議
2016年11月30日
細胞を用いた創薬における細胞培養工程から得られるデータの活用 招待有り
加藤竜司
CBI学会2016年大会 2016年10月27日
治療用細胞品質向上のための培養環境データの活用 招待有り
加藤竜司
シンポジウム「時空間バイオインテグリティ」 2016年6月22日
顕微鏡画像を用いた細胞形態情報解析による非破壊評価 招待有り
加藤竜司
日本組織培養学会第89回大会 2016年5月25日
細胞画像情報解析による細胞搬送状態の影響評価
藤谷将也、加藤竜司
第15回日本再生医療学会総会 2016年3月17日
細胞形態情報解析を用いた再生医療用MSCにおける凍結ダメージの定量評価
松本恵、蟹江慧、清水一憲、本多裕之、加藤竜司
第15回日本再生医療学会総会 2016年3月17日
細胞形態情報解析を用いた細胞製品製造における品質管理 招待有り
加藤竜司
第5回超異分野学会 2016年3月13日
細胞品質管理の自動化へ向けた取組みと将来展望-再生医療等製品製造産業に関わる工学技術- 招待有り
加藤竜司
木原記念横浜生命科学振興財団「先端バイオ関連産業への未来の参入余地を考える」 2016年2月25日
再生医療葉細胞の培養と品質管理 招待有り
加藤竜司
第11回日本獣医再生医療学会 2016年2月7日
再生医療における産業革命に向けて
加藤竜司
KKE Vision 2015 2015年11月20日
細胞画像情報解析を用いた細胞品質管理の可能性 招待有り
加藤竜司
再生医療分野 若手研究者交流会 池田理化賞受賞記念会 2015年10月31日
非染色顕微鏡画像を用いたリアルタイムフェノタイプスクリーニングの可能性 招待有り
加藤竜司
CBI学会2015年大会 2015年10月29日
再生医療を支える培養プロセスからの情報計測と活用 招待有り
加藤竜司
第67回日本生物工学会大会 2015年10月28日
細胞形態情報解析を用いたリアルタイム細胞応答評価の可能性 招待有り
加藤竜司
第67回日本生物工学会大会 2015年10月27日
1細胞から得られる形態情報を用いた品質評価 招待有り
加藤竜司
第67回日本生物工学会大会 2015年10月26日
細胞品質管理のための細胞画像情報処理技術 招待有り
加藤竜司
第33回ヒト細胞学会 2015年8月23日
画像情報処理技術を用いた再生医療における細胞品質管理 招待有り
加藤竜司
日本生物工学会中部支部主催 第4回CHUBU懇話会 2015年8月21日
細胞形態情報解析を用いたリアルタイムな細胞評価と薬剤スクリーニング 招待有り
加藤竜司
田辺三菱製薬株式会社 特別講演会、開催場所:田辺三菱製薬株式会社横浜総合研究所 2015年6月4日
細胞形態情報を用いた幹細胞制御因子の早期予測スクリーニング
加藤竜司、藤谷将也、佐々木寛人、岡田法大、蟹江慧、清田泰次郎、本多裕之
第14回 日本再生医療学会総会 2015年3月21日
細胞形態情報を用いたiPS細胞培養手技の定量化
加藤竜司、吉田啓、岡田光加、長坂理紗子、佐々木寛人、蟹江慧、菅三佳、柳原佳奈、福田隆之、清田泰次郎、古江美保
第14回 日本再生医療学会総会 2015年3月20日
短鎖ペプチド全網羅マイクロアレイを用いた細胞培養基質としてのペプチド評価
蟹江慧、堀川美希、河合駿、緒方藍歌、成田裕司、本多裕之、加藤竜司
第14回 日本再生医療学会総会 2015年3月19日
画像を用いた細胞品質評価における細胞形態特徴量の構造化解析
河合駿、竹内一郎、今村基樹、蟹江慧、加藤竜司
化学工学会 第80年会 2015年3月19日
高分子材料の物性変化による短鎖ペプチ ドの細胞接着性への影響
栗本理央、蟹江慧、井戸田直和、宇都甲一郎、荏原充宏、塚原剛彦、原光生、永野修作、成田裕司、本多裕之、加藤竜司
化学工学会 第80年会 2015年3月19日
骨髄由来および脂肪組織由来間葉系幹細胞の継代培養における品質劣化モニタリング
佐々木寛人、蟹江慧、澤田留美、清田泰次郎、本多裕之、加藤竜司
第14回 日本再生医療学会総会 2015年3月19日
動画撮影を利用した細胞培養作業数値化による作業効率化
蟹江慧、佐々木寛人、玉田正樹、加藤竜司
第14回 日本再生医療学会総会 2015年3月19日
iPS細胞コロニーにおける局所的性質解析のためのテクスチャプロファイリング
佐藤理紗、佐々木啓、長坂理紗子、姜時友、蟹江慧、加藤竜司、湯浅哲也
第14回 日本再生医療学会総会 2015年3月19日
再生医療向け培養細胞の画像を用いた品質管理技術と培養技術標準化への可能性 招待有り
加藤竜司
“未来へのバイオ技術”勉強会 2015年3月12日
再生医療のためのバイオマテリアルの評価と設計 招待有り
加藤竜司
東北大学多元物質科学研究所・特別講演 2015年2月2日
iPS細胞品質管理のためのコロニー画像情報解析 招待有り
加藤竜司
第5回 スクリーニング学研究会 2014年11月28日
細胞画像情報解析を用いた再生医療における培養基材評価 招待有り
加藤竜司
大日本印刷株式会社・特別講演会 2014年9月3日
細胞画像情報解析を用いた再生医療における品質管理の可能性
加藤竜司
再生医療イノベーションフォーラム(FIRM)・特別講演会 2014年5月20日
細胞培養画像情報解析を用いた再生医療用細胞の品質管理 招待有り
加藤竜司
日本医工学治療学会第30回学術大会 2014年3月23日
細胞品質管理のための画像情報解析の可能性と課題 招待有り
加藤竜司
富士フイルム株式会社講演会 2014年1月23日
細胞形態画像解析を用いた非侵襲的分子評価 招待有り
加藤竜司
日本動物実験代替法学会26回大会 2013年12月20日
再生医療の産業化におけるボトルネック 品質管理~シーズとニーズ~ 招待有り
加藤竜司
愛知県産業労働部次世代産業室再生医療関連機器開発研究会講演会 2013年11月19日
再生医療実用化に向けた画像情報処理を用いた細胞品質管理 招待有り
加藤竜司
三井業際研究所再生医療技術調査委員会講演会 2013年11月12日
再生医療実用化に向けた医工連携技術開発の試み 招待有り
加藤竜司
東京大学化学生命工学専攻・談話会 2013年8月3日
Morphology-based Informatics for Non-invasive Evaluation of Cell Quality for the industrialization of Regenerative Medicine 招待有り 国際会議
Ryuji Kato
The 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC'13) 2013年7月6日
Orientation Based Segmentation for Phase-Contrast Microscopic Image of Confluent Cell 国際会議
Kei Sasaki, Tetsuya Yuasa, Hiroto Sasaki, Ryuji Kato
The 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC'13) 2013年7月5日
コンフレント細胞分化度評価のための細胞画像情報からの動的積算マップ法(MapIQ)
加藤竜司、梶浦圭一、蟹江慧、金美海、紀ノ岡正博、本多裕之
第12回日本再生医療学会 2013年3月21日
骨芽細胞成熟化促進ペプチドの網羅的スクリーニング法の開発
蟹江慧、鈴木庸元、成田裕司、本多裕之、加藤竜司
第12回日本再生医療学会 2013年3月21日
細胞動的情報解析による品質評価と再生医療への実用化促進
加藤竜司
第1回中部地区医療・バイオ系シーズ発表会 2012年12月4日
骨髄由来間葉系幹細胞の画像情報解析による骨分化度予測
加藤竜司、松岡史子、佐々木寛人、縣秀樹、各務秀明、清田泰次郎、本多裕之
第11回日本再生医療学会総会 2012年6月13日
細胞形態の客観的解析のための細胞認識手法
加藤竜司、坪井泰樹、佐々木寛人、蟹江慧、清田泰次郎、本多裕之
第11回日本再生医療学会総会 2012年6月13日
細胞画像情報解析を用いた再生医療のための細胞品質評価 招待有り
加藤竜司
第51回日本生体医工学大会 2012年5月10日
細胞計測を用いた細胞間相互作用の画像・遺伝子統合解析
2025年4月 - 2030年3月
CREST
加藤 竜司
担当区分:研究分担者 資金種別:競争的資金
配分額:4000000円
2 細胞計測技術によって個々の細胞間相互作用の時系列画像データを取得し、画像認識技術を用いてその画像データから分類した細胞を分取した後、1 細胞遺伝子解析を行うプロセスを開発する
AI画像解析を応用した細胞加工製品の品質評価技術の研究開発
2024年4月 - 2027年3月
医薬品等規制調和・評価研究事業
加藤 竜司
資金種別:競争的資金
配分額:8000000円
ヒト脊髄前駆細胞安定製造のための高度なプロセス開発と品質管理技術の開発 国際共著
2024年4月 - 2026年3月
二国間国際共同研究
担当区分:研究代表者 資金種別:競争的資金
配分額:4000000円
AI支援型MPSを用いたヒトiPS由来神経細胞による神経毒性試験法の開発
研究課題番号:22674402 2022年4月 - 2025年3月
化学物質のヒト健康影響を評価するためのin vitro代替試験法の実用化に向けた比較・検証研究
加藤 竜司
担当区分:研究分担者 資金種別:競争的資金
配分額:1000000円 ( 直接経費:1000000円 、 間接経費:1000000円 )
FLNAを標的とした進行性核上性麻痺の病態解明と治療法開発
研究課題番号:21444551 2021年4月 - 2024年3月
希少難治性疾患の克服に結びつく病態解明研究分野/希少難治性疾患の病態解明研究(病態解明)
加藤 竜司
担当区分:研究分担者 資金種別:競争的資金
配分額:1300000円 ( 直接経費:1000000円 、 間接経費:300000円 )
ヒトiPS細胞技術を用いた新たな心毒性評価法の開発と国際標準化
研究課題番号:21443894 2021年4月 - 2024年3月
国立研究開発法人日本医療研究開発機構 医薬品等規制調和・評価研究事業
加藤 竜司
担当区分:研究分担者 資金種別:競争的資金
配分額:650000円 ( 直接経費:500000円 、 間接経費:150000円 )
ヒト細胞加工製品の製造に向けたQbDに基づく管理戦略の構築と新たな核となるエコシステムの形成
研究課題番号:20351415 2020年11月 - 2025年3月
AMED: 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 QbDに基づく再生医療等製品製造の基盤開発事業
加藤竜司
担当区分:研究分担者
配分額:10000000円 ( 直接経費:7692308円 、 間接経費:2307692円 )
細胞画像情報解析を用いた培養機械化における品質管理デザインスペースの理解
研究課題番号:20319913 2020年7月 - 2023年3月
AMED: 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 医薬品等規制調和・評価研究事業
加藤竜司
担当区分:研究代表者 資金種別:競争的資金
配分額:4550000円 ( 直接経費:3500000円 、 間接経費:1050000円 )
SARS-CoV-2のみを識別する抗原ペプチドやその特異抗体を用いた早期・大量診断システムの開発
2020年4月 - 2021年3月
AMED: 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 ウイルス当感染症対策に資する医療機器・システム等の構築に向けた基礎研究支援
加藤竜司
担当区分:研究分担者
配分額:3900000円 ( 直接経費:3000000円 、 間接経費:900000円 )
連続生産等に適した高性能な国産細胞細胞株の開発
2018年4月 - 2021年3月
AMED: 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業
加藤竜司
担当区分:研究分担者
配分額:1300000円 ( 直接経費:1000000円 、 間接経費:300000円 )
研究課題/研究課題番号:23K08268 2023年4月 - 2026年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(C)
尾関 貴啓, 荏原 充宏, 宇都 甲一郎, 加藤 竜司, 成田 裕司, 緒方 藍歌, 蟹江 慧
担当区分:研究分担者
手術中の出血は、患者の生命を脅かすこともある危険な合併症であり、いかに迅速に止血するかが患者の予後を左右する。市販の局所止血剤(フィブリン糊やコラーゲン、トロンビンなど)の多くは生物由来成分で感染症や抗原性発現のリスクがあるため、非生物由来で止血操作性が良く、また多様な出血に対しても高い止血性能を有する、新たな局所止血材の開発が求められる。本研究では、血液凝固作用を持つ合成高分子メタクリルオキシエチルフォスファチジルセリン(MPS)とフィブリン形成促進機能性ペプチドを用いて新たな局所止血材を開発し、動物実験で有用性を明らかにする。
血液凝固ポリマー・ペプチド複合体を用いた局所止血材料の開発
2023年4月 - 2026年3月
科学研究費補助金 基盤研究C
尾関 貴啓
担当区分:研究分担者
生体タンパク模倣短鎖ペプチドの創成と低侵襲的大動脈瘤治療法開発の試み
研究課題/研究課題番号:22H03155 2022年4月 - 2025年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(B)
成田 裕司, 荏原 充宏, 宇都 甲一郎, 加藤 竜司, 緒方 藍歌, 六鹿 雅登, 蟹江 慧
担当区分:研究分担者
大動脈瘤に対する低侵襲治療法の開発として、間葉系幹細胞投与によるの臨床治験が米国で行われているが、細胞製剤は生物由来原料であるため、厳密な品質管理が求められるうえ、感染リスクや免疫反応などの有害事象が懸念される。一方で、ペプチド医薬は化学合成による安定した工業生産が可能である。本研究では、抗炎症作用をもつタンパクSLPIに由来する短鎖機能性ペプチド医薬を創成し、大動脈瘤に対する新たな低侵襲治療法を開発する。ペプチド医薬による治療効果が得られれは、患者に利する医学的意義は高く、国内外でも類を見ない治療法となる。また、本ペプチドは関節リウマチなどの慢性炎症疾患にも応用できる可能性がある。
生体吸収性ポリマーと機能性ペプチドの複合化による再生型癒着防止人工心膜の開発
研究課題/研究課題番号:21K08820 2021年4月 - 2024年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(C)
緒方 藍歌, 原 光生, 宇都 甲一郎, 加藤 竜司, 成田 裕司, 蟹江 慧
担当区分:研究分担者
本研究では、生体吸収性ポリマーに心膜構成細胞の機能を制御するペプチドを化学修飾した、自己心膜再生を促す「再生型癒着防止人工心膜」を開発し、その有用性を検討する。具体的に、生体吸収性ポリマーのポリカプロラクトン(PCL)を用いてシートを作成し物性評価を行ったのち、シートに機能性ペプチドを化学的に修飾する。中皮細胞および線維芽細胞をペプチド修飾シート上に播種して細胞接着性等を評価する。良好な結果が得られたら、ペプチド修飾シートを心膜癒着モデル動物で有用性を評価する。
心臓血管外科手術では、手技の複雑化やステージ手術等の増加に伴い、再手術症例が増加している。再手術時には心臓は周辺組織と癒着しており、癒着剥離操作は、手術手技の難易度を上げるだけでなく、剥離時の臓器損傷が致命的出血性合併症を招くことがある。また癒着は術後拡張障害を惹起し、HFpEFといった心不全の原因となる。現在臨床で使用されている人工心膜(ePTFE)は、開胸時に臓器損傷を回避する物理的遮蔽の役割は果たすが、癒着防止能力に乏しい。また、非吸収性材料のため体内に遺残して繊維化したり、感染の温床となりうる。正常心膜では、単層中皮細胞から分泌される滑液(心嚢液)が、臓器同士の摩擦を軽減し、癒着病態の中心であるフィブリン形成を防止する役割を持つ。従って、心膜組織を再生させることで癒着防止に寄与するであろうと考えた。本研究では、生体吸収性ポリマーに心膜構成細胞の機能を制御するペプチドを化学修飾した、自己心膜再生を促す「再生型癒着防止人工心膜」を開発し、その有用性を検討する。
本年度では、ポリカプロラクトン(PCL)とポリ乳酸(PDLLA)の共重合体 P(CL-DLLA)を用いてペプチド修飾を試みた。 P(CL-DLLA)は、非特異的に細胞が接着してしまうため、中皮細胞を接着させて線維芽細胞は接着を抑制させるようなポリマー表面構造改質が必要である。これまでにプラズマ処理とシラン化によるペプチド修飾の表面改質で線維芽細胞接着の低減がみられたが、ポリマー自体が分解が進んでいたことが判明した。新しいロットのポリマーで再度プラズマ処理とシラン化したところ、ポリマーが溶けてしまいペプチド修飾ができなくなった。したがって、別の表面処理方法を確立する必要が生じた。
ペプチド修飾のためのポリマー基材表面を改質する新たな方法の確立が課題であるが、当初の計画の通りに概ね進展しているため。
疎水性または浸水性のポリマーを用いて基材表面をスピンコートすることによる改質を図る。ペプチド修飾が成功したら、修飾されたペプチドを定量測定する。また、ペプチド修飾したシート上に中皮細胞および線維芽細胞を播種し、継時的に顕微鏡観察する。生存細胞数の測定を行い、細胞接着性および増殖能を評価する。
ヒト味覚・嗅覚受容体応答の網羅的解析によるフレーバープロファイリング技術の開発
研究課題/研究課題番号:21H02144 2021年4月 - 2024年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(B)
伊藤 圭祐, 加藤 竜司, 伊藤 創平, 中野 祥吾, 寺田 祐子
担当区分:研究分担者
食品のおいしさにおいて、味と香り(フレーバー)の知覚は重要である。本研究では、ヒト味覚・嗅覚受容体の応答を指標として食品の味と香りを客観的・定量的にプロファイリングできる新技術の確立を目指し、ヒト味覚・嗅覚受容体の新規網羅的解析法を開発する。
三次元培養により出現する腫瘍細胞の特性解析に基づいた新規肺がん治療標的の探索
研究課題/研究課題番号:21K08902 2021年4月 - 2024年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(C)
山本 寛斉, 豊岡 伸一, 冨田 秀太, 諏澤 憲, 江口 傑徳, 加藤 竜司
担当区分:研究分担者
三次元(3D)培養での腫瘍細胞は二次元(2D)培養と比べ、細胞間インタラクションが生体内に近く、腫瘍微小環境を反映していることが知られている。また、がん難治性に関与する幹細胞性の維持や治療抵抗性の評価にも従来の2D 培養によるアッセイ系より適している。申請者らは、その中でも腫瘍細胞の凝集形態には多様性があり、特にがんの悪性度が高い集団が存在することを発見した。本研究では、より生体内の環境を反映する3D 培養により肺がん細胞の特性を評価し、悪性度と関連する遺伝子を同定し、これを標的とする治療戦略の確立を目指す。
近年、免疫チェックポイント阻害剤の登場により、がん細胞周囲の微小環境(腫瘍微小環境)が治療標的として注目されている。三次元(3D)培養での腫瘍細胞は二次元(2D)培養と比べ、細胞間インタラクションが生体内に近く、腫瘍微小環境を反映していることが知られている。また、がん難治性に関与する幹細胞性の維持や治療抵抗性の評価にも従来の2D 培養によるアッセイ系よりも適している。申請者らは、その中でも腫瘍細胞の凝集形態には多様性があり、特にがんの悪性度が高い集団が存在することを発見した。本研究は、より生体内の環境を反映する3D 培養により肺がん細胞の特性を評価し、悪性度と関連する遺伝子を同定し、これを標的とする治療戦略の確立を目指すものである。
令和3年度は、肺がん細胞株 (n = 30) を用いて3D 培養による細胞凝集塊の形態学的特徴の確認を進め、Grape-like, Spheroid, Monolayer sheet, Other typeの4つに分類した。また、腫瘍学的特徴を明らかにするために、これらの形態学的特徴と増殖能・浸潤能・遊走能の表現型との関連について解析を進めたところ、Monolayer sheet typeの細胞株は浸潤能・遊走能がSpheroid typeの細胞株よりも高いという結果であった。また、各肺がん細胞株のin vivoでの腫瘍形成能をマウスモデルを用いて検討を進めている。
当初の予定であった、肺がん細胞株の3D 培養による細胞凝集塊の形態学的特徴を分類することができ、また形態学的特徴と、増殖能・浸潤能・遊走能という表現型との関連の解析も進めることができたため。
肺がん細胞株の形態学的特徴や表現型に関連する遺伝子を、網羅的遺伝子解析によって探索を行う予定である。遺伝子が同定された場合、治療標的となり得るか検証する予定である。
研究課題/研究課題番号:20K09124 2020年4月 - 2023年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(C)
伊藤 英樹, 荏原 充宏, 宇都 甲一郎, 加藤 竜司, 成田 裕司, 緒方 藍歌, 蟹江 慧
担当区分:研究分担者
骨切開を伴う手術では骨切断面から多くの出血を伴うため、一般的にはボーンワックスで骨切断面にパッキングする止血法が用いられている。しかしボーンワックスは非分解・非吸収性で、残存による骨癒合・治癒阻害や術後感染等の合併症、骨癒合・再生の遅延を助長する可能性がある。従って、新たな骨髄止血材料の開発は多くの患者に有益である。申請者らは、独自技術で開発したポリカプロラクトン(PCL)をベースとした生体吸収性ポリマーと骨再生誘導ペプチドによる新規骨髄止血材料を創出してきた。本研究では、材料の質的向上を図るため、各設計条件を見直す基礎研究を行い、前臨床研究も含めた動物実験にて有用性を検証する。
骨切開を伴う手術では骨切断面から多くの出血を伴うため、一般的にはボーンワックスで骨切断面にパッキングする物理的な止血法が用いられている。しかしボーンワックスは非分解・非吸収性であるため、残存による骨癒合・治癒阻害や術後感染等の合併症を助長する可能性がある。さらに骨癒合・再生の遅延は術後の社会復帰を妨げ、患者のQOLに影響を及ぼす。従って、これらが解決できる新たな骨切断面に用いる止血材料の開発は多くの患者に有益である。申請者らは、独自技術で開発したポリカプロラクトン(PCL)をベースとした生体吸収性ポリマーと骨再生誘導ペプチドによる新規骨髄止血材料を創出してきた。しかし、ポリマー、ペプチドの設計条件によって操作性や骨再生能に影響を及ぼすことが判明した。本研究では、材料の質的向上を図るため、各設計条件を見直す基礎研究を行い、さらに前臨床研究も含めた動物実験にて有用性を検証する。
これまでに、PCL、ポリ乳酸(PLLA)、ハイドロキシアパタイト(Hap)との混合比などを精密に設計することでボーンワックスに似た物理特性および操作性を持つポリマー基材:P(CL-DDLA)ーHapによる新規骨髄止血材を創出したが、ハイドロキシアパタイトは、粒径が骨分化誘導に影響することがわかった。粒径μmとnmの2種類を用い、間葉系幹細胞から骨分化誘導培養を行ったところ、μmのHapの方で分化促進した。また、新規止血剤(P(CL-DDLA)ーHap-peptide)の安全性試験として細胞毒性を調べた。ボーンワックスは中程度の毒性を示したが、新規止血剤は毒性を示さないことがわかった。
現在までの進捗状況として、品質向上のための検討としてポリマー物性の改善や細胞毒性がないこを示した。また、本年度の検討課題であったペプチド短鎖化の検討に着手しているが、まだ有意な結果が得られておらず、当初の計画より進捗がやや遅れていると判断した。
ペプチド短鎖化の検討を行う。In silicoおよびin vitroスクリーニングで得られた候補ペプチドは、ポリマー基材に混合して動物実験にて効果の判定を行う。
研究課題/研究課題番号:19H03737 2019年4月 - 2022年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(B)
碓氷 章彦, 荏原 充宏, 宇都 甲一郎, 加藤 竜司, 成田 裕司, 緒方 藍歌, 蟹江 慧
担当区分:研究分担者
大動脈瘤に対する人工血管置換術は侵襲が大きく、新たな低侵襲な治療法の開発が望まれる。我々は、これまでに間葉系幹細胞(MSC)静脈内投与による大動脈瘤治療の有効性を示してきた。治癒メカニズムにはMSCのパラクライン作用が示唆され、MSC産生因子の中に抗炎症作用・組織修復に関わる因子としてProgranulin(PGRN)およびSLPIを同定し、それらによる大動脈瘤治療効果の可能性を見出した。
本研究は、リコンビナントタンパクPGRN, SLPI投与による効果検証を行ったのち、合成ペプチド医薬として大動脈瘤治療の検討を行い、ペプチド医薬としての有効性を明らかにする。
研究課題/研究課題番号:15H04937 2015年4月 - 2019年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(B)
碓氷 章彦, 荏原 充宏, 加藤 竜司, 成田 裕司, 緒方 藍歌, 蟹江 慧
担当区分:研究分担者
大動脈瘤に対する人工血管置換術は侵襲が大きく、新たな低侵襲治療法の開発が望まれる。これまでに抗炎症作用を持つ間葉系幹細胞(MSC)による大動脈瘤径縮小効果を報告した。本研究では、MSC産生因子の中から抗炎症作用を持つタンパクprogranulin (PGRN)とSecretory Leukocyte proteinase inhibitor (SLPI)を同定した。これらタンパクを大動脈瘤モデルマウスに投与することにより、大動脈瘤進展抑制を認め、治療に有用であることを明らかにした。また、これらタンパクのアミノ酸配列をリファレンスに設計したペプチドは、in vitroにて抗炎症性効果を認めた。
これまでに間葉系幹細胞による大動脈瘤縮小効果を報告してきたが、幹細胞療法は投与した細胞の安全性を担保する必要があり、臨床応用へのハードルが高い。それに比べ、MSC産生因子から合成するペプチドによる治療は、投与幹細胞に起因する問題(腫瘍化や異所性形質転換)を回避することができる。また、合成ペプチドは抗原性がないため安全性は確保できると考える。本研究では、MSC産生因子から同定したタンパクPGRNとSLPIが大動脈瘤治療に有効であることを確認した。また、このタンパクのアミノ酸配列をリファレンスとしたペプチドも抗炎症作用を認めている。従って、本研究で得られた成果は学術的・社会的意義があると考える。
血液凝固ポリマーとペプチドを用いた非生物由来の新しい止血材の開発
研究課題/研究課題番号:22493703 2022年4月 - 2025年3月
科学研究費補助金 科学研究費挑戦的研究(萌芽)
成田 裕司
担当区分:研究分担者
骨再生マテリアル創出のための『ペプチド-高分子』コンビナトリアル探索研究
研究課題/研究課題番号:20K05227 2020年4月 - 2023年3月
蟹江 慧
担当区分:研究分担者
本研究は、細胞の増殖・分化をコントロール(細胞選択性)する、骨再生マテリアルに適した材料開発を最終目標とする。医療材料表面で表したい細胞選択性は、土台である高分子材料と機能性分子(ペプチド)の組合せによる総合的な効果で決まると考えられる。しかし、高分子材料やペプチドは種類や配合比、濃度だけでも無数に考えられ、総当たりで設計していては非効率である。本研究では、高分子材料とペプチドの物性値計測をし、情報処理解析技術やコンビナトリアル技術を用い、ハイブリッド骨再生マテリアルの創出を目指す。
ヒト小腸における8,400種類ジ・トリペプチド吸収基盤の解明
研究課題/研究課題番号:18H03195 2018年4月 - 2021年3月
伊藤 圭祐
担当区分:研究分担者
ヒトが摂取した食品たんぱく質は、消化管での加水分解の後、ペプチドもしくはアミノ酸として小腸上皮細胞より吸収される。特にペプチドの吸収効率はアミノ酸よりも高く、窒素源の吸収実体として中心的な役割を果たしている。ヒトにおいて体内へのペプチド吸収を担う輸送体は、プロトン共役型オリゴペプチドペプチド輸送体(POT)ファミリーのhPEPT1、hPEPT2であり、8,400種類のジ・トリペプチドが、小腸ではhPEPT1を介して吸収され、腎臓ではhPEPT2を介して原尿中から再吸収される。膨大なバリエーションの基質群を認識するPOTの“基質多選択性”はペプチド栄養の根幹であるが、その詳細は未だ十分には解明されていない。本研究では、申請者らが開発したペプチド輸送体(POT)解析システムを基盤技術として、ヒト小腸での食品由来ペプチドの吸収を担うhPEPT1について、8,400種類のジ・トリペプチドの網羅的吸収特性解析を実施し、“基質多選択性”の全貌を解明する。2018年度にはPOT発現細胞を構築した。しかしその一方で我々が開発したPOT解析法は蛍光ペプチドの取り込みの競合阻害を原理とする間接的な輸送能評価系である。そこで2019年度は2018年度に化学合成によって調整したジ・トリペプチドを用いて各種真核生物由来POTの網羅的親和性解析を進めるとともに、実際にペプチドの輸送効率を調べるため、ジペプチドの網羅的解析法(ジペプチドミクス)を確立した。ジペプチド分析にはLC/MS/MSを用い、誘導体化した合成ジペプチドをサンプルとして網羅的な定量解析が可能なこと、また混合物サンプルを用いた場合でも成功裏に定量解析できることが示された。
これまでにPOT発現細胞、POT解析法、また実際の輸送を調べるためのジペプチドミクスの開発に至った。2018年度は実験試薬の調達の遅れが生じたものの、ここまでの段階で目標達成に必要な解析系や素材はほぼ揃ってきていることから、現時点での研究進捗状況としては概ね順調と評価した。
本年度の研究では、ヒトを含めた真核生物POTのin silico親和性予測モデルの構築と、基質認識メカニズムの解析を進める。具体的には、ペプチド群のPOT親和性解析データを重回帰分析する際、ペプチド全体を一つの分子として捉え、“各空間座標における物理化学的因子(“OH基の数”や“logP値”等)の総和”をアルゴリズムとした、汎用性の高いin silico基質親和性予測モデルの構築を検討する。また基質認識メカニズムとして、POTへの結合配向についても解析する。
弾性率制御ハニカム多孔膜とラマン計測による幹細胞のメカノトランスダクション解明
研究課題/研究課題番号:17H01223 2017年4月 - 2020年3月
藪 浩
担当区分:研究分担者
弾性率制御されたハニカムスキャフォールドの作製法を確立し、ヒト間葉系幹細胞(hMSC)やiPS細胞などの幹細胞および神経系細胞などについてその接着・増殖・分化をモニタリングすることに成功した。これらのデータベースを基に特徴的な分化制御能を与える材料変面条件を得ることに成功した。また、Coupled Cahn-Hilliard方程式を基にした高分子微粒子構造制御の理論モデル構築に成功し、本モデルを基に自己組織化による有機無機コンポジット微粒子の作製に成功した。磁性粒子と金ナノ粒子をコンポジットした高分子微粒子は液中で磁場によって任意の部位のラマン散乱測定が可能であることを明らかとした。
幹細胞の分化制御は再生医療において重要な技術であり、これまでサイトカインや遺伝子導入など、液性因子を用いた分化誘導が行われてきた。本研究は幹細胞の培養環境であるスキャフォールドの構造と力学物性が幹細胞の接着・増殖・分化に与える影響を明らかとするものであり、本研究により明らかにされた幹細胞分化とスキャフォールド等の培養条件の相関は、再生医療の発展に資するものである。
さらに本研究で開発した微粒子による局所部位でのラマン散乱計測プローブは、細胞などの液体中でも特定の位置の化学物質の動態情報を3次元的に取得することを可能にするものであり、上記のスキャフォールドによる幹細胞分化機序の解明に貢献する。
細菌固定化蛋白質の水中接着能を利用する固体表面のワンポット自在修飾技術の創出
研究課題/研究課題番号:17H01345 2017年4月 - 2020年3月
堀 克敏
担当区分:研究分担者
細胞内分子確認ペプチドのデザインと細胞機能改変
研究課題/研究課題番号:16H04575 2016年4月 - 2019年3月
本多 裕之
担当区分:研究分担者
ペプチドは豊富なバリエーションからの創薬につながる化合物が報告されている。また小分子ペプチドは細胞内で機能する新しい医薬化合物として期待されている。そこで、1)非天然アミノ酸も含めたランダムペプチドライブラリーを作製し、2)細胞膜透過性ペプチド(CPP)を連結して膜透過性を付与することで、細胞内で機能する新規ペプチドの探索を試みた。また、3)CPPの影響を排除するために、CPPと機能性ペプチドが細胞内で解離するシステムの構築を検討した。ペプチドアレイ上でのジスルフィド結合を形成する方法を確立し、ジスルフィド形成を分子内反応とすることで、ヘテロ二量体ペプチドを選択的に合成する手法を開発した。
細胞内に導入し内部に侵入した直後に切断できる仕組みは細胞内機能性ペプチドの探索において必要不可欠な技術である。また環状化ペプチドライブラリーによる探索も高機能ペプチドの探索において重要な手法であり、細胞内機能性ペプチド医薬の開発につながる技術である。
新規機能性ペプチド含有担体と臍帯由来幹細胞を用いた骨・軟骨再生に関する基礎的研究
研究課題/研究課題番号:26462729 2014年4月 - 2018年3月
蛯沢 克己
担当区分:研究分担者
ペプチドアレイ上における細胞制御ペプチドスクリーニング法で骨・軟骨分化促進ペプチドを、候補タンパク質中から探索し、機能的足場設計のための候補ペプチドのリストアップを行った。これらペプチドを自己配列ペプチド担体に化学修飾を行い、ハイドロゲルを作製した。本材料に臍帯由来間葉系幹細胞を播種・培養を行い、マウス皮下へ移植し、骨形成および軟骨形成の生化学および組織学的評価を行った。いずれのサンプルでも骨及び軟骨特有の細胞外器質の形成が乏しかった。本研究では、候補タンパク質中からリストアップしたペプチドを修飾した担体に、臍帯由来間葉系幹細胞を播種した複合体を、骨および軟骨へ効率的に分化誘導できなかった。
熱による新規骨形成促進法の開発:マグネタイト微粒子の応用
研究課題/研究課題番号:26670659 2014年4月 - 2017年3月
西田 佳弘
担当区分:研究分担者
熱により骨新生が促進されることをラットおよびラビットの動物実験系およびATDC-5、MC3T3細胞株を使用したin vitro実験によって明らかにした。
ラットにおいてアルギン酸ゲルにマグネタイトリポソーム微粒子を混合し、交番磁場下に1回加温することで旺盛な骨形成が得られた。加温材料をすでに臨床応用されている人工骨(ハイドロキシアパタイト)と鉄粒子を含んだ造影剤に変更し、ラット・ラビットにおいて複数回加温の骨新生促進効果を明らかにした。
ハニカムスキャフォールドを用いた幹細胞操作技術の新展開
研究課題/研究課題番号:26620170 2014年4月 - 2016年3月
藪 浩
担当区分:研究分担者
ポリブタジエン(PB)およびポリスチレン(PS)を溶媒に溶かし、界面活性剤を加えてキャスト製膜することにより、ハニカム状多孔質膜の作製を行った。また、リファレンス用として、それぞれのフラット膜を作製した。PBについては、UV露光により光架橋を行った。表面弾性率を原子間力顕微鏡を用いて測定し、弾性率が未架橋PB<架橋PB<PSであることが示唆された。それぞれの基板上でヒト間葉系幹細胞を様々な分化誘導培地で培養したところ、細胞の接着および分化が弾性率と孔径等のパラメータによって異なる事が明らかとなった。これらの知見は幹細胞操作技術の新しい展開をもたらすと期待される。
万能細胞培養技術標準化のための培養経過全貌のFingerprint評価法
研究課題/研究課題番号:26630427 2014年4月 - 2016年3月
加藤 竜司
担当区分:研究代表者
配分額:3900000円 ( 直接経費:3000000円 、 間接経費:900000円 )
iPS細胞などの多能性幹細胞は、高度な培養技術を必要としており、現状は熟練者の培養スキルに依存している。今後このような幹細胞を広く活用するには「最適な培養法の標準化」が必須であり、そのためには細胞培養工程全体の数値化法の開発が急務である。本研究では、iPS細胞をモデル細胞として、未分化能との関連が深いことが知られるiPSコロニー形について、全コロニー・全履歴の形態情報の変化を数値化・可視化する手法「Total Culture Fingerprint法」を開発した。これによって培養工程の各種ストレスと、これに関わる幹細胞の品質低下とコロニー形態の変化について定量的なモデル化が可能なことを示した。
細胞アレイ評価法を用いた細胞内機能性ペプチド探索技術の確立
研究課題/研究課題番号:25289292 2013年4月 - 2017年3月
本多 裕之
担当区分:研究分担者
細胞膜透過性ペプチド(CPP)を連結したペプチドライブラリーを作製し、ミトコンドリア標的細胞死ペプチドを、ヒト乳腺がんMCF-7細胞を使って探索した。5残基目のSをWに置換した配列置換体、LNLIWKLFでは元ペプチドと比較して細胞死活性が約4倍向上し、F,V,Yなど疎水性アミノ酸に置換した置換体でも高活性を示した。細胞周期停止で細胞死を誘導するペプチドに関しても活性の高い配列置換ペプチドの探索に成功した。また、アミノ酸を4グループに群分けし、4残基ライブラリーで機能性ペプチド探索する手法を開発した。得られた高活性ルールを用いて8残基ペプチドの探索が可能であることがわかった。
細胞選択性ペプチドを用いた医療機器被覆用ミニマムECMの設計
研究課題/研究課題番号:23680055 2011年4月 - 2014年3月
加藤 竜司
担当区分:研究代表者
配分額:27430000円 ( 直接経費:21100000円 、 間接経費:6330000円 )
本研究は、次世代医療機器のための革新的バイオマテリアルとして細胞選択性を有する人工合成細胞外マトリクス『ミニマム(最小単位)ECM』の設計を、ペプチドのアレイ化技術とバイオインフォマティクス解析技術を融合させて行うことを目標として行った。結果、3残基の網羅的なペプチドに対して細胞選択性・血液凝固阻害能・ECM結合能を全て評価することで、ミニマムECMとして有効性の高い配列を多数取得・ランキングすることに成功した。さらには、これら細胞選択性配列と医療機器表面の物理化学的相性のルール化に成功し、より効果的にペプチド被覆を行える手法を開発するに至った。
細胞形態変化をインジケータとする超効率的培地評価法の確立と革新的培地開発
研究課題/研究課題番号:23650286 2011年 - 2013年
加藤 竜司
担当区分:研究代表者
配分額:3640000円 ( 直接経費:2800000円 、 間接経費:840000円 )
本研究は、再生医療や創薬産業で用いられる未分化細胞の多能性維持状態を維持するために最適な培地を。迅速かつ効率的に設計する方法の開発であり、培地中の成分の違いによって現れる細胞の形の変化をインジケータとして用い、「細胞の形を見ただけで培地機能性が評価できる」次世代培地機能性スクリーニング法の確立とこれを用いた革新的培地開発である。結果、間葉系幹細胞の培養状態の細胞画像を用いて培養環境をプロファイリングできること、またそれを利用すると分化の誘導・阻害をするような培地添加因子をスクリーニングできることを確認し、細胞の品質を評価しながら最適な培地を選択できるような解析システムを構築するに至った。
細胞形態の画像解析による骨髄間質細胞の新たな品質管理システムの構築
研究課題/研究課題番号:23659912 2011年 - 2012年
各務 秀明
担当区分:研究分担者
本研究の目的は、新たな品質管理システムを開発することである。初 めに、最新の細胞画像解析技術を用いて分化誘導中の細胞画像から増殖曲線、細胞面積、外部 刺激に対する細胞面積変化、回転運動等の細胞特徴量とその経時的変化を記録した。これらの 評価を生化学的、分子生物学的機能的評価の結果と対比させることで、培養細胞の分化度や機 能異常を検知する細胞診断の基準を決定し、細胞診断ソフトウエアを開発した。
動脈のリモデリングを抑制し、自己組織化するステントグラフトの開発
研究課題/研究課題番号:22591539 2010年 - 2012年
水谷 真一
担当区分:研究分担者
(研究の目的)本研究の目的は、革新的な大動脈瘤治療であるステントグラフト内挿術の重大な術後晩期合併症のステント位置移動やそれに伴うエンドリークを抑制するための自己組織化を目指した「インテリジェント化ステントグラフト」の開発である。
(本年度研究結果)
(1) ペプチド付与担体の開発:ペプチドインフォマティクスを活用し、単一アミノ酸配列において、組織化を促すと考えられる線維芽細胞の接着・増殖選択性の高い配列を検索(内皮細胞、平滑筋細胞との比較)すると、7残基のチロシンやアルギニンにおいて、線維芽細胞選択性が比較的高いことがわかった。
ペプチド混和した、ポリグリコール酸、ポリ乳酸の共重合ポリマーを、エレクトロスピニング(E-spin)法を用いて不織布を作製した。この不織布を用いても、細胞選択性は維持されることがわかった。(2)ドキシサイクリン徐放担体の作製:マトリクスメタロプロテアーゼ(MMP)に拮抗して、動脈のリモデリングを抑制するドキシサイクリンを生体吸収性ポリマーに混和し、E-spinで紡糸したところ、ドキシサイクリンは、in vivoで、2週間で約50%を、4週間で約70%を徐放した。この担体は、平滑筋細胞やマクロファージのMMPやサイトカイン分泌に抑制的に働き、エラスチンを維持し、アポリポプロテインEノックアウトマウス動脈瘤モデルおいて動脈瘤進展抑制効果を示した。
今後これらの技術を応用し、ステントグラフトの作製を試みる予定である。
ECM模倣ペプチドデザイン法を応用した内皮化促進ステントの開発
2008年4月 - 2010年3月
科学研究費補助金 科学研究費萌芽
加藤竜司
担当区分:研究代表者
ペプチドアレイを活用したコレステロール代謝改善ペプチドの作用機構解明と応用
2008年4月 - 2010年3月
科学研究費補助金 科学研究費基盤(B)
長岡利
担当区分:研究分担者
薬剤溶出性単体を用いた内視鏡粘膜切除術後食道瘢痕狭窄の予防
2008年4月 - 2009年3月
科学研究費補助金 科学研究費基盤(C)
丹羽康正
担当区分:研究分担者
「再生医療臨床応用に向けた細胞培養システム構築-情報処理による培養制御因子の研究-」
2005年4月 - 2007年3月
科学研究費補助金 若手研究(B),課題番号:17700391
加藤 竜司
担当区分:研究代表者
観察装置および観察方法
加藤竜司、田中健二郎、本村 麻子、菅沼 寛、五十嵐陽子
観察装置および観察方法
加藤竜司、田中健二郎、本村 麻子、菅沼 寛、五十嵐陽子、杉山 陽子、佐野 知巳様
情報処理装置、情報処理方法およびコンピュータプログラム
加藤竜司、田中健二郎、久田拓海、竹内宏彰、後藤浩之、河原正浩
培養補助装置、培養システム、培養補助方法およびプログラム
加藤 竜司、田中健二郎、竹内宏彰、松田博行、松田和佳奈
情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法およびコンピュータプログラム
加藤竜司、竹本悠人、椎名健、百瀬賢吾
細胞分析モデル生成装置及び細胞分析モデル生成方法、細胞分析装置及び細胞分析方法、並びにプログラム
加藤竜司、他
細胞分析結果出力装置、細胞分析結果出力方法及びプログラム
加藤竜司、他
細胞分析用情報生成装置、細胞分析用情報生成方法及びプログラム
加藤竜司、蟹江慧、佐々木寛人
細胞分析用情報生成装置、細胞分析用情報生成方法及びプログラム
加藤竜司、他
細胞分析モデル生成装置及び細胞分析モデル生成方法、細胞分析装置及び 細胞分析方法、並びにプログラム
加藤竜司、他
細胞分析結果出力装置、細胞分析結果出力方法及びプログラム
加藤竜司、他
細胞品質管理方法及び細胞の生産方法
加藤竜司、梶浦圭一、金美海、紀ノ岡正博
細胞培養環境評価方法及びその装置
加藤竜司、梶浦圭一、本多裕之、金美海、紀ノ岡正博
細胞培養環境評価方法及びその装置
加藤竜司、小島健児、牛田泰徳、本多裕之、白石卓夫、武澤康範
医療機器コーティングのための細胞特異的成長促進ペプチドの応用
加藤竜司、他
化学物質のスクリーニング法
加藤竜司、他
細胞培養評価装置、インキュベータ、プログラム、および、培養法
加藤竜司、他
細胞培養評価装置、インキュベータ、プログラム、および、培養法
加藤竜司、他
細胞培養評価装置、インキュベータ、プログラム、および、培養法
加藤竜司、他
細胞培養評価装置、インキュベータ、プログラム、および、培養法
加藤竜司、他
細胞培養評価装置、インキュベータ、プログラム、および、培養法
加藤竜司、他
細胞培養評価装置、インキュベータ、プログラム、および、培養法
加藤竜司、他
細胞培養評価装置、インキュベータ、プログラム、および、培養法
加藤竜司、他
細胞特異的ペプチドおびその用途
加藤竜司、蟹江慧、趙瑛梓、成田裕司、本多裕之
機能性ペプチドを表すルールの抽出法、機能性ペプチドの設計法及び調製方、ポリペプチドまたはポリペプチド含有組成物の評価法、並びに機能性ペプチド
培養状態評価装置、インキュベータおよびプログラム
加藤竜司、本多裕之、山本若菜
細胞品質予測モデル
培養工程プロセスを管理するプログラム
加藤竜司、各務秀明、蛯沢克己、上田実
細胞死誘導のためのペプチドおよび医薬
小林猛、本多裕之、加藤竜司、国松己歳、奥野郁佳子
先端生物科学
2016
バイオテクノロジー基礎論
2016
基盤創薬学概論
2016
先端産業特論
2016
多分野融合実践実習
2016
多分野融合実践演習
2016
生物プロセス工学
2015
先端産業特論
2015
基盤創薬学概論
2015
基礎セミナーA (文理融合)
2015
多分野融合実践実習
2015
多分野融合実践演習
2015
創薬評価科学
2015
先端生物科学
2015
バイオテクノロジー基礎論
2015
創薬評価科学
2014
多分野融合実践実習
2014
多分野融合実践演習
2014
基盤創薬学概論
2014
生物プロセス工学
2014
基礎セミナーA (文理融合)
2014
先端生物科学
2014
バイオテクノロジー基礎論
2014
生命の科学
2021年4月 - 2021年7月 (椙山女学園大学)
科目区分:学部教養科目 国名:日本国
山梨大学・発生工学技術・開発セミナー
2019年1月 (山梨大学)
科目区分:大学院専門科目 国名:日本国
「情報科学特論」「応用生命システム工学特論」
2010年4月 (山形大学工学研究科)
JIS Q 2101制定
日本規格協会 2024年2月
JIS Q 2101の原案作成委員会委員長
役割:編集, 企画, 調査担当, 報告書執筆
日本企画協会 2023年7月 - 2024年2月
国際シンポジウムの企画運営・Korea-Japan Joint Meeting on Biomolecules and Nano-particles
役割:企画, 運営参加・支援
2023年5月
春日井高校理数コース特別授業
役割:講師
2024年1月
名大祭・研究室レクチャー「生きた薬を知る」
役割:講師
名大祭2023 2023年6月
名古屋大付属校「学びの杜」 最新の薬の科学~生きた薬を創る~
役割:講師
名古屋大学付属高校 名古屋大付属校「学びの杜」 2021年8月
第21回再生医療学会総会プログラム委員
役割:運営参加・支援
第21回再生医療学会総会運営委員会 2021年4月 - 2021年8月
2021年超異分野学会シンポジウム「「ここまで来た!ライフサイエンス研究のオートメーション」
役割:講師, 運営参加・支援
株式会社リバネス 2021年3月
経済産業省受託事業 「再生医療ならびにその技術を応用した細胞の産業化に向けた国際標準化」委員活動
役割:助言・指導, 運営参加・支援, 調査担当, 報告書執筆
一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム 2020年4月
瑞陵高校特別授業 「創薬科学の先端技術を知る」
役割:講師
愛知県立瑞陵高校 2020年1月
豪州・日本の国際共同シンポジウムAustralia-Japan Funding (AJF) Symposium: ”Exploiting technologies for personalised and precision medicine”開催
役割:講師, 運営参加・支援, 報告書執筆
Australia-Japan Funding 2019年12月
経済産業省・再生医療におけるQbD開発会議 選定委員
役割:運営参加・支援, 調査担当, 報告書執筆
経済産業省 2019年12月 - 2020年2月
豊西総合大学出前授業 「生きている薬を創る」
役割:講師
愛知県豊田西高校 2019年11月
European Orthopaedic Research Society (EORS) 2019 Maastricht, Netherlands 国際学会でのシンポジウム開催・Freiberg University・Bernd Rolauffs博士との共同開催 「Engineering and predicting cell shape for controlling cellular and subcellular mechanobiology and function」
役割:講師, 運営参加・支援
European Orthopaedic Research Society 2019年10月
日本動物細胞工学会JAACT2019シンポジウムオーガナイザー・シンポジウム3 「再生医療を支える基盤材料」
役割:運営参加・支援
日本動物細胞工学会 2019年7月
名大祭 研究室公開ラボレクチャー 「薬を作る科学を知る」
役割:講師
名古屋大学名大祭実行委員 2019年6月
河合文化教育研究所主催 教育特別講演会 「創薬科学 最前線 ~生きた薬をつくる~」
役割:講師
河合文化教育研究所 2019年4月
Australia-Japan Foundation Grantによる2国間交流事業の推進・University of Adelaide (Smid博士)との共同採択
役割:講師, 運営参加・支援
Australia-Japan Funding 2019年4月 - 2022年3月
ヒト細胞自動培養加工装置設計ガイドライン策定
役割:講師, 運営参加・支援
再生医療(ヒト細胞製造システム)開発WG委員会 2019年4月 - 2020年3月
瑞陵高校特別授業 「創薬科学の先端技術を知る」
役割:講師
愛知県立瑞陵高校 2019年1月
名大祭 研究室公開ラボレクチャー 「薬を作る科学を知る」
役割:講師
名古屋大学名大祭実行委員 2018年6月
経済産業省委託事業 「政府戦略分野に係る国際標準化活動」委員活動
役割:助言・指導, 運営参加・支援, 調査担当, 報告書執筆
一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム 2018年4月 - 2020年3月
ISO TC276 WG4 細胞製造標準化 Project Leader
役割:助言・指導, 運営参加・支援, 調査担当, 報告書執筆
ISO TC276 WG4 2018年4月
ISO TC276 WG4 Expert
役割:助言・指導, 運営参加・支援, 調査担当, 報告書執筆
ISO TC276 WG4 2018年4月
オーストラリア政府研究調査費NHMRC University of Adelaide (Smid博士)との共同採択
役割:講師, 運営参加・支援, 調査担当, 報告書執筆
National Health and Medical Research Council (NHMRC), Australia 2018年2月 - 2018年3月
JSPS 短期S 外国人研究者招へい(University of Adelaide (Smid博士)の招へい
役割:運営参加・支援, 報告書執筆
JSPS 2018年1月
吹上ホール(名古屋市中小企業振興会館) 「医療・バイオシーズ発表会」 における企画講演・「臨床現場における医療機器ニーズとエンジニアリング・アプローチ」
役割:講師, 運営参加・支援
名古屋大学産学連携本部 2017年12月
日本動物細胞工学会JAACT2017シンポジウムオーガナイザー・シンポジウム 「ヒト幹細胞の大量培養 ~細胞治療薬の実用化を目指して~」
役割:講師, 運営参加・支援
日本動物細胞工学会 2017年10月
科学技術交流財団後援・研究会「次世代創薬のためのトランスレーショナルサイエンス研究会」の採択と開催
役割:講師, 運営参加・支援
科学技術交流財団 2017年7月
名大祭 研究室公開ラボレクチャー 「創薬セミナー」
役割:講師
名古屋大学名大祭実行委員 2017年6月
瑞陵高校特別授業 「薬と細胞の科学」
役割:講師
愛知県立瑞陵高校 2017年6月
細胞評価及び製造基盤標準化委員会 委員
役割:助言・指導, 運営参加・支援, 調査担当, 報告書執筆
一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム 2017年5月
豊西総合大学出前授業 「薬と細胞の科学」
役割:講師
愛知県豊田西高校 2016年11月
NHK「ひとの大学」公開講座での講演・「再生医療と日本のものづくり」
役割:講師
NHK名古屋 2016年10月
マンスフィールド-PhRMA研究者プログラム 2016 第4期スカラーとしての米国訪問
役割:報告書執筆, 寄稿
マンスフィールド財団 2016年9月
第4回 細胞凝集研究会2016 主催
役割:講師, 運営参加・支援, 報告書執筆
細胞凝集研究会 2016年9月
第5回超異分野学会シンポジウムオーガナイザー
役割:講師, 運営参加・支援
株式会社リバネス 2016年3月
さいえんすカフェつるまでの講演・「薬と細胞の科学」
役割:講師
名古屋大学 2015年12月
日本生物工学会シンポジウムオーガナイザー・「動物細胞工学における非侵襲的細胞性状計測法の紹介」
役割:講師, 運営参加・支援
日本生物工学会 2015年10月
日本生物工学会シンポジウムオーガナイザー・「若手研究者が提案する動物細胞一つずつを加工・品質管理する技術」
役割:講師, 運営参加・支援
日本生物工学会 2015年10月
日本生物工学会若手会 夏のセミナー 主催
役割:運営参加・支援, 報告書執筆, 寄稿
生物工学若手研究者の集い 2015年7月
瑞陵高校特別授業 「瑞陵高校特別授業」
役割:講師
愛知県立瑞陵高校 2014年11月
日本動物細胞工学会JAACT2014シンポジウムオーガナイザー・シンポジウム 「Recent developments of Stem Cell Applications – leaders in industrialization」
役割:講師, 運営参加・支援
日本動物細胞工学会 2014年11月
第24回基礎及び最新の分析化学講習会と愛知地区講演会 「生物分析値の取り扱い〜分析データを客観的に扱うには〜」
役割:講師
日本分析化学会 2014年7月
バイオサイエンとインダストリー選定委員
役割:運営参加・支援
バイオサイエンス&インダストリー協会 2014年4月 - 2016年3月
名古屋大学オープンレクチャー2013 「再生医療と薬のはなし」
役割:講師
名古屋大学 2013年11月
日本生物工学会 セルプロセッシング計測評価研究部会主催シンポジウムオーガナイザー・シンポジウム 「実用化に資する動物細胞培養技術~幹細胞の応用とボトルネックの解決に向けて~」
役割:運営参加・支援
日本生物工学会 セルプロセッシング計測評価研究部会 2013年9月
日本生物工学会 セルプロセッシング計測評価研究部会 主催 第2回若手研究シンポジウムオーガナイザー
役割:運営参加・支援
日本生物工学会 セルプロセッシング計測評価研究部会 2010年7月
日本生物工学会 セルプロセッシング計測評価研究部会 主催 Young Researches Award (研究奨励賞) 創設 第1回若手研究シンポジウム オーガナイザー
役割:運営参加・支援
日本生物工学会 セルプロセッシング計測評価研究部会 2009年12月
東海高校特別授業
役割:講師
東海高校 2009年2月
名古屋大学教育研究改革・改善プロジェクト
役割:運営参加・支援, 報告書執筆, 寄稿
名古屋大学 2007年10月 - 2009年1月
JSPS ひらめき☆ときめき サイエンス ~ようこそ大学の研究室へ~主催
役割:運営参加・支援, 寄稿
JSPS 2006年1月
第9回ものづくり日本大賞 受賞者一覧 会誌・広報誌
経済産業局 https://www.monodzukuri.meti.go.jp/backnumber/09/index.html 2023年1月
第9回「ものづくり日本大賞」受賞者決定! 会誌・広報誌
中国経済産業局 https://www.chugoku.meti.go.jp/info/press/2023/230110.pdf 2023年1月
プレスリリース:「細胞の形」から治療薬を超効率的に予測 インターネットメディア
名古屋大学 https://www.nagoya-u.ac.jp/researchinfo/result/2022/06/-ai.html 2022年6月
プレスリリース:再生医療用細胞の画像診断を支援するCloud型Ai細胞品質管理システム~AiCELLEXの製品化と事業化を開始: インターネットメディア
名古屋大学 https://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/researchinfo/upload_images/20171120_ps_1.pdf 2017年11月
プレスリリース:「非破壊」「迅速」「低コスト」にiPS細胞の状態を評価できる品質管理技術を開発 インターネットメディア
名古屋大学 https://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/researchinfo/upload_images/20160926_ps.pdf 2016年9月
日本生物工学会中部支部例会
役割:企画立案・運営等
日本生物工学会中部支部 2024年1月
日本生物工学会中部支部・飛翔賞選考
役割:企画立案・運営等
日本生物工学会中部支部 2024年1月 - 2024年3月
日本動物細胞工学会JAACT2023シンポジウムオーガナイザー・シンポジウム「S2 Regenerative Medicine Driven by Advancing Technologies」 国際学術貢献
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等
日本動物細胞工学会JAACT2023 2023年11月 - 2023年12月
Japan Delegate Representative, The 28th Symposium of Young Asian Biological Engineers’ Community 国際学術貢献
役割:企画立案・運営等
Symposium of Young Asian Biological Engineers’ Community 2023年7月
Editor of Journal of Bioscience and Bioengineering
役割:審査・評価, 査読
Journal of Bioscience and Bioengineering 2023年4月 - 2024年3月
Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society (TERMIS) European Chapter Conference 2023, Symposium Organizer and Keynote speaker
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等, 監修
2023年3月
第22回日本再生医療学会総会 シンポジウム28再生医療実現化のためのイメージング技術の可能性と展望 オーガナイザー
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等, 監修
第22回日本再生医療学会総会 2023年3月
国際学術コンソーシアム(AC21)International meeting 日本側オーガナイザー(日・豪・タイ)
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等, 監修
国際学術コンソーシアム(AC21) 2023年1月
The 27th Symposium of Young Asian Biological Engineers’ Community, Japan organizing delegate
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等, 監修, 審査・評価
2022年12月
第35回 日本動物細胞工学会2022年度大会 (JAACT2022)シンポジウム1 細胞製造とQbDを考える ~よりよい再生医療等製品製造を目指して~ オーガナイザー
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等, 監修
日本動物細胞工学会 2022年7月
Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society (TERMIS) European Chapter Conference 2022, Symposium Organizer and Keynote speaker
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等, 監修
2022年6月
Session organizer, Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society (TERMIS) AP chapter 国際学術貢献
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等
Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society (TERMIS) AP chapter 2023年10月
Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society (TERMIS)2021 「Engineering, quantifying, understanding, and modelling cellular geometry for controlling cell function and artificial intelligence-supported outcome prediction」
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等
2021年11月
第21回再生医療学会総会プログラム委員
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等, 審査・評価
第21回再生医療学会総会運営委員会 2021年4月 - 2021年8月
2021年超異分野学会シンポジウム「「ここまで来た!ライフサイエンス研究のオートメーション」
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等
株式会社リバネス 2021年3月
日本動物細胞工学会JAACT2020シンポジウムオーガナイザー・シンポジウム「A New Decade of Cell Therapies」
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等
日本動物細胞工学会 2020年11月
European Orthopaedic Research Society (EORS) 2019 Maastricht, Netherlands 国際学会でのシンポジウム開催・Freiberg University・Bernd Rolauffs博士との共同開催 「Engineering and predicting cell shape for controlling cellular and subcellular mechanobiology and function」
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等
European Orthopaedic Research Society 2019年10月
日本動物細胞工学会JAACT2019シンポジウムオーガナイザー・シンポジウム3 「再生医療を支える基盤材料」
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等
日本動物細胞工学会 2019年7月
吹上ホール(名古屋市中小企業振興会館) 「医療・バイオシーズ発表会」 における企画講演・「臨床現場における医療機器ニーズとエンジニアリング・アプローチ」
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等
名古屋大学産学連携本部 2017年12月
日本動物細胞工学会JAACT2017シンポジウムオーガナイザー・シンポジウム 「ヒト幹細胞の大量培養 ~細胞治療薬の実用化を目指して~」
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等
日本動物細胞工学会 2017年10月
第4回 細胞凝集研究会2016 主催
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等
細胞凝集研究会 2016年9月
第5回超異分野学会シンポジウムオーガナイザー
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等
株式会社リバネス 2016年3月
日本生物工学会シンポジウムオーガナイザー・「動物細胞工学における非侵襲的細胞性状計測法の紹介」
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等
日本生物工学会 2015年10月
日本生物工学会シンポジウムオーガナイザー・「若手研究者が提案する動物細胞一つずつを加工・品質管理する技術」
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等
日本生物工学会 2015年10月
日本生物工学会若手会 夏のセミナー 主催
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等
生物工学若手研究者の集い 2015年7月
日本動物細胞工学会JAACT2014シンポジウムオーガナイザー・シンポジウム 「Recent developments of Stem Cell Applications – leaders in industrialization」
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等
日本動物細胞工学会 2014年11月
日本生物工学会 セルプロセッシング計測評価研究部会主催シンポジウムオーガナイザー・シンポジウム 「実用化に資する動物細胞培養技術~幹細胞の応用とボトルネックの解決に向けて~」
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等, 審査・評価
日本生物工学会 セルプロセッシング計測評価研究部会 2013年9月
日本生物工学会 セルプロセッシング計測評価研究部会 主催 第2回若手研究シンポジウムオーガナイザー
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等, 審査・評価
日本生物工学会 セルプロセッシング計測評価研究部会 2010年7月
日本生物工学会 セルプロセッシング計測評価研究部会 主催 Young Researches Award (研究奨励賞) 創設 第1回若手研究シンポジウム オーガナイザー
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等, 審査・評価
日本生物工学会 セルプロセッシング計測評価研究部会 2009年12月