教養教育院 統括部 兼任教員
大学院人文学研究科
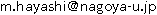
2025/03/18 更新

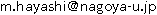
Ph.D. ( 2000年8月 University of Colorado at Boulder )
Master of Arts ( 1994年12月 University of Colorado at Boulder )
文学士 ( 1990年3月 京都大学 )
相互行為言語学
会話分析
人文・社会 / 言語学 / 会話分析
人文・社会 / 言語学 / 相互行為言語学
人文・社会 / 言語学 / 機能主義言語学
名古屋大学大学院人文学研究科 日本語教育学分野 教授
2019年4月 - 現在
国名:日本国
名古屋大学大学院人文学研究科 日本語教育学分野 准教授
2017年4月 - 2019年3月
国名:日本国
名古屋大学大学院国際言語文化研究科 日本語教育学講座 准教授
2016年4月 - 2017年3月
国名:日本国
University of Illinois at Urbana-Champaign Department of East Asian Languages and Cultures 准教授
2006年8月 - 2016年3月
国名:アメリカ合衆国
University of Illinois at Urbana-Champaign Department of East Asian Languages and Cultures 助教授
2000年8月 - 2006年8月
国名:アメリカ合衆国
University of Colorado at Boulder Department of Linguistics
- 2000年8月
国名: アメリカ合衆国
備考: Ph.D.
University of Colorado at Boulder Department of Linguistics
- 1994年12月
国名: アメリカ合衆国
京都大学 文学部 英語学英文学
- 1990年3月
国名: 日本国
International Pragmatics Association
International Society for Conversation Analysis
社会言語科学会
Interactional Linguistics (journal) editorial board member
2018年 - 現在
団体区分:その他
Research on Language and Social Interaction (journal) editorial board member
2018年 - 現在
団体区分:その他
Studies in Language and Social Interaction, monograph series, John Benjamins Publishing editorial board member
2017年 - 現在
団体区分:その他
Comparing across languages and cultures 招待有り 国際共著
Makoto Hayashi & Stephanie Hyeri Kim
The Cambridge Handbook of Methods in Conversation Analysis 頁: 780 - 808 2024年12月
Post-confirmation modifications in response to polar questions 招待有り
K. Hayano, M. Hayashi
Responses to Polar Questions across Languages and Contexts 頁: 272 - 300 2023年12月
会話における順番交替の手続き 招待有り
林 誠
エスノメソドロジー・会話分析ハンドブック 頁: 189 - 197 2023年4月
サッカー指導場面での「身体的実演」に見られるコーチと選手の相互行為 招待有り
林 誠・安井永子
実践の論理を描く:相互行為のなかの知識・身体・こころ 頁: 158 - 175 2023年3月
Kushida, S; Hayashi, M
RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL INTERACTION 55 巻 ( 1 ) 頁: 59 - 78 2022年1月
Hiramoto, T; Hayashi, M
ACTION ASCRIPTION IN INTERACTION 頁: 208 - 233 2022年
〈逸脱〉と〈資源〉としての非流暢性 招待有り 国際共著
高木智世・串田秀也・黒嶋智美・林 誠・森田笑・澤井雪乃
ことばと文字 14 巻 頁: 59 - 69 2021年4月
<i>Tte Yuu Ka</i> as a Repair Preface in Japanese 査読有り
Hayashi, M; Hosoda, Y; Morimoto, I
RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL INTERACTION 52 巻 ( 2 ) 頁: 104 - 123 2019年4月
Polar answers 査読有り 国際共著 Open Access
Enfield, NJ; Stivers, T; Brown, P; Englert, C; Harjunpää, K; Hayashi, M; Heinemann, T; Hoymann, G; Keisanen, T; Rauniomaa, M; Raymond, CW; Rossano, F; Yoon, KE; Zwitserlood, I; Levinson, SC
JOURNAL OF LINGUISTICS 55 巻 ( 2 ) 頁: 277 - 304 2019年4月
会話分析と多言語比較 招待有り
林 誠
会話分析の広がり 頁: 223 - 252 2018年9月
会話分析における対照研究 招待有り 査読有り Open Access
林 誠
社会言語科学 21 巻 ( 1 ) 頁: 4 - 18 2018年9月
A-prefaced responses to inquiry in Japanese 招待有り
Hayashi, M; Hayano, K
BETWEEN TURN AND SEQUENCE: TURN-INITIAL PARTICLES ACROSS LANGUAGES 31 巻 頁: 193 - 223 2018年7月
Dwelling, Construing, and Accidental Features 招待有り
Hayashi, M
CO-OPERATIVE ENGAGEMENTS IN INTERTWINED SEMIOSIS: ESSAYS IN HONOUR OF CHARLES GOODWIN 19 巻 頁: 160 - 163 2018年
確認要求に用いられる感動詞的用法の「なに」:認識的スタンス標識の相互行為上の働き 査読有り Open Access
遠藤智子, 横森大輔, 林 誠
社会言語科学 20 巻 ( 1 ) 頁: 100 - 114 2017年9月
会話におけるターンの共同構築 招待有り
林誠
日本語学 頁: 128 - 139 2017年4月
Morphological self-repair Self-repair within the word 査読有り 国際共著
Fox, BA; Wouk, F; Fincke, S; Flores, WH; Hayashi, M; Laakso, M; Maschler, Y; Mehrabi, A; Sorjonen, ML; Uhmann, S; Yang, HJ
STUDIES IN LANGUAGE 41 巻 ( 3 ) 頁: 638 - 659 2017年
WH質問への抵抗--感動詞「いや」の相互行為上の働き 招待有り
串田秀也, 林誠
感動詞の言語学 頁: 169 - 211 2015年
Turn formats for other-initiated repair and their relation to trouble sources: Some observations from Japanese and Korean conversations 査読有り 国際共著
Makoto Hayashi, Stephanie Hyeri Kim
Journal of Pragmatics 87 巻 頁: 198 - 217 2015年
Activity, participation, and joint turn construction: A conversation analytic exploration of `grammar-in-action' 招待有り
Makoto Hayashi
Usage-Based Approaches to Japanese Grammar: Toward the Understanding of Human Language 頁: 223 - 258 2014年
Responding with resistance to wh-questions in Japanese talk-in-interaction 査読有り
Makoto Hayashi, Shuya Kushida
Research on Language and Social Interaction 46 巻 頁: 231 - 255 2013年
Turn allocation and turn sharing 招待有り
Makoto Hayashi
The Handbook of Conversation Analysis 頁: 167 - 190 2013年
Proffering insertable elements: A study of other-initiated repair in Japanese 招待有り 国際共著
Makoto Hayashi, Kaoru Hayano
Conversational Repair and Human Understanding 頁: 293 - 321 2013年
Conversational repair and human understanding: An introduction 国際共著
Makoto Hayashi, Geoffrey Raymond, Jack Sidnell
Conversational Repair and Human Understanding 頁: 1 - 40 2013年
Claiming uncertainty in recollection: A study of kke-marked utterances in Japanese conversation 査読有り
Makoto Hayashi
Discourse Processes 49 巻 頁: 391 - 425 2012年
Transformative answers: One way to resist a question's constraints 査読有り 国際共著
Tanya Stivers, Makoto Hayashi
Language in Society 39 巻 頁: 1 - 25 2010年
An overview of the question-response system in Japanese 招待有り 査読有り Open Access
Makoto Hayashi
Journal of Pragmatics 42 巻 頁: 2685 - 2702 2010年
A cross-linguistic exploration of demonstratives in interaction: With particular reference to the context of word-formulation trouble 招待有り 国際共著
Makoto Hayashi, Kyung-Eun Yoon
Fillers, Pauses and Placeholders 頁: 33 - 66 2010年
Marking a "noticing of departure" in talk: Eh-prefaced turns in Japanese conversation 査読有り
Makoto Hayashi
Journal of Pragmatics 41 巻 ( 10 ) 頁: 2100 - 2129 2009年10月
A cross-linguistic investigation of the site of initiation in same turn self repair 招待有り 国際共著
Fox, B., Wouk, F., Hayashi, M., Fincke, S., Tao, L., Sorjonen, M.-L., Laakso, M. and Flores, W.
Conversation Analysis: Comparative Perspectives 頁: 60 - 103 2009年9月
Negotiating boundaries in talk 招待有り 国際共著
Makoto Hayashi, Kyung-eun Yoon
頁: 248 - 276 2009年9月
Universals and cultural variation in turn taking in conversation 査読有り 国際共著
Stivers, T., Enfield, N. J., Brown, P., Englert, C., Hayashi, M., Heinemann, T., Hoymann, G., Rossano, F., de Ruiter J. P., Yoon, K.-E., and Levinson, S. C.
Proceedings of the National Academy of Sciences 106 巻 ( 26 ) 頁: 10587 - 10592 2009年6月
会話における「指示」と発話の文法構造 招待有り
林 誠
言葉と認知のメカニズム - 山梨正明教授還暦記念論文集 頁: 603 - 619 2008年9月
相互行為の資源としての投射と文法 - 指示詞「あれ」の行為投射的用法をめぐって 招待有り 査読有り Open Access
林 誠
社会言語科学 10 巻 ( 2 ) 頁: 16 - 28 2008年9月
The achievement of intersubjectivity through embodied completions: A study of interactions between first and second language speakers 査読有り 国際共著
Junko Mori, Makoto Hayashi
Applied Linguistics 27 巻 ( 2 ) 頁: 195 - 219 2006年6月
A cross-linguistic exploration of demonstratives in interaction: With particular reference to the context of word-formulation trouble 査読有り 国際共著
Makoto Hayashi, Kyung-eun Yoon
Studies in Language 30 巻 ( 3 ) 頁: 485 - 540 2006年
Joint turn construction through language and the body: Notes on embodiment in conjoined participation in situated activities 査読有り
Makoto Hayashi
Semiotica 156 巻 ( 1/4 ) 頁: 21 - 53 2005年12月
「文」内におけるインターアクション - 日本語助詞の相互行為上の役割をめぐって 招待有り 査読有り
林 誠
活動としての文と発話 頁: 1 - 26 2005年10月
Referential problems and turn construction: An exploration of an intersection between grammar and interaction 査読有り
Makoto Hayashi
TEXT 25 巻 ( 4 ) 頁: 437 - 468 2005年7月
Projection and grammar: Notes on the `action-projecting' use of the distal demonstrative are in Japanese 査読有り
Makoto Hayashi
Journal of Pragmatics 36 巻 ( 8 ) 頁: 1337 - 1374 2004年8月
Discourse within a sentence: An exploration of postpositions in Japanese as an interactional resource 査読有り
Makoto Hayashi
Language in Society 33 巻 ( 3 ) 頁: 343 - 376 2004年7月
Language and the body as resources for collaborative action: A study of word searches in Japanese conversation 査読有り
Makoto Hayashi
Research on Language and Social Interaction 36 巻 ( 2 ) 頁: 109 - 141 2003年
Contingent achievement of co-tellership in a Japanese conversation: An analysis of talk, gaze, and gesture 招待有り 国際共著
Makoto Hayashi, Junko Mori, Tomoyo Takagi
The Language of Turn and Sequence 頁: 81 - 122 2002年2月
Postposition-initiated utterances in Japanese conversation: An interactional account of a grammatical practice
Makoto Hayashi
Studies in Interactional Linguistics 頁: 317 - 343 2001年1月
Where grammar and interaction meet: A study of co-participant completion in Japanese conversation 招待有り 査読有り
Makoto Hayashi
Human Studies 22 巻 ( 2-4 ) 頁: 475 - 499 1999年10月
The role of empathy in sentence production: A functional analysis of aphasic and normal elicited narratives in Japanese and English 招待有り 国際共著
Menn, L. Kamio, A., Hayashi, M., Fujita, I., Sasanuma, S., and Boles, L.
Function and Structure: In Honor of Susumu Kuno 頁: 317 - 355 1999年6月
Co-construction in Japanese revisited: We do finish each other's sentences 招待有り 国際共著
Makoto Hayashi, Junko Mori
Japanese/Korean Linguistics 7 巻 頁: 77 - 93 1998年5月
The interaction of preserved pragmatics and impaired syntax in Japanese and English aphasic speech 査読有り 国際共著
Menn, L. Reilly, K., Hayashi, M., Kamio, A., Fujita, I., Sasanuma, S.
Brain and Language 61 巻 ( 2 ) 頁: 183 - 225 1998年2月
An exploration of sentence-final uses of the quotative particle in Japanese spoken discourse 招待有り
Makoto Hayashi
Japanese/Korean Linguistics 6 巻 頁: 565 - 581 1997年9月
Resources and repair: A cross-linguistic study of syntax and repair 招待有り 国際共著
Barbara A. Fox, Makoto Hayashi, Robert Jasperson
Interaction and Grammar, 頁: 185 - 237 1996年12月
A comparative study of self-repair in English and Japanese conversation 招待有り
Makoto Hayashi
Japanese/Korean Linguistics 4 巻 頁: 77 - 93 1994年4月
Semantics and interaction: Three exploratory case studies 査読有り 国際共著
Robert Jasperson, Makoto Hayashi, Barbara A. Fox
TEXT 14 巻 ( 4 ) 頁: 555 - 580 1994年1月
会話分析入門
串田秀也, 平本毅, 林誠( 担当: 共著)
勁草書房 2017年
Conversational Repair and Human Understanding 査読有り 国際共著
Makoto Hayashi, Geoffrey Raymond, Jack Sidnell( 担当: 共編者(共編著者))
Cambridge University Press 2013年
Joint Utterance Construction in Japanese Conversation
Makoto Hayashi( 担当: 単著)
John Benjamins Publishing Company 2003年
Makoto Hayashi
Encyclopedia of Terminology for Conversation Analysis and Interactional Linguistics 2023年
Choral co-production 招待有り
Makoto Hayashi
Encyclopedia of Terminology for Conversation Analysis and Interactional Linguistics 2023年
Makoto Hayashi
Encyclopedia of Terminology for Conversation Analysis and Interactional Linguistics 2023年
書評 伊藤翼斗(著)『発話冒頭における言語要素の語順と相互行為』大阪大学出版会,2018 招待有り
林 誠
社会言語科学22 巻 ( 1 ) 頁: 267 - 271 2019年9月
Offering contrastive alternatives in understanding checks: Two related types of other-initiated repair in Japanese. 国際会議
Makoto Hayashi
31st Japanese/Korean Linguistics Conference 2024年10月31日 Monash University
“I will tell/ask him”: Action ascription in remote foreign language interpretation services in Japan 国際会議
Mika Ishino & Makoto Hayashi
International Institute for Ethnomethodology and Conversation Analysis 2024 2024年6月26日 International Institute for Ethnomethodology and Conversation Analysis
会話分析における対照研究 招待有り
林 誠
同志社大学英文学会2023年度年次大会 2023年10月29日 同志社大学英文学会
Language typology meets interactional practice: The case of turn formats for other-initiated repair in Japanese and Korean 招待有り 国際会議
Makoto Hayashi
5th International Conference on Interactional Linguistics and Chinese Language Studies 2023年4月8日 Chinese Academy of Social Sciences Institute of Linguistics
Explorations of grammar and interaction: The case of Japanese 招待有り 国際会議
Makoto Hayashi
The Ocean University of China Conversation Analysis Lecture Series 2022年11月4日 The Ocean University of China Conversation Analysis Reseach Group
「非流暢性」への会話分析的アプローチ 招待有り
林誠
第1回社会言語科学会シンポジウム 2019年9月15日 社会言語科学会
『相互行為言語学』への招待—What is ‘interactional linguistics’?— 招待有り
林誠
第18回日本語文法学会大会 2017年12月2日 日本語文法学会
Articulating the inferable: Nani-prefaced polar questions in Japanese conversatin and their English counterparts 招待有り 国際会議
Makoto Hayashi
The English Linguistic Society of Japan International Spring Forum 2017 2017年4月22日 The English Linguistic Society of Japan
Turn formats for other-initiated repair and their relation to trouble sources: Some observations from Japanese and Korean conversations 招待有り 国際会議
Makoto Hayashi
University of Colorado at Boulder Department of Linguistics Colloquium 2016年2月26日 University of Colorado at Boulder Department of Linguistics
Collateral Effects(付随効果)と相互行為言語学の展望 招待有り
林誠
エスノメソドロジー・会話分析研究会2014年研究大会 2014年10月12日 エスノメソドロジー・会話分析研究会
会話分析から見た文法研究の新展開 招待有り
林誠
日本語用論学会中部支部研究会 2014年9月9日 日本語用論学会中部支部
他者修復開始の発話デザインとトラブル源の関係をめぐって 招待有り
林誠
NDS研究会 2014年9月9日 NDS研究会
Iya(‘No’)-prefaced responses to wh-questions in Japanese conversation 招待有り 国際会議
Makoto Hayashi
University of Illinois SLATE Lecture Series 2013年3月6日 University of Illinois SLATE Program
Other-initiated repair (OIR) in Japanese: An exploration of OIR turn formats containing ‘wh’-words 招待有り 国際会議
Makoto Hayashi
Workshop on Japanese Language and Interaction 2012年3月21日 National University of Singapore Department of Japanese Studies
Projection as a foundation for social coordination, grammar as a resource for projection 招待有り 国際会議
Makoto Hayashi
Workshop on the Interactional Foundations of Language 2011年7月16日 The Linguistic Society of America
Proffering insertable elements: A study of other-initiated repair in Japanese 招待有り 国際会議
Makoto Hayashi
University of Wisconsin-Madison Interaction Interest Group Colloquium 2010年10月15日 University of Wisconsin-Madison Interaction Interest Group
Responding with resistance to WH-questions in Japanese talk-in-interaction 招待有り 国際会議
Makoto Hayashi
Language, Interaction, and Social Organization Seminar Series 2010年5月21日 The Language, Interaction, and Social Organization (LISO) Unit at UC Santa Barbara
Referential problems and turn construction: An exploration of an intersection of grammar and interaction 招待有り 国際会議
Makoto Hayashi
Conference on Culture, Language, and Social Practice 2009年10月4日 The Program in Culture, Language, and Social Practice at CU Boulder
「参加の組織化」の観点から見た「文法」再検討:“ワードサーチ”を通しての一考察 招待有り
林誠
第19回第二言語習得研究会全国大会 2008年12月13日 第二言語習得研究会
Other-initiated repair in Japanese: An overview of OIR turn formats containing ‘wh’-words 招待有り 国際会議
Makoto Hayashi
Repair Workshop 2008年3月29日 University of Toronto Department of Anthropology
Marking ‘departure’ in talk: Eh-initiated turns in Japanese conversation 招待有り 国際会議
Makoto Hayashi
Speaker Series at the Center for Language, Interaction, and Culture (CLIC) 2007年2月7日 The UCLA Center for Language, Interaction, and Culture (CLIC)
Conversation analytic perspectives 招待有り 国際会議
Makoto Hayashi
Pre-conference workshop at the 15th Japanese/Korean Linguistics Conference 2005年10月5日 University of Wisconsin-Madison Department of East Asian Languages and Literatures
‘Learning-in-action’ outside of classroom: Toward an understanding of learning as a socially distributed interactive phenomenon 招待有り 国際会議
Makoto Hayashi, Junko Mori
University of Illinois SLATE Lecture Series 2003年4月17日 University of Illinois SLATE Program
Notes on the ‘action-projecting’ use of the distal demonstrative pronoun are in Japanese conversation 招待有り 国際会議
Makoto Hayashi
Workshop on ‘Projection’ 2003年3月6日 Max Planck Institute for Psycholinguistics
An exploration of language and gesture in Japanese 招待有り 国際会議
Makoto Hayashi
Interaction and Language Workshop 2001年10月20日 University of Wisconsin-Madison Interaction Interest Group
Practices for word searches in Japanese conversation: Language and the body as resources for collaborative action 招待有り 国際会議
Makoto Hayashi
University of Illinois Center for East Asian and Pacific Studies Brown Bag Lecture Series 2001年10月8日 University of Illinois Center for East Asian and Pacific Studies
‘Postposition-initiated utterances’ in Japanese conversation: An interactional account of a grammatical practice 招待有り 国際会議
Makoto Hayashi
Parasession on Discourse-based Grammar at the 14th Annual International Conference on Pragmatics and Language Learning 2000年4月13日 University of Illinois Division of English as an International Language
Repetitional disconfirming responses to polar questions in Japanese 国際会議
Kaoru Hayano, Makoto Hayashi
2023 International Conference on Conversation Analysis 2023年6月28日 International Society for Conversation Analysis
Claiming a sequential relevance: The use of nanka as prefacing demonstrations of accountability in initial and third positions 国際会議
Makoto Hayashi, Satomi Kuroshima
2023 International Conference on Conversation Analysis 2023年6月28日 International Society for Conversation Analysis
Proffering the unsaid: A form of understanding check in Japanese 国際会議
Makoto Hayashi, Hayato Chuman
17th International Pragmatics Conference 2021年6月28日 International Pragmatics Association
Beginning to explain: Nanka-prefaced responsive and initial actions in Japanese conversation 国際会議
Satomi Kuroshima, Makoto Hayashi
17th International Pragmatics Conference 2021年6月29日 International Pragmatics Association
Doing visualizing in coping with speaking difficulty: On koo-prefaced search for formulation in Japanese 国際会議
Shuya Kushida, Makoto Hayashi
16th International Pragmatics Conference 2019年6月12日 International Pragmatics Association
The status of “Do you have X?” utterances in service encounters in Japanese 国際会議
Makoto Hayashi
16th International Pragmatics Conference 2019年6月13日 International Pragmatics Association
Nn-prefaced answers to polar questions in Japanese 国際会議
Makoto Hayashi, Kaoru Hayano
International Conference on Conversation Analysis 2018 2018年7月13日 International Society for Conversation Analysis
修復の前置き(repair preface)としての「てゆうか」 招待有り
林誠
シンポジウム「日常会話コーパス」III 2018年3月19日 国立国語研究所
修復の前置き(repair preface)としての「てゆうか」 招待有り
林誠
第1回オハイオ州立大学-名古屋大学日本語・日本語教育研究ワークショップ 2018年2月23日 名古屋大学大学院人文学研究科
How about eggs?”: Action ascription in the family decision-making process during grocery shopping at a supermarket 国際会議
Takeshi Hiramoto, Makoto Hayashi
25th Japanese/Korean Linguistics Conference 2017年10月12日 University of Hawai‘i at Manoa Department of East Asian Languages and Literatures
Conversation Analysis and cross-linguistic/cross-cultural comparison 招待有り
Makoto Hayashi
「こう」を随伴する描写
串田秀也, 林誠
日本語用論学会第19回大会
Discussing Conversation Analysis: A case study on other-initiated repair in Japanese 招待有り 国際会議
Makoto Hayashi
University of Illinois Center for East Asian and Pacific Studies Brown Bag Lecture Series
Collateral Effects(付随効果)と相互行為言語学の展望 招待有り
林誠
ことば・認知・インタラクション3
A(“Oh”)-prefaced responses to inquiry in Japanese conversation 国際会議
Makoto Hayashi, Kaoru Hayano
International Conference on Conversation Analysis 2014 2014年6月26日 International Society for Conversation Analysis
確認要求に用いられる認識的スタンス標識としての「なに」について
遠藤智子, 横森大輔, 林誠
第35回社会言語科学会研究大会
Other-initiated repair on reference: Some preliminary observations from Japanese 招待有り 国際会議
Makoto Hayashi
Symposium on Reference in Interaction from Cross-Cultural Perspective
Responding with resistance to WH-questions in Japanese talk-in-interaction 国際会議
Shuya Kushida, Makoto Hayashi
International Conference on Conversation Analysis 2010 2010年7月7日 International Society for Conversation Analysis
Proffering insertable elements: A study of other-initiated repair in Japanese 国際会議
Makoto Hayashi, Kaoru Hayano
International Conference on Conversation Analysis 2010 2010年7月8日 International Society for Conversation Analysis
‘I once knew, but I don’t remember now’: Making a retrospective knowledge claim in Japanese interaction 国際会議
Makoto Hayashi
95th Annual Convention of National Communication Association 2009年11月13日 National Communication Association
Eh-prefaced questions in response to informings in Japanese conversation 国際会議
Makoto Hayashi
93rd Annual Convention of National Communication Association 2007年11月15日 National Communication Association
Negotiating boundaries in talk: On the ‘3rd-position’ deployment of minimal response tokens in Japanese and Korean conversations 国際会議
Makoto Hayashi
92nd Annual Convention of National Communication Association 2006年11月19日 National Communication Association
On the ‘post-minimal-response’ deployment of minimal response tokens in Japanese and Korean conversations 国際会議
Makoto Hayashi, Kyung-eun Yoon
International Conference on Conversation Analysis 2006 2006年5月12日 International Society for Conversation Analysis
Some ways in which grammar shapes local interactional practices. 国際会議
Makoto Hayashi
2005 Annual meeting of the American Anthropological Association 2005年12月3日 American Anthropological Association
Referential problems and turn construction 国際会議
Makoto Hayashi
9th International Pragmatics Conference 2005年7月12日 International Pragmatics Association
A cross-linguistic exploration of demonstratives in interaction: With particular reference to the context of word search 国際会議
Makoto Hayashi
7th Conference on Conceptual Structure, Discourse, and Language 2004年10月9日 University of Alberta Department of Linguistics
A cross-linguistic analysis of demonstratives in Japanese, Korean, and Mandarin as resources for dealing with word-formulation trouble in conversation 国際会議
Makoto Hayashi
2004 Association of Teachers of Japanese (ATJ) Seminar 2004年3月4日 Association of Teachers of Japanese (ATJ)
A family of phonetic practices: An exploration of the relationships among phonetics, syntax, and interaction 招待有り 国際会議
Traci Curl, Barbara Fox, Makoto Hayashi
EuroConference on Linguistic Structures and their Deployment in the Organization of Conversation 2002年9月8日
What can collaborative completion tell us about learning a foreign language? 国際会議
Junko Mori, Makoto Hayashi
International Conference on Conversation Analysis 2002 2002年5月21日 International Society for Conversation Analysis
Language and the body as resources for collaborative action: A study of word searches in Japanese conversation 国際会議
Makoto Hayashi
87th Annual Meeting of the National Communication Association 2001年11月3日 National Communication Association
‘Prospective indexicals’ in Japanese conversation: On the use of distal demonstratives as a resource for collaborative action during word searches 国際会議
Makoto Hayashi
2001 Association of Teachers of Japanese (ATJ) Seminar 2001年3月22日 Association of Teachers of Japanese (ATJ)
Sharing responsibility for checking information: A key to transmission of information in conversation 国際会議
Gail Ramsberger, Lise Menn, Makoto Hayashi
Academy of Aphasia Conference 2000 2000年10月23日 Academy of Aphasia
‘Postposition-initiated utterances’ in Japanese conversation: An interactional account of a grammatical practice 国際会議
Makoto Hayashi
5th Annual Conference on Language, Interaction, and Culture 1999年5月1日 The UCLA Center for Language, Interaction, and Culture (CLIC)
Where grammar and interaction meet: A study of co-participant completion in Japanese conversation 国際会議
Makoto Hayashi
Ethnomethodology and Conversation Analysis: East and West 1997年8月23日 International Institute for Ethnomethodology and Conversation Analysis
Co-construction in Japanese revisited: We do ‘finish each other’s sentences’ 国際会議
Makoto Hayashi, Junko Mori
7th Japanese/Korean Linguistics Conference 1996年11月10日 University of California at Los Angeles Department of East Asian Languages and Cultures
An analysis of talk, gaze, and gesture: A contingent achievement of co-tellership in Japanese conversation 国際会議
Makoto Hayashi, Junko Mori, Tomoyo Takagi
5th International Pragmatics Conference 1996年7月8日 International Pragmatics Association
Toward a general account of U::N in Japanese conversation 国際会議
Makoto Hayashi
1996 Annual Conference of the American Association for Applied Linguistics 1996年3月26日 American Association for Applied Linguistics
Discourse-pragmatic functions of sentence-final uses of the quotative particle Japanese 国際会議
Makoto Hayashi
6th Japanese/Korean Linguistics Conference 1995年8月9日 University of Hawai‘i at Manoa Department of East Asian Languages and Literatures
Cognitive factors in the choice of syntactic form by aphasic and normal speakers of English and Japanese: The speaker's impulse 国際会議
Lise Menn, Kate F. Reilly, Makoto Hayashi
1995 Linguistic Society of America Annual Meeting 1995年1月7日 Linguistic Society of America
A comparative study of repair in English and Japanese conversation 国際会議
Makoto Hayashi
4th Japanese/Korean Linguistics Conference 1993年10月16日 University of California at Los Angeles Department of East Asian Languages and Cultures
日本語相互行為における依頼・応答に見られる参与者間の相互調整:会話分析の観点から
研究課題番号:17K02721 2017年4月 - 2021年3月
日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤研究(C)
林 誠
担当区分:研究代表者 資金種別:競争的資金
配分額:4290000円 ( 直接経費:3300000円 、 間接経費:990000円 )
平成31年度/令和元年度の本課題の実施状況は以下の通りである。
1. 本課題の研究チームメンバーは、2019年6月9-14日に香港理工大学で開催された国際語用論学会(International Pragmatics Conference)にてパネル発表を行った。世界各国から学会に参加した多数の研究者を聴衆に迎え、活発な意見交換を行なった。その際に得た、非常にためになるフィードバックをもとに、学会後、各メンバーはそれぞれの発表原稿を学術論文の形にまとめる作業に入った(現在も進行中)。令和2年6月末をめどに研究成果を学術論文をまとめ、学術誌Journal of Pragmaticsに特集号として論文集を発表する方向で作業中である。
2. 前年度に引き続き、リサーチアシスタントを2名雇用し,既存のビデオデータ(①大学生協のパソコンカウンターにおけるサービス場面の相互行為、②日常会話,③少年サッカーの指導場面における相互行為,④マッサージ店における施術者と利用客の相互行為)の文字起こしを進めた。現段階で、データのおよそ7割の文字起こしを完了することができたが、令和2年度も引き続き文字起こしを継続する予定である。
今年度は、プロジェクトチームの各メンバーが研究成果を香港で開催された国際語用論学会(International Pragmatics Conference)で発表し、聴衆と貴重な意見交換をすることができた。これは最終年度の目標である学術誌の特集号での研究成果の発表への、大きな弾みとなるもので、現在、各メンバーは国際語用論学会で得られたフィードバックをもとに論文執筆に取り組んでいる。
令和2年度は,最終目標である学術誌Journal of Pragmaticsの特集号における研究成果の発表を目指す。現在のところ、論文第1稿を6月末までにまとめ、互いにフィードバックをしあったのち、秋口には改訂稿をJournal of Pragmaticsに送付し、査読プロセスにかける手順で進めている。
研究課題/研究課題番号:24K03864 2024年4月 - 2027年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(C)
林 誠, 遠藤 智子, 中馬 隼人
担当区分:研究代表者
配分額:4680000円 ( 直接経費:3600000円 、 間接経費:1080000円 )
本研究は、会話における発話の産出・聞き取り、理解の問題を解決するためのプラクティスである修復に焦点を当て、その言語形式と機能に関して多言語間で比較対照を行い、通言語的に見られる共通性を同定するとともに、各言語に見られる固有性を明らかにする。この対照分析を通して、相互行為プラクティスと言語の関係性、およびその関係性を動機づけるコミュニケーション上の原理の一端を解明することを目指す。
日本語相互行為における依頼・応答に見られる参与者間の相互調整:会話分析の観点から
研究課題/研究課題番号:17K02721 2017年4月 - 2021年3月
科学研究費補助金 基盤研究(C)
林 誠
担当区分:研究代表者 資金種別:競争的資金
配分額:4290000円 ( 直接経費:3300000円 、 間接経費:990000円 )
平成31年度/令和元年度の本課題の実施状況は以下の通りである。
1. 本課題の研究チームメンバーは、2019年6月9-14日に香港理工大学で開催された国際語用論学会(International Pragmatics Conference)にてパネル発表を行った。世界各国から学会に参加した多数の研究者を聴衆に迎え、活発な意見交換を行なった。その際に得た、非常にためになるフィードバックをもとに、学会後、各メンバーはそれぞれの発表原稿を学術論文の形にまとめる作業に入った(現在も進行中)。令和2年6月末をめどに研究成果を学術論文をまとめ、学術誌Journal of Pragmaticsに特集号として論文集を発表する方向で作業中である。
2. 前年度に引き続き、リサーチアシスタントを2名雇用し,既存のビデオデータ(①大学生協のパソコンカウンターにおけるサービス場面の相互行為、②日常会話,③少年サッカーの指導場面における相互行為,④マッサージ店における施術者と利用客の相互行為)の文字起こしを進めた。現段階で、データのおよそ7割の文字起こしを完了することができたが、令和2年度も引き続き文字起こしを継続する予定である。
今年度は、プロジェクトチームの各メンバーが研究成果を香港で開催された国際語用論学会(International Pragmatics Conference)で発表し、聴衆と貴重な意見交換をすることができた。これは最終年度の目標である学術誌の特集号での研究成果の発表への、大きな弾みとなるもので、現在、各メンバーは国際語用論学会で得られたフィードバックをもとに論文執筆に取り組んでいる。
令和2年度は,最終目標である学術誌Journal of Pragmaticsの特集号における研究成果の発表を目指す。現在のところ、論文第1稿を6月末までにまとめ、互いにフィードバックをしあったのち、秋口には改訂稿をJournal of Pragmaticsに送付し、査読プロセスにかける手順で進めている。
研究課題/研究課題番号:21K01898 2021年4月 - 2025年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(C)
高木 智世, 串田 秀也, 林 誠, 黒嶋 智美
担当区分:研究分担者
本研究は、日常会話をはじめとする社会的相互行為に見られる非流暢的現象を会話分析という社会学的手法を用いて探求する。相互行為における非流暢性は、一方では「滑らかに」相互行為を進めるという相互行為そのもののメカニズムにかかわる規範からの「逸脱」であるが、他方では、デリケートな事象を話題にしたりデリケートな行為を遂行したりするときに利用される、相互行為の「資源」でもある。本研究では、非流暢性のこうした側面を焦点として、非流暢性の「逸脱性」と「資源としての利用可能性」が実際の相互行為においてどのように立ち現れているかを精査し、非流暢性が果たす役割を実証的に解明する。
相互行為の参加者は、基本的に、できる限りスムーズに相互行為を進めることに強く志向するということが、これまでの会話分析的研究において指摘されており、それは、経験的にも理解しやすい。この意味において、相互行為における非流暢性は逸脱的な現象と言える。しかし、他方では、例えば、デリケートな事象を話題にしたり、デリケートな行為を遂行したりするときに敢えて非流暢的な言い方をすることによって、そのデリケートさの認識を表示し、話者は慎重にふるまっているというスタンスを示すことができる。つまり、非流暢性は相互行為の「資源」でもある。
本研究では、非流暢性のこうした両義的性質を焦点として、非流暢性の「逸脱性」と「資源としての利用可能性」が実際のさまざまな相互行為場面においてどのように立ち現れているかを精査し、非流暢性が果たす役割を実証的に解明することを目指してきた。
当初の補助期間最終年度として予定されていた2023年度までで明らかになったのは以下のことである。「あのー」「そのー」「ええと」など、いわゆる「フィラー」として従来一括して扱われたり、認知的なプロセスを示すマーカーとしてのみ扱われることが多かった、間投詞的に用いられる言語形式が、それぞれ相互行為の中で特有の働きを担っており、相互行為の現場においてその時々で生じている具体的な相互行為的課題(「直前のやりとりと非連続的な発話を産出しようとしている」、「すぐに反応を産出できないがその場で求められているタスクを達成しようとしている」など相互行為において繰り返し生じうる課題)に対処するために利用可能な相互行為資源であるということである。
本研究課題の成果は、本研究課題代表者、分担者、協力者の共同執筆による図書として公開予定である。
2023年度は、6月にオーストラリアで開催された国際会話分析学会(ICCA2023)において、Disfluency as methodical practices for interactionというテーマで代表者・分担者・協力者が参加するパネルを実施し、これまでの成果を発表することができた。研究代表者・分担者・協力者がそれぞれこの学会発表に向けて準備をする中で分析が飛躍的に進められ、本研究課題が目標とした成果に近づいたと言える。
この成果を、会話分析・談話分析研究者のみならず、日本語教育研究者や実践者、また、発話の中の非流暢的現象に関心がある一般読者にもわかりやすくまとめ、提示する図書の出版に向けて準備を進めている。打ち合わせ会議を重ねて方向性(図書の構成、難度、読者層、スタイルなど)を定め、現時点では、各自が担当章の執筆を進めているところである。
なお、分析対象としているフィラー的形式の中でも、「なんか」は非常に多様な用いられ方がなされているため、分析に当初の想定よりも多くの時間が必要であることがわかり、2024年度まで補助期間を延長することとなった。
当初は2023年度が補助期間最終年度となる予定だったが、配分された補助金の一部を有効に使用するために補助期間の延長を申請し、2024年度が最終年度となる。とりわけ、多様な様相を示す「なんか」の分析が難航しているため、2024年度は、「なんか」の分析の精度を高めることに注力したい。10月末にはオーストラリアで開催するJapanese Korean Linguistics Conferenceでワークショップを開催し、「なんか」の分析の現状を参加者と共有して議論をすることによって分析の精緻化を図る。このワークショップでは、韓国語における類似の現象(フィラー的形式の使用)との比較も予定されているため、新たな分析の切り口を見出すことも期待される。
図書の出版については、上述のように、現在、本科研費課題メンバーがそれぞれ分担する章の初稿を執筆中である。これまでにない新たな視点から相互行為における非流暢性や「フィラー類」を捉え直し、流暢さの優先性を前提とする従来の見方に一石を投じる研究成果を公開することを目指している。会話分析研究者のみが理解できるような学術書ではなく、できるだけ多くの読者の興味を惹きつけ、有益な知見として広く共有できるような内容にするべく、執筆者間でさらに議論を積み重ねたい。2024年度後半に、メンバー間で互いに初稿を検討して2024年度中の原稿の完成、脱稿をめざす。
研究課題/研究課題番号:21K00524 2021年4月 - 2025年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(C)
安井 永子, 林 誠, 高梨 克也, 岡田 みさを
担当区分:研究分担者
本研究では、文法を、会話とは別に存在するシステムとして捉える従来の言語学では明らかにできなかった、相互行為における文法の役割について探る。会話のビデオデータを用いた相互行為分析により、文法と身体動作の産出との関連について体系的な解明を行い、文法の新たな捉え方を提示することを目的とする。身体動作が中心となる活動(ダンスの教授場面など)を分析対象とし、語順などの文法構造が、発話に伴う身体の動きとどう関わるかについて明らかにする。その上で、異言語間との比較により、日本語文法固有の特徴が、身体動作の産出にどう影響を与えるか、及び、言語のどのような類型論的特徴が、身体動作の産出と関わるのかを検討する。
本研究は、身体動作が中心となる活動のビデオデータを用い、日本語の発話の構造や語彙の選択が、発話者やその他の参与者の身体動作の産出とどのように関わるのかを探る相互行為分析研究である。
3年目となる2023年度は、プロジェクトの整備に尽力した。まず、本科研費の研究期間終了後もプロジェクトを継続させるため、科研費の前年度応募を行なった。その際、協力者や分担者として関わってもらえる国内外の研究者に声をかけ、メンバーの拡充を図った。また、プロジェクトの進め方の見直しも行なった。これまでは、各自で個別に研究テーマを設定し、各自で分析に取り組むことで、文法と身体にかんする研究数を増やしていくことを目指していたが、取り扱う身体的活動の種類も、行為や連鎖や現象もバラバラでは、まとまった成果としてとらえにくいという問題が生じていた。そこで、今後は、注目する現象/文形式/行為を絞り、類似事例を幅広い場面から集めていくことで、共同で分析を進める方針に切り替えることとなった。
その他の活動は以下の通りである。
・国内外にて、各々の学会発表を行なった。
・代表者の安井と分担者の岡田が、スウェーデン、リンショーピン大学にて開催されたEmbodied syntax network conferenceに出席し、ヨーロッパ圏言語での関連研究について最新の動向を確認したほか、海外で同様の関心を持つ研究者たちとの交流や意見交換を行った。
これまでは、各自で個別に研究テーマを設定し、各自で分析に取り組むことで、文法と身体にかんする研究数を増やしていくことを目指していた。その上で、それぞれの成果をまとめた雑誌の特集号を発行するための準備に取り掛かるつもりであった。しかしながら、取り扱う身体的活動の種類も、行為や連鎖や現象も異なる上に、文法と身体にかかわるテーマで分析を進めうるだけの事例が集まりにくいなどの問題が生じていた。そのため、今後の方針を転換させる必要が生じており、思うようにプロジェクトを進めることができなかった。
また、2024年度が最終年度となるため、継続して本プロジェクトを進められるよう、科研費の前年度応募を行なったが、(基盤Bへの応募を目指したこともあり)採択には至らなかった。
以上の理由により、「やや遅れている」状況である。
発話と身体動作の関わりに、発話における日本語固有の文法的特徴がかかわることを明確に示す成果がまだ出ていないのが大きな課題である。そこで、今後は方針を変更させ、注目する現象/文形式/行為を絞り、類似事例を各自のデータより収集し、事例数を増やすことを試みつつ、共同で分析を進めていきたい。
今後は、これまでよりもミーティングの頻度を上げ、定期的にオンラインにてデータを検討する機会をもうけ、年度末までには論文にまとめられるような分析を進めておくことを目標とする。
英語(コミュニケーション)
2020
英語(上級)
2020
言語と社会Ⅰ
2020
日本語教育学演習Ⅱb
2020
日本語教育学講義Ⅱb
2020
博士論文研究Ⅱb
2020
日本語教育学講義Ⅱa
2020
日本語教育学演習Ⅱa
2020
博士論文研究Ⅱa
2020
第7回会話分析研究発表会 国際学術貢献
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等, 査読
会話分析研究会 2024年9月
第5回会話分析中級者(以上)セミナー
役割:企画立案・運営等, 学術調査立案・実施
2023年3月
第11回会話分析初級者セミナー 国際学術貢献
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等
会話分析研究会 2024年8月
第5回会話分析研究発表会
役割:企画立案・運営等, 審査・評価, 学術調査立案・実施
会話分析研究会 2022年8月
第4回会話分析研究発表会
役割:企画立案・運営等, 審査・評価, 学術調査立案・実施
会話分析研究会 2021年8月 - 2021年9月
第3回会話分析研究発表会
役割:企画立案・運営等
会話分析研究会 2020年9月