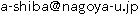
近年では「構文(構造)」という単位に着目し,構造と要素との相互作用という見方を,様々な言語レベルに適用し,構造と要素がどのように相互に関わりながら全体としての統合的体系を成しているのか,ということを研究しています。
2025/10/10 更新

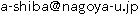
博士(学術) ( 2009年5月 東京外国語大学 )
非情物主語の受身
非情の受身
自発
自然発生自動詞
太陽コーパス
可能動詞
可能
受身
動作主
再帰構文
中動態
ラレル文
対照研究
構文
ヴォイス
人文・社会 / 日本語学 / 日本語学
人文・社会 / 言語学 / 言語学
人文・社会 / 日本語学
人文・社会 / 言語学
ヴォイスの通時的・対照言語学的研究
名古屋大学 大学院人文学研究科 人文学専攻 教授
2025年4月 - 現在
名古屋大学 初修外国語スペイン語 主任
2018年4月 - 現在
名古屋大学 人文学研究科 准教授
2017年4月 - 現在
名古屋大学大学院 国際言語文化研究科 准教授
2015年4月 - 2017年3月
国立国語研究所プロジェクト非常勤研究員
2013年7月 - 2015年3月
国名:日本国
東京外国語大学世界言語社会教育センター非常勤研究員
2009年7月 - 2012年3月
国名:日本国
東京外国語大学非常勤講師
2009年4月 - 2014年3月
国名:日本国
日本言語学会
日本語学会
日本語文法学会
日本イスパニヤ学会
東京スペイン語研究会
2015年4月 - 現在
日本語/日本語教育研究会
2023年8月 - 現在
東アジア国際言語学会 理事
2023年4月 - 現在
名古屋言語研究会
2022年4月 - 現在
ヨーロッパ日本研究協会
2021年4月 - 現在
東アジア国際言語学会 理事
2025年4月 - 現在
団体区分:学協会
東アジア国際言語学会 編集委員
2025年4月 - 現在
団体区分:学協会
日本語学会 会場校委員
2024年12月 - 2025年5月
日本語学会 編集委員
2024年5月 - 現在
名古屋言語研究会 副会長
2024年4月 - 現在
団体区分:学協会
日本言語学会 広報担当委員
2022年9月 - 2025年8月
日本語文法学会 大会委員
2022年4月
日本語文法学会 評議員
2021年4月 - 現在
日本語文法学会 大会委員
2017年4月 - 2020年3月
国立国語研究所所長賞
2016年2月 国立国語研究所
現代日本語のヴォイスにおける2つの体系:視点の転換と自動詞化・他動詞化 招待有り Open Access
志波彩子
東アジア国際言語研究 ( 7 ) 頁: 57 - 75 2025年3月
Passive and related constructions with verbal suffix -(r)are- in Early Middle Japanese: The case of Konjaku Monogatari-shū Open Access
Ayako Shiba
The Journal of Humanities (Nagoya University) 7 巻 2024年3月
ジャンル・テキストとその要素としての構文―受身構文を例に― 査読有り
志波彩子
日本語文法 23 巻 ( 2 ) 頁: 70 - 86 2023年10月
他動性構文としての関係構文 論理的関係を表す構文 招待有り
志波彩子
東アジア国際言語研究 5 巻 頁: 176 - 194 2023年4月
知覚動詞「見える」の推定構文への拡がり―共時態における文法化― Open Access
名古屋大学人文学研究論集 6 巻 2023年3月
日本語学における受身構文 招待有り
志波彩子
日本語受動文の新しい捉え方(庵功雄(編)) 頁: 1 - 26 2022年12月
自然発生(自動詞)から自発へー古代日本語と現代スペイン語の対照- 招待有り
志波彩子
日本語文法史研究 6 巻 2022年11月
【書評】角田太作著『日本語の地殻変動:ラレル,テアル,サセルの文法変化』 招待有り Open Access
志波彩子
日本語の研究 18 巻 ( 2 ) 頁: 89 - 96 2022年8月
【書評】川野靖子著『壁塗り代替をはじめとする格体制の交替現象の研究―位置変化と状態変化の類型交替―』 招待有り Open Access
日本語の研究 18 巻 ( 1 ) 頁: 94 - 101 2022年4月
日本語の他動性構文の記述を目指して―奥田靖雄構文理論の継承と発展 Open Access
志波彩子
人文学研究論集 5 巻 頁: 127 - 147 2022年3月
「XヲYニスル」構文の記述的研究―状態変化と態度(意義づけ)― 査読有り Open Access
劉 佳, 志波 彩子
Nagoya Linguistics 16 巻 頁: 29 - 44 2022年3月
自動詞・受身・可能・自発―自動詞的表現のパラディグマティックな体系― 査読有り
志波彩子
論究日本近代語 2 巻 2022年3月
受身,可能とその周辺構文によるヴォイス体系の対照言語学的考察-古代日本語と現代スペイン語- 査読有り Open Access
志波彩子
言語研究 158 巻 頁: 91 - 116 2020年12月
スペイン語のse中動態(再帰構文)における可能の意味 Open Access
志波 彩子, SHIBA Ayako
名古屋大学人文学研究論集 ( 3 ) 頁: 175 - 195 2020年3月
近代日本語における依存構文の発達―構文はどのように発生・発達・定着するのか― 査読有り Open Access
志波彩子
国立国語研究所論集 ( 16 ) 頁: 51 - 76 2018年10月
ラル構文によるヴォイス体系―非情の受身の類型が限られていた理由をめぐって― 招待有り
志波彩子
バリエーションの中の日本語史 頁: 175 - 195 2018年5月
受身と可能の交渉 Open Access
志波 彩子, SHIBA Ayako
名古屋大学人文学研究論集 1 巻 頁: 305 - 323 2018年3月
近代日本語の間接疑問構文とその周辺―従属カ節を持つ構文のネットワーク― 査読有り Open Access
志波 彩子
国立国語研究所論集 ( 10 ) 頁: 193-220 2016年1月
「「ト見ラレル」の推定性をめぐって―ラシイ,ヨウダ,(シ)ソウダ,ダロウとの比較も含め―」 査読有り
志波彩子
日本語文法 13 巻 ( 2 ) 頁: 122-138 2013年9月
Changes in the Meaning and Construction of Polysemous Words: The case of mieru and mirareru 査読有り
SHIBA Ayako
Corpus Analysis and Diachronic Linguistics (John Benjamins) 頁: 243–264 2011年12月
よくわかる日本語学
金水敏( 担当: 分担執筆 , 範囲: 受身文,自発・可能,疑問文)
ミネルヴァ書房 2024年7月 ( ISBN:4623096203 )
日本語受動文の新しい捉え方
庵功雄( 担当: 分担執筆 , 範囲: 日本語学における受身構文)
くろしお出版 2022年11月
初級スペイン語 エクセレンテ!!!
志波彩子, 渡辺有美, 水戸博之, 西村秀人( 担当: 共著 , 範囲: 全体的に文法解説と会話練習,各種練習問題を執筆)
朝日出版 2021年1月
日本語文法史キーワード辞典
青木博史, 高山善行( 担当: 分担執筆 , 範囲: 「受身」の項)
ひつじ書房 2020年12月
現代日本語の受身構文タイプとテクストジャンル
志波彩子( 担当: 単著)
和泉書院 2015年2月 ( ISBN:978-4-7576-0734-7 )
【書評】角田太作著『日本語の知覚変動:ラレル,テアル,サセルの文法変化』 招待有り
志波彩子
日本語の研究18 巻 ( 2 ) 頁: 89 - 96 2022年8月
受身・可能・自発・再帰・自動―古代日本語とスペイン語の対照から見えること 招待有り
志波彩子
東京外国語大学国際日本学研究院主催,連続講演会2021,第1回 2021年7月30日 東京外国語大学国際日本学研究院
ラレ構文「行はる」の変遷―主催・尊敬から非情主語受身へ―
志波彩子
2025年日本語学会春季大会 2025年5月10日
スペイン語の自発構文の構造的条件-“se me"を中心に
日本イスパニヤ学会第70回大会(京都外国語大学) 2024年10月12日
日本語ヴォイス史の諸相(指定討論者として登壇) 招待有り
志波彩子(指定討論者)
名古屋大学国語国文学会 2023年12月9日
Meaning and function of the -(r)are- construction in Classical Japanese: Influence of text style
Shiba, Ayako
EAJS2023 2023年8月18日
古代語の自然発生的自動詞とラレ構文の連続性について
志波彩子
日本語学会2022年度春季大会
Comparative study of grammatical voice system: Contenporary Japanese, Early Middle Japanese and Contemporary Spanish
Shiba, Ayako
EAJS2021 2021年8月27日
ジャンル・テキストとその要素としての構文タイプ―構造と要素の相互作用― 招待有り
志波彩子
日本語文法学会第21回大会(オンライン) 2020年12月12日
奥田靖雄構文理論の継承と発展;奥田靖雄のヲ格連語論ー他動性構文としての継承と発展
志波彩子, 早津恵美子, 茶谷恭代, 前田直子
日本語学会2020年度秋季大会(オンライン) 2020年10月25日
ラル構文によるヴォイス体系―非情の受身はなぜ存在しなかったか―
志波彩子
バリエーションの中での日本語史
古代日本語ラル構文の構文ネットワーク
志波彩子
日本言語学会第158回大会 2019年6月23日
スペイン語のse中動態における可能の意味
志波彩子
日本イスパニヤ学会第64回大会(南山大学) 2018年10月13日
Interaction between text genres and constructions 国際会議
Ayako SHIBA
ICLC 15 (International Cognitive Linguistics Conference) 2019年8月9日
古代日本語のラレ構文とジャンルー『源氏物語』と『今昔物語集』を例に―
志波彩子
テキストの中の文法第4回研究会 2023年3月28日
古代日本語の自発,受身とテキストジャンルー『源氏物語』と『今昔物語集』を例に
志波彩子
「テキストの中の文法」第6回研究会 2024年3月7日
自然発生の体系の中の受身と自発と可能 招待有り
志波彩子
東アジア国際言語学会シンポジウム 2023年11月4日
日本語学と日本語教育学におけるヴォイスの統一的把握に向けて
志波彩子
奥田靖雄言語学研究会 2024年9月3日
日本語とスペイン語の逆使役・受身と非意図構文
志波彩子
ヴォイスの通時的・対照言語学的考察第2回研究会 2025年3月27日
川村祐斗『サ系接続表現の史的展開―“別れの挨拶語”化を事例として―』
王雲姣『現代日本語における心理動詞の研究』
権裕羅『現代日本語の形容詞の分類 -構文における振る舞いを基準にして-』
ジャンルと文法—文法を揺るがす・形づくる・とどめる—(企画,司会)
余飛洋『雅語「ものす(る)」の歴史的研究』
宋幹秘「動詞における能動と受身の非対称性 ―「呼ぶ」「行う」「置く」「言う」を中心に―」
蔣瑶瑶「評価のモダリティ「テモイイ」の記述的研究 ―構造的条件と語用論的条件―」(修士論文)
翟首藝「とりたて詞「でも」の記述的研究 ―例示「でも」と極端「でも」を区別する構文的条件を中心にー」
杜保娣「叙法副詞「できるだけ」の叙法性と程度性をめぐって」
劉雨萌「無標可能表現の形成条件について」
南明世『行為の過程から見る日本語の失敗を表す複合動詞の研究 -中国語との対照から-』
徐曼『「V–コトニスル」構文の記述的研究』
黄小岑『「ワケダ」の記述的研究 —意味用法と構文的特徴を中心に—』
韓暖『証拠性表現「みたい」についての記述的研究』
譚斯琪『近代日本語における非情主語受身の変遷に関する一考察』
劉嘉勇『日本語のラレル構文と中国語の“被”構文の 対照言語学的研究』
夏程承「シテオクの構造的タイプと外部構造パターン -全体と部分の相互作用という観点から-」
三宅俊浩『無意志自動詞を出自とする日本語可能表現の歴史的研究』
黄秋実「「名詞+自体」と「名詞+そのもの」の使い分けに関する一考察」
羅潤天「アスペクトと意志性による心理動詞の分類」
蔡玉婷「「VかけのN」構文と「VたてのN」構文に関する記述的研究」
陳泳姗「限定を表す「ばかり」「だけ」の意味・機能と構文的特徴の記述的研究」
冀媛媛『近代から現代における「誰も」の通時的変遷―「誰もが」「誰しも」等の類似表現との比較を含めて―』
王会欣『認識動詞の日中対照研究―「思う」と“想”を中心に―』
劉佳「「XヲYニスル」構文の記述的研究 -状態変化と意義づけ-」
張娜「文末の助動詞「ものだ」の記述的研究」
全弘起『カ節を持つ構文の記述的研究 ―間接疑問の周辺―』
何月琦「中国語母語話者による第二言語としての受身構文の習得―学習者コーパスをデータとして―」(博士論文)
曲順昱「非情物主語の使役構文」
山口響史『受益・受害構文の歴史的研究』
史英男「事への働きかけ構文の記述的研究 -抽象名詞をヲ格にとる他動性構文-」
馬旭瑞「デ格名詞が表す相互関係とその構文の特徴―手段と原因を中心に―」
王会欣「思考動詞「思ウ」「思エル」「思ワレル」の構文と意味的違いの記述的研究」
陳瑤「~ことができる」文の意味と構造的特徴の記述研究 -可能動詞との比較も含めて-」
李研禕「感情心理動詞のテンス・アスペクト体系」
徐捷「形式名詞「トコロ」による接続表現の記述的研究 -「トコロデ」と「トコロヲ」を中心に-」
応用言語学データ分析論(名古屋大学大学院講義)
全弘起「カト節を持つ引用構文の記述的研究―間接疑問構文との関係を含めて―」
何月キ「ヴォイスの誤用分析と日本語教育への応用―中国語を母語とする日本語学習者を中心に―」
張子粒「日本語受身文の外部構造の記述的研究」
ジャンル・テキストの中の文法:テキストとその要素としての構文の相互作用
研究課題/研究課題番号:21K18359 2021年7月 - 2024年3月
科学研究費助成事業 挑戦的研究(萌芽)
志波 彩子, 矢島 正浩, 宮地 朝子, 井本 亮, 前田 直子, 勝川 裕子, 大島 義和, 永澤 済, 田村 加代子, 齋藤 文俊
担当区分:研究代表者
配分額:6240000円 ( 直接経費:4800000円 、 間接経費:1440000円 )
コーパスから収集したデータをもとに,収集した例文を構文タイプごとに分類し,前後にどのような構文が現れるか,またジャンルごとにどのような特徴的な構文間の結びつきがあるのかを考察する。こうした構文間の関係は必ずしも隣接する前後関係とは限らず,テキスト内の離れた位置に存在する構文同士が連関し合っている,ということも考えられる。また,歴史的観点からは,特に書き言葉ジャンルにおける構文とテキストとの関係を見ていく。これまで分析が手薄であった古代や中世,近世,近代における変体漢文や漢文訓読体を含めた書き言葉テキストと構文との関係を探っていく。
今年度は課題採択の通知があったのが7月であったため,スタートはやや遅れたが,10月と3月に2回の研究会を開催し,研究発表を行った。第1回目の研究会では,メンバー全員が何をテーマに研究していくかということを発表し,互いに意見交換した。第2回目の研究会では,共時態研究班から,井本が形容詞連用修飾構文のジャンル(特殊文脈)内での特殊な意味の表れ方について発表,歴史研究班では矢島が上方落語・速記本を対象として理由を表す形式の使用法を調査し、日常談話・音声落語との比較を通じて、同資料に実現する複数の言語層のありようについて検討した。また,永澤が現代と近代の判決文における理由節の表れ方を調査し,判決文に特徴的な「から」構文の使用があることを議論した。参加したメンバーから多くの質問やコメントが寄せられ,相互に刺激的な研究発表になった。
さらに,研究発表を受け,各ジャンルの特徴を規定する「指標」のようなものを設定する必要があるという議論になり,媒体,目的,内容,話し手の特徴,聞き手の特徴,求められる文体など,暫定的な指標をいくつか議論した。そして,今後の調査の中で,これらの指標を意識しながら分析を進めていくことを確認した。
研究代表者の志波は,上代と中古のラレル構文と自動詞構文との関係を調査している。現在のところ,万葉集と源氏物語を中心に,『日本語歴史コーパス』(国立国語研究所)から収集した用例を分類している。万葉集や源氏物語などの典型的な和文テキストにおけるラレル構文と自動詞構文の使用を調査し,両者の関係について考察している。
採択の通知が遅かったため,ややスタートが遅れたものの,2回の研究会を開催することができ,それぞれが今後の研究を進める上でのヒントを得ることができたため。また,研究発表を受け,ジャンルを規定する指標についての議論が深まり,今後の調査に活かしていけると考えられるため。
今後は,今年度議論したジャンルのいくつかの指標(媒体,目的,内容,話し手・聞き手の特徴,求められる文体,など)を意識しながら,それぞれのメンバーが自身の研究対象とジャンルとの関係を考察し,これによって,ジャンルの指標にも修正を加えていきたいと考える。
代表者の志波は,技術補佐員の力も借りて,今昔物語のデータを整理し,これらのジャンルにおけるラレル構文の使用の違いを調査したいと考えている。また,そこで明らかになったラレル構文の使用の違いが,各ジャンルにおける他の構文の使用とどのように関連しているかを考察する予定である。例えば,典型的な和文資料である源氏物語においては,ラレル構文は自発構文がもっとも中心的な,頻度の高い構文であるが,和漢混交文の今昔物語では自発構文はほとんど見られない。こうした違いが何に起因するのかを明らかにし,ジャンルと構文の関係を精査していく予定である。
大学初修外国語の読み書き習得の研究:書記体系と言語性認知能力の関係を中心に
研究課題/研究課題番号:25K00474 2025年4月 - 2030年3月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B)
宇都木 昭, キム ミンス, 勝川 裕子, 志波 彩子, 神長 伸幸
担当区分:研究分担者
第一言語の読み書き習得やディスレクシアに関する研究では、文字や書記体系によって習得の困難さに違いがあること、および、そこに個人差が大きいことが知られている。これをふまえ、本研究では第二言語のうちでもとりわけ、大学の初修外国語(いわゆる第二外国語)教育における読み書き習得を扱う。具体的には、異なる書記体系上の特徴を持つ言語として、韓国語、中国語、スペイン語を本研究の対象とする。さらに、個人差が生じる要因を明らかにするため、音韻意識や言語性ワーキングメモリなどの能力を調査し、読み書き習得の程度との相関をみる。
研究課題/研究課題番号:24K00072 2024年4月 - 2029年3月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B)
志波 彩子, 長屋 尚典, 永澤 済, 早津 恵美子, 佐々木 冠
担当区分:研究代表者
配分額:18590000円 ( 直接経費:14300000円 、 間接経費:4290000円 )
本研究は,日本語のラレル,サセルを中心に,自動詞,他動詞,可能,自発,授受といった様々な構文の間の相互関係を共時的かつ通時的に記述することで,日本語のヴォイス体系の総合的把握を目指すものである。古代日本語から中世,近世,近代,現代にいたる各構文のあり様を,テキスト的な違いも考慮に入れながら記述することで,日本語のヴォイスの発達過程を明らかにしていく。さらに,日本語の方言やスペイン語,タガログ語,中国語などとの対照を通して,諸言語のヴォイス体系に共通の特徴を明らかにし,同時に日本語に固有の特徴を浮き彫りにいていく。
ジャンル・テキストの中の文法:テキストとその要素としての構文の相互作用
2021年4月 - 2024年3月
JSPS 科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究
担当区分:研究代表者
構文ネットワークによるヴォイスの歴史的・対照言語学的記述研究
研究課題/研究課題番号:16K02726 2016年4月 - 2019年3月
志波 彩子
担当区分:研究代表者
配分額:3380000円 ( 直接経費:2600000円 、 間接経費:780000円 )
古代日本語に「ゴミが捨てられた」のような事態実現の局面を捉える無生物主語受身文が存在しなかったのは,西欧諸言語の中動態がこの種の受身文を発達させた領域に,日本語は自発・可能構文を中心に発達させたからであるとして,スペイン語の中動態と古代日本語のラル構文の体系を対照し,論証した。両言語は,「自然発生」の意味の自動詞から,動作主がいなければ起こり得ない事態をも自動詞的に捉える構文を同じように拡張させているが,スペイン語が「人によって事態が自然発生する(変化が実現する)」という意の受身を確立したのに対し,日本語は「人に対して事態が自然発生する/しない」という自発・可能を中心に確立した。
本研究は,独自の観点から古代語のラルが持つ受身(人主語),可能,自発,尊敬といった多義性にせまり,自然発生的自動詞文とのつながりと相違点を明らかにした。自然発生的自動詞文から再分析によって取り出されたラルは,人間に視点を置いて,「人間に対して行為が自然発生する(変化が実現する)」という述べ方で述べる構文であったと考えられる。このため,中立視点の非情主語受身文を持たなかった。こうしたラル構文の特性が,上のような多義の体系を作り出したと考えられる。
構文ネットワークによるヴォイスの歴史的・対照言語学的記述研究
2016年4月 - 2018年3月
日本学術振興会 科学研究費補助金(基盤C)
志波彩子
担当区分:研究代表者 資金種別:競争的資金
現代日本語の受身構文タイプとテクストタイプ
研究課題/研究課題番号:205077 2015年
日本学術振興会 科学研究費補助金・研究成果公開促進費・学術図書
志波彩子
日本語学(学部生向け)
2023年4月 - 現在 (名古屋大学)
日本語教育文法研究
2022年4月 - 現在 (名古屋大学大学院人文学研究科)
多言語修得基礎
2022年4月 - 2023年3月
日本語教育学発展演習
2022年4月 (名古屋大学大学院人文学研究科)
日本語教育学特殊研究
2022年4月 (名古屋大学大学院人文学研究科)
日本語教育文法論
2017年4月 - 2021年3月 (名古屋大学)
中級スペイン語
2016年4月 (名古屋大学)
スペイン語基礎
2015年4月 - 現在 (名古屋大学)