大学院国際開発研究科
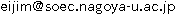
2023/03/31 更新

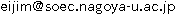
経済学博士 ( 2005年12月 ミシガン大学 )
ミシガン大学 経済学研究科 開発経済
- 2005年5月
国名: アメリカ合衆国
ミシガン大学 公共政策
- 1998年5月
国名: アメリカ合衆国
一橋大学 経済学部
- 1992年3月
国名: 日本国
American Economic Association (AEA)
Relative Deprivation and Health: Which Reference Groups Matter? 査読有り Open Access
Eiji Mangyo, Albert Park
Journal of Human Resources 46 巻 ( 3 ) 頁: 459-481 2011年
Water Accessibility and Child Health: Use of the Leave-Out Strategy of Instruments 査読有り
Dirga Kumar Lamichhane, Eiji Mangyo
Journal of Health Economics 30 巻 ( 5 ) 頁: 1000-1010 2011年
Vulnerability of Households to Health Shocks: An Indonesian Study 査読有り
Thi Nhu Nguyet, Eiji Mangyo
Bulletin of Indonesian Economic Studies 46 巻 ( 2 ) 頁: 213-235 2010年
Who Benefits More from Higher Household Consumption? The Intra-household Allocation of Nutrients in China 査読有り
Eiji Mangyo
Journal of Development Economics 86 巻 ( 2 ) 頁: 296-312 2008年
The Effect of Water Accessibility on Child Health in China 査読有り
Eiji Mangyo
Journal of Health Economics 27 巻 ( 5 ) 頁: 1343-1356 2008年
胎児期・乳幼児期における日常の栄養摂取が成人後の教育、健康、経済状況に与える影響
研究課題/研究課題番号:22K01459 2022年4月 - 2025年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(C)
萬行 英二
担当区分:研究代表者
配分額:4160000円 ( 直接経費:3200000円 、 間接経費:960000円 )
研究テーマ:胎児期および乳幼児期における日常の栄養摂取が、成人後の教育、健康、経済状況に与える影響~インドネシアにおける降雨量変動と米生産変動を自然実験として捉えて
本研究の重要性にもかかわらず、本仮説について因果推定を行った既存研究は2つしかない。その理由は、胎児期および乳幼児期という長期に渡る日常の栄養摂取についてデータを取ることが難しいことと、日常の栄養摂取という個々の家計の選択行動は、子どもが成人後の健康や経済状況などの結果変数を決定する上で内生的であるためである。この問題に対処するため、本研究では、インドネシアの食文化や米農業の知識に基づき、降雨量変動を米生産変動の操作変数として利用。
メコン河流域内「越境移民」の空間的相関と域内セーフティネット構想の研究
研究課題/研究課題番号:21H00639 2021年4月 - 2025年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(B)
大門 毅, 北野 尚宏, 萬行 英二, 内海 悠二, 長辻 貴之
担当区分:研究分担者
本研究の目的は,メコン河流域諸国間のインフラ整備により拡大した物的・人的接続性に伴い活発化した越境移民が、疫病・失業等の地域的に偏在するリスクの多寡に影響を受け居住パターンを形成することを地理情報として可視化し、空間情報を踏まえた制度インフラを構築できないかを問うものである。人口動態の空間的把握を行いながら、セーフティネットの制度面を拡充するという構想である。越境移民が抱えるリスクを空間情報として可視化し、リスクを軽減するための構想を描くこと、さらには構想を推し進めるための法制度や財政支出、対外援助の現状や域内セーフティネットの将来像を模索することが、本研究の核心的問いである。
本研究の目的はメコン河流域(GMS)諸国間のインフラ整備により拡大した物的・人的接続性に伴い活発化した越境移民が、疫病・失業等の地域的に偏在するリスクの多寡に影響を受け居住パターンを形成することを地理情報として可視化し、空間情報を踏まえた制度インフラを構築できないかを問うものである。特に、経済特区(SEZ)に進出する企業が雇用する越境移民に焦点をあてた、「域内セーフティネット構想」の有効性を検討する。人口動態の空間的把握を行いながら、セーフティネットの制度面を拡充するという構想である。空間的実態把握のため、越境移民が抱えるリスクを空間情報として「可視化」し、リスクを軽減するための構想を描くこと、さらには構想を推し進めるための法制度や財政支出、対外援助の現状や域内セーフティネットの将来像を模索することが、本研究の核心的問いである。
この問いに対して、GMS域内の人口流動の特徴を(道路・鉄道等)インフラ整備と関連づけ、空間情報として把握し、空間的相関の有無と関与する因子を明らかにすることについては計画通りに進捗したが、移民越境個票データについては収集できておらず、そのため計量分析に着手することはできなかった。
一方、GMS各国のセーフティネットに関する現状の政策的・制度的課題の整理や、世銀・ADB等のドナーのセーフティネット政策をとりまとめ、対外援助・投資について政策的含意を導出することについては複数回の研究会を実施し、計画通りに進捗した。
現地調査が実施できない代替案として、関係国についてインターネットを通じて個票調査を行った。各国サンプル数1000で4カ国4000の個票を入手することに成功した。現地調査の実施が制約を受ける中で今後もこうした方法を取り入れていく計画である。
現地調査を予定していたが海外渡航への制限がと渡航予定国で解除されず実施することができなかった。また、入手予定の越境移民データの個票データがミャンマーの政情不安等もあり、入手が遅れたことがその主要因である。
【現地調査】GMS各国が渡航を解除しはじめており、カンボジア、ベトナム、タイ、ラオス方面への渡航を行う計画。現地渡航ができない場合には、リモート方式(ZOOM/TEAMS)を通じてそれ以外の国についてもヒアリング等を行う計画。
【データ分析】越境移民データの更なる収集、モデル化、分析
【研究会】内外の研究者も交え、研究分担者の研究成果を共有し、国際ジャーナルに投稿予定の論文作成を開始する予定。
研究課題/研究課題番号:19K01625 2019年4月 - 2022年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(C)
萬行 英二
担当区分:研究代表者
配分額:4290000円 ( 直接経費:3300000円 、 間接経費:990000円 )
本研究では、2015年にネパールで発生した最大震度8強の地震による人的物的被害を社会経済ステータス(SES)グループ別に分析する。既存研究が指摘しているのは、地震による人的物的被害は低SESグループおいてより大きいことであるが、本研究では、既存研究の統計推定上の問題(サンプル選択の問題)にも対処しながら、地震震度と人的物的被害との関係を、その非線形性も考慮に入れて、SESグループ別に分析する。さらに、SESグループ別の地震被害に違いが発生するメカニズムとして、①高SESグループによる地震頑強地域への居住地選択(residential segregation)と②高・低SESグループ間の居住家屋の頑強性の違いを検証する。
2015年にネパールで発生した最大震度8強の地震による人的物的被害を社会経済ステータス(SES)グループ別に分析。また、SESグループ別の地震被害に違いが発生するメカニズムとして、高・低SESグループ間の居住家屋の頑強性の違いを検証。主要な発見は以下。
1.高・低SESグループ間の人的物的被害の差は、震度が増加するにつれて拡大。2.震度が増加するにつれて、居住家屋の頑強性(建築資材)の違いを通じてもたらされた被害の割合は、高・低SESグループともに、拡大。3.居住家屋の頑強性(建築資材)の違いを通じてもたらされた被害の割合は、すべての震度において、高SESグループよりも低SESグループで高い。
既存研究では高・低SESグループ間に存在する可能性がある震度の差はコントロールした上で、同じ震度のもとで高・低SESグループ間の人的物的被害の差について分析している。本研究は、既存研究と異なり、高・低SESグループ間に存在する可能性のある震度の違いはコントロールしない。地震が発生した際に高・低SESグループそれぞれが経験した人的物的被害を震度との関係で捉える。この分析で明らかになる情報は、救命活動(救命資源)の優先地域を決定したり、家屋の耐震化などの自然災害対策のための補助金などの資源配分を効率化するために有益である。(家屋耐震化工事にかかわる補助金を低SES地域に優先配分するなど。)
社会的因子である社会経済ステータスが生物的因子である健康に影響を与えるメカニズム
研究課題/研究課題番号:16K03619 2016年4月 - 2019年3月
萬行 英二
担当区分:研究代表者
配分額:4420000円 ( 直接経費:3400000円 、 間接経費:1020000円 )
バングラデシュにおいて飲料水に含まれるヒ素が乳幼児の健康に与える影響を分析。バ国では大多数の家計が地下水を飲料水として利用しているが、バ国における地下水の中には地質化学的に自然発生したヒ素が多くの地域で含まれており、地下水の中のヒ素含有量は地域的なバラツキがある。1990年代のヒ素啓発キャンペーンによりバ政府はヒ素濃度の高い井戸の使用を止めて、比較的ヒ素濃度の低い井戸の使用を推奨。本研究の成果として次のことがわかった。キャンペーン前後の乳幼児の健康状態の改善は、ヒ素濃度の高い地域でヒ素濃度の低い地域より大きかったが、家長の教育程度の違いによって乳幼児の健康状態の改善の程度には大きな差があった。
人々の間に存在する健康の格差について、その発生のメカニズムは、ほぼ全くと言っていいほど解明されていない。これまで多くの研究が指摘していることは、教育や所得などの社会経済ステータス(SES)と健康状態は正相関していることである。本研究は、バングラデシュのヒ素啓発キャンペーンを自然実験として捉え、家計の教育の違いによって飲料水の取得についての行動に違いがあり、それが家計の乳幼児の子供の健康状態の違いにつながっている可能性を指摘した。