大学院法学研究科
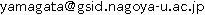
2025/02/18 更新

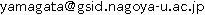
法学修士 ( 1989年12月 シェフィールド大学 )
法学修士 ( 1985年3月 京都大学 )
紛争の平和的解決及び国連集団安全保障体制
その他 / その他 / 国際法学
人間の安全保障と保護する責任
国際司法裁判所の研究
条約解釈規則
名古屋大学大学院国際開発研究科教授
2005年10月
国名:日本国
立命館大学国際関係学部教授
2002年4月 - 2005年9月
国名:日本国
立命館大学国際関係学部助教授
1994年4月 - 2002年3月
国名:日本国
岡山商科大学法経学部法学科講師
1991年4月 - 1994年3月
国名:日本国
日本学術振興会特別研究員
1990年4月 - 1991年3月
国名:日本国
京都大学法学部助手
1989年4月 - 1990年3月
国名:日本国
シェフィールド大学 法学部
1987年10月 - 1989年12月
国名: グレートブリテン・北アイルランド連合王国(英国)
京都大学 法学研究科 公法専攻
1985年4月 - 1989年3月
国名: 日本国
京都大学 法学研究科 公法専攻
1983年4月 - 1985年3月
国名: 日本国
静岡大学 人文学部 法学科
1978年4月 - 1982年3月
国名: 日本国
国際法学会
世界法学会
American Society of International Law
International Law Association
国際人権法学会
日本国際経済法学会
国際司法裁判所における貨幣用金原則の再構成 招待有り
山形英郎
浅田正彦他編『国家と海洋の国際法』 上巻 巻 2025年2月
国際司法裁判所における人権訴訟の展開と「相互融合」の功罪 招待有り
山形英郎
申惠丰編『国際的メカニズム』(新国際人権法講座第4巻) 頁: 145 - 172 2024年2月
国際司法裁判所における第三者法益原則の誕生 招待有り
山形英郎
法学雑誌(大阪公立大学) 69 巻 ( 3・4 ) 頁: 35 - 68 2023年3月
国際法からみたロシアのウクライナ侵攻 招待有り
山形英郎
経済 ( 323 ) 頁: 31 - 42 2022年8月
紛争解決 招待有り
山形英郎
浅田正彦編『国際法【第5版】』 頁: 433 - 466 2022年3月
「平成」日本の安全保障法政策:「二つの法体系」の収斂 招待有り
山形英郎
法の科学 ( 52 ) 頁: 18 - 29 2021年9月
第三者法益原則 招待有り
山形英郎
国際法判例百選第3版 頁: 198 - 199 2021年9月
条約解釈と解釈手法 招待有り
山形英郎
法学教室 2021年8月 巻 ( 491 ) 頁: 20 - 24 2021年8月
国際法から読み解くソレイマニ司令官殺害事件と自衛隊中東派遣 招待有り
山形英郎
法と民主主義 ( 548 ) 頁: 51 - 55 2020年5月
ASEANの国際機構性とASEAN Way 招待有り
山形英郎
芹田健太郎他編『実証の国際法学の継承』 頁: 705ー723 2019年12月
南シナ海事件と日本:沖ノ鳥島の法的地位 招待有り
山形英郎
静岡大学法経研究 23 巻 ( 3・4 ) 頁: 213-238 2019年4月
Multilateral Management of the South China Sea Dispute 招待有り
YAMAGATA Hideo
International Review of Contemporary Law 2018 巻 頁: 77-90 2018年11月
Multinational Management of the South China Sea Dispute 招待有り
YAMAGATA Hideo
National Union of Peoples' Lawyers ed., Conference on the South China Sea Dispute and the Search for Peaceful Resolution 頁: 92-110 2017年10月
「紛争解決」 招待有り
山形英郎
浅田正彦編『国際法』第3版 頁: 409-440 2016年4月
「日本国政府の集団的自衛権理解とその現実的効果」
山形英郎
法の科学 ( 46 ) 頁: 74-80 2015年9月
「国連の歩み:戦争と主権の相克」 招待有り
山形英郎
日本の科学者 50 巻 ( 8 ) 頁: 6-11 2015年8月
The Chinese Non-Appearing Strategy in the Arbitration Initiated by the Philippines under the 1982 UNCLOS 査読有り
Mai Hong Quy (ed.), Legal Issues Regarding the Incident of China's Placement of Oil Rig Haiyang Shiyou 981 in Vietnam's EEZ and CS 頁: 153-161 2015年5月
「必要最小限度の限定的な集団的自衛権論」 招待有り
山形英郎
法律時報 86 巻 ( 10 ) 頁: 66-71 2014年9月
「紛争解決」
山形英郎
浅田正彦編『国際法』第2版 頁: 377-405 2013年4月
「国際法形成過程における理論の役割」 招待有り
山形英郎
法の科学 ( 43 ) 頁: 44-57 2012年9月
「21世紀国際法における民族自決権の意義」 招待有り
山形英郎
法政論集(名古屋大学) ( 245 ) 頁: 517-560 2012年8月
「条約解釈の補助的手段たる準備作業の意義」 招待有り
山形英郎
松田竹男・田中則夫・薬師寺公夫・坂本茂樹編『現代国際法の思想と構造Ⅰ』東信堂 頁: 258-303 2012年3月
「国際組織の権限に対するICJの司法的コントロール」 招待有り
山形英郎
ジュリスト増刊『国際法判例百選』 頁: 214-215 2011年9月
「紛争解決」
山形英郎
浅田正彦編『国際法』東信堂 頁: 349-374 2011年4月
「国際司法裁判所における条約解釈手段の展開」
日本国際経済法学会年報 ( 19 ) 頁: 27-54 2010年10月
「自由権規約のダイナミズム」
ジュリスト ( 1409 ) 頁: 47-56 2010年10月
「人間の安全保障と国家の安全保障」
『安保改定50年』(法律時報増刊) 頁: 71-78 2010年6月
「条約解釈目的と条約解釈手段」
法学雑誌(大阪市立大学) 56 巻 ( 3/4 ) 頁: 425-459 2010年3月
「条約の解釈とは何か」
法学セミナー ( 661 ) 頁: 18-21 2010年1月
「平和構築における国際社会の役割」
大坪滋、木村宏恒、伊東早苗編『国際開発学入門』 頁: 461-463、478-489 2009年12月
「国際の平和と安全の維持」
家正治、小畑郁、桐山孝信編『国際機構』(第4版) 頁: 63-97 2009年10月
Responsibility to Protect Democracy as a Robust International Legal Order 査読有り
Ritsumeikan International Affairs 7 巻 頁: 21-47 2009年3月
「集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する適用事件」 招待有り
山形英郎
国際人権 ( 19 ) 頁: 191-196 2008年11月
「グローバリゼーションと国際法:価値絶対的国際法の出現」 招待有り
大久保史郎編『グローバリゼーションと人間の安全保障』日本評論社 頁: 95-124 2007年7月
「『人道的干渉』から『住民保護責任』への転換?」 査読有り
国際開発研究フォーラム ( 34 ) 頁: 67-85 2007年3月
「対テロ戦争と自衛権」
中逵啓治編『東アジア共同体という幻想』ナカニシヤ出版 頁: 153-180 2006年8月
「国際司法裁判所における反訴手続」
浅田正彦編『21世紀国際法の課題』有信堂 頁: 253-283 2006年7月
「国際裁判所の多様化」 査読有り
国際法外交雑誌 104 巻 ( 4 ) 頁: 37-62 2006年1月
“Law and Lawyers in the Service of the People for Peace, Justice and Development”
Igarashi Mashihiro, Yamagata Hideo, Okada Izumi, Okada Junko, Itakura Minako, Kiriyama Takanobu, Obata Kaoru, Nakasaka Emiko, Takamura Yukari, Sugishima Masaki
38 巻 ( 3 ) 頁: 811 - 863 2005年12月
「国際法への挑戦:『人間の安全保障』」 招待有り
佐藤誠・安藤次男編『人間の安全保障:世界危機への挑戦』 頁: 29 - 58 2004年11月
「国際司法裁判所における反訴の受理可能性」 招待有り
安藤仁介・中村道・位田隆一編『21世紀の国際機構:課題と展望』 頁: 369 - 406 2004年5月
「伝統的な政治的紛争理論と戦争違法化」 招待有り
山手治之・香西茂編『国際社会の法構造:その歴史と構造』 頁: 117 - 151 2003年3月
“Self-Defence against the Terrorist Attacks on September 11, 2001” 招待有り 査読有り
Korea Review of International Studies 5 巻 頁: 49 - 69 2003年
「九・一一以降の国際法の世界」 招待有り
法の科学 ( 33 ) 頁: 111 - 135 2003年
“A New Century of the Japan-US Defence Cooperation for the Far Eastern Security”
Ritsumeikan Journal of International Relations and Area Studies ( 20 ) 頁: 49 - 61 2002年3月
“International Law for the New Millennium”
Kiriyama Takanobu, Yamagata Hideo, Nishimura Tomoaki, Sugishima Masaki, Igarashi Masahiro
Ritsumeikan Jounal of International Relations and Area Studies ( 20 ) 頁: 123 - 142 2002年3月
「同時多発テロに対する『報復』攻撃」
法律時報 74 巻 ( 1 ) 頁: 82 - 85 2002年1月
「ラグラン事件」 査読有り
国際人権 ( 13 ) 頁: 113 - 116 2002年
「法律的紛争(法律問題)と政治的紛争(政治問題)」 招待有り
山本草二・古川照美・松井芳郎編」『国際法判例百選』 頁: 186 - 187 2001年4月
“Towards New Democratic International Law”
Tanaka Norio, Igarashi Masahiro, Kiriyama Takanobu, Okada Junko, Yamagata Hideo
Ryukoku Law Review 29 巻 ( 3 ) 頁: 709 - 788 1996年12月
「国際司法裁判所における仮保全措置の法的効力」
法の科学 ( 23 ) 頁: 182 - 191 1995年7月
「国際紛争解決システムにおける司法的解決の意義」 査読有り
世界法年報 ( 13 ) 頁: 28 - 44 1993年10月
「伝統的な政治的紛争理論の再検討」
現代法学の諸相(岡山商科大学法経学部創設記念論集) 頁: 202 - 227 1992年11月
「国際司法裁判所における欠席裁判(2完)」 査読有り
法学論叢(京都大学) 126 巻 ( 1 ) 頁: 24 - 57 1989年10月
「国際司法裁判所における欠席裁判(1)」 査読有り
法学論叢 125 巻 ( 2 ) 頁: 20 - 42 1989年5月
『国際法入門:逆から学ぶ【第3版】』
山形英郎( 担当: 編集)
法律文化社 2022年10月
『国際法入門:逆から学ぶ【第2版】』
山形英郎、比屋定泰治、楢林建司、黒崎将広、桐山孝信、松井章浩、西方聡哉、西村智朗、岡田順子、木原正樹、板倉美奈子、中坂恵美子、前田直子、稲角光恵、川島富士雄、繁田泰宏、中井伊都子、小坂田裕子、徳川信治、湯山智之( 担当: 編集)
法律文化社 2018年10月 ( ISBN:978-4-589-03960-6 )
『集団的自衛権容認を批判する』
渡辺治・山形英郎・浦田一郎・君島東彦・小沢隆一( 担当: 共著 , 範囲: 第2章「国際法から見た集団的自衛権行使容認の問題点」)
日本評論社 2014年8月 ( ISBN:978-4-535-40845-6 )
『国際法入門~逆から学ぶ~』
山形英郎(編)( 担当: 共著)
法律文化社 2014年4月 ( ISBN:978-4-589-03586-8 )
松井芳郎・木棚照一・薬師寺公夫・山形英郎編『グローバル化する世界と法の課題』
( 担当: 共著 , 範囲: 国際法における『形式的法源』と『実質的法源』)
東信堂 2006年3月
家正治編『講義国際組織入門』
家正治・城山正幸・末吉洋文・戸田五郎・中井伊都子・西村智朗・山形英郎( 担当: 共著 , 範囲: 「紛争処理」、「国連と安全保障」、「平和維持活動」、「地域的機関と安全保障」、「軍備縮小および軍備管理に関する国際組織」)
不磨書房 2003年10月
関下稔・小林誠・山形英郎・森岡真史・南野泰義共編著『プロブレマティーク国際関係』
( 担当: 共編者(共編著者) , 範囲: 第4章「国際連合と平和の維持」)
東信堂 1996年4月
敵基地攻撃論と国際法上の自衛権 招待有り
山形英郎
住民と自治 ( 2022年9月号 ) 頁: 34 - 35 2022年8月
書評「松井芳郎著『武力禁止原則の歴史と現状』」 招待有り
法の科学 ( 50 ) 頁: 159 - 162 2019年9月
「在テヘラン米国大使館事件」、「仲裁裁判判決の無効」、「ロッカビー事件」、「ジェノサイド条約適用事件」、「ラグラン事件」 招待有り
薬師寺公夫・坂元茂樹・浅田正彦・酒井啓亘編『判例国際法第3版』 2019年6月
「在テヘラン米国大使館事件」、 「仲裁裁判判決の無効」、「ロッカビー事件」、「ジェノサイド条約適用事件」、「ラグラン事件」 招待有り
松井芳郎編集代表『判例国際法(第2版)』 2006年5月
「義務的裁判」、「欠席裁判」、「ジェノサイド条約適用事件」、「訴答書面」、「中米司法裁判所」、「反訴」 招待有り 査読有り
国際法学会編『国際関係法辞典』(第2版) 2005年9月
「国際司法裁判」
猪口孝・田中明彦・恒川恵一・薬師寺泰蔵・山内昌之編『国際政治事典』 2005年
「簡易手続部」、「勧告的意見」、「欠席裁判」、「国際司法裁判所」、「国際司法裁判所規程」、「国際紛争平和的処理一般議定書」、「国際紛争平和的処理条約」、「コンプロミー」、「裁判準則」、「裁判条約」、「裁判不能」、「ジュネーブ議定書」、「常設国際司法裁判所」、「常設仲裁裁判所」、「先決的抗弁」、「訴訟参加」、「仲裁裁判」、「仲裁手続に関するモデル規則」、「特別裁判部」、「任意的裁判」、「ノッテボーム・ルール」、「マリア・ルース号事件」 招待有り
『コンサイス法律用語事典』 2003年
紹介「波多野里望他『国際司法裁判所:判決と意見』第1巻および第2巻」 査読有り
国際法外交雑誌99 巻 ( 1 ) 頁: 99 - 103 2000年4月
“Yuji Iwasawa, International Law, Human Rights and Japanese Law” 査読有り
British Year Book of International Law70 巻 頁: 257 - 258 2000年
「在テヘラン米国大使館事件」、「ロッカビー事件」、「ジェノサイド条約適用事件」、「ブリアード事件」、「ラグラン事件」、「武力行使に関する事件」および索引 招待有り
田畑茂二郎・竹本正幸・松井芳郎編『判例国際法』 2000年
「欠席裁判」、「訴答書面」、「中米司法裁判所」、「反訴」 招待有り
国際法学会編『国際関係法辞典』 1999年
「ICJの管轄権」、「ICJの仮保全措置」 招待有り
香西茂・竹本正幸・坂元茂樹編『プラクティス国際法』 頁: 120 - 125 1998年8月
「法選予想48題国際公法」 招待有り
『受験新報』 ( 1998年7月号 ) 1998年7月
「国際司法裁判所争訟事件一覧表」「国際司法裁判所勧告的意見一覧表」「国際法年表」 招待有り
田畑茂二郎・高林秀雄編集代表『ベーシック条約集』 1997年3月
「学会回顧:国際法」 招待有り
小畑郁・山形英郎
法律時報67 巻 ( 13 ) 頁: 162 - 167 1995年12月
「国際司法判例:カタールとバーレーンの海洋画定および領域問題に関する事件」
立命館国際研究7 巻 ( 4 ) 頁: 124 - 141 1995年
「学会回顧:国際法」 招待有り
小畑郁・山形英郎
法律時報66 巻 ( 13 ) 頁: 159 - 165 1994年12月
国際司法判例「ジェノサイド条約適用事件:仮保全措置指示要請命令」
岡山商科大学法学論叢 ( 2 ) 頁: 113 - 141 1994年2月
国際司法判例「ジェノサイド条約適用事件:第2次仮保全措置指示要請命令」
岡山商大論叢30 巻 ( 1 ) 頁: 195 - 232 1994年
国際司法判例「1971年モントリオール条約事件」
岡山商科大学法学論叢 ( 1 ) 頁: 129 - 144 1993年2月
国際司法判例「ナウル・リン鉱事件」
岡山商大論叢29 巻 ( 2 ) 頁: 231 - 270 1993年
「建物明渡請求事件」 招待有り
太寿堂鼎・高林秀雄・山手治之・香西茂・竹本正幸・安藤仁介編『セミナー国際法』 頁: 95 - 98 1992年7月
紹介「T. D. Gill, Litigation Strategy at the International Court」 査読有り
国際法外交雑誌90 巻 ( 1 ) 頁: 111 - 114 1991年4月
国際司法裁判所における貨幣用金原則の再検討
山形英郎
国際法学会2024年度研究大会 2024年9月4日 国際法学会
Russian Aggression against Ukraine 招待有り 国際会議
2022年11月2日
平成日本の国際法政策 招待有り
山形英郎
民主主義科学者協会法律部会学術総会 2020年12月6日 民主主義科学者協会法律部会
Multilateral Management of the South China Sea Dispute 招待有り 国際会議
The South China Sea Dispute and Search for a Peaceful Resolution
Development of ASEAN from the Perspective of International Organizations Law: ASEAN Way v. Organization-hood 招待有り 国際会議
Fiscal year 2016 International Conference on Legal Assistance Studies
China's Mishandling of the South China Sea Arbitration 招待有り 国際会議
Legal Issues Relating to the Award of the Hague Permanent Court of Arbitration
Rocks and Artificial Islands under the 1982 UNCLOS 国際会議
YAMAGATA Hideo
集団的自衛権と日米安保
山形英郎
アジア国際法学会日本協会第6回秋期研究会
Unsettled Legal Status of Okinotorishima: A Rock or an Island? 国際会議
YAMAGATA Hideo
The Construction of Artificial Islands in the Ease Sea and Its Impacts on Peace, Security, Economic and Trade Development in the Region
Japan's Proactive Defense Policy and Its Implications on the South China Sea Dispute 国際会議
YAMAGATA Hideo
New Tensions in the South China Sea
変容する国際社会における集団的自衛権と集団安全保障の位相
山形英郎
民主主義科学者協会法律部会学術総会
The Chinese No-Appearing Strategy in the Arbitration Initiated by the Philippines under the 1982 UNCLOS 国際会議
YAMAGATA Hideo
International Conference on Legal Issues Regarding the Incident of China's Placement of the Oil Rig Haiyang Shiyou 981 in the Seas of Vietnam
国際法形成過程における理論の役割
山形英郎
民主主義科学者協会法律部会学術総会
21世紀国際法における民族自決権の意義
山形英郎
世界法学会
*国際司法裁判所における条約解釈手法の展開
日本国際経済法学会
Changing Rules Regulating Use of Force in International Law? 国際会議
*Responsibility to Protect Democracy 国際会議
Four Societies' Conference of International Law
*国際裁判所の多様化
国際法学会
「国際紛争解決システムにおける司法的解決の意義」 招待有り
世界法学会研究大会 1993年 世界法学会
「安全保障理事会に対する司法的コントロール」
国際法学会秋期研究大会 1995年 国際法学会
Responsibility to Protect
2008年9月
資金種別:競争的資金
国際司法裁判所による「静かな革命」:対世的権利義務の導入と第三者法益原則の矛盾
研究課題/研究課題番号:23K01111 2023年4月 - 2027年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(C)
山形 英郎
担当区分:研究代表者
配分額:4810000円 ( 直接経費:3700000円 、 間接経費:1110000円 )
研究課題/研究課題番号:19KK0029 2019年10月 - 2022年3月
科学研究費助成事業 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B))
石川 知子, 西川 由紀子, 山形 英郎
担当区分:研究分担者
本研究は、クロスボーダーの経済活動がもたらす新たな安全保障上の脅威の増大及び、現在の貿易・投資をめぐる国際的枠組みが、かかる安全保障上の脅威に対応していないとの問題意識に基づき、国際社会が、今後さらに高まることが予想される経済グローバライゼーションと安全保障との間の緊張関係に効果的に対処するためには、この問題に係る国際協力の枠組みの構築が不可欠であると考え、この問題に係る国際協力の枠組みとして考え得る複数の理論的可能性、かつ、その実践に係る実務的な問題を、国際法学及び国際政治学双方の視点から検討する。
2020年度は、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、研究代表者、研究分担者、海外研究協力者のいずれも、予定していた海外調査は行うことができず、文献調査を中心とした研究活動を行うこととなった。研究代表者は、海外調査の困難を踏まえ、文献調査中心に研究が進められるテーマとして、サイバーセキュリティに焦点を絞ることとし、海外研究協力者と共同で、"Policy, and Borderless Security Threats: Potential & Limitations of the Current Framework"というタイトルで編著の執筆を企画し、2020年度にBook proposalのドラフトを完成させた。サイバーセキュリティをめぐる国家、民間セクター、専門家の各責任と、国際的な協力メカニズムの構築の必要性、具体的な方策につき、国際法及び国際関係論の専門家による分析を行う予定であり、著者候補者によるミーティングを2回に渡り開催した。研究代表者は、サイバーセキュリティ問題を抱える投資を受け入れる国の国際法上の責任に焦点をあてるため、米州人権裁判所、アフリカ人権委員会、欧州人権裁判所の判例を中心とした判例調査を網羅的に行った。本調査は、2021年度に執筆予定の上記著書のサンプル章の土台となる。海外研究協力者は、民間事業者によるサイバー被害(プライバシー等人権侵害)の責任が、国際法上国に帰属する場面の有無と範囲につき検討を行う。
その他、2020年度中、研究代表者、研究分担者、海外研究協力者はそれぞれ、安全保障に広く関連する論文、分担著書の発表、学会や国際シンポジウムにおける発表を行っている。
新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、研究代表者、研究分担者、海外研究協力者のいずれも、予定していた海外調査が行えていない(研究代表者と海外研究協力者が最後に行った海外研究調査は、2020年2月である。)一方、文献調査に基づき、編著のBook Proposalの執筆は行うことができた。また、2020年度中にそれぞれが、本研究課題に関する論文、分担著書、研究発表を行っており、一定の研究成果を挙げている。
2021年度は、計画している、研究代表者と海外研究協力者の編著"Policy, and Borderless Security Threats: Potential & Limitations of the Current Framework"のサンプル章を執筆し、出版社との交渉を行い、出版契約の締結を目指す。また、新型コロナウィルス感染症の拡大状況次第であるが、可能であれば欧州で調査及び発表の場を設けたいと考えている。
日本国憲法第9条における専守防衛法理の研究:自衛権論を超えた安全保障論
研究課題/研究課題番号:18H00794 2018年4月 - 2021年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(B)
山形 英郎, 桐山 孝信, 奥野 恒久, 西川 由紀子
担当区分:研究代表者
配分額:4810000円 ( 直接経費:3700000円 、 間接経費:1110000円 )
本プロジェクトは、日本国憲法第9条における専守防衛の法理を研究することを目的としている。憲法第9条では自衛権を中心に議論が集約していたが、自衛権を超えて専守防衛を基礎にした憲法論を構築する狙いを有している。
本年度は、2020年度初頭発生したアメリカ合衆国によるイランの司令官ソレイマニ氏殺害事件を取り上げ、自衛権で以て正当化できるかのどうか、そしてイランが行った在イラク米国基地空爆を同様に自衛権で正当化できるかを考察した。時事問題であるが、自衛艦を情報収集の目的でホルムズ海峡付近に派遣する決定についても、憲法論との関係で検討した。アメリカ合衆国及びイラン双方の空爆は、少なくともイラクの領土主権を害するものであり、イラクに対する武力行使であることを明らかにした。加えて、自衛権の要件である「武力攻撃の発生」が存在したと言えるかという点について、大いなる疑問を提出した。結論としては、アメリカ合衆国もイランも、自衛権の正当な行使と認めることはできず、違法な武力行使を繰り返しただけであるということになる。
また、第9条をめぐっては、二つの法体系論が長谷川正安によって提唱されていた。すなわち日米安全保障条約体制と第9条を根幹とする日本国憲法体制が、矛盾しながら存在するという理論である。しかし、平成の時代において、国連において集団安全保障体制は、授権方式の採用により同盟体制に依拠せざるをえなくなり、同盟を中心とした安全保障体制に変容した。それに伴い、日米安保体制もグローバル安保体制に変容し、2015年の集団的自衛権容認によって、二つの法体系論は、同盟体制を中心とする国連体制の下で、一元化されたことを明確にした。
令和2年度が最終年度であるため、記入しない。
令和2年度が最終年度であるため、記入しない。
研究課題/研究課題番号:16KT0088 2016年7月 - 2022年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(B)
伊東 早苗, 岡田 勇, 東村 岳史, 西川 由紀子, 山形 英郎, 島田 弦, 日下 渉, 石川 知子, 藤川 清史, 上田 晶子, 劉 靖
担当区分:研究分担者
コロナ禍により、海外出張ができず、現地調査を行うことはできなかった。しかしながら、計画していた東アジアの開発協力をテーマにした書籍出版のための執筆活動を継続し、2020年9月、2021年3月の2回、本科研事業参加者に海外研究者4名を加え、オンラインで執筆者ワークショップおよび出版打ち合わせを実施した。とりわけ、序章を執筆する研究代表者と、日本、韓国、中国による開発協力の総論および事例を担当する執筆者との全体概念のすり合わせに時間を使い、この作業はワークショップ以降も、メールを通じて継続している。また、途中に執筆者の交代や追加があり、各章の完成までの執筆状況には差があるものの、重要な5章分の草稿は完成している。ただし、新型コロナ感染症が世界に与える影響の大きさに鑑みて、コロナ後に変貌するであろう開発協力の様相を執筆の際に考慮に入れる必要性が生じている。
東アジア地域以外では、ラテンアメリカの開発主義国家と新自由主義の相克をテーマにしたオンラインでの研究打ち合わせ、米中による開発協力の狭間で揺れ動くフィリピン外交に関係する論文執筆等を実施した他、国際法の観点から、東南アジアの法整備支援に関わる国際協力についての書籍出版、グローバルな国際仲裁や民主化について、オンラインによる研究打ち合わせや学会報告を実施した。さらに、気候変動に関わる国際協力の枠組みについて、変貌する国際関係を視野に入れた研究発表を行った。これらを通じ、開発協力に関わる異なる地域やセクターにみられる個別の局面とグローバルな開発協力の全体枠組みがどのように関係し、どのような言説の変化を生んでいるか、さらに、それらはコロナ後にどのように変貌するかを参加者間で随時、議論し、出版する書籍の内容に反映させてきた。
前年度に引き続き、昨年度はほぼ全時期にわたる新型コロナ感染症への対応により、研究活動に大きな影響が出た。オンラインでの打ち合わせや学会参加が可能になった面はあるものの、現地に赴くことでしか得ることができない種類の実証的なデータを収集することができなかった。また、前年度に引き続き、研究代表者が名古屋大学の副総長を務めたことにより、大学執行部としてのコロナ対応他、大学全体に関わる諸業務に時間をとられ、本科研事業の代表者として研究統括のための強いリーダーシップを発揮することが困難な状況であった。
2021年4月より、研究代表者は大学執行部の任期を終え、部局教員の立場に戻った。それにより、本研究事業に割くことのできる時間とエネルギーの優先順位が大幅に変わった。現在、本科研事業の総まとめである書籍出版事業を最優先事項として、国内外の執筆者と連絡をとりあい、打ち合わせを重ねている。コロナ禍の状況に鑑み、今年度も現地調査等は計画せず、執筆活動およびオンラインでの打ち合わせや研究集会の開催に専念する。
住民保護責任:破綻国家研究序説
2007年4月 - 2010年3月
科学研究費補助金 萌芽研究
山形英郎
担当区分:研究代表者
武力行使単独主義の国際法理論:新現代正戦論の研究
2004年4月 - 2006年3月
科学研究費補助金 基盤研究(C)
山形英郎
担当区分:研究代表者
ウクライナ戦争と国際平和秩序
役割:講師
非核の政府を求める会 2023年1月
国際法から敵基地攻撃を考える
役割:講師
名古屋9条の会 2022年4月
日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員および国際事業委員会書面審査員
2010年8月 - 2011年7月