大学院法学研究科
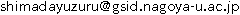
2025/03/31 更新

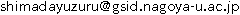
博士(学術) ( 2002年3月 名古屋大学 )
修士(学術) ( 1995年3月 名古屋大学 )
学士(法学) ( 1993年3月 金沢大学 )
平和構築と法
インドネシア法
開発法学
アジア法
比較法
その他 / その他 / 基礎法学
インドネシアにおける法と人権
![]()
アチェ津波被害復興プロセスにおける法の役割
![]()
法と開発
![]()
名古屋大学 国際開発研究科 教授
2015年4月 - 現在
国名:日本国
名古屋大学大学院・国際開発研究科・准教授
2007年 - 2015年3月
国名:日本国
名古屋外国語大学・外国語学部・講師
2005年 - 2007年
国名:日本国
日本学術振興会・特別研究員
2003年 - 2005年
国名:日本国
日本貿易振興会・アジア経済研究所・国内客員研究員
2000年 - 2001年
国名:日本国
名古屋大学 国際開発研究科 国際協力専攻
1995年4月 - 2002年3月
国名: 日本国
名古屋大学 国際開発研究科 国際協力専攻
1993年4月 - 1995年3月
国名: 日本国
金沢大学 法学部
1989年4月 - 1993年3月
国名: 日本国
アジア法学会
日本法社会学会
国際開発学会
国際開発学会 常任理事(人材育成委員会委員長)
2018年10月 - 2020年9月
団体区分:学協会
Legal Changes during Joko Widodo’s Administration – Backsliding of Democracy? 招待有り 査読有り
Shimada Yuzuru
International Quarterly for Asian Studies 55 巻 ( 2 ) 頁: 269 - 287 2024年9月
ポスト権威主義インドネシアにおける移行期正義:法制度とその限界
島田弦
社会体制と法 19 巻 頁: 17 - 33 2022年6月
SHIMADA Yuzuru
Brawijaya Law Journal 9 巻 ( 1 ) 頁: 90 - 106 2022年4月
インドネシアにおける移行期正義:権威主義体積の人権侵害とポスト権威主義憲法体制 招待有り
島田 弦
比較法研究 82 巻 頁: 159 - 169 2021年12月
「新刊紹介:金子由芳著『ミャンマーの法と開発—変動する社会経済と法整備の課題』(晃洋書房、2018年、228ページ)」
島田弦
国際開発研究 28 巻 ( 2 ) 頁: 171-174 2019年11月
「ASEAN法とインドネシア法の緊張関係:インドネシアにおける立憲主義とASEAN憲章との関係についての考察」
島田弦
『社会体制と法』 ( 16/17 ) 頁: 20-31 2019年2月
「法と開発」
島田弦
国際開発学会編『国際開発学事典』丸善出版 頁: 228-229 2018年12月
「国家法と非公式法」
島田弦
国際開発学会編『国際開発学事典』丸善出版 頁: 228-229 2018年12月
日本における地方自治の発展と中央地方関係:インドネシアとの比較 査読有り
頁: 1-7 2018年7月
Pembangunan Otonomi Daerah Jepang dan Hubungan Pusat-Daerah: Satu Perbandingan dengan Indonesia(日本における地方自治の発展と中央地方関係:インドネシアとの比較) 査読有り
島田弦
Budy Sugandi and Ali Rif'fan eds., Pemerintah dan Pemerintahan Daerah: Refleksi pada Era Reformasi, Insight Indonesia 頁: 1-7 2018年7月
Development of legal theory for environment protection and remedy for victims in Japan
Yuzuru Shimada
Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR) 98 巻 頁: 19-24 2018年
インドネシアにおける法令の種類、序列および整合性に関する法的枠組み(二・完) 招待有り
島田弦
ICD News 71 巻 頁: 69-78 2017年6月
The Object of Comparison in the Comparative Study of Constitutional Law 査読有り
Shimada Yuzuru
Besson, Heckendorn and Jube eds. Comparing Comparative Law 頁: 35-58 2017年4月
インドネシアにおける法令の種類、序列および整合性に関する法的枠組み(一) 招待有り
島田弦
ICD News 70 巻 頁: 95-103 2017年3月
東南アジア法史研究回顧 招待有り 査読有り Open Access
島田弦,西澤希久男,桑原尚子
法制史研究 66 巻 頁: 133−178 2017年3月
「インドネシア人民協議会の地位および機能-インドネシアの代議制における『代表』概念の考察」
島田弦
アジア法研究 9 巻 頁: 159-172 2016年3月
インドネシアにおけるシャリア法適用の変化:アチェ州における事例を中心に
島田弦
社会体制と法 14 巻 頁: 33-50 2014年3月
新刊紹介:松尾弘『開発法学の基礎理論-良い統治のための法律学』(勁草書房、2012年)
島田弦
国際開発研究 22 巻 ( 2 ) 頁: 69-71 2013年11月
インドネシア人の法律に対する意識
島田 弦
月刊インドネシア ( 770 ) 頁: 6-14 2012年7月
インドネシアにおける法の支配と民主化:移行過程における法律扶助運動 査読有り Open Access
島田 弦
国際開発研究フォーラム 42 巻 頁: 105-123 2012年3月
インドネシアにおける法律扶助運動の一側面:インドネシア法律扶助協会創設者・アドナン・ブユン・ナスティオン 査読有り Open Access
島田弦
名古屋大學法政論集 245 巻 頁: 277-298 2012年
平和構築における法制度改革-東ティモールの司法制度構築を事例として 招待有り 査読有り Open Access
島田 弦
国際開発研究 20 巻 ( 2 ) 頁: 65-78 2011年11月
*インドネシア・アダット法研究における19世紀オランダ法学の影響―ファン・フォレンホーフェンのアダット法研究に関する考察 査読有り Open Access
島田弦
国際開発研究フォーラム 38 巻 頁: 55-69 2009年3月
「インドネシアの環境紛争処理制度」 招待有り Open Access
島田弦
公害等調整委員会編『環境裁判・法執行に関するアジア・太平洋地域会議について』 頁: 193-203 2008年11月
アチェ津波災害復興プロセスにおける法の役割
島田弦
名古屋大学環境学研究科『2004年北部スマトラ地震調査報告III』 頁: 79-82 2007年2月
「アチェ津波被害復興における国家法・宗教法・慣習法の役割」
名古屋大学環境学研究科『2004年北部スマトラ地震調査報告II』 - 巻 ( - ) 頁: 132-136 2006年
*「インドネシアにおける植民地支配と「近代経験」-インドネシア国家原理とアダット法研究」 査読有り
『社会体制と法』 ( 6 ) 頁: 50-67 2005年
北村一郎編『アクセスガイド外国法』東京大学出版会、「インドネシア法」
- 巻 ( - ) 頁: 383-392 2004年
「インドネシアの憲法事情」
国立国会図書館調査及び立法考査局編『諸外国の憲法事情 3』国立国会図書館、2003年12月、 - 巻 ( - ) 頁: 64-84 2003年
「インドネシア最高裁判決にみる改革の矛盾」
『アジ研ワールド・トレンド』 8 巻 ( 2 ) 頁: 24-27 2002年
*「インドネシアの開発主義と人権を巡る裁判――90年代の判例分析」 査読有り
アジア経済第41巻第2号 41 巻 ( 2 ) 頁: 2-32 2000年2月
「インドネシアにおける開発と人権――1999年政党法の検討」
法学セミナー 44 巻 ( 10 ) 頁: 65-68 1999年10月
アジア法整備支援叢書・多様な法世界における法整備支援
島田弦、桑原尚子( 担当: 共編者(共編著者))
旬報社 2021年4月
アジア法整備支援叢書・インドネシア:民主化とグローバリゼーションへの挑戦
島田弦他( 担当: 編集)
旬報社 2020年6月 ( ISBN:9784845116393 )
*"The Role of Law in the Reconstruction Process of the Aceh Tsunami Disaster" in Per Bergling, Jenny Ederlof and Veronica L. Taylor eds. Rule of Law Promotion: Global Perspectives, Local Applications
( 担当: 単著)
Iustus 2010年1月
「インドネシア」鮎京正訓編『アジア法ガイドブック』名古屋大学出版会、130-155頁。
( 担当: 単著)
名古屋大学出版会 2009年10月
「イスラーム法」鮎京正訓編『アジア法ガイドブック』名古屋大学出版会、390-398頁。
( 担当: 単著)
名古屋大学出版会 2009年10月
*島田弦「改革期のインドネシアにおける汚職対策と法の支配」孝忠延夫・鈴木賢編著『北東アジアにおける法治の現状と課題』成文堂、2008。
( 担当: 単著)
成文堂 2008年10月
小林昌之編『アジア諸国の司法改革』、「インドネシアにおける司法改革――ポスト・スハルト期における司法権および裁判所の課題」
( 担当: 共著)
アジア経済研究所 2002年
「21.東ティモール民主共和国」鮎京正訓他編『新版アジア憲法集』
島田弦( 担当: 分担執筆 , 範囲: 「21.東ティモール民主共和国」)
明石書店 2021年12月
「3.ブルネイ・ダルサラーム国」鮎京正訓他編『新版アジア憲法集』
島田弦( 担当: 分担執筆 , 範囲: 「3.ブルネイ・ダルサラーム国」)
明石書店 2021年12月
「7.インドネシア共和国」鮎京正訓他編『新版アジア憲法集』
島田弦( 担当: 分担執筆 , 範囲: 「7.インドネシア共和国」)
明石書店 2021年12月
「制度と開発ー法と開発の制度論」島田弦・桑原尚子編著『法整備支援叢書・多様な法世界における法整備支援』
島田弦( 担当: 分担執筆 , 範囲: 第I部第5章)
旬報社 2021年4月
「『法の支配』と法整備支援」島田弦・桑原尚子編著『アジア法整備支援・多様な法世界における法整備支援』
島田弦( 担当: 分担執筆 , 範囲: 第I部第1章)
旬報社 2021年4月
「インドネシアについての概観」島田弦編著『アジア法整備支援叢書・インドネシア:民主化とグローバリゼーションへの挑戦』
島田弦( 担当: 単著)
旬報社 2020年6月
「はじめに」島田弦編著『アジア法整備支援叢書・インドネシア:民主化とグローバリゼーションへの挑戦』
島田弦( 担当: 単著)
旬報社 2020年6月
「東ティモールの国家構築と法制度構築」島田弦編著『アジア法整備支援叢書・インドネシア:民主化とグローバリゼーションへの挑戦』
島田弦( 担当: 単著)
旬報社 2020年6月
「インドネシア憲法思想の展開:人権概念を中心に」島田弦編著『アジア法整備支援叢書・インドネシア:民主化とグローバリゼーションへの挑戦』
島田弦( 担当: 単著)
旬報社 2020年6月
「インドネシア法」高田寛他編著『世界の法律事情:グローバル・リーガル・リサーチ』
島田 弦( 担当: 単著)
文眞堂 2016年6月
「V-2 災害リスク管理の法制度」高橋誠・田中重好・木股文昭編著『スマトラ地震による津波被害と復興』282-296頁
島田弦( 担当: 単著)
古今書院 2014年2月 ( ISBN:9784772241717 )
「III-3 被災後の法的課題」高橋誠・田中重好・木股文昭編著『スマトラ地震による津波被害と復興』136-148頁
島田弦( 担当: 単著)
古今書院 2014年2月 ( ISBN:9784772241717 )
"Legal systems for disaster management in Indonesia" in Djati Mardiatno and Makoto Takahashi eds., Community approach to disaster
Shimada Yuzuru( 担当: 単著)
Gadjah Mada university press 2012年7月 ( ISBN:979-420-787-X )
「開発における法の役割」大坪滋・木村宏恒・伊東早苗編『国際開発学入門-開発学の学際的構築』
( 担当: 単著)
勁草書房 2009年12月
Politics of Marginality in Indonesian Legislations in the Joko Widodo Administration 国際会議
Shimada Yuzuru
Asia Law and Society Association 2024年12月14日 Asia Law and Society Association
Local regulations quality and the local economy in Indonesia: A geospatial exploratory analysis 国際共著 国際会議
Yuzuru Shimada, Bangkit A. Wiryaman, Carlos Mendez-Guerra
Asian Law and Society Association Meeting 2023 2023年12月15日 Asia Law and Society Association
インドネシアにおけるCOVID-19パンデミック対策に関する諸法制
島田弦
アジア法学会学術総会 2022年6月19日 アジア法学会
Civil and Political Rights in Indonesia under old and new constitutionalism: Comparing human rights situation in the Soeharto regime and the Reformation era 国際会議
Shimada Yuzuru
Asian Law and Society Association (ALSA) Conference
Strategy and Regulatory Reform Practices in Japan: Harmonization of central and local regulations in the era of local autonomy 招待有り 国際会議
Shimada Yuzuru
Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (National Conference on the Constitutional Law)
Revisiting the freedom of expression in Indonesia: Socio-legal review of oppression against freedom under the New Order and its continuity 国際会議
Shimada Yuzuru
IANC's 1st Conference on Socio Legal Studies
Tension between ASEAN law and Indonesian law in the age of democratization 招待有り 国際会議
Shimada Yuzuru
the Indonesian Constitutional Court International Symposium
Development of legal theory for environment protection and remedy for pollution victims in Japan 招待有り 国際会議
Shimada Yuzuru
the 1st International Conference Postgraduate School Universitas Airlangga
Development of legal theory for environment protection and remedy for victims in Japan 招待有り 国際会議
Shimada Yuzuru
PROCEEDINGS OF THE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE POSTGRADUATE SCHOOL OF UNIVERSITAS AIRLANGGA: IMPLEMENTATION OF CLIMATE CHANGE AGREEMENT TO MEET SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (ICPSUAS 2017)
Concept of 'sovereignty' in Indonesia: Discussing the MPR 招待有り 国際会議
International Workshop "State, Constitutionalism & Citizenship in Southeast Asia"
The Place of Non-Judicial Staff in the Judicial Administration: Preliminary Research on Court Clerk in Indonesian District Court 国際会議
Shimada Yuzuru
Asian Law and Society Association (ALSA) Conference
ASEAN法とインドネシア法の緊張関係 国際会議
島田弦
社会体制と法研究会・研究総会
Transplantation of Legal Thought: Comparing actors and their ideasof law in legal transplantation in the Constitution of Japan andIndonesia 国際会議
Yuzuru Shimada
Yuzuru Shimada
Democracy and Constitutionalism in Indonesian Constitutional Court: Discussion from the Cases on Education Expenses in the National Budget 国際会議
Yuzuru Shimada
EuroSEAS 2015
インドネシア議会制における代表:人民協議会の地位および機能から
島田 弦
アジア法学会
Succession of Judiciary from colony to the Independent Indonesia: The roots of bureaucratic judiciary and its weakness 国際会議
Yuzuru Shimada
Asian Law Institute Annual Conference
法と開発の多様化と深化-アジアにおける動向と影響の検討
島田 弦
アジア法学会研究大会
Recent development of legal system on disaster management in Indonesia and its function: The role of law to support sustainability of society under the disaster 国際会議
SHIMADA Yuzuru
8th Asian Law Institute Conference
インドネシアにおける災害リスク対策法への伝統的共同体規範の統合:アチェの教訓と中部ジャワにおける実践 国際会議
SHIMADA Yuzuru,
インドネシアの法律事情-国家賠償を中心に
転換期アジアの「法の支配」再考:法と社会の相互作用から見る比較法研究
2015年10月 - 2016年9月
三菱財団助成
資金種別:競争的資金
【研究の背景】
現在、「法の支配」プログラムは、開発途上国に向けた国際開発協力において不可欠な要素となっている。わが国政府がアジア諸国を中心に実施している法整備支援においても、当該社会における「法の支配」の定着がその目標に掲げられている。しかしながら、とりわけ非欧米地域においては、経済的、社会的又は文化的諸事情から、「公式」の法制度を通じて紛争解決、権利の救済又は平等の実現が常に図られているわけではない。むしろ、「公式」の法制度に対する人々の信頼が欠如している例が散見される。また、妥協が困難な政治的対立を司法制度へ持ち込む、いわゆる「政治の司法化」現象が起きている。このような状況下で今日、「法の支配」の理解・態様は一層複雑化している。
【研究の目的】
本研究では、アジア諸国を題材として、社会と法との相互作用を重視する法学研究(Socio-legal Research)から「法の支配」の再定義を試みる。Socio-legal Researchというアプローチを用いる理由は、従来の法理学的・規範論的な法学研究が直面するアジア比較法研究の限界を乗り越え、社会的現実から「法の支配」を捉え直すことで新たな視点を獲得できると考えるからである。そして、非欧米諸国における「法の支配」の類型モデル(試案)を策定することが目的である。本研究で試案する「法の支配」類型モデルは、学術的な貢献だけでなく、国際開発協力における実効性ある「法の支配」プログラムに資することも射程とする。
現地調査は、主として、それぞれ特徴を有する国を対象として遂行する。すなわち、司法積極主義かつ「法の支配」が根付いていると評されるインド、司法消極主義と評されるマレーシア、シンガポール、権威主義体制から民主的体制への移行が確立しつつあるインドネシア、社会主義からの体制移行国であるモンゴル、初期の移行過程にあるミャンマーを現地調査の対象国とする。
インドネシア裁判所制度の変遷:裁判官人事と官僚的司法の歴史分析
2014年1月 - 2015年12月
JFE21世紀財団・アジア歴史研究助成
資金種別:競争的資金
インドネシアにおける裁判所の組織・運営について、オランダ植民地期から現代までの変化を歴史的に明らかにし、インドネシア司法行政の問題点と改革の方向性について、裁判官の人事という視点から考察する。植民地および独立後の裁判官の人事制度(任免、異動)および、司法と政府の関係を調査する。植民地以降の行政による人事から、最高裁による人事への変化に注目する。
インドネシア法における外国法の影響:リーガル・エンパワーメント支援への基礎研究
2012年10月 - 2013年9月
特定国派遣事業(オランダ)
資金種別:競争的資金
本研究の目的は、非欧米国であるインドネシア法の形成と発展における西洋法および近代法学の影響を明らかにすることである。
オランダ・ライデン大学Van Vollenhoven Insituteにおける共同研究を行った。
「開発のためのアジア学術ネットワーク」を活用した若手研究者育成:制度開発への貢献
2011年7月 - 2011年12月
日本学術振興会若手研究者招聘事業
資金種別:競争的資金
本交流計画では、「開発のためのアジア学術ネットワーク」(ANDA)に参加するアジア8カ国の研究教育機関に所属する修士課程を中心とする若手研究者・大学院生が、国際開発学において重要な課題となっている、すなわち"制度開発"(インスティテューショナル・ディベロプメント)に関する研究能力を高めることを目的とする。交流計画は若手研究者招聘と研究者交流から構成する。
平成20年度に、JSPSアジア・アフリカ学術基盤形成事業「グローバル化時代のアジアにおける新たなダイナミズムの胎動と産業人材育成」の一環で、本事業遂行のための研究協力体制となるアジア11カ国11大学間の研究・交流のためのネットワーク「Academic Network for Development in Asia (ANDA)(開発のためのアジア学術ネットワーク)」を構築した。事業開始からの3年間、本研究科は、これらの大学を拠点として、共同研究、国際セミナー開催などの活動を通じて、アジアの持続的発展のための政策提言や人材育成に貢献してきた。
若手研究者招聘では、ANDA参加機関において研究を行う修士課程学生・若手研究者を、本研究科に3週間招聘し研修を行う。ANDAは、平成20年に名古屋大学国際開発研究科を中心として、アジア諸国の主要大学をメンバーとして設立した大学間学術協力ネットワークである。本研究科では、特定問題群について集中的に学ぶため8つのプログラム科目群が設置されている。具体的には、本事業では、これらプログラム毎に2名の若手研究者を招聘し、プログラム内の講義及び演習へ参加し国際開発学に関する個別分野の最新動向・理論について習得し、また講義・教育方法についての技術を向上させる。更に、プログラム毎の所属スタッフとの共同検討会を実施し、研究能力・研究手法の向上を図る。また、研究報告会を実施し、招聘研究者間および本学研究者・大学院院生との間で各国の具体的状況について意見交換を行い、必要な研究課題について検討する。このプロセスを通じて、制度改革と能力向上を目標とする開発アプローチに必要な専門性と学際的・包括的な研究を意識した若手育成を目指す。
東南アジア諸国への近代憲法と民主主義の移入・変容過程と憲法政治に関する比較研究
研究課題/研究課題番号:24K00215 2024年4月 - 2028年3月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B)
島田 弦, 坂野, 瀬戸 裕之, 鮎京 正訓
担当区分:研究代表者 資金種別:競争的資金
配分額:18070000円 ( 直接経費:13900000円 、 間接経費:4170000円 )
東南アジアにおける憲法思想および民主主義制度の移入過程とその後の変容を比較し、①「権力の制限と人権の保障」を核心とする近代憲法モデルが現在の東南アジアでどのように位置づけることができるか、②もう一つの移入された制度としての民主主義が、各国の憲法政治に与える影響を明らかにする。
そこで、インドネシア、タイ、ベトナム、ラオスの4カ国を対象とし、憲法学の歴史的経過、政治制度の変遷、およびその憲法政治への影響を研究する。特に、①憲法の理論的側面として、憲法史および憲法学の歴史的経過と議論状況に加え、政治経済学的側面を重視し、②制度の変化、③憲法政治における合理的選択にという視点からも分析を行う。
衛星データと法令マッピングによるインドネシアの地域経済と分権に係る空間計量分析 国際共著
研究課題/研究課題番号:23H03617 2023年4月 - 2027年3月
日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤研究(B)
染矢將和
担当区分:研究分担者 資金種別:競争的資金
配分額:15470000円 ( 直接経費:11900000円 、 間接経費:3570000円 )
インドネシア・オランダ裁判制度改革の比較:法の移植と経路依存的発展の実証的分析
2013年4月 - 2017年3月
科学研究費補助金 基盤研究(C)
担当区分:研究代表者
本研究は、インドネシアおよびオランダの司法制度および司法実務の変化を歴史的に比較検証することにより、インドネシアにおいて実現しうる司法制度の発展および改革について考察することを目的とする。この研究計画では、法制度の発展は外部からの法および法制度の移植を契機となるとする「法の移植」論と、初期条件に規定される法制度の経路依存性という、比較法の方法論を実証的にことを目的とする。すなわち、インドネシア司法制度の母型となった、東インド植民地(現インドネシア)へ移植されたオランダ裁判制度実務の問題点、およびオランダにおけるその後の変化と、独立後のインドネシアにおける司法制度の変化を比較しつつ、類似した初期条件に規定された法および制度の発展について比較分析することを目的とする。
途上国におけるコミュニティベースの災害復興戦略とリスク管理
2011年4月 - 2015年3月
科学研究費補助金 基盤研究(B)
高橋誠
担当区分:研究分担者
民主化過程における「法の支配」-インドネシアにおける「法の支配」アクターの研究
2009年4月 - 2013年3月
科学研究費補助金 若手研究(B)
担当区分:研究代表者
「法の移植」論のアジア法への応用:インドネシア法へのオランダ法学理論の影響から
2006年4月 - 2009年3月
科学研究費補助金 若手研究(B),課題番号:18730013
島田 弦
担当区分:研究代表者
研究課題/研究課題番号:24K03164 2024年4月 - 2028年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(B)
水野 広祐, 高野 さやか, 藤原 敬大, 島田 弦, 笹岡 正俊
担当区分:研究分担者
今日のインドネシアにおいて国土の65%を占める政府指定の森林地域には5000万人の住民が住み、多くは必要な政府許可を得ていない。1960年土地基本法は、土地権は慣習法に基づくと規定している。また、多くの土地は未登記で住民は土地証書を持たない。本研究は、①慣習法に基づく土地権の実態とは何か。②土地権の不確定状況がうまれた経緯を、国有地(植民地期)と国家管理地(独立後)との関係史から明らかにする③スハルト大統領退陣・改革後の諸政策のこれら問題への影響を明らかにする。住民の土地権が不確定であるという喫緊の問題を分析し「慣習法に基づく土地法制度は可能か」と問い、インドネシア慣習法研究に革新をもたらす。
衛星データと法令マッピングによるインドネシアの地域経済と分権に係る空間計量分析
研究課題/研究課題番号:23H03617 2023年4月 - 2027年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(B)
染矢 將和, 島田 弦, メンデス カルロス
担当区分:研究分担者
本研究は、インドネシアの基礎自治体(県・市)ごとの多様な許認可・税制などに関する地方条例に反映される地方ガバナンスの質および地域の経済と地方分権の関係を明らかにする。基礎自治体の経済や所得格差については、衛星画像データを利用し、既存のデータを再構築し新たな地方自治体のデータベースを開発する。地方条例は、法令マッピングにより条例を共通の基準から公的制度としての投資許認可・税制に関する規制と、非公的制度の代替変数として権利制約的な条例を分類し、データベースを構築する。そのうえで、地方分権や地方ガバナンス、経済の関係をマルチスケール地理的重み付け回帰法により分析する。
衛星データと法令マッピングによるインドネシアの地域経済と分権に係る空間計量分析
研究課題/研究課題番号:23K28307 2023年4月 - 2027年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(B)
染矢 將和, メンデス カルロス, 島田 弦
担当区分:研究分担者
インドネシアの基礎地方自治体をサンプルとし、各自治体の制定する条例の規制の対象や範囲、種類を基に法令マッピングの手法により組成された制度要因に関する変数、地方分権の変数として地方自治体の歳出や歳入の一般政府の歳出や歳入に対する割合、経済変数として自治体の総生産(国内総生産に相当)や衛星照明データを主要な目的変数としてインフレ等その他の制御変数や衛星照明データを自治体の総生産の代理変数として使用して制度・経済・地方分権の間の関係の大きさや因果関係の方向性と隣接する地方自治体の当該自治体への空間的影響をマルチスケール地理的重み付け回帰法により定量的に明らかにする。
東アジアにおける憲法裁判制度と司法の変容ー韓国・台湾を中心に
研究課題/研究課題番号:20H01423 2020年4月 - 2024年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(B)
國分 典子, 蔡 秀卿, 牧野 力也, 松井 直之, 水島 玲央, 赤坂 正浩, 島田 弦, D. Gangabaatar, 岡 克彦
担当区分:研究分担者
本研究は、東アジアにおいて憲法裁判システムの活性化がどのような司法の変容を生み出しているかを分析するものである。
東アジアの憲法裁判については、政治部門との関係の考察は行われてきたが、憲法裁判が各国の司法自体をどのように変容させているかには注目されて来なかった。アジアでは伝統的に司法に対する不信が強い地域が多い。その中で憲法裁判機関の活動が活発化し国民の支持を得ることは、従来からの司法担当機関に対しても一定の影響を与えていると考えられる。そこで憲法裁判制度と従来型司法部門との関係に着目し、司法自体の変容を検討することをここでの重点課題とし、そこから法の支配の強化、民主主義への影響を展望する。
今年度は ① 韓国・台湾における「ドイツ型」導入の背景および発展理由要因の研究 ② 「ドイツ型」導入による韓国・台湾における従来型司法との関係性についての研究 の二点に重点をおいて、各参加者が調査・分析を行うことを予定していた。①に関する法史学的調査研究は2020年度に重点的に行う予定であったが、COVID-19のために海外での調査研究はなお調査が必要な部分が残っていたため、2021年度(繰越期間も含む)はそれぞれの研究参加者が担当地域で関連学術書の文献調査および現地研究者へのインタビュー等を行ったほか、韓国に関しては現地研究協力者から憲法の各領域における憲法裁判状況の報告を受けた。②に関しては、韓国に関しCOVID-19の既成が緩和された2022年に入って韓国担当の國分、岡、水島が現地で専門家へのインタビューおよび資料調査を行った。
台湾については、9月6日に台湾の中央研究院法律研究所李建良所長を招き、オンラインで研究会を行った。台湾は従来の大法官の権限を構成し直し、ドイツ的な憲法裁判所モデルに近い制度を導入することになったところである。そこで司法と政治の関係性に関する専門家である李所長が、①台湾で「政治的な判断」と評された大法官解釈にどのようなものがあるか、②台湾で大法官解釈はいかに政治的に影響を受けないように工夫しているのか、といった観点から報告を行い、その後、参加者の疑問点にさらに台湾行政法の専門家である研究分担者の蔡がこれを補足する報告を行って台湾の現状についての全員の知見を深めた。
また9月29日にインドネシアの専門家である研究分担者島田がインドネシアの憲法裁判の制度および問題点に関する報告を行い、2022年12月4日に台湾担当の松井が台湾司法発展の背景について、韓国担当の水島がこれまでに行った調査結果に基づく上記②の観点からの報告を行い、全員で討論を行った。
COVID-19による海外渡航の制限によって、資料収集が遅れている。制限緩和後、海外調査を行い始めているが、各分担者の所属大学での都合等により、現地調査のできる期間が限られており、資料収集を十分に行えていない。
本研究プロジェクトが対象とする地域についての法学分野の資料その他の情報は現地でなければ入手できないものが多い。2022年度夏ごろからCOVID-19を理由とする制限が緩和されたので、2023年には、個々の研究参加者がいまだ十分分析できていない部分についての調査・検討を集中的に行う。さらに2023年5月には日本におけるCOVID-19の「5類移行」により日本への外国人研究者の招聘もしやすくなったため、韓国については2023年度に韓国から元大法院研究官を招聘し、講演を依頼するとともに、これまでの本プロジェクトでの研究過程で生じた疑問について確認する予定である。
2020年度の「今後の研究の推進方策」で述べたモンゴル在住の研究分担者ガンガバータルがモンゴル憲法裁判所裁判官に就任したため、ZOOMによる講演会形式で、モンゴル憲法裁判所の設立過程、設立にあたっての海外からの影響、通常裁判所との関係性などについて話をしてもらい、モンゴル憲法裁判所の特徴や韓国、日本、インドネシアとの比較も行う予定である。
また、これまで対面での研究会を行うことができなかったので、各研究分担者の研究進捗状況の報告と最終的なまとめに向けての意見交換を行い、成果報告へと繋げたい。
大規模災害復興後の途上国における地域開発と災害リスク軽減の統合的研究
研究課題/研究課題番号:19H01381 2019年4月 - 2023年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(B)
高橋 誠, 室井 研二, 伊賀 聖屋, 島田 弦
担当区分:研究分担者
本研究は、インドネシアにおける近年の大規模地震災害を主な事例とし、先進国等の災害事例にも適宜言及して、自然災害からの復興を社会・空間構造の変化という観点から総括し、復興後のコミュニティベースの災害リスク軽減の取り組みと、経済・土地・社会の各側面における長期的な地域開発を実態調査に即して統合的に検討することによって、開発途上国における災害脆弱性と地域開発との相互関係を明らかにする。とりわけ、復興後の地域開発が災害リスクそのものを生み出すプロセスと、リスクに対処するコミュニティのガバナンスに注目して、災害発生機構について総合的に理解し、安全・安心な地域社会づくりのありようについても議論する。
前年度から継続して、インドネシアの現地研究協力者とオンラインでの研究打合せを定期的に実施するとともに、既収集データや過去の質問紙調査を丹念に再整理し、衛星画像や統計地図を分析した。また、バンダアチェの現地調査を2年半ぶりに実施し、景観観察と住民への聞き取り調査によって仮説の妥当性を検討した。その結果、バンダアチェでは、2013年頃から顕在化した南東部郊外の非被災地におけるリボン状の商業地とミニ住宅開発地、2018年頃からの被災地における埋め立て中規模新規住宅地がその後それぞれ周辺部に拡大してきた。市街地周辺部のこうした開発地では、洪水リスクの増大が近年危惧される傾向にあり、土地開発が災害リスクを埋め込まない傾向が示唆された。こうした傾向の背後に、国家法制における場当たり的な災害リスク管理、地方分権化以降の地方政策における開発指向の高まり、投機的な土地所有と土地運用、ある種の技術至上主義的な自然環境の捉え方などがかかわるとともに、結果として新規居住者によるローカル社会の再編が確認された。このことを量的調査によって実証するために、大規模な質問紙調査を具体的に計画し、質問紙の設計とサンプリングをおこなった。比較対象として日本の東日本大震災被災地における復興後の社会変動と南海トラフ想定地域における事前復興に関する調査を継続し、上記のことが日本でも起こりうる可能性を検討した。また、途上国の過剰都市化と社会的脆弱性との関連について中国武漢市において質問紙調査をおこない、その結果をまとめ国際学術誌に論文を投稿した。以上の結果の一部は、名古屋大学における公開シンポジウムで総合的に議論し、アチェのシアクラ大学に加えてインドネシアの基幹大学であるバンドン工科大学とガジャマダ大学で学生セミナーを開催して報告するとともに、国際アチェ・インド洋地域研究所において講演し、現地研究者と共有した。
2020年度当初より新型コロナウイルス感染症拡大のためインドネシアなどへの海外渡航が全くできなくなり、住民への質問紙調査やインタビュー調査を含む、フォローアップの現地調査を実施することができていなかった。そのため繰り越し申請をおこない、2022年度6月頃よりインドネシア政府および日本政府の感染症対策が徐々に緩和されたため、大規模な質問紙調査の実施に向けて具体的な準備に入った。ただし、2022年度後半までの感染症の散発的な流行による日本政府の急な政策転換と、ポストコロナの現地における不安定な受け入れ態勢のため、現地調査は必ずしも計画どおりに進捗しなかった。
基本的に当初計画に従い、可能な限り現地調査をおこない、住民へのインタビュー調査や質問紙調査を実施し、詳細に検証する計画を立てた。次年度の予算によって、バンダアチェ獅子とその周辺地域において大規模な質問紙調査(サンプル数=約1300)をすでに実施し、予察的な分析をおこなっているが、早急にその結果をまとめ、研究発表と論文執筆をおこなうとともに、可能な限り現地にて報告会を開催し、報告書を刊行する予定である。
ポスト権威主義型憲法モデルの構築:改革期インドネシアにおける憲法および立憲主義
研究課題/研究課題番号:19K01260 2019年4月 - 2023年3月
島田 弦
担当区分:研究代表者
配分額:4420000円 ( 直接経費:3400000円 、 間接経費:1020000円 )
権威主義から民主化へ移行したインドネシア憲法体制の変化と継続性、独自性を明らかにし、ポスト権威主義の憲法モデルの構築する。1999年以降、インドネシアの権威主義体制を支えた憲法が改正され、抑圧的な法令が廃止された。しかし、実際の憲法の運用および法令の制定・適用は、欧米的な立憲主義とは異なるものとなっている。そこで、比較憲法学の課題として、ポスト権威主義体制における憲法の特徴、権威主義からの変化と連続性を明らかにする必要がある。この目的のため、憲法改正過程、関係法令制定プロセス、法の適用、判決の分析、社会・政治的利害関係を多角的に考察し、ポスト権威主義国家の憲法の特徴と機能を明らかにする。
本研究は、権威主義から民主化へ移行したインドネシア憲法体制の変化と継続性、課題、独自性を明らかにし、比較憲法学の課題となっている非自由主義立憲主義としてポスト権威主義の憲法モデルの構築することを目的としている。1998年、インドネシアのスハルト権威主義体制が終わり、その後、権威主義体制を支えた憲法が改正され、抑圧的な法令が廃止された。しかし、実際の憲法の運用および法令の制定・適用は、欧米的な立憲主義 とは異なるものとなっている。そこで、ポスト権威主義体制における憲法の特徴、権威主義からの変化と連続性を明らかにする必要がある。
この目的のため、本研究課題では、憲法改正の過程と議論、関係法令の制定プロセス、行政決定など法の適用、裁判判決の分析、および、憲法・法令に関する社会・政治的利害関係を多角的に考察する方法で、インドネシアを事例にポスト権威主義国家の憲法の特徴と機能を明らかにする。
2019年度は、関係する法令及び判例の収集とその内容の整理、方法論の一つとしている法令マッピングの準備、報道・調査報告書などの資料から聞き取り調査を行うための対象・項目の選定を計画していた。
このため、2019年9月及び11月にインドネシアを訪問し、大学、在野研究者、法律NGO、憲法裁判所、マスメディアを訪問し聞き取り調査をし、また、研究会での研究報告を行った。現在、この調査を元にインドネシアで重視されている改正刑法案、改正労働法案について調査結果をまとめるための作業をしている。2020年3月に3回目の調査および研究報告に行く予定であったが、新型コロナウィルス肺炎による渡航禁止がしかれ不可能になった。現在は、インターネットを通じた資料収集、オンライン会議を通じた専門家との共同研究を続けているが、若干の遅れが出ている。
2019年度は、関係する法令及び判例の収集とその内容の整理、方法論の一つとしている法令マッピングの準備、報道・調査報告書などの資料から聞き取り調査を行うための対象・項目の選定を行う計画であった。
2019年9月及び11月にインドネシアを訪問し、大学、在野研究者、法律NGO、憲法裁判所、マスメディアを訪問し聞き取り調査をし、また、研究協力者との研究会での報告を行った。現在、この調査を元にインドネシアで重視されている改正刑法案、改正労働法案について調査結果をまとめるための作業をしている。
しかし、2020年3月に現地調査及びインドネシアにおける研究報告を予定していたが、渡航制限が敷かれキャンセルとなったため、研究進捗に若干の遅れが出ている。インターネット上の法令・資料の収集及びオンライン会議システムを活用したインドネシア法専門家との意見交換、研究報告を行っている。特にオンライン会議は大学研究者などとの協力では、非常に有用である。しかし、新たな調査先の開拓、ネット環境が十分でないか、使用したがらない調査先とのコンタクトに支障が出ている。
2020年度は、(1)2019年度に行った中央法令の分析及びマッピング化の作業を行う。(2)また、その進捗に遭わせて、法令制定及び運用にかかわる利害関係者のネットワークを明らかにする研究、(3)2021年度以降に行う予定の地方分権化と地方条例の予備調査に乗り出す計画である。
しかし、2020年度前半は現地での調査を行うことができないと見込んでいるので、状況が改善され次第、2020年度後半以降に集中して現地調査を行う計画を立てている。
当面は、手元資料を活用して(1)及び(2)の研究の一部を着実に進めていくこととしている。(3)については、メディア報道やインドネシア側研究者との意見交換をもとに、調査対象の地方を選定し、訪問調査を行う必要があるが、実現可能性については不透明な部分が多い。法令のほとんどがインターネット上で入手可能であり、制定過程についても一部利用可能な中央法令とは異なり、地方条例は現地での行政関係者やNGOへの聞き取りと資料提供依頼が不可欠だからである。現在、独自の現地調査の計画を変更し、インドネシア現地での若手研究者に調査協力を求めることを検討している。
研究課題/研究課題番号:17H02444 2017年4月 - 2020年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(B)
鮎京 正訓, 國分 典子, 島田 弦, 中村 真咲, 瀬戸 裕之, 牧野 絵美, 傘谷 祐之, KUONG TEILEE
担当区分:研究分担者
本研究は、2015年12月に発足したASEAN共同体のもとで、ASEANのいくつかの国々では近代立憲主義とは異質の憲法原理が支配しており、それを”異形な”憲法像と呼び、その具体的な内容と背景を研究することを主題とした。本研究では、ASEAN各国の憲法の翻訳とともに憲法制定過程を具体的に検証する作業を行なってきた。ところが、ミャンマーのクーデターの発生、中国の香港、新疆ウイグル自治区への強権政治、ロシアのウクライナ侵攻をつうじて、本研究で仮説的に”異形”と形容したものの姿が、はっきりと示されてきた。それは、明確に、”反立憲主義、反民主主義”の憲法像の新たな登場として特色づけられるものであった。
日本の憲法研究においては、欧米諸国を中心とする研究が支配的であり、近代立憲主義や人権尊重とは異なる憲法原理持つ国々の研究は、単に”遅れた”国の現象と捉えられ、いずれは近代立憲主義へと向かうものであるという想定のもとで、考察されてきた。本研究のメンバーは、ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマーなど、日本の憲法学界では取り組んでこなかったASEAN地域の憲法像を本格的、専門的に追求しており、その点で本研究は、学術研究上の際立った独自性を有している。加えて、ASEAN諸国へ、日本のローファームをはじめとして多くの企業もビジネス展開を行なっており、これらに正確な憲法知識を提供することができる。
研究課題/研究課題番号:16KT0088 2016年7月 - 2022年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(B)
伊東 早苗, 岡田 勇, 東村 岳史, 西川 由紀子, 山形 英郎, 島田 弦, 日下 渉, 石川 知子, 藤川 清史, 上田 晶子, 劉 靖
担当区分:研究分担者
研究期間中、コロナ禍の勃発により、海外調査を縮小する必要性が生じたものの、文献・資料調査やインタビュー調査を通じて収集したデータをもとに、研究成果を学会等で発表することができた。また、Practical Action Publishing(英)と出版契約を結び、書籍を出版する準備をしている。The Easternization of Development: The Politics of East Asia’s Developmentalist Cooperationがタイトルで、本科研事業分担研究者の他、ソウル国立大学、上海対外貿易大学、コンスタンツ大学の研究者が執筆を担当している。
本研究では、国際開発のパラダイム転換に伴う東アジア諸国の政治的駆け引きを「開発主義国家的(国際)協力」として概念化した。また、そこで想定されている「開発」とは、公共財の提供を通じて経済成長を促進し、その果実をトリクルダウン効果を通じて貧困削減につなげるプロセスだと議論し、「人間の福祉(Human well-being)」を中心とした従来の開発概念と区別した。さらに、欧米研究者が「開発の南化(Southernization of Development)」ととらえている現象に対し、「開発の東洋化(Easternization of Development)」という視点を提供した。
ASEAN経済共同体構築による加盟国法へのインパクト
研究課題/研究課題番号:16H01981 2016年4月 - 2019年3月
小畑 郁
担当区分:研究分担者
ASEANは、共同体設立宣言にもかかわらず、その機関自身の域内統治統制力は依然として弱く、むしろ域内から域外に広がるネットワークのハブとみる方が実態にあっている。その下で、加盟国法は、市場統合により自律的な調和に向い、ASEANは、それを助けるように、頻繁に開かれる会議を軸として、独自のものというより国際スタンダードの導入を促進している。
加盟国政治において構造化している権威主義的要素を回避するために、この地域に影響を及ぼしているアクターの政策は、機能主義的色彩を色濃く有している。しかし、今日の過剰な市場化に鑑みると、どのように立憲的価値を導入していくか、を課題として意識する必要がある。
EUでは、域内の経済協力の高度化は、EU法が法の統一をもたらし、これを基盤として価値の共有を前提とする憲法秩序の構築に向かった。これに対して、ASEANでは、域内の法の調和は、ネットワークのなかでの国際基準の推奨という形で進んでいる。このように、本研究は、地域的な国際経済協力のダイナミクスについて、EUとは異なる、しかし機能している論理を発見した。
したがって、ここでは、機能する市場経済を確立し、地域の人々の福祉を実現するためには、はるかに複雑な戦略をとる必要がある。さしあたり、価値を性急に振りかざすことを慎み、過剰な市場化がもたらす具体的な問題に対して協力していくことが有効であろう。
法整備支援重点支援対象国における法学教育
研究課題/研究課題番号:15H05176 2015年4月 - 2019年3月
四本 健二
担当区分:研究分担者
これまでの日本政府による法整備支援事業は、重要支援対象国の法曹や司法行政官の法学知識や司法事務の執行に必要なスキル、法学専門性を事前に調査し、現状を評価することなく続けられてきた。そこで、本研究は、重要支援対象諸国に加えて重要支援対象国からの留学生を数多く受け入れているインド及びタイの主要な大学法学部における法学教育に関する研究が、重要支援対象国における法と司法の質に内在する制約を「法と司法の担い手が受けた法学教育」という視点から浮き彫りにし、課題を明らかにすることができるという観点から、法整備支援重点支援対象国の主要大学法学部における法学教育全体の実態と課題を明らかにした。
本研究は、法学研究者と教育学研究者との協働によって学際的に進められた。また本研究は、さらには研究対象国の大学と法学教員、JICA派遣専門家との協力によってよりよい研究成果をあげた。これらの研究成果は、現地の法学教員にフィードバックし、法学教育の改善に役立てて貰うことができ、協力を得た関係機関にフィードバックすることで人材養成の案件形成に際して、カウンターパートの知識やスキルを把握するための基礎データとして活用することができる。また、指導教員にとって留学生が学部でどのような法学教育を受けてきたかを把握できる点で、研究対象国から法学系の留学生を受け入れている大学院にとっても有用である。
多層的復興モデルに基づく巨大地震災害の国際比較研究
研究課題/研究課題番号:15H01905 2015年4月 - 2019年3月
高橋 誠
担当区分:研究分担者
本研究では、2004年スマトラ地震、2008年四川大地震、2011年東北地方太平洋沖地震によって引き起こされた最近の巨大地震災害と復興に見られる共通点と相違点を整理し、政府や社会の対応に関わる多層的復興モデルに基づいて復興過程を再定式化し、復興そのものが新たな災害リスクを生み出す傾向があること、被災後の防災制度の改変にもかかわらず、被災経験が必ずしも地域知として埋め込まれず、履行レベルで問題を抱えていた被災前のリスク管理の状況と構造的に変わらないこと、それらの要因が復興時における調整メカニズムの欠如にあり、このことが復興後のコミュニティガバナンスやリスクガバナンスに通底することなどを指摘した。
巨大地震災害は低頻度だが、一旦起こると社会に壊滅的な被害を与える。ひとつの国や地域では災害経験が教訓として残りにくく、その知見を時間と空間を超えて共有するための理論的視座が学術上も防災上も重要である。それにもかかわらず、少なくとも日本の災害研究では、短期的な政策課題に即応するように研究課題が設定される傾向にあるため、自然ハザードの自然科学的研究と建物や構造物の工学的研究が中心である。一般には、政府が科学的にリスクに対応すれば被害が避けられると考えられているが、それが機能するための条件として、コミュニティのリスクガバナンスをめぐる調整メカニズムの重要性を指摘した点において、本研究の意義がある。
平和構築特論
2014
開発法学
2013
国際開発論
2008年4月 - 2009年3月 (椙山女学園大学)
政治と社会
2008年4月 - 2009年3月 (名古屋学芸大学)
日本国憲法
2007年4月 - 現在 (名古屋外国語大学)
科目区分:学部教養科目