工学部 環境土木・建築学科(旧)
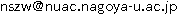
2025/12/03 更新

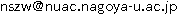
博士(工学) ( 1993年3月 東京大学 )
工学修士 ( 1985年3月 東京大学 )
未利用資源
未利用エネルギー
震災
上下水道
ドライドック
土木史
技術史
再生
地方都市
中国東北
満洲
植民地
近代建築
建築史
煉瓦造
鉄筋コンクリート造
木造
社会基盤(土木・建築・防災) / 建築史、意匠 / 建築史
東アジアの都市基盤施設に関する研究
![]()
東アジアの近代建築に関する研究
![]()
日本の植民地建築に関する研究
![]()
未利用資源・エネルギーの把握と価値化
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
名古屋大学 未来社会創造機構 脱炭素社会創造センター 所長(センター長)
2022年4月 - 2023年3月
名古屋大学 カーボンニュートラル推進室 室長
2021年11月 - 2023年3月
名古屋大学 環境学研究科附属持続的共発展教育研究センター 所長(センター長)
2021年4月 - 2023年3月
名古屋大学 環境学研究科 部長(学部長・研究科長)
2019年4月 - 2021年3月
名古屋大学 教育研究評議会 評議員
2016年4月 - 2021年3月
名古屋大学 大学院環境学研究科 副研究科長
2016年4月 - 2019年3月
名古屋大学 工学部 環境土木・建築学科長
2015年4月 - 2016年3月
名古屋大学 大学院環境学研究科 教授
2014年4月 - 現在
国名:日本国
名古屋大学 重要文化財馬場家住宅研究センター 重要文化財馬場家住宅研究センター副センター長
2013年4月 - 2017年3月
名古屋大学 減災連携研究センター 協力教員
2012年1月 - 現在
名古屋大学 大学院環境学研究科 准教授
2007年4月 - 2014年3月
国名:日本国
名古屋大学 大学院環境学研究科 助教授
2001年4月 - 2007年3月
国名:日本国
内閣府 政策統括官(科学技術政策担当) 参事官補佐(併任)
2001年4月 - 2003年3月
国名:日本国
名古屋大学 大学院工学研究科 助教授
1997年4月 - 2001年3月
国名:日本国
豊橋技術科学大学 建設工学系 助手
1992年4月 - 1997年3月
国名:日本国
東京大学 工学系研究科 建築学
1985年4月 - 1992年3月
国名: 日本国
東京大学 大学院工学系研究科 建築学専攻
1983年4月 - 1985年3月
名古屋大学 工学部 建築学
1979年4月 - 1983年3月
国名: 日本国
日本建築学会
建築史学会 常任委員会委員
2001年4月 - 2023年3月
土木学会
科学技術社会論学会
日本国際政治学会
建築史学会 監事
2023年4月 - 2025年4月
建築史学会 会長
2021年4月 - 2023年3月
都市史学会
豊橋市公会堂保存活用計画策定委員会 委員長
2025年7月 - 現在
団体区分:自治体
名古屋市立大学 博士論文審査委員会委員
2025年7月 - 現在
団体区分:その他
豊橋商工会議所 都市デザイン文化賞審査委員長
2024年7月 - 現在
団体区分:その他
豊橋市文化財審議会 審議委員
2024年4月 - 現在
団体区分:自治体
豊橋市教育委員会 豊橋市文化財保存活用地域計画協議会委員
2023年7月 - 現在
団体区分:自治体
名古屋市 伊藤家住宅の保存活用に関する懇談会構成員
2023年5月 - 現在
団体区分:自治体
愛知県立芸術大学 愛知県立芸術大学建築環境評価専門部会委員
2023年4月 - 現在
団体区分:その他
愛知県文化財保護審議会 会長
2022年7月 - 2024年3月
団体区分:自治体
法政大学 博士学位授与のための審査小委員会委員
2022年6月
団体区分:その他
西尾市教育委員会 西尾市岩瀬文庫書庫・西尾市立図書館おもちゃ館保存活用計画策定委員会委員
2022年4月 - 現在
団体区分:自治体
「あいち文化芸術振興計画(仮称)」策定に係る有識者会議 委員
2022年4月 - 2023年3月
団体区分:自治体
愛知県立芸術大学 愛知県立芸術大学キャンパスマスタープラン2021策定委員
2021年7月 - 2022年3月
団体区分:その他
刈谷市 刈谷市郷土資料館改修指導
2021年4月 - 2022年3月
団体区分:自治体
名古屋市 歴史的建造物保存活用アドバイザー(歴まちアドバイザー)
2021年4月 - 2022年3月
団体区分:自治体
前橋工科大学 前橋工科大学博士学位論文外部審査委員
2021年1月 - 2021年3月
団体区分:その他
西尾市教育委員会 西尾市岩瀬文庫書庫・西尾市立図書館おもちゃ館保存活用計画策定委員会委員
2020年12月 - 2022年3月
団体区分:自治体
なごや歴史的建造物保存活用協議会選定委員会 なごや歴史的建造物保存活用協議会選定委員
2020年10月 - 2021年9月
団体区分:自治体
蟹江町文化財保存活用地域計画作成協議会 委員
2020年9月 - 2023年3月
団体区分:自治体
聚楽園大仏等文化財調査 聚楽園大仏等文化財調査報告書執筆者
2020年8月 - 2020年10月
団体区分:自治体
一般財団法人名古屋大学出版会 理事長
2020年7月 - 現在
団体区分:その他
伊藤家住宅の保存及び活用に関する懇談会 構成員
2020年6月 - 現在
団体区分:自治体
伊藤家住宅の建物調査に関する意見交換会 構成員
2020年6月 - 現在
団体区分:自治体
文化審議会文化財分科会 専門委員
2020年4月 - 現在
団体区分:政府
伊藤家住宅の保存及び活用に関する懇談会 構成員
2018年10月 - 2019年3月
団体区分:自治体
滝学園本館ほか2 棟保存活用計画策定委員会 委員長
2018年3月 - 2020年3月
団体区分:その他
諏訪市文化センター保存活用計画策定検討会 委員
2017年11月 - 2018年3月
団体区分:自治体
重要文化財旧額田郡公会堂及物産陳列所保存活用計画策定検討委員会 委員長
2016年11月 - 2018年3月
団体区分:自治体
2017東アジア建築文化国際会議天津大会学術委員会 学術委員
2016年11月 - 2017年10月
団体区分:学協会
重要文化財片倉館保存活用計画調査委員会 副委員長
2016年10月 - 2018年3月
団体区分:その他
国指定史跡小菅修船場保存・整備委員会 委員
2016年9月 - 2017年3月
団体区分:その他
特別史跡名古屋城全体整備検討会議建造物部会 構成員
2015年12月 - 2016年3月
団体区分:自治体
旧日向別邸等研究委員会 委員長
2014年12月 - 2023年10月
団体区分:自治体
一般財団法人名古屋大学出版会 理事
2014年7月 - 2020年6月
2015東アジア建築文化国際会議光州大会学術委員会 学術委員
2014年6月 - 2015年11月
団体区分:学協会
愛知県海部郡蟹江町文化財保護審議会 審議委員
2014年4月 - 現在
愛知県文化財保護審議会 審議委員
2014年4月 - 2024年3月
団体区分:自治体
公益財団法人名古屋まちづくり公社名古屋都市センターまちづくり基金運用委員会 委員長
2013年4月 - 2016年3月
国指定史跡小菅修船場跡保存管理計画策定委員会 委員
2012年11月 - 2013年5月
公益財団法人明治村評議委員会 委員
2012年4月 - 現在
名古屋市文化財調査委員会 委員
2012年4月 - 2022年3月
団体区分:自治体
「九州・山口の近代化産業遺産群」世界遺産登録推進協議会比較調査(造船)委員会 委員
2011年5月 - 2012年3月
岡崎市旧本多邸復原工事検討委員会 委員
2010年10月 - 2012年3月
団体区分:自治体
名古屋歴史的建造物保存活用推進会議 委員
2010年8月 - 2014年3月
大日本報徳社仰徳記念館等修復事業学術調査委員会 委員
2010年4月 - 2012年3月
団体区分:その他
旧豊川海軍工廠近代遺跡調査指導委員会 委員長
2009年6月 - 2011年3月
名古屋市広告・景観審議会 委員
2007年6月 - 2011年5月
熱海市日向別邸等調査研究委員会 委員
2005年6月 - 2014年12月
財団法人明治村評議員会 評議員
2005年6月 - 2012年3月
三重県近代和風建築調査指導委員会 委員
2004年11月 - 2006年8月
中央防災会議災害教訓の継承に関する専門調査会小委員会(濃尾地震) 委員
2004年9月 - 2006年3月
旧川上貞奴邸復原その他工事検討委員会 委員
2003年10月 - 2005年3月
団体区分:自治体
博物館明治村建築委員会 建築委員
1999年8月 - 現在
2009年日本建築学会賞(論文)
2009年5月 社団法人日本建築学会
平成17年度名古屋市都市景観賞(まちづくり部門、奨励賞、団体)
2006年1月 名古屋都市センター
第3回建築史学会賞
1999年4月 建築史学会
日本建築学会東海賞
1995年2月 日本建築学会東海部
横井謙介の建築活動とその建築作品の特徴に関する研究 査読有り Open Access
項一朗, 西澤泰彦
日本建築学会計画系論文集 90 巻 ( 836 ) 頁: 2292 - 2303 2025年10月
20世紀前半における大連の集合住宅付複合建築の成立過程に関する研究ー設計競技による新しい建築形式の提示 査読有り Open Access
項 一朗,西澤泰彦
日本建築学会計画系論文集 90 巻 ( 834 ) 頁: 1793 - 1804 2025年8月
宗像主一の建築活動とその建築作品の特徴に関する研究 査読有り Open Access
項 一朗,西澤泰彦
日本建築学会計画系論文集 89 巻 ( 826 ) 頁: 2465 - 2476 2024年12月
20世紀前半における大連の集合住宅付複合建築に関する研究 ―その計画の特徴と都市形成との関係― 査読有り Open Access
項一朗,西澤泰彦
日本建築学会計画系論文集 89 巻 ( 818 ) 頁: 731 - 742 2024年4月
1930年竣工の大連連鎖商店に関する研究―その建設過程・建物の特徴・当時の評価― 査読有り Open Access
項 一朗, 西澤泰彦
日本建築学会計画系論文集 88 巻 ( 810 ) 頁: 2392 - 2403 2023年8月
新たな国立大学モデル「東海国立大学機構」としてカーボンニュートラル達成に取り組む 招待有り
西澤泰彦
クリーンエネルギー 32 巻 ( 7 ) 頁: 70 - 75 2023年7月
大連連鎖商店の平面の特徴に関する研究
項一朗,西澤泰彦
日本建築学会東海支部研究報告集 ( 61 ) 頁: 601 - 604 2023年2月
The Research and Practice of Urban Planning by Chinese Architecture Students Studying in Japan in the First Half of the 20th Century 査読有り
Fangxing LI, Yasuhiko NISHIZAWA
The 13th International Symposium on Architectural Interchanges in Asia 2022年12月
近代中国留学日本建築学生研究——以趙世瑄為代表的留日建築生與鉄路有関的活動 査読有り
李 芳星,西澤泰彦
中国近現代建築研究與保護 12 巻 頁: 477 - 485 2022年9月
20 世紀前半に来日した中国人建築学生の卒業後の進路に関する研究 査読有り Open Access
李 芳星, 西澤泰彦
日本建築学会計画系論文集 87 巻 ( 796 ) 頁: 1062 - 1073 2022年6月
1904-1907 年のソウル・龍山における日本軍の軍用地設定に関する研究 査読有り Open Access
南龍協,西澤泰彦
日本建築学会計画系論文集 87 巻 ( 795 ) 頁: 925 - 935 2022年5月
韓国・ソウルにおける旧日本軍の駐屯地設定に関する研究 査読有り Open Access
日本建築学会計画系論文集
日本建築学会計画系論文集 86 巻 ( 784 ) 頁: 1752 - 1763 2021年6月
20世紀前半に来日した中国人建築学生の留学実態に関する研究 査読有り Open Access
李 芳星,西澤泰彦
日本建築学会計画系論文集 86 巻 ( 780 ) 頁: 637 - 648 2021年2月
1899年開港の韓国・群山における各国居留地の市街地建設過程に関する研究 査読有り Open Access
文智恩,西澤泰彦
日本建築学会計画系論文集 85 巻 ( 769 ) 頁: 725-733 2020年3月
燃えない街ー1900-10年代の建築規則が求めたこと 招待有り
西澤泰彦
神奈川大学アジア・レビュー 7 巻 頁: 53-55 2020年3月
1899年開港の韓国・群山における居留地設定に関する研究 査読有り Open Access
文智恩,西澤泰彦
日本建築学会計画系論文集 84 巻 ( 757 ) 頁: 725-732 2019年3月
1934年施行の「朝鮮市街地計画令」による群山市街地計画に関する研究 査読有り Open Access
文 智恩, 西澤泰彦
日本建築学会計画系論文集 84 巻 ( 755 ) 頁: 229-237 2019年1月
建築史上における総督府庁舎の位置付け 招待有り
西澤泰彦
( 73 ) 頁: 158-172 2018年11月
関於台湾鋼筋混凝土結構的創始期実例及所出現的結構問題論考 査読有り
西澤泰彦
第16次中国近代建築史学術年会会刊 頁: 405-412 2018年7月
20世紀前半の大連における都市空間形成と建築 招待有り
西澤泰彦
翰林日本学 ( 29 ) 頁: 243-271 2016年12月
1919年実施的大連市建築法規的特徴 査読有り
西澤泰彦
中国近代建築研究與保護第十号(第15次中国近代建築史学術年会論文集) ( 10 ) 頁: 374-380 2016年7月
20世紀前半葉建築人員与材料的移動―以戦前中国東北地区為例 査読有り
西澤泰彦
中国近代建築研究与保護 9 巻 頁: 703‐712 2014年6月
アーキインフォマティック―建築歴史・意匠委員会・近代建築史小委員会 招待有り
西澤泰彦
建築雑誌 ( 1658 ) 頁: 32 2014年5月
20世紀前葉活動於東亜的日本建築家的所見所聞與建築資詢伝播之相関研究 招待有り
西澤泰彦
2014台湾建築史論壇「人材技術與資詢的国際交流」 2 巻 頁: 169-180 2014年5月
「ヘリテッジ」としての国立競技場を保存せよ、さもなくばオリンピックの返上を! 招待有り
西澤泰彦
建築ジャーナル ( 1221 ) 頁: 20-22 2014年2月
建築文化を議論する起爆剤 招待有り
西澤泰彦
建築ジャーナル ( 1216 ) 頁: 33 2013年9月
1891年濃尾地震建築破壊與其后之日本建築界対応ー領先世界的抗震研究之始 招待有り
西澤泰彦
2013年近代建築技術史国際学術研討会論文集 頁: 8‐12 2013年8月
2012年の歴史学界―回顧と展望―日本近現代 招待有り
中西聡、奈良勝司、中元嵩智、谷口祐信、田浦雅徳、城下賢一、内籐隆夫、北沢満、山口由等、竹内裕介、吉川卓治、西澤泰彦、服部亜由未、二谷智子、沓沢耕介
史学雑誌 122 巻 ( 5 ) 頁: 147-190 2013年5月
日中における近代建築総覧の編集と近代建築史研究について 招待有り 査読有り
西澤泰彦
建築学報 ( 530 ) 頁: 76‐78 2012年10月
近代建築の評価と活用 招待有り
西澤泰彦
登録文化財の保存と活用(2012年度日本建築学会大会建築歴史・意匠部門研究協議会資料) 頁: 10-15 2012年9月
大学の建築群が伝える時代の記憶 招待有り
西澤泰彦
大学空間の社会的価値とその共創的継承(2012年度日本建築学会都市計画部門研究懇談会資料) 頁: 9-12 2012年9月
不都合なことを考える必要性 招待有り
西澤泰彦
環―歴史・環境・文明 ( 49 ) 頁: 171-173 2012年4月
愛知県における「不思議な」RC造建築物 招待有り
西澤泰彦
2011年度日本建築学会大会(関東)建築歴史・意匠部門研究協議会資料 頁: 103-106 2011年8月
使い続けよう市民の資産―名古屋市公会堂竣工80周年 招待有り
西澤泰彦
朝日新聞 頁: 4 2011年4月
景観破壊與建築保存-日本地方城市所発生的事件 招待有り
西澤泰彦
2010東亜都市與建築保存国際研討会論文集 頁: 73-101 2010年11月
植民地建築の保存再生と『日本近代建築総覧』 招待有り
西澤泰彦
シンポジウム日本近代建築史研究の軌跡―『日本近代建築総覧』刊行から30年を考える 頁: 24-25 2010年10月
日本近代建築保存活用之諸問題 招待有り
西澤泰彦
第二届歴史建築遺産保護與可持続発展国際会議論文集 頁: 163-169 2010年9月
豊橋ハリストス正教会の聖堂建築の研究―最近発見・発刊された資料による建設経緯と設計の分析 査読有り Open Access
泉田英雄、伊藤晴康、西澤泰彦
日本建築学会計画系論文集 75 巻 ( 654 ) 頁: 1997-2005 2010年8月
後藤の複眼的「ものの見方」―リレー連載「今、なぜ後藤新平か」58 招待有り
西澤泰彦
機 ( 220 ) 頁: 18-19 2010年7月
歴史的建造物―建築アセスを導入せよ
西澤泰彦
朝日新聞 ( 2009年3月19日 ) 頁: 17 2009年3月
建築家西村清太郎の旧蔵資料と業績 招待有り
西澤泰彦
三重県近代和風建築総合調査報告 頁: 25-32 2009年3月
新刊紹介『近代日本の建築活動の地域性―広島の近代建築とその設計者たち』 招待有り
西澤泰彦
建築史学 ( 52 ) 頁: 78-80 2009年3月
自著を語る―『日本植民地建築論』からの展開― 招待有り
西澤泰彦
近現代東北アジア地域史研究会ニューズレター ( 20 ) 頁: 71-79 2008年12月
新刊紹介『ヴォーリズ建築の百年』 招待有り
西澤泰彦
建築史学 ( 51 ) 頁: 164-165 2008年9月
モダニズム建築の評価と保存・再生への起爆剤名古屋大学豊田講堂のOCOMOMO100選選定と改修工事 招待有り
西澤泰彦
C&D(シーアンドディー) ( 148 ) 頁: 11-12 2008年2月
日本の住宅史における芝川又右衛門邸 招待有り
西澤泰彦
明治村だより ( 50 ) 頁: 4-6 2007年12月
満鉄が造った東アジアの「世界都市」
西澤泰彦
東京人 22 巻 ( 11 ) 頁: 58-63 2007年10月
建物と街並みを評価すること
建築雑誌 122 巻 ( 1565 ) 頁: 38 2007年5月
依佐美送信所の建物について
西澤泰彦
刈谷市史だより ( 47 ) 頁: 1-2 2007年3月
歴史の中の地震17濃尾地震(1891年)-事実と印象が混在した被害記録と冷静だった建築界の対応 招待有り
月刊地震レポートSAISMO 11 巻 ( 1 ) 頁: 10-11 2007年1月
日本帝国内の建築に関する物・人・情報の流れ 査読有り Open Access
西澤泰彦
国際政治 ( 146 ) 頁: 39-53 2006年11月
書評・橋谷弘著『帝国日本のと植民地都市』 招待有り
西澤泰彦
日本植民地研究 ( 18 ) 頁: 86-92 2006年6月
多人数講義における問題点と教育方法 招待有り Open Access
西澤泰彦
名古屋高等教育研究 ( 6 ) 頁: 45-57 2006年3月
建築の保存再生を目指した新たな活動
西澤泰彦
建築雑誌 ( 1538 ) 頁: 48-49 2005年10月
遺物を資産に変える試み―名古屋市瑞穂区でのまちづくり活動
西澤泰彦
シーアンドディー ( 136 ) 頁: 46-47 2004年12月
1905年施行的《大連房屋建造管理暫行規則》的理念及其実態 査読有り
西澤泰彦
中国近代建築研究与保護・3号(2002年中国近代建築史国際討論会論文集) ( 3 ) 頁: 248-256 2004年4月
視点と史観の明確化
西澤泰彦
建築雑誌 ( 1514 ) 頁: 27 2004年2月
中国・東北地方-「満鉄建築」の横綱 招待有り
西澤泰彦
建築雑誌 ( 1512 ) 頁: 6 2003年12月
地方都市の近代近代建築
西澤泰彦
建築雑誌 ( 1506 ) 頁: 53 2003年6月
総合科学技術会議における環境分野の取り組みと産学官連携 招待有り
渡辺信,生田和正,恒川篤史,西澤泰彦,宮川俊彦
水環境学会誌 26 巻 ( 2 ) 頁: 2-7 2003年2月
リサイクルアーキテクチュアー5名古屋市演劇練習館―常識を覆した再利用
西澤泰彦
建築知識 ( 564 ) 頁: 247-254 2003年1月
地方都市の近代化を考える
西澤泰彦
愛知県史だより ( 14 ) 頁: 2-4 2002年10月
満洲国政府の建築
西澤泰彦
環 ( 10 ) 頁: 244-256 2002年7月
文明開化の風景 招待有り
明治村だより ( 26 ) 頁: 4-5 2001年12月
旧南満洲鉄道株式会社的住宅政策 査読有り
西澤泰彦
中国近代建築研究与保護・2号(2000年中国近代建築史国際討論会論文集) ( 2 ) 頁: 87-102 2001年7月
「間」を持つ都市型住宅
西澤泰彦
confort(コンフォルト) ( 41 ) 頁: 97-102 2000年4月
近代化遺産としてのドライドック
西澤泰彦
明治村だより ( 19 ) 頁: 5-9 1999年12月
清末在東北日本公館建築 査読有り
西澤泰彦
中国近代建築研究与保護・1号(1998年中国近代建築史国際討論会論文集) ( 1 ) 頁: 23-32 1999年9月
明治時代に建設された日本のドライドックに関する研究 Open Access
西澤泰彦
土木史研究 ( 19 ) 頁: 147-158 1999年5月
旧満鉄大連医院本館建設過程及歴史評価 査読有り
第五次中国近代建築史研究討論会論文集 ( 5 ) 頁: 144-155 1997年3月
初期モダニズムと建築家土浦亀城
SD(スペース・デザイン) ( 382 ) 頁: 15-20 1996年
弟子は師を越えて-土浦亀域とライト
F.L.ライトと弟子たち 頁: 30-39 1995年
軍艦とアール・ヌーヴォー-帝政ロシアの極東政策
ハザマ・テクノスフェアー ( 10 ) 頁: 32-45 1995年
満洲国政府の建築組織の沿革について 査読有り Open Access
西澤泰彦
日本建築学会計画系論文集 ( 462 ) 頁: 185-194 1994年8月
南満洲鉄道株式会社の建築家ーその特徴と変遷ー 査読有り Open Access
西澤泰彦
アジア経済 35 巻 ( 7 ) 頁: 23-52 1994年7月
南満洲鉄道株式会社の建築組織の沿革について 査読有り Open Access
西澤泰彦
日本建築学会計画系論文集 ( 457 ) 頁: 216-225 1994年3月
建築家岡田時太郎の中国東北地方進出について 査読有り Open Access
西澤泰彦
日本建築学会計画系論文報告集 ( 452 ) 頁: 187-196 1993年10月
建築家中村與資平の経歴と建築活動について 査読有り Open Access
西澤泰彦
日本建築学会計画系論文報告集 ( 450 ) 頁: 151-160 1993年8月
関東都督府の建築組織とその活動について 査読有り Open Access
西澤泰彦
日本建築学会計画系論文報告集 ( 442 ) 頁: 117-126 1992年12月
哈爾濱新芸術運動的歴史地位 査読有り
第三次中国近代建築史研究討論会論文集 ( 3 ) 頁: 72-74 1991年7月
類は友を呼ぶ-建築家中村与資平と彼をめぐる人々
ドームをぬける蒼い風-中村与資平展記念誌 1989年
草創期的満鉄建築課 査読有り
西澤泰彦
華中建築 ( 20 ) 頁: 102-104 1988年9月
建築家土浦亀城と昭和初期モダニズム
SD 頁: 286 1988年
旧横浜船渠第2号ドックの土木技術史的価値
旧横浜船渠第2号ドック調査報告書 1988年
米海軍横須賀基地内洋風建造物調査報告書(共著)
横須賀市文化財調査報告書 頁: 17 1988年
関於日本人在中国東北地区建築活動之研究 査読有り
西澤泰彦
華中建築 ( 15 ) 頁: 90-96 1987年2月
「満洲」在地社会と植民者 国際共著
上田貴子,西澤泰彦ほか6名( 担当: 共編者(共編著者) , 範囲: 全体編集,序章,第2章,あとがき)
京都大学学術出版会 2025年2月 ( ISBN:9784814005758 )
ビジュアル脱炭素のしくみ ②脱炭素社会をめざす
名古屋大学未来社会創造機構脱炭素社旗創造センター( 担当: 編集 , 範囲: はじめに)
ゆまに書房 2024年3月 ( ISBN:978-4-8433-6525-0 )
ビジュアル脱炭素のしくみ ①これからのエネルギーを考える
名古屋大学未来社会創造機構脱炭素社旗創造センター( 担当: 編集 , 範囲: はじめに)
ゆまに書房 2023年12月 ( ISBN:978-4-8433-6524-3 )
後藤新平-衛生への道1857-1929
藤原良雄編( 担当: 分担執筆 , 範囲: 満鉄経営における衛生)
藤原書店 2023年3月 ( ISBN:978-4-86578-381-0 )
満洲国と日中戦争の真実
保阪正康,西澤泰彦ほか11名( 担当: 分担執筆 , 範囲: 大連、奉天、長春…世界最先端の都市と建物はいかにつくられたのか)
株式会社PHP研究所 2022年3月 ( ISBN:978-4-569-85148-8 )
大日本帝国期の建築物が語る近代史 国際共著
西澤泰彦( 担当: 共著 , 範囲: 東アジアにおける日本の支配と建築)
勉誠出版 2022年2月 ( ISBN:978-4-585-32512-3 )
空想から計画へ―近代都市に埋もれた夢の発掘
中川理、西澤泰彦、ほか26名( 担当: 分担執筆 , 範囲: 一九〇〇年代から一九一〇年代の建築規則が求めたこと)
思文閣 2021年3月 ( ISBN:978-4-7842-2002-1 )
日本の近代・現代を支えた建築ー建築技術100選
日本の近代・現代を支えた建築―建築技術100選ー委員会( 担当: 分担執筆 , 範囲: 097植民地建築)
一般財団法人日本建築センター 2019年6月 ( ISBN:978-4-88910-177-5 )
重要文化財旧開智学校校舎調査研究報告書
松本市教育委員会( 担当: 分担執筆)
松本市教育委員会 2018年3月
Towards the Implemention of the New Urban Agenda - Contributions from Japan and Germany to Make Cities More Environmentally Sustainable
Bernhard Muller, Hiroyuki Shimizu, Atsushi Katagi, Yasuhiko Nishizawa, et al.( 担当: 分担執筆 , 範囲: Chapter 13 Preservation and Utilization of Urban Heritage of East Asia and Japan)
Springer International Publishing AG 2018年1月 ( ISBN:978-3-319-61375-8 )
経済社会の歴史
中西聡,松沢祐作,小島庸平,山内太,西澤泰彦,ほか13名( 担当: 分担執筆)
名古屋大学出版会 2017年12月 ( ISBN:978-4-8158-0893-8 )
旧長野地方裁判所松本支部庁舎調査報告書ー市民が守った文化財ー旧長野地方裁判所松本支部庁舎の歩み
西澤泰彦, 梅干野成央, 窪田雅之, 千賀康孝( 担当: 分担執筆 , 範囲: Ⅴ-3 明治期の建築としての価値)
松本市立博物館分館 松本市歴史の里 2017年3月
日本近代建築家列伝
鈴木博之,藤森照信,西澤泰彦ほか25名( 担当: 分担執筆)
鹿島出版会 2017年1月 ( ISBN:978-4-306-04645-0 )
図説満鉄ー「満洲」の巨人(増補新装版)
西澤泰彦( 担当: 単著)
河出書房新社 2015年4月 ( ISBN:978-4-309-76232-6 )
古地図で楽しむなごや今昔
溝口常俊,池田誠一,奥貫圭一,西澤泰彦など25名( 担当: 共著)
風媒社 2014年4月 ( ISBN:978-4-8331-0159-2 )
Constructing the Colonial Land - Entwined Perspective of East Asia around WWⅡ
Izumi Kuroishi, Yasuhiko Nishizawa, Cole Roskam, Xu Subin, Akihito Aoi, Chao-Ching Fu, Paula Morais, Junichiro Ishida.( 担当: 共著)
Ashgate 2014年2月 ( ISBN:9781409428183 )
3・11と私 東日本大震災で考えたこと
西澤泰彦など100名( 担当: 単著)
藤原書店 2012年8月 ( ISBN:978-4-89431-870-7 )
建築遺産―保存と再生の思考
後藤治,足立祐司,光井渉,佐藤憲一,永井康雄,大川真,藤川昌樹,窪寺茂,伊郷吉信,西澤泰彦,佐藤弘夫,長岡龍作,藤井恵介,田路貴浩,矢野和之,花里利一,清水真一,高橋恒夫,斉藤善之,青井哲人( 担当: 共著)
東北大学出版会 2012年3月 ( ISBN:978-4-86163-189-4 )
東アジアの日本人建築家―世紀末から日中戦争
西澤泰彦( 担当: 単著)
柏書房 2011年11月 ( ISBN:9784760139989 )
植民地建築紀行―満洲・朝鮮・台湾を歩く
西澤泰彦( 担当: 単著)
吉川弘文館 2011年10月 ( ISBN:ISBN978-4-642-05730 )
名古屋市中区誌
林董一他32名( 担当: 共著)
中区制施行100周年記念事業実行委員会 2010年12月
シリーズ後藤新平とは何か-都市デザイン
鈴木博之、陣内秀信、藤森照信、田中重光、西澤泰彦( 担当: 共著)
藤原書店 2010年5月
日本の植民地建築
西澤泰彦( 担当: 単著)
河出書房新社 2009年10月
再生名建築
足立祐司、内田青蔵、大川三雄、藤谷陽悦、石田潤一郎、角幸博、千代章一郎、中川理、中森勉、西澤泰彦、藤岡洋保、山形政昭( 担当: 共著)
鹿島出版会 2009年9月
蒲郡の建築
蒲郡市博物館編、杉野丞、澤田多喜二、浅野清、天野武弘、西澤泰彦( 担当: 共著)
蒲郡市教育委員会 2009年3月
*日本植民地建築論
西澤泰彦( 担当: 単著)
名古屋大学出版会 2008年2月
愛知県指定有形文化財豊橋ハリストス正教会聖使徒福音者馬太聖堂建築調査報告書
豊橋ハリストス正教会聖堂建築調査団編、泉田英雄、伊藤晴康、西澤泰彦執筆( 担当: 共著)
豊橋市教育委員会美術博物館 2007年6月
満洲-記憶と歴史(共著)
山本有造,西村成雄,猪俣祐介,小都晶子,上田貴子,坂部晶子,蘭信三,南誠,藤原辰史,西澤泰彦( 担当: 共著)
京都大学学術出版会 2007年3月
『満鉄とは何だったか』(共著)
( 担当: 共著)
藤原書店 2006年11月
岩波講座「帝国」日本の学知・第8巻・空間形成と世界認識」(共著)
( 担当: 共著)
岩波書店 2006年10月
図説「満洲」都市物語(増補改訂版)
西澤泰彦( 担当: 単著)
河出書房新社 2006年5月
『愛知県史・別編・文化財1・建造物・史跡』
愛知県史編さん委員会( 担当: 共著)
愛知県 2006年3月
西尾市の近代建築
松井直樹編、西澤泰彦著( 担当: 共著)
西尾市教育委員会 2006年3月
環境学研究ソースブック(共編著)
( 担当: 共著)
藤原書店 2005年12月
消された校舎―旭丘高校校舎建て替えてんまつ記(共編著)
( 担当: 共著)
風媒社 2005年10月
明治村建造物移築工事報告書第十一集聖ザビエル天主堂(共編著)
西尾雅敏、遠藤輝子、西澤泰彦( 担当: 共著)
2005年3月
アジア都市文化学の可能性(共著)
( 担当: 共著)
清文堂 2003年3月
図説満鉄-「満洲」の巨人
西澤泰彦( 担当: 単著)
河出書房新社 2000年8月
近代日本の郊外住宅地(共編著)
( 担当: 共著)
鹿島出版会 2000年3月
図説大連都市物語
( 担当: 単著)
河出書房新社 1999年8月
海を渡った日本人建築家
( 担当: 単著)
彰国社 1996年12月
図説「満洲」都市物語
( 担当: 単著)
河出書房新社 1996年8月
全調査東アジア近代の都市と建築(共編著)
( 担当: 共著)
筑摩書房 1996年3月
「満洲国」の研究(共著)
( 担当: 共著)
緑蔭書房 1995年
中国近代建築総覧瀋陽編(The Architectural Heritage of Modern China, Shenyang)(共著)
中国建築工業出版社 1995年
近代を歩く(共著)
ひくまの出版 1994年
「満洲国」の研究(共著)
京都大学人文科学研究所 1993年
中国近代建築総覧哈爾濱編(The Architectural Heritage of Modern China, Harbin)(共著)
中国建築工業出版社 1992年
近代和風建築(共著)
鹿島出版会 1988年
アジアの都市と建築(共著)
鹿島出版会 1986年
「雄弁に時代を語る」貴重な写真ー二〇世紀前半の中国東北地方の実態を示す 招待有り
西澤泰彦
週刊読書人 ( 3481 ) 頁: 4 - 4 2023年3月
記憶の継承を考える新たな取り組み 招待有り
西澤泰彦
建築雑誌136 巻 ( 1753 ) 頁: 34 - 35 2021年9月
公共施設のRC造化によって生じたこと 国際会議
西澤泰彦
科研(B)_近代日本公共施設RC造化シンポジウム「公共施設のRC造化が示すこと」 2025年11月29日 科研(B)近代日本の公共施設RC造化研究班+トヨタ財団国際助成プログラム「文化遺産としての近現代建築物の保存活用にむけた学びあいと人的ネットワーク構築」
History of Nagoya University 国際会議
NISHIZAWA Yasuhiko
The Seoul Institute-Nagoya University Joint Seminar “Urban Disaster Analysis and Response” 2025年11月10日 Depr. of Architecture, Nagoya Univ.and seoul Institute
Introduction of Nagoya University andToyoda Auditorium completed in 1960 国際会議
NISHIZAWA Yasuhiko
The October 17 Special Forum based on Memorandum of Understanding for Academic Exchange and Cooperation between College of Planning and Design, National Cheng Kung University and Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University 2025年10月17日 Depr. of Architecture, Nagoya Univ.and Chen Kun Univ.
名古屋大学環境学研究科の紹介 国際会議
西澤泰彦
韓国全国市道研究院協議会と名古屋大学環境学研究科との交流会 2025年6月8日 名古屋大学環境学研究科および韓国全国市道研究院協議会
日本における近現代建築物の保存活用の諸問題 招待有り 国際会議
西澤泰彦
トヨタ財団国際助成プロジェクト 文化遺産としての近現代建築物の保存活用にむけた学びあいと人的ネットワーク構築 第1回研究会 2024年11月25日 京都大学工学研究科建築学専攻荒木研究室
Introduction of Nagoya University and Building damage caused by the Nobi Earthquake in 1891 招待有り 国際会議
NISHIZAWA Yasuhiko
Workshop for Agreement for Academic Exchange and Cooperation between School of Civil Engineering, Tianjin University and Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University 2024年11月6日 Depr. of Architecture, Nagoya Univ.and School of Civil engineering Tianjin Univ.
A study on urban development methodologies in Western Dairen during the 1920s 国際会議
Xiang Yilang, Yasuhiko Nishizawa
2024年9月12日 Architectural Institute of Japan
20世紀初頭の台湾における鉄筋コンクリート造建築物に関する考察-その2 招待有り 国際会議
西澤泰彦
2024年7月31日 成功大学計画設計学院+名古屋大学+北海道大学+日本製鉄+国家地震研究センター
二十世紀初於台灣鋼筋混凝土建築物研究 招待有り 国際会議
西澤泰彦
2024年3月4日 成功大学計画設計学院建築系+名古屋大学環境学研究科都市環境学専攻建築学系
地域が建てたRC造校舎・講堂の例
西澤泰彦
科研(B)_近代日本公共施設RC造化シンポジウム 関東大震災前後のRC造建物を考える(その2) 2024年2月13日 科研(B)_近代日本公共施設RC造化研究班(代表:西澤泰彦)
20世紀前半の東アジアにおける建築情報の伝播に関する考察 招待有り 国際会議
西澤泰彦
東アジア近代化遺産関連保存と推動研究の国際シンポジウム 2023年11月10日 中原大学および文化資産局
植民地建築の遺物化・遺産化・資産化 招待有り 国際会議
西澤泰彦
光復後の首都ソウルのアイデンティティ、そして未来 2023年10月26日 ソウル市立大学およびソウル歴史博物館
大学等コアリション・地域ゼロカーボンワーキンググループ 第二期活動報告及び第三期活動計画について 招待有り
西澤泰彦
カーボンニュートラルに貢献する大学等コアリション総会 2023年9月7日 カーボンニュートラルに貢献する大学等コアリション
東三河の 身近な 歴史的建造物を考える ~ 遺産を未来の資産に繋ぐ試み ~ 招待有り
西澤泰彦
2023年東三河地域問題セミナー 2023年4月19日 公益 社団法人東三河地域研究センター
Introduction of Nagoya University and Toyoda Auditorium completed in 1960 国際会議
Nishizawa, Yasuhiko
Taiwan-Japan Workshop for Environmental Engineering and Architecture at Nagoya University 2023年2月19日 Nagae Group
近代東アジアの海港都市と建築ー関門・仁川・大連 招待有り 国際会議
西澤泰彦
東アジア友好博物館シンポジウム「東アジアの海港都市と建築ー北九州・仁川・大連」 2022年11月5日 北九州市立自然史・歴史博物館
建築家中村與資平の挑戦と静岡市庁舎 招待有り
西澤泰彦
展覧会「時を超え静岡に集う小川三知作品」特別講演 2022年8月27日 小川三知を讃える会
登録文化財に係る「所見」の作成 招待有り
西澤泰彦
歴まちびとスキルアップ講座(2) 2022年3月26日 名古屋まちづくり公社
歴史的建造物の評価と登録文化財 国際会議
西澤泰彦
web研究会「建築・都市から考える1900 年前後の東アジア」 2022年2月19日 西澤泰彦・尹仁石
文化財建造物としての聚楽園大仏の評価-先人の工夫を褒める試み 招待有り
西澤泰彦
聚楽園大仏文化財講演会 2022年2月6日 東海市教育委員会
登録文化財に係る「所見」の作成 招待有り
西澤泰彦
歴まちびとスキルアップ講座 2022年2月5日 名古屋まちづくり公社
脱炭素社会の実現に向けた東海国立大学機構としての新たなチャレンジ 招待有り 国際会議
西澤泰彦
第 32回国際経済政策研究センター・キタン国際学術シンポジウムーポストコロナ時代の グローバル・サプライチェーン再建 2022年1月19日 名古屋大学大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センター 一般社団法人キタン会 (名古屋大学経済学部 /経済学研究科同窓会 ) 日本貿易振興機構 ・ アジア経済研究所 IDE-JETRO
カーボンニュートラル推進室について
西澤泰彦
「エネルギーの確保と供給」シンポジウム 名古屋大学における脱炭素を考える 脱 2022年12月24日 東海国立大学機構カーボンニュートラル推進室および名古屋大学環境学研究科
満鉄大連医院本館が持つ社会的意味 国際会議
西澤泰彦
東アジア日本硏究者協議会 第5回国際学術大会 2021年11月27日 東アジア日本研究者協議会
身近な歴史的建造物の保存活用計画立案 招待有り
西澤泰彦
なごや歴まちびと養成講座 2021年11月20日 名古屋まちづくり公社
Various evaluations of Toyoda Auditorium in Nagoya University since 1960 国際会議
Nishizawa Yasuhiko
APRU University Museum Research Symposium 2021 2021年11月16日 NUS Baba House & NUS Department of Architecture
西澤泰彦
防災推進国民大会 2021 セッション/日本学術会議公開シンポジウム/第 12 回防災学術連携シンポジウム 2021年11月6日 一般社団法人防災学術連携体
まとめと閉会あいさつ
西澤泰彦
松阪プロジェクト・ワークショップ『臨床環境学アプローチと大学・地方自治体間連携:四調査の合同結果発表と行政からのフィードバッ ク』 2021年11月4日 名古屋大学環境学研究科附属持続的共発展教育研究センター
災害の記憶を継承するまちづくりをどのように進めるか
西澤泰彦
シンポジウム「東日本大震災10周年を機に頻発する複合災害を考える」 2021年3月6日 日本建築学会
災害の記憶の検証とは何か
西澤泰彦
WG5「災害の記憶を継承するまちづくりをどのように進めるか」ワークショップ 2021年3月6日 日本建築学会
『 日本植民地建築論 』 の再構築 建築の様式・構造・平面の視点から 招待有り
西澤泰彦
科研「日本植民地期遺産をめぐる歴史認識の文化人類学的研究-建築物のライフヒストリーから」 2021年2月20日 広島県立大学上水流久彦
日本における建築遺産の評価方法 招待有り 国際会議
西澤泰彦
2020年12月19日 大連理工大学
1905-1945年中国东北地区的城市建设与建筑:以沈阳和长春为例 招待有り 国際会議
西澤泰彦
旧開智学校校舎の設計過程 招待有り
西澤泰彦
旧開智学校校舎国宝指定記念シンポジウム
燃えない街―1900年代~1910年代の建築規則が求めたもの 招待有り
西澤泰彦
日韓建築シンポジウム「専門家が語る韓国と日本の近代建築史研究の魅力-研究の回顧と展望」
台湾電話交換室の竣工時期
西澤泰彦
2019年日本建築学会大会学術講演(北陸)
1891年濃尾地震建築破壞與其後日本建築界的對應-領先世界的建築抗震研究之始- 国際会議
西澤泰彦
関於台湾鋼筋混凝土結構的創始期実例及所出現的結構問題論考 招待有り 国際会議
西澤泰彦
第16次中国近代建築学術年会
総督府庁舎の建築史上の位置づけ 招待有り 国際会議
西澤泰彦
ソウル市立大学百周年記念国際シンポジウム
近代建築と旧松本区裁判所庁舎 招待有り
西澤泰彦
西澤泰彦
20世紀前半葉建築人員与材料的移動―以中国東北地区為例 国際会議
西澤泰彦
2018天津大学建築学院講座
20世紀前半の大連における都市空間形成と建築 国際会議
西澤泰彦
2018天津大学建築学院講座
20世紀前半葉建築人員与材料的移動―以戦前中国東北地区為例 招待有り 国際会議
西澤泰彦
〔中国〕東北大学江河建築学院特別講義
人々が書き残した震災―濃尾地震と東南海地震 招待有り
西澤泰彦
減災館第23回特別展スペシャルギャラリートーク
歴史的建造物の評価と再生ー愛知県での事例 招待有り
西澤泰彦
NPO法人信州伝統的建造物保存技術研究会講演会
濃尾地震と日本の近代化 招待有り
西澤泰彦
シンポジウム「濃尾地震から125年」
近代建築評価與再生活用ー東亜各地事例之考察 国際会議
西澤泰彦
河北工業大学建築学院特別講義
近代建築評価與再生活用ー東亜各地事例之考察 国際会議
西澤泰彦
天津大学建築学院特別講義
20世紀前半の大連における都市空間形成と建築 招待有り 国際会議
西澤泰彦
空間と移動から見た東アジアの近代
旧開智学校の魅力再発見 招待有り
西澤泰彦
重要文化財旧開智学校校舎創建140周年記念特別展関連事業
群山に残る日本人建築家設計の建物ー旧朝鮮銀行群山支店を中心にー 招待有り 国際会議
西澤泰彦
群山市都市再生大学講座
対談・擬洋風建築を語る 招待有り
藤森照信,西澤泰彦
重要文化財旧開智学校校舎創建140周年記念事業特別講演会
「海を渡った建築家」としての土浦亀城 招待有り
西澤泰彦
土浦邸フレンズ第2回研究会
明治熊本地震の再考
西澤泰彦
第6回中部歴史地震研究会
人・モノ・情報の移動ー建築分野を事例として
西澤泰彦
二〇世紀東アジアをめぐる人の移動と社会統合に関する総合的研究満洲班第1回WS
中国近代建築史研究の動向 国際会議
西澤泰彦
文化遺産国際協力コンソーシアム第20回東アジア・中央アジア分科会
学校建築のおもしろさー擬洋風建築を中心に
吉川卓治,斉藤金司,西澤泰彦
名古屋大学重要文化財馬場家住宅研究センター平成26年度研究交流会
20世紀前半葉建築人員与材料的移動―以戦前中国東北地区為例 国際会議
西澤泰彦
第14次中国近代建築史学術年会
20世紀前葉活動於東亜的日本建築家的所見所聞與建築資詢伝播之相関研究 国際会議
西澤泰彦
2014台湾建築史学会論壇
1891年濃尾地震建築災害與其後日本建築界対応ー建築耐震研究之世界的始点 国際会議
西澤泰彦
中原大学近代都市史研究研修会
1891年濃尾地震建築破壊與其后之日本建築界対応ー領先世界的抗震研究之始 国際会議
西澤泰彦
2013中国近代建築技術史国際討論会
『日本近代建築総覧』再考
西澤泰彦
2013年度建築史学会大会記念シンポジウム「建築史研究の戦後―建築史と建築学」
近代建築の評価と活用
西澤泰彦
登録文化財の保存と活用
大学の建築群が伝える時代の記憶
西澤泰彦
大学空間の社会的価値とその共創的継承
南満洲鉄道附属地施行的建築規則之特徴 国際会議
西澤泰彦
第13次中国近代建築史学術年会(2012)
建築史の視点から見た戦前期日本の「四大公会堂」
西澤泰彦
「産業化と生活環境」研究会2012年度第6回研究会
濃尾地震の建築被害とその影響
西澤泰彦
防災・日本再生シンポジウム 濃尾地震から120年 その教訓を振り返る
日本近代建築保存活用之諸問題 国際会議
西澤泰彦
2011東北亞建築文化遺産国際研究討論会
博物館明治村と近代建築の保存 国際会議
西澤泰彦
京畿大学校大学院特別講義
近代化遺産の保存・再生・活用―愛知県での事例について思うこと
西澤泰彦
愛知県都市教育長協議会講演会
愛知県庁をはじめとした歴史的建造物の保存再生活用
西澤泰彦
日本材料学会東海支部第2回講演会
「まちの魅力」を見る
西澤泰彦
那古野まちの魅力発見ワークショップ
建築の保存・再生・活用―愛知県での事例から考えること
西澤泰彦
JIA東海・保存情報出版記念講演会
長屋と戸建て―瑞穂区の良さを再び考える
西澤泰彦
瑞穂うるおいまちづくり会+瑞穂区役所まちづくり推進室ワークショップ
植民地建築の保存再生と『日本近代建築総覧』
山口廣、坂本勝比古、越野武、竺覚曉、藤森照信、増田彰久、堀勇良、角幸博、中川理、大川三雄、西澤泰彦、村松伸
シンポジウム「日本近代建築史研究の軌跡―『日本近代建築総覧』刊行から30年を考える」
近代化遺産概論
西澤泰彦
岡崎市市民講座「近代化遺産を学び考える」
景観破壊與建築保存
西澤泰彦
東亞都市與建築保存国際研討会
東アジア地域の建築分野における人・モノ・情報の移動 ―日本人建築家を中心に― 国際会議
西澤泰彦
東アジア地域の日本植民地における建築・都市比較研究
日本近代建筑保存活用之問題 国際会議
西澤泰彦
第2回歴史建築遺産保護與持続発展国際論壇会
建築史家から見た馬場家住宅の面白さ
笹本正治、溝口常俊、西澤泰彦、谷口元
重要文化財「馬場家住宅」公開講座
近代空間を考える
松重充浩、劉建輝、松本俊郎、西澤泰彦、井上徹
シンポジウムシンポジウム<満洲研究のフロンティアをもとめて-『「満洲」の成立』を手がかりとして>
文化財建造物活用の意義
西澤泰彦
「地域の文化財建造物を判定できる専門家」養成研修
シンポジウムのまとめ
近代建築史研究の最先端第6回「近代(日本)×近代(西洋)-モダニズム研究の方法論をめぐって」
名古屋の歴史・文化資産の活用のあり方
西澤泰彦
第三回開府500年のまちの姿懇談会
東三河の近代和風建築
西澤泰彦
2009年度日本建築学会東海支部歴史意匠委員会研究懇談会「愛知県の近代和風建築―その特徴と魅力―」
近代建築の保存再生とまちづくり活動
西澤泰彦
2009年度日本建築学会東海支部研究発表会シンポジウム
近代建築の保存再生を考える
西澤泰彦
JIA保存再生セミナー
*日本の明治時代の造船所―ドライドックを中心に―
石田千尋、ウィルバート・ウェバー、横川清、バッカー・マンチェス、菊地勝広、西澤泰彦、レオン・ホンブルク、堀勇良
日蘭通商400年記念/日本とオランダ・ドイツの歴史的乾ドックとその周辺
おしゃれな瑞穂区
西澤泰彦
おしゃれな瑞穂区を探そう
20世紀前半の東アジア地域における日本人建築家の活動に関する研究
西澤泰彦
2009年日本建築学会賞受賞者記念講演
*20世紀前半の東アジア地域における日本人建築家の活動に関する研究 国際会議
西澤泰彦
2009年日本建築学会賞受賞講演
近代建築の保存と活用-愛知県の事例から思うこと
西澤泰彦
近代建築史への旅・スケッチ展
文化財建造物活用の意義
西澤泰彦
「地域の文化財建造物を判定できる専門家」養成研修
*東アジアにおける「海を渡った建築家」とその活動に関する考察 国際会議
西澤泰彦
東アジアの都市環境文化遺産をいかに継承するか
Some Topics about Preservation and Utilization of Modern Architecture in Japan 国際会議
The Coference of Docomomo Korea in 2009
鉄筋コンクリート造建築の普及と都市の近代化
西澤泰彦
20世紀の生活様式と社会環境を考える研究会2008年度第6回研究会
80年の時をこえて市庁舎が伝えるもの
西澤泰彦
第1回文化建築見学ツアー&開催記念講演会「近代建築が一宮の文化を耕す」
豊橋ハリストス正教会聖堂の建築的魅力
西澤泰彦
日本ハリストス正教会西日本教区研修会
地域の遺物から文化的資産へ―資産としての農業倉庫を考える―
西澤泰彦
福釜産業組合農業倉庫説明会
既存ストックの活用による都市の魅力向上
西澤泰彦
指定都市外郭団体連絡協議会講演会
まちの魅力とは-住宅の味わい方
西澤泰彦
名古屋市瑞穂生涯学習センター公開講座・名古屋学マイスター講座
建築が語る満洲の記憶
笠木絵津子,西澤泰彦
満洲を廻る記憶のかたち
文化財建造物の保存
西澤泰彦
「地域の文化財建造物を判定できる専門家」育成研修
豊橋ハリストス正教会聖堂の位置づけ
泉田英雄、伊藤晴康
とよはし歴史探訪「重要文化財指定記念講演会」
建築史からのコメント
石井三記、深尾祐造、細野耕司、岩谷十郎、川村康、西澤泰彦
法制史学会第60回総会ミニシンポジウム「法と正義のルプレザンタシオン-法制史における図像解釈の新たな可能性」
建物の保存-最近の動向-
西澤泰彦
2007年度公共建築月間レトロ建築ウオッチング
日本における建築史研究の発展と建築物の保存・再生 国際会議
西澤泰彦
日本における建築史研究の発展と建築物の保存・再生
日本における建築史研究の発展と建築物の保存・再生 国際会議
西澤泰彦
日本における建築史研究の発展と建築物の保存・再生
津島市本町筋の景観-その価値と保全の重要性
西澤泰彦
津島市街並み整備事業講座
街の楽しみ方
西澤泰彦
名古屋市瑞穂区役所+瑞穂うるおいまちづくり会ワークショップ
滝信四郎と蒲郡ホテルの建築
蒲郡市海辺の文学記念館開館10周年記念講演会
日本の住宅史における芝川邸の位置づけについて
足立裕司、西澤泰彦、坂本勝比古
芝川又右衛門邸をめぐって
濃尾地震・誤解された巨大地震の教訓
西澤泰彦
第2回防災サイエンスカフェ
濃尾地震と建物の耐震化
勅使川原正臣、西澤泰彦
防災フェスタ in 名古屋大学
建物の取り壊しと景観
景観の破壊と創造
濃尾地震と建築物の耐震化
西澤泰彦
第26回名古屋大学防災アカデミー
住宅の味わい方
名古屋市瑞穂区役所+瑞穂うるおいまちづくり会ワークショップ
邸宅建築の成立と普及
西澤泰彦
まちづくりびと養成講座
歴史的建造物保存の重要性
愛知県建築士事務所協会東三河支部講演会
都市の記憶を伝える風景
森まゆみ、西澤泰彦
都市の記憶
モダニズムと土浦亀城
モダニズムと昭和
住宅のかたちを決めるもの
名古屋市瑞穂区役所+瑞穂うるおいまちづくり会ワークショップ
濃尾地震から導く現代への教訓
山岡耕春、松田之利、北原糸子、西澤泰彦
岐阜県地震防災の日制定記念フォーラム
水のある風景
陣内秀信、西澤泰彦
豊橋市市制100周年記念事業・豊橋アートユニット芸術展覧会記念講演会
日本帝国内の建築に関する物・人・情報の流れ
植民地台湾をめぐる日本・中国・南洋-帝国・アイデンティティ・ネットワーク-
近代化遺産としてのドライドック
大型構造物の保存と修復
中国東北地方における日本人建築技術者・建築家の系譜
駒木定正、角幸博、西澤泰彦、中川武
近代日本のフロンティア
蟹江町文化財保存活用地域計画
蟹江町
西尾市岩瀬文庫書庫・西尾市立図書館おもちゃ館保存活用計画
西尾市岩瀬文庫書庫・西尾市立図書館おもちゃ館保存活用計画策定委員会
滝学園本館ほか2 棟保存活用計画
諏訪市文化センター保存活用計画策定に係る指導助言
重要文化財開智学校校舎調査研究報告書作成の助言指導
旧額田郡公会堂及物産陳列館保存活用計画の策定
旧長野地方裁判所松本支部庁舎の調査研究における調査指導
国指定史跡小菅修船場跡整備基本計画策定および整備事業計画の審議
学会短信 EAAC 2015 Gwangju 大会
豊橋市指定文化財愛知大学公館建築調査
国指定史跡小菅修船場跡保存管理計画策定
社団法人大日本報徳社仰徳記念館仰徳学寮冀北学舎学術調査および修復事業
旧愛知県第二尋常中学校講堂現状調査
新刊紹介 河野良平『建築家土浦亀城―住宅の特徴と変遷』
展覧会レポート「建築家・本野精吾」展
中国東北地方の都市における建築遺産の保存と活用に関する研究
日本植民地建築の戦後における状況と評価に関する研究―台北・ソウル・大連における事例研究
旧豊川海軍工廠近代遺跡調査
新刊紹介 李明・石丸紀興著『近代日本の建築活動の地域性―広島の近代建築とその設計者たち』
20世紀前半の大連における郊外住宅地に関する調査
19世紀西欧建築が東アジア近代建築に与えた影響に関する研究
「中国近代における西洋建築の受容過程と外国人建築家の活動に関する研究」を研究テーマとした留学
中国における日本人建築家の活動に関する建築史学的研究のための建築遺構調査並びに文献調査
文化遺産としての近現代建築物の保存活用にむけた学びあいと人的ネットワーク構築
2024年11月 - 現在
トヨタ財団 トヨタ財団国際助成 国際助成
西澤泰彦
担当区分:研究分担者 資金種別:競争的資金
セキュアでユビキタスな資源・エネルギー共創拠点
2022年11月 - 現在
共創の場形成支援プログラム
担当区分:研究分担者 資金種別:競争的資金
韓国における旧日本陸軍駐屯地設定とその転用に関する国際共同研究 国際共著
2020年4月 - 2024年4月
公益財団法人大林財団 2019年度国際交流助成
西澤泰彦,砂本文彦,尹 仁石
担当区分:研究代表者 資金種別:競争的資金
配分額:900000円 ( 直接経費:900000円 )
韓国における旧日本陸軍駐屯地の設定過程と戦後の転用に関する研究を韓国・成均館大学校尹仁石教授、神戸女子大学砂本文彦教授、名古屋大学西澤泰彦の三者でおこなう国際共同研究である。対象地は韓国内に設定された旧日本陸軍用地であり、その設計課程と、戦後の転用方法に関する研究である。
近代日本の公会堂建築の再評価に関する研究
2018年4月 - 2019年3月
公益財団法人大林財団 2017年度研究助成
西澤泰彦
資金種別:競争的資金
戦前に建てられた公会堂建築の再評価をおこなう。
中国東北地方の都市における建築遺産の保存と活用に関する研究―瀋陽とハルビンにおける事例研究
2009年4月 - 2010年3月
財団法人大林都市研究振興財団
資金種別:競争的資金
本研究は、20世紀前半に帝政ロシアや日本の支配を受けた中国東北地方の都市において、その時期に建てられた建築物に着目し、それらが現在の都市の中で果たしている役割を明らかにするものである。特に、中国東北地方の主要都市である瀋陽とハルビンを対象とし、次のような調査を行いながら研究を進めるものである。(ⅰ)建築リスト作成:両都市において、帝政ロシアや日本の支配を受けていた20世紀前半に建てられた主要な建築物のリストを作成する。このリストについては、すでに1988年~92年におこなわれた『中国近代建築総覧哈爾濱編』『中国近代建築総覧瀋陽編』編集のための調査結果をもとにするが、両者ともに、当時の現存建築リストであるため、それ以前に取り壊された建物は掲載されていない。そこで、本研究では、その後におこなわれた西澤と劉による哈爾濱の調査研究成果と西澤と陳によっておこなわれた瀋陽の調査研究成果を盛り込んだ復元的な詳細なリストを作成する。(ⅱ)現存状況調査:リストに記載された建物の現存状況を調べ、取り壊された物件についてはその理由を明らかにし、現存建物についても戦後の変遷を明らかにする。(ⅲ)歴史的建築物保存活用制度の調査:両都市において実施されている歴史的建築物保存の制度と現存建築物との関係を把握し、現在進んでいる都市再開発との関係を明確にする。特に1980年代から「保護建築」の制度を設けたハルビンについては、その制度の運用実態を把握し、保護建築の役割を示す。また、瀋陽では、中心市街地の活性化とともに20世紀前半の歴史的建造物が次々と壊されているため、その状況を把握し、歴史的建造物を有効活用について検討する。
日本植民地建築の戦後における状況と評価に関する研究―台北・ソウル・大連における事例研究
2009年4月 - 2010年3月
財団法人前田記念工学振興財団研究助成金
資金種別:競争的資金
日本の植民地・支配地に建てられた「植民地建築」について、支配の拠点となった台北、ソウル、大連を事例として、それたの市街地に建てられた植民地建築の戦後の状況を把握し、植民地建築に対する批評の変遷を把握する。
住宅営団の設立理念と事業実態に関する研究
2005年4月 - 2006年3月
財団法人第一住宅建設協会
資金種別:競争的資金
1941年に設立された住宅営団について、その設立理念を文献資料から明らかにし、また、名古屋支所が展開した事業実態の特徴を解明した。特に、名古屋支所では、土地区画整理事業と連動して、住宅営団による住宅地開発と住宅建設がおこなわれたことが明確になった。
近代日本のドライドック建設に関する研究
1997年4月 - 1998年3月
財団法人前田記念工学振興財団
資金種別:競争的資金
幕末~明治時代にかけて建設されたドライドックの建設状況やそれぞれのドライドックの技術・形態・規模などの特徴を明らかにし、ドライドック建設の通史の記述をおこなった。
近代日本における公共施設の鉄筋コンクリート造化に関する建築史的研究
研究課題/研究課題番号:21H01517 2021年4月 - 2026年3月
日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤研究(B)
西澤 泰彦
担当区分:研究代表者 資金種別:競争的資金
配分額:15600000円 ( 直接経費:12000000円 、 間接経費:3600000円 )
喪失技術としての炭滓・鉱滓煉瓦の復元-現代インドの複合SDGs課題解決に向けて-
研究課題/研究課題番号:23K26249 2023年4月 - 2027年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(B)
Sanjay PAREEK, 市原 猛志, 荒木 慶一, 内平 隆之, 山出 美弥, 西澤 泰彦, 山岸 吉弘
担当区分:研究分担者
明治・大正・昭和時代に我が国で普及した炭(たん)滓(さい)煉瓦(炭鉱から排出される石炭灰が主原料)と鉱(こう)滓(さい)煉瓦(製鉄時の副産物であるスラグが主原料)と呼ばれる無焼成(焼かない)煉瓦の製造技術を復元する。また、復元で得られた知見を、インドで深刻化する複合SDGs課題の解決に向けた無焼成煉瓦の普及推進や、我が国で姿を消しつつある炭滓・鉱滓煉瓦の歴史的建造物の保全・再生に活用するための検討を行う。
明治・大正・昭和時代に我が国で普及した炭(たん)滓(さい)煉瓦(炭鉱から排出される石炭灰が主原料)と鉱(こう)滓(さい)煉瓦(製鉄時の副産物であるスラグが主原料)と呼ばれる無焼成(焼かない)煉瓦の製造技術を復元する。また、復元で得られた知見を、インドで深刻化する複合SDGs課題の解決に向けた無焼成煉瓦の普及推進や、我が国で姿を消しつつある炭滓・鉱滓煉瓦の歴史的建造物の保全・再生に活用するための検討を行う。
■国内各地域の製造技術と現存建物の調査
一部鉱滓煉瓦に関して、北九州の官製八幡製鐡所について詳細な調査が完了した。更に、東北の釜石製鐡所の調査は完了した。
■製造技術の分析と復元
炭滓・鉱滓煉瓦の材料(石炭灰、スラグ、骨材、石灰etc.)の調合や前処理(粉砕、加熱、etc.)、練り混ぜ方法、成型方法(プレス、たたき)、養生方法(加熱時の温度履歴)を実験変数として多数の炭滓・鉱滓煉瓦を試作し、これらの実験変数と力学性能、耐久性、色彩、微細組織の関係を特定するための実験を開始した。
■国内各地域の製造技術と現存建物の調査
一部鉱滓煉瓦に関して、北九州の官製八幡製鐡所について詳細な調査が完了した。更に、東北の釜石製鐡所の調査は完了した。
■製造技術の分析と復元
炭滓・鉱滓煉瓦の材料(石炭灰、スラグ、骨材、石灰etc.)の調合や前処理(粉砕、加熱、etc.)、練り混ぜ方法、成型方法(プレス、たたき)、養生方法(加熱時の温度履歴)を実験変数として多数の炭滓・鉱滓煉瓦を試作し、これらの実験変数と力学性能、耐久性、色彩、微細組織の関係を特定するための実験を開始した。
■国内各地域の製造技術と現存建物の調査
東北の釜石製鐡所や北海道の室蘭製鐡所への技術移転がどのようになされたかについては不明な点が多く残る。炭滓煉瓦に関して、山口県宇部・小野田地域については内平により詳細な調査がなされているが、北九州の筑豊炭田など他の地域における現存建物や製造技術の調査は十分でない。
日本製鉄東日本製鉄所釜石地区や室蘭製鉄所周辺の現存建物の調査や、釜石市が釜石製鐵所から移管された公文書資料の文献調査などを通して、国内での鉱滓煉瓦の製造技術の技術移転について調査する。また、山口県宇部・小野田地域以外の炭滓煉瓦について、現存建物や製造技術の調査を行う。
■製造技術の分析と復元
炭滓・鉱滓煉瓦の材料(石炭灰、スラグ、骨材、石灰etc.)の調合や前処理(粉砕、加熱、etc.)、練り混ぜ方法、成型方法(プレス、たたき)、養生方法(加熱時の温度履歴)を実験変数として多数の炭滓・鉱滓煉瓦を試作し、これらの実験変数と力学性能、耐久性、色彩、微細組織の関係を特定するための実験を行う。
公立学校・廃校をコミュニティ・ハブに転換する計画・運営・プロセスとその評価指標
研究課題/研究課題番号:22H01662 2022年4月 - 2026年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(B)
小松 尚, 小篠 隆生, 西澤 泰彦, 斎尾 直子, 加藤 悠介, 山出 美弥, 李 燕
担当区分:研究分担者 資金種別:競争的資金
配分額:325000円 ( 直接経費:250000円 、 間接経費:75000円 )
少子化が進む中、公立学校だけでなく廃校跡地を市民や地域社会の多様な今日的ニーズに応える公的サービスや社会的事業、地域交流等が相乗的に展開可能な地域まちづくり拠点「コミュニティ・ハブ」に転換する意義は大きい。また、これまでの日本や海外における関連する取り組みを見ると、その実現可能性も高い。さらにその研究成果は、各自治体が進める公共施設再編計画に大きく貢献することが期待できる。そこで本研究では、公立学校及び廃校跡地の「コミュニティ・ハブ」への転換や形成について、行政を含む多主体の創発的協働かつ持続可能なまちづくりの一環として取り組み、実現するための計画論とその評価指標を、多角的視点で解明する。
大正・昭和期における住宅関連産業の展開と「暮らし」の変容に関する総合的研究
研究課題/研究課題番号:17H02552 2017年4月 - 2021年3月
科学研究費補助金 基盤研究(B)
中西 聡
担当区分:研究分担者 資金種別:競争的資金
配分額:520000円 ( 直接経費:400000円 、 間接経費:120000円 )
本研究では、実地調査の業種に対応させて、製材・鉱山業班、陶磁器業班、そして「暮らしの変容」を学際的に研究する生活環境班を設置し、それぞれの班ごとに史料調査と共同研究を進め、各班の研究成果や進行状況を研究組織全体で共有するための研究会を兼ねて、「暮らしの変容」に関連する諸研究の勉強会や研究報告会を数回開催した。
具体的には、製材・鉱山業班は、奈良県吉野の製材・鉱山業者の古文書に関する共同調査を2018年9月と2019年3月に行い、新出史料の整理を進めるとともに、研究対象の家の製材経営・鉱山経営や生活の様相に関する研究成果を共著書や単著書、および学術論文で発表した。陶磁器業班は、愛知県名古屋の陶磁器業の同業組合に関する共同調査を2018年9月と2019年3月に行うとともに、愛知県名古屋と瀬戸、岐阜県の陶磁器業産地の業界の方々へのヒアリング調査を実施した。そのなかで、第二次世界大戦をはさむ前後における陶磁器業産地の多治見と瀬戸、そして集散地の名古屋との関係がどのように変容したか、もしくは変わらなかったかに焦点を合わせて、共同研究成果をまとめることとなった。また、生活環境班は、愛知県津島の資産家の共同調査を、2018年9月と2019年3月に行い、その研究成果の一端を研究代表者が学会大会で発表した。
なお、「暮らしの変容」に関連する諸研究の勉強会では、近年刊行された近現代日本の生活環境に関する著書の合評を行ったり、メンバーが研究成果の報告を行って、各班の研究成果を今後どのようにまとめていくかについて検討した。
各班の調査は予定通り順調に行われており、製材・鉱山業班では、研究対象の家から新出史料が発見され、その整理を新たに始めた。陶磁器業班も業界の方々へのヒアリング調査を行えたことで、研究成果のまとめ方の手がかりを得ることができた。そして生活環境班では、本格的に共同研究を開始することができ、研究成果の一端を研究代表者が学会大会で発表した。
製材・鉱山業班は、2019年度も奈良県吉野の共同調査と研究を進めて中間報告会を開催し、2020年度に研究成果を学会大会のパネルディスカッションなどで発表したいと考えている。陶磁器業班は、2019年度も継続して愛知県名古屋の共同調査と研究を進めるとともに、2019年秋の学会大会のパネルディスカッションで共同研究の成果を発表したいと考えている。そして生活環境班は、2019年度の愛知県津島の共同調査を継続して進めるとともに、昨年度より始めた「暮らしの変容」に関する諸研究の勉強会や研究報告会を定期的に開催する予定である。
近代満洲における技術導入と社会変容:在地社会と植民社会の相互作用に着目して
研究課題/研究課題番号:17H02010 2017年4月 - 2021年3月
科学研究費補助金 基盤研究(B)
上田 貴子
担当区分:研究分担者
配分額:780000円 ( 直接経費:600000円 、 間接経費:180000円 )
研究チーム全体としては、途中経過を紹介し知見の交換の機会として2018年度第1回研究会を8月11日(土)近畿大学で開催した。分担者の西澤泰彦による報告「建築工事現場の監理―満鉄大連医院本館工事をめぐって」を中心に議論を行った。9月11日勉強会として院生を中心に研究の進捗状況をシェアした。今年度の最も中心的な研究実績としては12月15日近畿大学において、農業技術に焦点をあてた国際ワークショップ「近代満洲をめぐる有機物の循環~草原・森林・農地そして都市へ~」を行ったことである。
また、分担者各自がそれぞれ機会をとらえて、研究の途中経過報告を行った。代表者の上田貴子は「日本人の見た奉天、中国人の生きた奉天」と題して東洋史研究会大会で報告を行い、植民側である日本人と在地の中国人が同じ生活空間をどうとらえるか、そこにある相互作用について報告を行った。分担者の永井リサは日本土壌肥料学会において「中国近代における獣骨肥料供給地としての屠畜場の成立について―天津屠畜場を中心に―」、12月15日のワークショップでも「草原とシラス台地:20 世紀初頭の内モンゴル東部草原からの有機物流出」と題して報告を行い、近代の到来によって獣骨の価値が新たに見いだされ、在地に影響を与える点を報告した。同じく分担者の坂部は植民者と在地社会の相互作用についての一連の研究成果の報告をおこなった。
協力者のキンウィは植民者である日本の勢力が羊毛産業を満洲に扶植するにあたり現地をどのようにとらえているか「「満蒙」における日本の牧羊調査―軍部と満鉄を中心に―」(『都市文化研究』第21号)において論じた。また1年目2年目の調査を踏まえて「モンゴル牧畜社会における預託制度の変容」を日本モンゴル文化学会で発表した。これについては引き続き論点を整理して継続研究を行っている。
2018年8月11日に近畿大学にて第1回研究会を行い、西澤泰彦による報告「建築工事現場の監理―満鉄大連医院本館工事をめぐって」をもとに、在地社会から調達される労働者の管理を建築現場でどのように行うかについて具体的な議論を行うものとなった。
9月には中国東北地域での調査を行う予定であったが、台風による関西空港被災のため、メンバーの一部はこの時期の調査を断念した。この調査ができなかった点を補うためにデジタル化された史料『吉林警団公報』(1926-1931)を購入した。これは社会状況の分析に用いるためである。
12月15日近畿大学において、「近代満洲をめぐる有機物の循環~草原・森林・農地そして都市へ~」と題して国際ワークショップを行った。永井リサ「草原とシラス台地:20 世紀初頭の内モンゴル東部草原からの有機物流出」キンウィ「日本帝国の内モンゴル草原へのまなざし:日本帝国の牧羊調査を中心に」報告をもとに植民者が近代満洲にどのように関心をもつかについて議論した。
海外からは昨年から引き続き中国からサイジラホ氏が参加、新たに台湾国立中興大学の侯嘉星氏にご協力いただき、澳門科学技術大学のMiriam Kaminishi氏、UCLAの池翔氏を招聘し12月15日の国際ワークショップで研究交流を行った。その成果は、侯嘉星氏と池翔氏がorganizer、上田がchair とdiscussantを務めたAssociation for Asian Studies(AAS)Annual Meeting(Denver, USA)のパネルResource Management, Global Market, and the Making of Modern Manchuriaで発表した。
2018年度は前年度に行った海外の研究者との連携をさらに深め、今後の研究成果の国際的な発信を見通すことができた。
史料調査・現地調査については基本的には3年目である2019年度に一定のめどをつけ、各自の実証研究をまとめる作業に入る。中国での档案調査が近年厳しくなっているが、業界団体や機関内の公報などの定期刊行物を史料として利用することなど、档案史料以外を用いたアプローチを行っていく。さらに研究会・ワークショップでの経過報告を行い、最終年度に成果を国際学会で発表準備のために研究グループ内での研究の議論を深めることを目指す。
2年目である2018年度は農業に焦点をあてたワークショップを実施することができ、これにより医療・農業・人間の管理それぞれについてワークショップが行われた。3年目の今年度はこれら3つの分野に通底する「近代性」をもった技術の導入とそれによる社会変容に関する仮説のより緻密な検証を行う。そのために、6月10月に社会変容に焦点をあてた研究会およびワークショップを行う。8月には若手研究者の成果報告となる研究発表を予定している。また12月には医療・農業・人間の管理の近代的技術と社会変容を結びつけうる仮説を俎上に乗せて論点の明確化を図る。これにより本科研における一定の知見が出そろうはずである。
分担者・研究協力者の研究は総じて高い水準の実証的研究を行っている。また日本の満洲および中国東北地域をめぐる研究は世界的に高い水準のものであるにもかかわらず、海外での認知度の低さを国際学会での参加を通じ実感した。この点から本科研グループの研究成果は最終年度である2020年度末(2021年3月)Association for Asian Studies(AAS)でのパネル発表を行い、国際的に発信していくことを計画している。
二〇世紀東アジアをめぐる人の移動と社会統合に関する総合的研究
研究課題/研究課題番号:25245060 2013年10月 - 2018年3月
科学研究費補助金
蘭 信三
担当区分:研究分担者
本研究の成果は以下のようである。(1)20世紀東アジアの人の移動は、日本帝国の形成と崩壊とともに、世界的な労働力移動と密接に絡み合っていたことを諸事例から明確にした。(2)ドイツにおける「追放」と東アジアにおける「引揚げ」は比較可能であるだけでなく、米国を媒介としてそれは強く連関していたことを明らかとした。(3)長野県飯田市の20世紀を例に見てみると、南米移民や満洲移民の送出、終戦後の引揚げと中国への残留、日中国交正常化後の残留日本人の帰国、さらにはグローバル化以降の中国帰国者、日系南米人、フィリピン人の定住化など様々な人の移動が織りなされ、相互に連関していたことを明らかとした。
濃尾地震などの大規模地震による建築被害とその影響に関する建築史的研究
研究課題/研究課題番号:25420667 2013年4月 - 2018年3月
科学研究費補助金
西澤 泰彦
担当区分:研究代表者
配分額:5200000円 ( 直接経費:4000000円 、 間接経費:1200000円 )
本研究により次の3点が明らかになった。1点目は、大規模地震の被害把握について、内務省・府県・市郡町村という行政組織によって被害を網羅的に把握するシステムが明治熊本地震で確立されていたが、それは、水害の被害把握を援用したものであった。また、濃尾地震以降の地震災害では、建築の専門家が現地に赴き、専門家の視点から被災実態を調査していた。2点目は、それら専門家の調査に基づいて、建物耐震化の具体的提案がなされたことである。3点目は、特に木造建物耐震化の提案は、徐々に定着し、今日まで継続性のあるものであった。
地方都市に拠点を置いた建築家の活動と評価に関する研究-愛知県での事例研究
2008年4月 - 2013年3月
科学研究費補助金 基盤研究(C),課題番号:20560601
西澤 泰彦
担当区分:研究代表者
愛知県内に活動拠点を置いた建築家と建築組織の活動を建築の用・強・美の視点から評価した。
地方都市の近代建築に対する復元と評価に関する研究―愛知県でのケース・スタディ―
2002年4月 - 2006年3月
科学研究費補助金 基盤研究(C),課題番号:14550635
西澤泰彦
担当区分:研究代表者
日本の地方都市に建てられた近代建築に焦点を当て、地方都市の近代化との関係を中心に、近代建築の復元と評価を通じて、日本の近代建築史を総体的に捉えることを目的とした。そのための事例として、愛知県の豊橋・岡崎・西尾・刈谷・一宮・津島の6都市を選び、調査研究を進めた結果、次のことが判明した。1)公共施設整備と民間の金融機関や商業・事務所建築の建設が各都市の都市改造と連動して進められた。2)建築物の鉄筋コンクリート造化が都市の不燃化を確保していった。3)建築家の役割が重要であった。4)全く評価されずに取り壊された建物も多数あった。
歴史環境デザイン実習
2023
建築史第3
2023
建築史第1
2023
建築史
2023
多言語修得基礎
2022
環境学フィールドセミナー
2020
空間設計工学および演習第1
2018
環境学フィールドセミナー
2018
歴史環境デザイン実習
2018
建築史第3
2018
建築史第1
2018
建築史第1
2018
建築史
2018
図学
2018
図学
2017
環境学フィールドセミナー
2017
空間設計工学および演習第1
2017
歴史環境デザイン実習
2017
建築史第1
2017
建築史第3
2017
建築史
2017
歴史環境デザイン実習
2016
建築史
2016
建築史第3
2016
建築史第1
2016
空間設計工学および演習第1
2016
図学
2016
図学
2015
建築史第1
2015
歴史環境デザイン実習
2015
環境学フィールドセミナー
2015
建築史
2015
空間設計及び演習第1
2015
建築史第3
2015
歴史環境デザイン実習
2014
環境学フィールドセミナー
2014
建築史
2014
建築第3
2014
建築史第1
2014
空間設計工学および演習第1
2014
図学
2014
都市と環境
2013
空間設計工学および演習第1
2013
環境学フィールドセミナー
2013
歴史環境デザイン実習
2013
建築史第3
2013
建築史第1
2013
建築史
2013
図学
2013
歴史環境デザイン実習
2012
環境学フィールドセミナー
2012
建築史
2012
都市と環境
2012
建築史第3
2012
建築史第1
2012
空間設計工学および演習第1
2012
図学
2012
都市と環境
2011
図学
2011
建築史
2011
建築史第1
2011
建築史第3
2011
歴史環境デザイン実習
2011
環境学フィールドセミナー
2011
空間設計工学および演習第1
2011
大学院特別講義
2005年4月 - 2006年3月 (豊橋技術科学大学大学院)
都市環境デザイン特別研究DⅢ
2002年4月 - 2003年3月 (愛知淑徳大学)
都市論
2000年4月 - 2001年3月 (豊橋創造大学)
近代建築史
1998年4月 - 1999年3月 (名古屋造形芸術大学)
近代建築史
1997年4月 - 1998年3月 (大同工業大学)
地域WG旧幹事大学による第一フェーズの総括
役割:講師
カーボンニュートラル達成に貢献する大学等コアリション・地域ゼロカーボンWG 地域ゼロカーボンWG「地域連携における大学の役割」ミニセミナー・情報交換会 2025年2月
1891年濃尾地震の建築被害を考える
役割:講師
名古屋ひがし防災ボランティアネットワーク 第12回東区・地震を考える集い 2025年2月
改めて瑞穂の魅力を探すー7度目の挑戦ー
役割:講師
瑞穂うるおいまちづくり会 瑞穂うるおいまちづくり会2024年ワークショップ 2024年11月
カーボンニュートラルに貢献する大学等コアリションの5WG合同キックオフ・ミーティングへのインプット
役割:情報提供
カーボンニュートラルに貢献する大学等コアリション国際WG カーボンニュートラルに貢献する大学等コアリションの5WG合同キックオフ・ミーティング 2024年2月
学問としての瑞穂の魅力
役割:講師, 運営参加・支援
名古屋市瑞穂生涯学習センター 瑞穂ミステリーまち歩き~レトロなまちの魅力発見~ 2023年12月
まち歩きマップをたどる②~いにしえロマン織りなす山崎川~
役割:運営参加・支援, 実演
名古屋市瑞穂生涯学習センター 瑞穂ミステリーまち歩き~レトロなまちの魅力発見~ 2023年12月
まち歩きマップをたどる①~パノラマ展望“瑞穂区から外を見る”~
役割:運営参加・支援, 実演
名古屋市瑞穂生涯学習センター 瑞穂ミステリーまち歩き~レトロなまちの魅力発見~ 2023年11月
歩いてわかった瑞穂の魅力―20年の足積
役割:講師
名古屋市瑞穂生涯学習センター 名古屋学マイスター講座「みずほミステリーまち歩き」 2023年11月
総合知を活かす新たなアプローチ
役割:司会, 講師
東海国立大学機構カーボンニュートラル推進室 脱炭素社会の創造に向けた第2回シンポジウム 『 総合知を活かした新たなアプローチ 』 2023年3月
シンポジウム「守ろう活かそう蟹江の地域文化」
役割:パネリスト
蟹江町 シンポジウム「守ろう活かそう蟹江の地域文化」 2023年3月
カーボンニュートラルの実現に向けて~アカデミアの視点から考えること~
役割:講師
名古屋大学未来社会・システム研究所 第18回ホームカミングデー市民講座「2050年カーボンニュートラルの実現に向けて」 2022年10月
カーボンニュートラル推進体制の説明
役割:講師
東海国立大学機構カーボンニュートラル推進室 脱炭素社会の創造に向けた記念シンポジウム 『 脱炭素社会の創造に向けた大学の役割 』 2022年9月
次世代環境人材の育成:SDGsの先を目指して
役割:司会, 企画
名古屋大学大学院環境学研究科 名古屋大学大学院環境学研究科設立20周年記念シンポジウム 2021年10月
地域の諸相の把握方法を考える
役割:パネリスト, 情報提供
名古屋大学未来社会創造機構 第3回社会課題共有フォーラム_住みよい地域を考える:指標でみる「まち」の姿 2021年5月
「FUTUREライフスタイル実現に向けて~地域の魅力づくり」パネルディスカッション
役割:司会
名古屋大学未来社会創造機構 「FUTUREライフスタイル社会共創拠点」第1回社会課題共有フォーラム 2021年3月
岐阜大学公開講座「地(知)の拠点×SDGs」地域課題解決に向けた大学の挑戦
役割:コメンテーター
岐阜大学地域協学センター 岐阜大学公開講座「地(知)の拠点×SDGs」地域課題解決に向けた大学の挑戦 2020年12月
歴史的建造物の保存と活用
役割:講師, 助言・指導
公益財団法人名古屋まちづくり公社 なごや歴まちびと養成講座 名古屋都市センター 2020年2月 - 2021年12月
学問として語る瑞穂
役割:講師
名古屋市瑞穂生涯学習センター なごや学マイスター講座 名古屋市瑞穂生涯学習センター 2019年11月
まちの見方、歩き方、味わい方
役割:講師
名古屋市瑞穂生涯学習センター なごや学マイスター講座 名古屋市瑞穂生涯学習センター 2019年10月
公会堂建築の魅力ー別府市効果移動と四大公会堂の比較から
役割:講師
別府市教育委員会 湯けむり歴史講座 別府市公会堂 2019年9月
文化財建造物の評価と保存ー保存事例に学ぶ
役割:講師
静岡県建築士会連合会 地域文化財専門家育成研修 2019年7月
第20回まちとすまいの集い
役割:司会
名古屋大学建築学教室 現代中国の建築・都市 名古屋大学環境総合館レクチャーホール 2018年12月
第91回げんさいカフェ
役割:講師
名古屋大学減災連携研究センター 濃尾地震と震災報道 名古屋大学減災館 2018年12月
明治150年記念講座
役割:講師
豊橋市中央図書館 「明治50年」の豊橋ー建築から見た街の発展 豊橋市長図書館3回会議室 2018年12月
旧松本区裁判所庁舎重要文化財指定記念講演会
役割:講師
松本市立博物館分館重要文化財旧松本区裁判所 重要文化財旧松本区裁判所 松本市立博物館分館歴史の里 2018年4月
九州大学芸術工学部公開講座
役割:講師
九州大学芸術工学部 九州大学芸術工学部公開講座「東アジアの都市と建築」 九州大学大橋キャンパス5号館531講義室 2017年10月
公益財団法人名古屋まちづくり公社「名古屋歴まちびとフォローアップ講座」
役割:講師, 助言・指導
公益財団法人名古屋まちづくり公社 「名古屋歴まちびとフォローアップ講座」 名古屋市・星崎コミュニティセンター 2017年10月
歴史的建造物の保存活用に係る研修会
役割:講師
公益財団法人名古屋まちづくり公社 歴史的建造物の保存活用に係る研修会 名古屋市・中村公園記念館 2017年10月
松本市立博物館分館重要文化財馬場家住宅開館20周年記念講演会
役割:講師
松本市立博物館分館重要文化財馬場家住宅 松本市立博物館分館重要文化財馬場家住宅開館20周年記念講演会 松本市・重要文化財馬場家住宅 2017年9月
瑞穂生涯学習センター講座「レトロなまち『瑞穂』の魅力を伝えてみませんか」
役割:講師
名古屋市瑞穂生涯学習センター 瑞穂生涯学習センター講座「レトロなまち『瑞穂』の魅力を伝えてみませんか」 名古屋市瑞穂生涯学習センター 2017年5月 - 2017年6月
諏訪の近代建築
役割:講師
諏訪市教育委員会 東アジアの近代建築と森山松之助 諏訪市・片倉館会館 2017年2月
名古屋大学重要文化財馬場家住宅研究センター平成27年度公開講座
2015年9月
名古屋大学重要文化財馬場家住宅研究センター平成26年度公開講座
2014年9月
歴史的建造物保存活用シンポジウム「市民が育てる歴史的建造物」
2014年7月
瑞穂生涯学習センター講座「レトロなまち『瑞穂』の魅力を伝えてみませんか」
2014年5月 - 2014年6月
東枇杷島まちの魅力発見ワークショップ
2014年1月
2013年度名古屋市立大学人間科学研究所公開講演会・シンポジウム
2013年10月
名古屋市公会堂「歴史的建造物名古屋市公会堂語る・観る・触れる」第4回
2013年9月
おしゃれな瑞穂を語る―瑞穂うるおいまちづくり会10周年記念
2013年6月
豊橋市文化財センターオープン記念豊橋ハリストス正教会聖堂100歳
2013年5月
海部歴史研究会講演会「海部地域の地震災害の歴史に学ぶ」
2013年2月
建築士会東海北陸ブロック会
2013年2月
名古屋市都市整備公社「歴まちびと養成講座」
2013年1月 - 2013年7月
鳴海まちの魅力発見ワークショップ第2回
2013年1月
愛知建築士会防災セミナー
2012年10月
名古屋市公会堂「歴史的建造物名古屋市公会堂語る・観る・触れる」第3回
2012年10月
静岡県建築士会「地域の文化財建造物を判定できる専門家」育成研修
2012年7月
名古屋市都市整備公社「歴まちびと養成講座」
2012年1月 - 2012年7月
社団法人日本建築家協会登録建築家特別講習会
2012年1月
鳴海まちの魅力発見ワークショップ
2012年1月
旧豊川海軍工廠近代遺跡調査報告会
2011年11月
瑞穂生涯学習センター公開講座―レトロな瑞穂にタイムスリップ
2011年10月
静岡県建築士会「地域の文化財建造物を判定できる専門家」育成研修
2011年7月
名古屋市公会堂主催「歴史的建造物名古屋市公会堂・語る・観る・触れる」第2回
2011年5月
名古屋市公会堂主催「歴史的建造物名古屋市公会堂・語る・観る・触れる」第1回
2011年2月
名古屋市都市整備公社「歴まちびと養成講座」
2011年1月 - 2011年6月
愛知県都市教育長協議会研修会
2011年1月
中区百周年記念事業
2009年10月 - 2010年12月
城山・覚王山まちづくりシンポジウム
名古屋市千種区役所 基調講演「歴史的資産の評価と活用」 名古屋市千種区役所講堂 2018年11月
テクノシンポジウム名大 in 豊橋
名古屋大学工学部・工学研究科 テクノシンポジウム名大 in 豊橋 「工学のおもしろさについて教授とじっくり語ろう!」 豊橋商工会議所 2017年12月
名古屋大学重要文化財馬場家住宅研究センター平成28年度研究交流会
名古屋大学重要文化財馬場家住宅研究センター 名古屋大学重要文化財馬場家住宅研究センター平成28年度研究交流会 重要文化財馬場家住宅 2016年12月
有松まちづくり講演会
愛知建築士会 有松まちづくり講演会 2015年2月
RC造公共施設の再評価
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等
科研(B)_近代日本公共施設RC造化研究班 2025年1月
web研究会「建築・都市から考える1900年前後の東アジア」 国際学術貢献
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等
尹仁石+西澤泰彦 2024年2月
関東大震災前後のRC造建物を考える(その2) 国際学術貢献
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等
科研(B)_近代日本公共施設RC造化研究班(代表:西澤泰彦) 2024年2月
都市問題再考 国際学術貢献
役割:審査・評価
名古屋大学大学院人文学研究科附属超域文化社会センター ( 名古屋大学文系総合館カンファレンスホール ) 2024年1月
学校建築の鉄筋コンクリート造化と地域拠点化
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等
公共施設RC 造化研究グループ(代表:西澤 泰彦)+学校・廃校の地域拠点転換研究グループ(代表:小松 尚) 2023年12月
web研究会「建築・都市から考える1900年前後の東アジア」 国際学術貢献
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等
尹仁石+西澤泰彦 2023年10月